伊藤正直『戦後文学のみた<高度成長>』で、庄野潤三の『夕べの雲』が採り上げられている。
『戦後文学のみた<高度成長>』は、高度成長期に書かれた文芸、それも小説が、同時代の経済発展や経済システムをどのように捉えていたのかということについて、考察したものである。
高度経済成長期とは、政治史の分野では、55年体制の成立と崩壊で区分され、経済史の分野では、1955年の神武景気から1973年の第一次石油危機までとされ、さらに、社会史の分野では、1960年頃から70年代後半までの大衆社会の成立と溶解で区分することが多い。
長期間にわたって高い経済成長が持続し、高度成長の過程では、産業構造の重化学工業化が奔流のごとく進んだし、主要産業での技術革新と大規模な設備投資の進展は、企業の中で仕事のあり方や職場の編成を大きくさせた。
そして、このような労働と職場の変化は、農村から都市への大規模な人口移動を引き起こし、高度経済成長期の前期には中卒者が主力な労働力となり、後期には高卒者が、その中心となった。
産業構造の重化学工業化にともなう労働の質的変化や、都市化の進展と日本型近代家族の形成と変容は、現代文学の中で、どのように描かれ、反映されてきたのか。
生田転居後、ほぼ三年を経過してから執筆されたのが『夕べの雲』であった。
生田転居後、ほぼ三年を経過してから執筆されたのが『夕べの雲』であった。『夕べの雲』は、1964年9月から65年1月まで『日本経済新聞』夕刊に連載され、65年3月には講談社から単行本となった。本書は、1966年2月、第17回読売文学賞を授賞し、同年12月には須賀敦子の訳でミラノのフェロ出版社から”Nuvole di sera”のタイトルで翻訳出版された。(「都市型近代家族の形成—庄野潤三『夕べの雲』」)
本書で著者が注目したのは、庄野さんの代表作とも言われる『夕べの雲』だった。
生田の山の上に住む「大浦一家」五人家族の日常を淡々と描いた『夕べの雲』には、間違いなく、高度経済成長の時代を生きる一般市民の姿を見ることができる。
夫婦と3人で子どもたちで構成される「大浦家」は、1956年版『厚生白書』に登場した「標準五人世帯」そのものであり、高度成長期の核家族型小家族の典型な一家である。
もっとも、『夕べの雲』の大浦家の家族関係においては、戦前から受け継がれてきた権威主義的な家父長的関係は、まったくといっていいほどみられない。
この点について、大浦家の家族関係は、ポスト高度成長期に強調されるようになる友達夫婦、友達親子を先行していたとも言えるし、あるいは、まったく逆に、吉野源三郎『君たちはどう生きるか』が描いたような、古典的な知的ブルジョア家庭として捉えることもできると、著者は指摘している。
『夕べの雲』では、日々の瑣事の背後に、せつなさや寂寥感を感じとり続けている主人公の姿が現れる。
『夕べの雲』は、家庭生活それ自体、家庭生活のなかの親子間・夫婦間・兄弟間の日々の瑣事を淡々と描き、それらをそのものとして楽しみつつ、その背後に、せつなさ、寂寥感、無常感をかすかに感じとり続けている主人公の姿が折りにふれて現れる。そこに『夕べの雲』の限りない魅力が存在するのであるが、1996年の『貝がらと海の音』以降の、庄野の一連の「老夫婦もの」では、こうしたせつなさや寂寥感は影をひそめ、市井人の人生に対する自足が肯定的に描かれるようになる。(「都市型近代家族の形成—庄野潤三『夕べの雲』」)
『夕べの雲』を、「舞踏」や「プールサイド小景」にある、人生に対する不安とか恐怖の延長線上にあると考えて読んだのが、江藤淳だった。
江藤は、主人公である父親の姿をとらえて、『夕べの雲』を「治者の文学」と名付けたが、ここで抽出される「治者」は、古い観念の治者ではなく、根拠を断たれた都市生活者の恐怖と不安の体現者としての「治者」であった。
もっとも、本書の著者は、高度成長期に急速に進展する核家族化、小家族化のなかで普遍化してくる「父」の役割が、はたして江藤のいうような「治者」であったかどうかは別問題であるし、『夕べの』の大浦が、そうした恐怖や不安を意識下にもつものとして描かれているかといえば、それはやはり違うだろうと、否定的な見解を示している。
一方で、『貝がらと海の音』以降は「家族の幸福」「小市民の幸福」を意志的かつ自覚的に描こうとしたものであり、その出発点を『夕べの雲』に求めたのが、川本三郎だった。
夏目漱石以降、日本の近代文学は「家族の不幸」を描き続けてきたが、1960年代半ばに、日本の中産階級に属する多くの家族や、普通に社会人として生き、生活者として家庭生活を穏やかに営む市井人を主人公に据えた小説を、意志的・自覚的に描き始めたのが庄野潤三だったと、川本は考察している。
もっとも、この点についても、本書の著者は、小さな日常の幸福は、その背後に必ず「せつなさ」や「寂寥感」を包摂しているが、日本型近代家族の多くが、こうした感受性を共有していたか、生活上・精神上の余裕を保持していたかどうかは疑問であると、否定的に述べている。
『夕べの雲』では、私鉄沿線における地域開発の様相が、山間の農村地帯の喪失過程として描き出されている。
『夕べの雲』にある住宅公団の団地とは、この生田地区の西三田団地のことである。高度成長期前期の東京西郊の地域開発は、日本住宅公団、東京都住宅供給公社、東京都といった公的機関、民間鉄道資本、民間デベロッパーなどによって、ある部分では相乗的に、ある部分では競合的に、またある部分では無政府的に進められていったが、『夕べの雲』では、そうした私鉄沿線における地域開発の様相が、「静かな山間の農村地帯」の「自然の宝庫」の喪失過程としてクリアに描き出されている。(「都市型近代家族の形成—庄野潤三『夕べの雲』」)
ここで忘れてはならないのは、『夕べの雲』の主人公たる「大浦一家」も、「静かな山間の農村地帯」の原居住者ではなく、そこへ移り住んできた新たな都市生活者であったということだろう。
言ってみれば、静かな土地を求めてやってきた「大浦一家」にしても、開発に与する側の人間であったということで、ここに、高度経済成長期の新しい都市生活者の物語が生まれた。
庄野潤三の『夕べの雲』は、高度成長期以降に普遍化してくる都市生活者の家族像を、いわば先取り的に描き出すことに成功したのであり、沿線開発が生み出していく自然破壊のもたらす喪失についても、読者が「せつなさ」や「寂寥感」を共有しうる形で提示していると言えるのだ。
書名:戦後文学のみた<高度成長>
著者:伊藤正直
発行:2020/11/1
出版社:吉川弘文館(歴史文化ライブラリー)




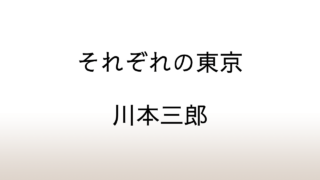

-150x150.jpg)









