有馬頼義「聖夜の欲情」読了。
有馬頼義の小説には、いつでも戦争の悲しみがある。
「聖夜の欲情」も、一義的には、難病によって身体の自由を失った少女(春香)の成長を、性の観点から描いた作品だが、その根底には戦争が深く関わっている。
「お父さまと、お母さまと、僕の三人が、あの戦争のために、発病当時の春香に何もしてやれなかったということは、一生、後悔として僕の中に残る」という長男(映)の台詞は、やはり、この作品の大きなテーマだったのだろう。
十六歳のときに志願して少年航空隊に入隊した映は、復員後に闇屋上がりの食料品店を始める。
かつて親友だった久谷は、学校へ戻るように映に促すが、映は家族を支えるために働く道を選んだ。
母は空襲で亡くなっていたし、役人だった父も、戦後間もなく亡くなってしまった。
映には、妹の春香と、弟の泰の生活を支えなければならないという責務があったのだ。
自宅では戦争未亡人の看護婦・里代が一緒に暮らしていて、父が亡くなった後、里代は映と深い関係を持っているようであったが、身体の自由のない春香には詳しいことは分からない。
やがて、弟の泰が、春香と同じ病気を発症した。
一歳違いの姉弟は、同じ病気を持つものだけが理解できる苦しみを共有しながら、愛情を深め合うようになる。
やがて、病魔が全身を冒せば、二人はまったくの人形になってしまうだろう。
クリスマスの夜、姉と弟は、越えることのできない一線を越えようとしていた。
「聖夜の欲情」は、近親相姦だけの物語ではない
簡単に言ってしまえば、「聖夜の欲情」は近親相姦の物語である。
難病にかかって身体の自由のない姉の肉体を弟が慰める。
題名の「欲情」という言葉には、美しい花を見て慈しむ「愛情」に対して、美しい花を手折って自分のものにしたいという「欲情」という意味が込められている。
いかに姉弟であっても、愛情を超えた欲情があるということを、筆者は描きたかったのだろうか。
少年航空隊へ行く前、兄の映は幼い春香にこんな話をしている。
「神さまにおねがいすると、なにかがかなえられるの?」「多分ね。しかし、サンタクロースのおじいさんとは違うよ。何かがほしい、と思う。それを何でもくれるのは、サンタクロースで、それが本当にその人をしあわせにするものならば、くれるのが神様だよ」(有馬頼義「聖夜の欲情」)
その兄も、少年航空隊から復員してからは、まるきり人が変わったようになってしまい、春香の心の拠り所は、映から久谷へ、久谷から弟の泰へと移り変わってゆく。
親友の妹に恋をして、いつか結婚をしたいと願っていた久谷でさえも、難病の春香と一緒に暮らす覚悟を持つことができない。
最後に残ったのが、同じ病気を発症した泰だけだったというところに、春香の本当の悲しみがあるような気がする。
ほとんど絶望の中にあって春香は、泰との肉体的な触れ合いの中に安らぎを見つけたのだ。
そう考えたとき、僕はこの小説を、単に「近親相姦の物語」とは呼びたくないような気持ちになる。
戦争によって治療の機会を奪われたかもしれない春香、戦争によって生き方を変えてしまった映、空襲で命を落とした母、集団疎開をしている間に母を失った泰、夫を戦死で失った戦争未亡人の里代。
この物語には、戦争の傷跡があまりにも多すぎて、だからこそ、戦争を主要なテーマだと言うことができない。
作品のテーマは、あくまでも春香の成長と自我であり、性への目覚めであると言うべきだろう。
ところで、本書の奥付を見たとき、そこには「昭和三十九年八月十五日発行」と書かれてあった。
これが果たして何を意味するものか、もう少し考えてみる必要がありそうだ。
書名:聖夜の欲情
著者:有馬頼義
発行:1964/8/15
出版社:河出書房





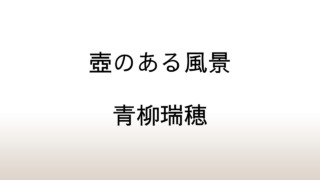
-150x150.jpg)









