斎藤慎爾「キネマの文学誌」読了。
本書は、文学者の書いた映画に関するエッセイなどをまとめた文学誌である。
これは、文学者たちの書いた映画案内だ
コンセプトは分かりやすい。
本書はわが国に映画が入ってきた明治中葉から平成までのおよそ百年の文学史、映画史を縦貫させた初の<キネマの文學誌>である。作家による映画評論、随筆ばかりでなく、日記、対談、インタビュー記事も収載した。いわば、明治・大正・昭和・平成四代の<近現代日本の精神史>もしくは<近現代日本の大衆文化史>とも呼べるものである。(斎藤慎爾「キネマの文学誌」編集余滴)
難しく考える必要はない。
これは、文学者たちの書いた映画案内だ。
映画が好きだから、映画案内の本を好んで読んでいる。
例えば、雑誌『ポパイ』特別編集『好きな映画を観よう。』とか、『アンドプレミアム』特別編集『あの人の映画案内。』とか(ムック本が大好き)。
本書『キネマの文学誌』も、そんな気軽な<映画案内>として読みたい。
一番古いものは、石川啄木の1908年(明治41年)の日記で、親友の金田一京助と、浅草で「キネオラマなるものを見る」と記されている。
次に、夏目漱石の1909年(明治42年)が続く。
昨夜子供が活動写真を見に行ったら、蘆花の不如帰をやったそうだ。そうしたら常子が泣いたそうだ。常子は九つである。どうして泣けるか不思議でならない。(夏目漱石「日記」より)
芥川龍之介はチャップリンを、谷崎潤一郎と佐藤春夫は『カリガリ博士』(1919)について書いている。
横光利一『日輪』(1925)、山本周五郎『結婚行進曲』(1928)、岡本かの子『マノン・レスコオ』(1927)、萩原朔太郎『アッシャー家の末裔』(1928)、川端康成『淪落の女の日記』(1929)と、文士の映画感想エッセイが続く。
ルイズ・ブルックスのファンだった牧野信一も、『淪落の女の日記』を試写で観ている。
僕は、これが公開されたら再び見物に趣き「試写」と「公開」の時との差異に就いて試して見ようと思っている。──そして、感化院の体操場で薄シャツ一枚で体操するブルックスの写真を探しもとめて、当分の間壁にかかげておこう──などと思っている。(牧野信一「淪落の女の日記」)
昭和に入って、映画に対する文士の関心が高まっていく様子が分かる。
井伏鱒二は、自作『多甚古村』を原作とする映画『多甚古村』(1940)を試写で観ている。
旧冬、私は映画「多甚古村」の試写を見て、そのとき私といっしょに見ていた友人が私に「まことにお気の毒ですね」と見舞いのような辞(ことば)を述べた。これは脚色者の態度について原作者の私に同情したものにちがいないが、脚色者の好みと私の好みが一致するわけでもなし、脚色者は脚色者、原作者は原作者、おのおの勝手気儘であって然るべきだと私は考えている。(井伏鱒二「試写見物」)
太宰治は、『新佐渡情話』(1936)や『兄いもうと』(1936)などを観ているが、「映画を好む人には、弱虫が多い」と、太宰らしいキャッチーな言葉から始まっている(「弱者の糧」)。
太宰にとって、映画館は現実逃避の場でもあったのだ。
戦後は、志賀直哉が書いた小野安二郎『長屋紳士録』(1947)の後に、梅崎春生『硫黄島の砂』(1949)、北原武夫『情婦マノン』(1949)、小林秀雄『天井桟敷の人々』と、洋画が続く。
石川淳は「フィルムあれこれ」と題して、1952年(昭和27年)の『文学界』に、かなり力の入った映画エッセイを書いている。
坂口安吾は、オードリー・ヘップバーンよりもマリリン・モンローが好きだった。
私はヘプバーンは好きではないが、マリリン・モンローは大好きである。モンローウォークという歩き方を取去ると残るものは清潔なあどけなさで、モンローぐらい不潔感の感じられない女優はめったにないように思う。(坂口安吾「ヘプバーンと自転車」)
もっとも、このエッセイは、『ローマの休日』(1953)を観に行ったところから始まっているから、坂口安吾も、ヘップバーン人気は気になっていたのかもしれない。
ヌーヴェルヴァーグからロマン・ポルノまで
時代の寵児・石原慎太郎は、ジェームス・ディーンの『理由なき反抗』(1955)を観ている。
永井荷風に至っては、ゾラの映画についてインタビューまで受けている(「永井荷風先生・ゾラの映画『女優ナナ』を語る」)から、みんな、本当に映画が好きだったらしい。
島尾敏雄『甘い生活』(1959)、大岡信『恋人たち』(1958)、埴谷雄高『ワルソー・ゲットー』(1961)、福永武彦『太陽はひとりぼっち』(1962)。
倉橋由美子なんて「わたしはどんな映画でもみます」と書いていて、何て心の広い女性なんだろうと思ってしまった(「スクリーンのまえのひとりの女性」)。
安岡章太郎は、映画を切り口にアメリカを語っていて、これは映画評というよりも、アメリカ文化論である(「郷愁の《新世界(アメリカ)》」)。
大佛次郎は、自作『帰郷』を原作にした映画『帰郷』(1964)について。
私の小説を読んだ方に、比較するこの「帰郷」を一度見ていただきたいと思った。まったく別の現代ものになっていながら、私の「帰郷」の心持ちがこの中に住んでいる。私は西河君のこれからの作品を注意して見ようと考えた。映画として格の正しい仕事をするひとがあるのをよろこんだのである。どうも無用に女を裸にして、あくどく客の下等な好奇心にこびるものが多過ぎるのだから。(大佛次郎「映画『帰郷』」)
一方で、吉岡実は日活ロマン・ポルノを評しているから、人それぞれである。
『人妻集団暴行致死事件』(1978)とか『団地妻 昼下がりの情事』(1971)とか、タイトルの煽情感がすごい。
東京近郊の川のほとりで、人目をはばかって、暮らしている、貧しい中年夫妻。そのささやかな幸福を、数人の若者の出来心が、破壊してしまう、ありきたりの悲劇なのだ。きわめて現実感にみちた、映画の流れが止まると、一つの神秘的な儀式がはじまる。夫は死んだ妻の裸身を、小さな湯舟で、新い清めて、おもむろに屍姦するように見える。(吉岡実「ロマン・ポルノ映画雑感」)
「人妻集団暴行致死事件」を「ありきたりの悲劇なのだ」などと、平然と断じているのは時代だろうか。
観る映画もそれぞれなら、映画を観た感想もそれぞれ。
文学と映画に興味のある人だったら、読んでおいて損はない映画ガイドである。
書名:キネマの文学誌
著者:斎藤慎爾
発行:2006/12/28
出版社:深夜叢書社


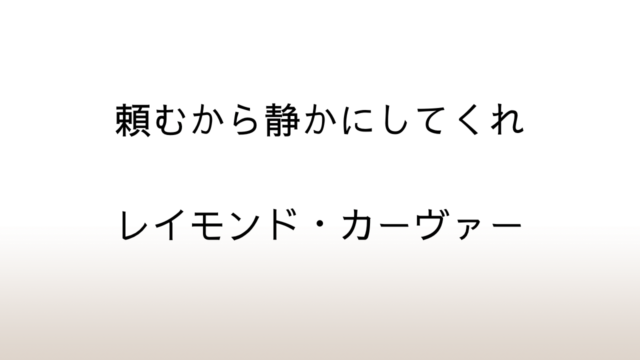



-150x150.jpg)









