野田知佑「川を下って都会の中へ」読了。
悠々として決して急がない。
計画は絶対ではないし、目標はゴールではない。
ただ自由に川を下ること。
それが、カヌーイスト・野田知佑のカヌー旅だ。
刊行は1988年(昭和63年)で、帯文には「BE-PAL 大人気”こぎおろしエッセイ”」「四万十川からユーコン川まで、個性あふれる笑いと怒りのカヌー・大ロマン!!」とある。
平たく言ってしまえば、カヌーイストによる川旅の記録で、国内外の川や海を巡る紀行文ともルポタージュとも言えるものだが、本書を支えているものは何よりも、著者(野田知佑)の人間的な魅力だろう。
人間・野田知佑の根本的な哲学は自由であることだ。
例えば、1986年の夏、野田さんは、ユーコン川の源流から河口まで3,000km以上の川旅を計画する。
「ゆっくり道草を食って遊びながら下るつもりだ」「インディアンかクマに食われることがなければ、川が氷結するまでには何とかベーリング海まで行けるだろう」と事前に話していた彼は、本当に多くの道草をして、心行くまで遊び倒す。
ユーコン川流域には、インディアンが暮らす小さな村がいくつもあって、気に入った村を見つけると、野田さんは住民と仲良くなって酒を飲み、何日でも逗留してしまう。
旅先で出会う外国人旅行者たちは「急がないと冬になってしまうぞ」と言いながら、ベーリング海を目指して通りすぎて行くが、野田さんの旅は決して急ぐということをしない。
結局「どう計算しても川が氷結する前にベーリング海まで行けないことが判った」という野田さんは、「ユーコン川の川下りはちょうど行程の半分の地点にある『ビーバー』という村で中止、帰国」してしまう。
計画が挫折したからといって、野田さんは決して悔しいとは思わないし、そもそも旅の予定を途中で切り上げたことを挫折とも感じていない。
「ただ漕ぎ下るだけなら夏の間に海まで行くだろうが、そういう川下りはぼくの流儀ではないし、面白くない」という、それが野田知佑の旅の哲学なのだ。
旅の途中で帰国した野田さんは、カヌーや装備の一式をビーバー村のインディアンに預けておいて、翌年の夏に続きを下るという。
まさしく悠々自適である。
ちなみに、ビーバー村については、新田次郎の『アラスカ物語』に詳しく、約80年前(1986年から)フランク安田という日本人が、飢餓に悩むエスキモーを引き連れて、このインディアンの土地に集団移住して作った村だ。
そういうことも、この本の中で紹介されているのを読んで学んだ。
野田さんは冒険家であるだけでなく読書家でもある。
旅の途中、日本語に飢えることがないようにと、野田さんはギターと一緒に50冊の本を旅に持っていく。
本当は「冒険家である前に読書家である」と言う方が正しいのかもしれない。
「ユーコンを創った時、神は疲れていたのだ」とは、カナダの詩人、ロバート・サービスの詩の一節だが、野田さんの川旅にはいつでも文学の匂いが漂っている。
ユーコン川の旅を終えた野田さんは、銚子の波崎海岸でアジのサビキ釣りを楽しみ、千曲川を下り、四万十川を旅する。
椎名誠(作家)や沢野ひとし(イラストレーター)、中村征夫(水中カメラマン)、佐藤秀明(カメラマン)などといった遊び仲間たちが集まり、ビールを飲みながら賑やかに川を下っていく。
野田さんの自由な生き方を支えているものは「俺は今、全く自分を信頼している」という独立心だ。
自分の持っている能力を100パーセント使って生きる、全力で生活する、完全燃焼・全力投球の生活をする。
自分自身に「100パーセントの自信」がなければ、こんなに自由な生き方なんてできるものではない。
そして、今、日本で生きる多くの人間が有していないものこそが、この「100パーセントの自信」だろう。
本書「川を下って都会の中へ」はカヌー旅の記録であるが、著者にとって、カヌー旅は生きることそのものでもある。
つまり、本書は、著者の生きてゆく行程を綴った「人生そのものの記録」とも言えるのだ。
旅に出かけるような気持ちで、こんな本を読み続けていくことができたらいいな。
書名:川を下って都会の中へ
著者:野田知佑
発行:1988/10/1
出版社:小学館



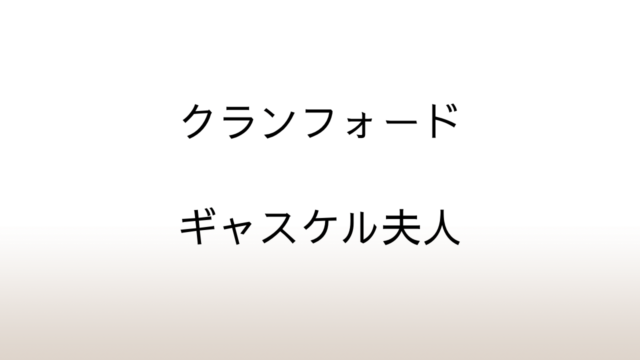


-150x150.jpg)









