庄野潤三「鉄の串」読了。
本作「鉄の串」は、「群像」昭和39年(1964年)2月号に発表された短篇小説である。
作品集では『絵合せ』(1971、講談社)に収録された(文庫化もされている)。
三人の中年男性がビア・ホールでビールを飲みながら交わしている、その他愛ない話を書き留めた物語である。
なにしろ、最初の場面から楽しい。
円い柱のかげのテーブルにいて、蓋つきのジョッキを前に話し込んでいる三人は、いつも店が混んで来て、あともう一組来れば満員、という時を計ったようにしてやって来る。
毎週、いつも同じ日に来る。そうして、坐ると、「やれやれ」というように三人、顔を見合せて笑う。「ああ、くたびれた」と一人が云うと、「くたびれた」「くたびれた」とあとの二人が相槌を打つ。本当にくたびれたように云って、溜息をついたりする。(庄野潤三「鉄の串」)
小説というよりも、まるで散文詩のようなリズムで、物語は滑り出していく。
いつものように海老の串焼きを注文すると、「三人の中でいちばんまるい顔をした男」(庄野さん自身のことだろう)が、子どもがケガをしたときの様子を話し始める。
そのとき、彼は、自分の家のそばの野原で、子どもと一緒に三角ベースの野球をやっていた。
彼と高校一年の女の子(長女だろう)と小学二年の男の子(次男だろう)が組んで、小学六年の男の子(長男だろう)と隣の男の子が相手チームだった。
ちなみに、庄野さんの長女・夏子が青山学院高校に入学するのは、昭和38年4月のことである。
夕闇の中で試合をしているうちに、娘が足首をケガしてしまった。
彼と妻は、これは捻挫だろうと考えて、最近、捻挫をして治したばかりの近所の人のところへ行って、処置の方法を聞いてくると、捻挫には大根おろしで冷やすといいらしいことが分かった。
そこで二人は、たくさんの大根おろしを作って、娘の足首を冷やすが、一向に良くなる気配がない。
病院へ行ってレントゲンで調べてもらうと、足首の一部が骨折していることが分かった。
「これには僕も面喰った。まさか骨が折れているなんて考えてもいなかったから。大根おろしをいくらつけても利き目がない筈だ」と彼は言って、三人で笑った。
その瞬間には顔が青くなってしまうような話でも、時が経てば笑い話になる。
庄野さんは、そんな「振り返れば笑い話」のようなエピソードを好んで書いた。
物語の後半では、娘が通院している病院へ、高いところから落ちたという作業員が急患として運ばれてくるエピソードが綴られている。
最初、患者を診る前に、ケガをしたときの状況だけを伝え聞いた医師は「もう助からないだろうなあ」と云ったが、結局、この作業員は一命を取り留めて、今もこの病院に入院しているらしい。
捻挫だと思っていたら骨折だった、もう助からないと思ったら無事だった。
人生は、そんなどんでん返しの繰り返しなのかもしれない。
「鉄の串」と「秋風と二人の男」は兄弟的な作品
ところで、作品名の「鉄の串」は、三人の男たちが注文した海老の串焼きに使われている鉄の串のことである。
三人が笑い出したところへ海老の串焼きが運ばれて来た。木の台皿に載った鉄板の上で、こぼれたソースが音を立てて煮えている。ピーマンと椎茸とじゃがいもの揚げたのと、それにベーコンで巻いた海老が三つと大きな玉葱が、鉄の串に刺さっている。(庄野潤三「鉄の串」)
「秋風と二人の男」(1969)という短篇小説にも、二人の男が飲んでいる店で海老の串焼きが出てくるが、これはきっと同じ店で、登場人物も同じ人間だったのだろう。
飲み屋での会話を中心にして物語が進んでいく構成も似ている。
三人の男が二人に変わっただけのことで、ということは、「鉄の串」と「秋風と二人の男」は兄弟的な作品と考えることができるかもしれない。
書名:絵合せ
著者:庄野潤三
発行:1971/5/24
出版社:講談社


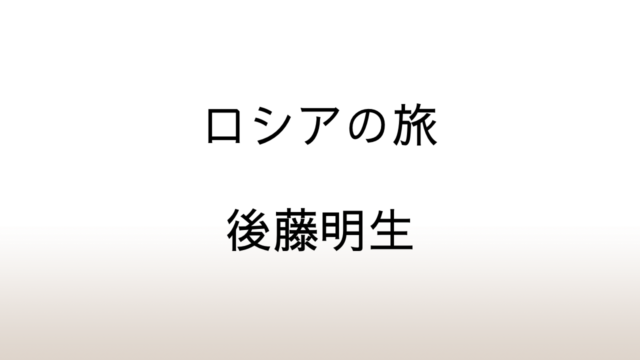
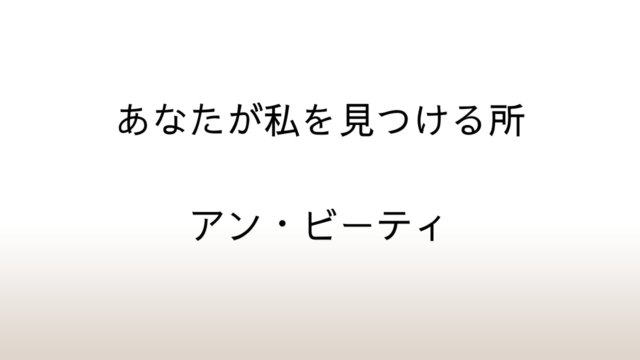


-150x150.jpg)









