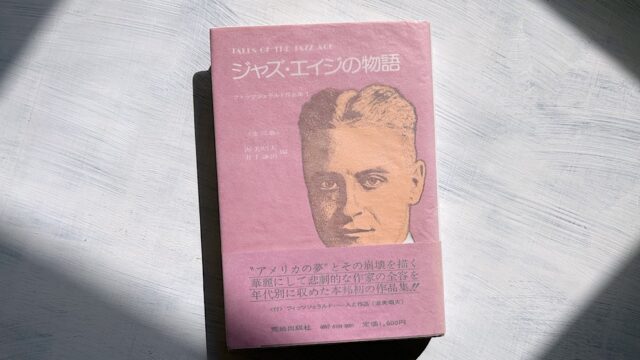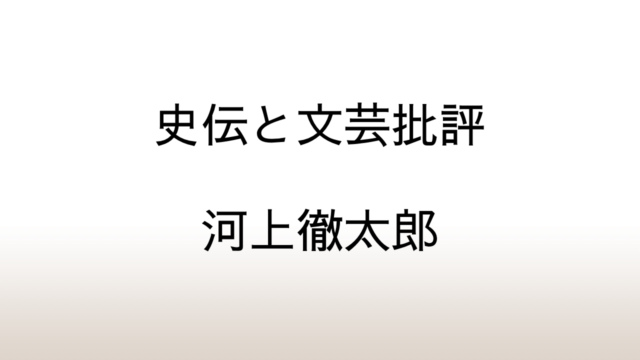南陀楼綾繁「中央線随筆傑作選」読了。
本作『中央線随筆傑作選』は、2024年(令和6年)9月に中公文庫から刊行されたアンソロジーである。
『中央線小説傑作選』(2022)の姉妹編。
阿佐ヶ谷会からサブカルチャーの街へ
「中央線」という言葉には、それだけで一種独特の魅惑的な響きがある。
その象徴こそ、友部正人のデビュー曲「一本道」(1972)だろう。
僕は今 阿佐ヶ谷の駅に立ち
電車を待っているところ
何もなかった事にしましょうと
今日も日が暮れました
ああ中央線よ 空を飛んで
あの娘の胸に突き刺され
(友部正人「一本道」)
もちろん、中央線は、70年代のみに独占されるものではない。
川本三郎は井伏鱒二『荻窪風土記』の次のくだりをご存知だろうか。「その頃(昭和二年)、文学青年たちの間では、電車で渋谷に便利なところとか、または、新宿や池袋の郊外などに引越して行くことが流行のようになっていた。新宿郊外の中央沿線方面には三流作家が移り、世田谷方面には左翼作家が移り、大森方面には流行作家が移って行く」(種村季弘「黄金の中央沿線」1985)
もちろん、川本三郎だって、井伏鱒二の『荻窪風土記』は読んでいただろう。

中央線沿線の文化的な歴史は、井伏鱒二が住み始めた昭和初期の頃には、もう始まっていたらしい。
戦後までは、阿佐ヶ谷会を中心とする文学者たちが中央沿線文化を牽引し、高度経済成長期には、演劇や音楽、漫画家などサブカルチャーの若者たちが、その後を引き継いだ。
この町をぼく等は阿佐谷村と呼んでいる。まさに人の出入りのはげしい都会の中の村なのだ。(永島慎二「阿佐谷村の午後」1985)
どの時代の中央線も、いかにも中央線らしい匂いを放っている。
昭和二十二年か、三年ごろだったと思う。その小部屋は吉行さんたちの作っている雑誌の編集所になっているらしかった。カストリ焼酎や密造ウィスキーなど持ち込んで飲む場所にもなっていたらしかった。(武田百合子「よしゆき賛江」1979)
中央線文学には、なぜか、生きているという生々しさがある。
人々が、実際に生きているところを、そのまま文学として再現しているせいかもしれない。
新宿駅から電車に乗ると、あたりは空襲であとかたもない焼け野原になっていた。どこまで走っても瓦礫の原っぱで、なに一つない。茫然と窓外をながめていると、ゆくての空に富士山が浮かんでいたのである。(芝木好子「東京の富士」1964)
西郊の町からは、焼け野原となった東京の町を見渡すこともできた。
またもや中央線だった。毎日中野駅まで行って間遠になった電車を待つのであったが、小高い中野駅のホームから南方に京王電車が走っているのが見えた。東には東京湾が見えた。東京の町は地面だけになっていたのである。昭和二十一年の春のことである。(伊藤礼「わたくしの中央線」2017)
戦後の中央線は、多くの文士たちの記憶に残っているようだ。
終戦の年の暮ごろ、阿佐谷一丁目共栄荘アパート横の路地に、総ヒノキ造りの、真新しい、とてもきれいな屋台車が出て、毎夜灯をともしはじめた。文字通り、戦後阿佐ヶ谷の第一灯で、阿佐ヶ谷盛り場の復興は、この屋台からはじまったのである。(上林暁「阿佐ヶ谷案内」1954)
上林暁は、もちろん、井伏鱒二率いる「阿佐ヶ谷会」のレギュラーメンバーである。
阿佐ヶ谷会については、木山捷平「阿佐ヶ谷会雑記」に詳しい。
中央線沿線の文人仲間で、大いに酒をのみかわす会に、阿佐ヶ谷会というのがある。会員は二十人あまり。(略)この会はもと、「阿佐ヶ谷将棋会」といったのである。(木山捷平「阿佐ヶ谷会雑記」1956)
遠いところでは、八王子市の瀧井孝作も、阿佐ヶ谷会のメンバーだった。
八王子駅の北口の駅前広場から、北の方に向いてまっすぐの広い街路には、両側に桑の木の並木が見える。桑の木の街路樹は、八王子駅前のこれが最初ではないかしら。(瀧井孝作「桑の並木」1962)
阿佐ヶ谷会のメンバーだけで、随筆選集が何冊かできあがってしまうかもしれない。
与謝野鉄幹・晶子夫妻も、荻窪の人だった。
荻窪は東京駅から四里もある東京の西郊に位置し、大震災前までは東京人の注意に上らず、私などは名さえも知らなかった程の辺鄙な農村であった。(与謝野晶子「我家の庭」1932)
荻窪で700坪の土地を借りた与謝野夫妻は、あまりに広すぎるという理由で、そのうち200坪を戸川秋骨(英文学者)へ譲ったという(だから、戸川秋骨は、与謝野夫妻の隣人だった)。
昨年までは柏木であった町内のこの横町は、表の大久保通りへ出るまでの、こまごまと日常性に満ちた通りである。路地から出た私は表通りへの途中でいつもここを通る。(佐多稲子「町内のこと」1971)
随筆と言っても、文学者の眼によって記録された町は、既に風土記としての風格を備えている。
灯影の明るい二階家を見あげながら私は多分あの部屋が井伏さんの窓かと思って、「小説家の井伏鱒二さんの家はこの辺にありますかあ」と大声で尋ねた。あの窓でなくともどこかで聞えるかと思ったからであったが、「うるさい。井伏鮭二(シャケジ)さんはこの裏だ!」と障子の中からどなり返された。(鈴木信太郎「荻窪近辺」1954)
さすが、鈴木信太郎の文章には、荻窪周辺の手描きの地図が添えられている。
紀行文学(散歩文学)としての中央線文学
荻窪といえば、石井桃子を忘れることもできない。
青梅街道は、チンチン電車と別れを告げると、少し駅寄りで線路をつっきり、踏切りを渡って北口へ通じていた。線路の上には、中央線の電車ばかりか、汽車(客車・貨車)が通っていたから、この踏切りではいつもかなりの人数の人たちが遮断機の上がるのを待っていた。(石井桃子「南口の亡霊」1995)
石井桃子は、ここで、井伏鱒二や太宰治と交流を持ったのだ。
太宰治が入水自殺した玉川上水のことは、津村節子が書いている。
三鷹に住むようになった頃、夫と上水べりをよく一緒に歩いたことを思い出す。仕事が多忙になり、旅行も取材のためしか行かなくなって二人で歩くことはなくなっていた。(津村節子「二人の散歩道」2010)
津村節子の夫(吉村昭)は、2006年(平成18年)に他界している。
小島信夫が触れているのは、中上健次のこと。
中上さんが八王子に居を移してからと思うが、やはり国立に住んでいた高瀬千図さんが、「白十字」で原稿を書き出した。(略)いつか中上さんに、彼女が「白十字」で原稿を書いていると話したら、彼女は、あの仲間の中で、一番アタマがよくて才能がある、といった。(小島信夫「国立の喫茶店」1992)
小説家というのは、喫茶店で原稿を書きたくなるものかしら。
町全体が自分の家で、喫茶店は自分の書斎、みたいな雰囲気がある。
駅前にある”しもおれ”という名の喫茶店で、川上さんがわたしの隣人であることを教えてくれたのは、ドイツ文学者であり旅の作家でもある池内紀さんだ。わたし達は二人とも、その喫茶店の常連なのである。(西江雅之「三鷹”蝦蟇屋敷”界隈」2006)
川上弘美と西江雅之とは、一つ塀を共有する隣人だったらしい(意外と気が付かないもんか)。
「あんつるさん」こと安藤鶴雄は、四谷見附から市ヶ谷へ至る土手がお気に入りだった。
わたしは、四谷見附橋という橋が好きで、地下鉄の駅の方からとりつけた陸橋のような、コンクリートの道に立って、四谷三丁目の写真館主・村瀬博さんに、二、三年前、写真を撮ってもらったことがある。(安藤鶴雄「四谷見附」1969)
中央線をテーマにした選集だから当たり前だが、中央線沿線の風景が、次から次へと出てきて楽しい。
言ってみれば、これもひとつの紀行文学のようなものだろう(あるいは散歩文学か)。
私は、戦争中と戦後の一時期を除いて、ずっと市ヶ谷駅の傍に住んでいる。ここは、戦後千代田区五番町と改められるまでは麹町区土手三番町といった。(吉行理恵「公園に漂っている夢」1976)
兄・吉行淳之介と、妹・吉行理恵の母(吉行あぐり)が「山ノ手美容院」を経営していたのは、市ヶ谷駅の近くだった。
近所には、内田百閒も暮らしていたという。
中央線とは関係ないが、小沢信夫の随筆に良い文章がある。
小説を読むことは、時に殆ど人生上の体験にほかならない。それが文学だ。(小沢信夫「新宿駅構内時計のこと」1983)
優れた随筆を読むことも、僕は、やはり、人生上の体験だと思う。
七時半まで誰か来ないものかと待っていたが誰も来なかった。そこで彼は起ち上って、室の隅に行って、原稿紙の反故や本や雑誌の堆の中を探しはじめた。読んでしまった本が二冊ばかり出て来た時に、「五十銭にはなるだろう」と呟いた。(中原中也「古本屋」1930)
中原中也は、飲み代を探していたのだ。
こういう散文が読めるところも、本書のような選集のメリットだろう。
秋の日侘しく散らばう青梅街道。此処には昔ながらの新宿が現存して居る。しかもガードを一つ距てて、淀橋の向うに二幸や三越のビルヂングが塁立し、空には青い広告風船があがって居る。何という悲しい景色だろう。(萩原朔太郎「悲しい新宿」1934)
萩原朔太郎の見た「悲しい景色」には、一人暮らしの侘しさが投影されていなかっただろうか(1929年以降、妻の不倫により家庭生活が破綻し、当時は単身生活を送っていた)。
阿佐ヶ谷から荻窪にかけての住宅街が、そのころ《胴村》とこっそり呼ばれていたことを知る人は少ない。横溝正史の怪奇小説にでも出てきそうなこの気味の悪い呼び名は、アイロニカルな蔑称だった。(久世光彦「阿佐ヶ谷は、怖くて美しかった」2001)
年を取って「お役御免になった人たち」、すなわち首になった人たちが多く集まって住んでいたので、首のない胴だけの「胴村」となったものらしい。
「コミさん」こと、田中小実昌も、中央線のイメージの強い人だった。
西荻窪南口の路地で飲んでいると、そこのママが、街のお客さんみたいねと言った。西荻窪南口の「街」という飲み屋で、毎晩のように飲んでいたことがある。(田中小実昌「西荻窪の借金」1982)
山口瞳は、地元・国立を愛した作家として有名である。
中央線の国立駅から私の家までの距離は、歩いて十五分である。人に訊かれれば、「歩いて十五分です」と答えてきた。(山口瞳「歩いて十五分」1991)
人気作『居酒屋兆治』のモデルも、国立市・南武線谷保駅近くの居酒屋「文蔵」だった。
こういう随筆集のメリットは、とにかく、次から次へと斜め読みして楽しいということだ。
小説みたいに深読みしたりしなくていいから、細かいことを気にせずに、どんどん読み進めることができる。
こういう本だったら、休日の一日で一冊読めるんだけどな(トルストイ『戦争と平和』は、仕事の合間に読んでいたので三週間かかった)。
「覚えているか、おでん屋の東さん」「ああ。あのおじいさんが死んだのはついこの間のことだもの」ぼくの『にんじん』のジャケットにもなっている東さんは、三年前の夏、事故で亡くなった。(友部正人「一九八二年のタイム・スリップ」1982)
今年の12月には、ちくま文庫から、友部正人の随筆選集『歌を探して 友部正人自選エッセイ集』が出版される(12月12日発売予定)。
読みたい本が、どんどん増えてしまって、僕の読書計画は破綻してしまいそうだ(現在は、島崎藤村の『新生』を読んでいます)。
書名:中央線随筆傑作選
編者:南陀楼綾繁
発行:2024/09/25
出版社:中公文庫