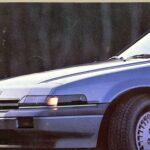阪神タイガースがリーグ優勝しました!
ありがとう、阪神タイガース、ありがとう、岡田監督(泣)
今年は凄いスター選手がいるわけでもないチーム構成の中、チームとしての総合力で勝ち取った優勝と言えるでしょうか。
それとも、岡田監督の愛弟子・鳥谷敬さんが「MVPは岡田監督」とコメントしているように、岡田監督の指導力による優勝だったのでしょうか。
いずれにしても、岡田監督抜きにして、今年のリーグ優勝はなかったように思います。
ということで、今回は、岡田監督の指導力やマネジメント力を学ぶことのできる前著作をまとめてみました。
若い部下職員を持つ管理職の方、必見ですよ。
Contents
なぜ、岡田監督が凄いのか?
ところで、どうして、岡田監督が凄いと言えるのでしょうか。
2005年の阪神タイガースのV戦士・鳥谷敬さんのコメントが、すごく分かりやすいと思います。
鳥谷敬さんのコメント
阪神タイガースのリーグ優勝が決まった後、愛弟子でもある鳥谷敬さんは「MVPは岡田監督」とコメントしました。
MVPが誰かと問われると判断が難しいですが、誰がチームに最も大きな変化をもたらしたかといえば、岡田彰布監督で間違いないでしょう。もし、岡田監督でなかったら…。(鳥谷敬「集英社オンライン」より)
理由としては、中野拓夢選手の遊撃から二塁へのコンバートや、ルーキー森下翔太選手の起用など、岡田監督でなければ難しかった組織マネジメントが、大きなポイントとなっているようです。
試合中の采配に関しても「勝負どころでの代打起用や、想像できない投手起用」など、岡田監督だからこその判断力が、リーグ優勝の原動力となったことは間違いありません。
打順やポジションを固定するなど、他にもいろいろな要因はあると思いますが、最も難しいと思われる「意識を変える」ということが、選手たちが1年間かけてじっくり成長し、自信をつけるということにつながったのでしょう。
チームを勝たせることが監督にとって一番の仕事なわけですから、選手の野球観を変え、チームの勝利に結びつけた岡田監督の手腕は、本当に「すばらしい」の一言です。(鳥谷敬「集英社オンライン」より)
試合後の監督コメントを見ても、岡田監督のマネジメント力には、一人の管理職として、参考になるものがたくさんあります。
この秋、日本には、岡田監督に学びたいと考えている組織マネージャーが、たくさんいるのではないでしょうか。
 出典:Unsplash
出典:Unsplash岡田彰布とは?
皆さんは、岡田監督のことを、どのくらい御存知でしょうか。
岡田監督の著作を紹介する前に、簡単に岡田監督の略歴を振り返っておきたいと思います(著者プロフィールですね)。
岡田監督の全歴史を振り返るのは大変なので、岡田監督の特に凄いところにスポットを当ててご紹介しましょう。
子どもの頃から阪神タイガースのファンだった
岡田監督の父親は、阪神タイガースの有力な後援者でした。
当然、その子どもである岡田監督も、幼少の頃からのタイガース・ファン。
甲子園球場では、敵陣である三塁側に席を取り、読売ジャイアンツに向かって野次を飛ばしていたそうです。
北陽高校時代に夏の甲子園に出場
岡田監督は、北陽高校1年生在籍時に、夏の甲子園大会に出場しています(1973年)。
このとき、ポジションはレフト、打順は2番か7番だったそうです。
なお、エースで4番だった3年生時には、大阪府大会の決勝で敗れて、甲子園出場は果たせませんでした。
早稲田大学で三冠王
早稲田大学の野球部に進んだ岡田監督は、東京六大学リーグで活躍。
サードで5番の1978年秋季リーグでは三冠王に輝き、4年ぶりのリーグ優勝を果たしました。
リーグ通算成績は88試合で309打数117安打、20本塁打、81打点、打率.379で、打点と打率は現在もリーグ記録となっています。
ちなみに、後輩となる鳥谷敬選手は通算115安打で、安打数では早稲田歴代2位の記録となっているそうです。
阪神タイガースで新人王を獲得
1980年のルーキーイヤーは、打率.290、18本塁打、54打点で、新人王を獲得しました。
オールスターゲームでは、史上最年少となる代打ホームランを記録しています(現在は更新されている)。
当時、阪神タイガースのサードには掛布雅之選手がいましたが、掛布選手の故障の穴埋めでサードを守るほか、セカンドにも多く就きました。
 出典:Unsplash
出典:Unsplash1985年リーグ優勝のV戦士
1985年に阪神タイガースがリーグ優勝したときは、5番・セカンドとして大活躍。
打率.342(リーグ2位、バースが首位打者だった)、35本塁打、101打点と、優勝の立役者の一人となりました。
対巨人戦の「バックスクリーン3連発」(掛布・バース・岡田)は、今もタイガース史に残る伝説となっています。
2005年、タイガース監督としてリーグ優勝
2004年に阪神タイガースの監督に就任すると、2年目の2005年にリーグ優勝。
「JFK」(ジェフ・ウィリアムス、藤川球児、久保田智之)と呼ばれる「勝利の方程式」を確立しました。
プロ2年目の鳥谷敬選手が、ショートとして定着したのも、この2005年のことです。
2023年、タイガース監督としてリーグ優勝
あれから18年。
阪神タイガースの監督として復帰した岡田監督は、復帰一年目にして圧倒的な強さでリーグ優勝を果たします。
2005年のようなスター選手がいない中、チームとして力を結集しての優勝でした。
(おまけ)我が家と岡田彰布選手
自分は、関西の人間ではありませんが、1979年からのタイガースファンです。
理由は、大好きだった小林繁投手が、読売巨人軍から阪神タイガースへと移籍したから。
その後、1980年に岡田彰布選手がタイガースに入団した後は、大の岡田彰布推しとなります。
写真は、1982年の正月に、岡田彰布選手から届いた年賀状。
以来、40年以上、岡田選手(岡田監督)を応援しています。
 1982年の正月に、岡田彰布選手から届いた年賀状
1982年の正月に、岡田彰布選手から届いた年賀状「選手の特性を生かす」岡田監督の指導法とは
岡田監督の指導法の特徴は、個々の選手の長所を伸ばすことだと言われています。
それは、2015年から2018年まで阪神タイガースの監督を務めた金本知憲監督とは、特に対照的な指導方法でした。
例えば、タイガースの監督に就任した当時、金本監督は、自身の推奨するウエイトトレーニングを選手にも導入し、チーム全体の長打力アップに取り組みます。
既にベテラン選手だった鳥谷敬選手にも、長打アップを求める「超変革」の指令が出て、鳥谷選手はバッティングフォームの変更を余儀なくされますが、もともと長距離バッターではない鳥谷選手は、この「超変革」によって、自分の持ち味を殺してしまうことに。
選手の特性を無視して、一律に組織の価値観にはめ込もうとする金本監督の指導方法は、昭和時代には一般的なものでしたが、選手の多様性を重視する昨今では、特に鳥谷選手のような現代的なタイプの選手にはマッチしなかったようです。
このあたりの事情は、鳥谷選手の著作にも書かれています。『他人の期待には応えなくていい』。さすが鳥谷!(笑)
選手層が薄い中、鳥谷選手に過度の期待がかかった面は否めませんが、金本監督の「超変革」は、監督のマネジメントが、選手の成績に大きく影響した(しかも、その後の野球人生にも影響した)極端な事例の一つとなってしまいました。
一方の岡田監督は「普通が一番」をモットーに、選手の持ち味を生かすことを最優先に心がけているようです。
例えば、中野選手のショートからセカンドへのコンバートも、中野選手の特性を踏まえたもので、結果的に、今シーズンの中野選手は高い打率を残すことに成功しています(現在は最多安打のタイトル争いをしている)。
若手選手の守備位置を確保するために、ベテラン鳥谷選手をコロコロとコンバートした金本監督とは、選手の育成方法に対する考え方が、根本的に異なっているんですね。
 出典:Unsplash
出典:Unsplash岡田彰布監督の著作
そんな岡田監督の指導法やマネジメント法の思想は、岡田監督自身の著作で学ぶことができます。
管理職の方は、岡田監督の著作を読んで、若い力を生かしたマネジメント法を参考にしてみてはいかがでしょうか。
僕は、岡田方式を大いに導入しようと考えています(笑)
金本・阪神 猛虎復活の処方箋(宝島社新書)
2017年に発売された『金本・阪神 猛虎復活の処方箋』です。
2005年以来、毎年のように優勝候補に挙げられながら、優勝を逃し続けている阪神タイガース。2016年は、金本知憲を新監督に迎え、大きな期待を持たせたものの、終わってみれば首位から24・5ゲームも離された4位。そんな歯がゆい状況にある近年の阪神について、タイガース優勝監督にもなった岡田彰布氏が、金本・阪神はなぜ勝てないのか、勝つためにはどうすればいいのか、等について、さまざまな角度から問題点を洗い出しつつ、再建案を語りつくします。(紹介文より)
ダメな組織を具体事例として、再建プランを提案する実践型の指導書です。
大切なことは、自分の組織はなぜダメなのかということを徹底的に分析すること。
つまり、組織としてのメタ認知なんですね。
自分の欠点と向き合えなければ、改善も再建も難しいということでしょうか。
そら、そうよ~勝つ理由、負ける理由(宝島社)
2014年に発売された『そら、そうよ~勝つ理由、負ける理由』です。
開幕前に勝敗は決している――。プロ野球チームの強弱とは、すなわちフロントと現場という「組織」による「準備力」の有無にある。自身が監督を務めていた際、なぜ阪神では優勝し、オリックスでは最下位に沈んだのか。自らその理由を、補強、育成、采配などさまざまな視点から分析し解説する、岡田理論の集大成。(紹介文より)
理論派の指導者である岡田監督のメソッドが体系的にまとめられた一冊です。
管理職ビジネスマンの入門書として、いかがでしょうか。
意識改革にも繋がる内容だと思いますよ。
プロ野球 構造改革論 (宝島社新書)
2014年に発売された『プロ野球 構造改革論』です。
3部リーグ、30球団制! ボールが飛んで何が悪い。育成できない育成制度はいらん。選手会長時代の裏話も収録! 野茂英雄メジャー挑戦の秘話。FA導入をめぐる水面下のバトル。このままではプロ野球は死んでしまう! 選手、選手会長、監督と常に改革を叫んできた岡田彰布氏だからこそ提言できる球界大手術。選手として、第3代プロ野球選手会長として、そして阪神・オリックスの監督として“プロ野球”にかかわった岡田彰布氏だからこそ提言できるプロ野球の構造改革論。野茂のメジャー流出、FA制度導入など選手会長時代の“改革”と“葛藤”の裏話から、人気凋落が止まらない今のプロ野球への熱い想いを込めた一冊。(紹介文より)
プロ野球という業界の構造改革を提唱した岡田理論。
これを読むと、岡田監督が、何を考えながら采配しているのかが分かるような気がします(笑)
常に改革を意識している岡田監督のポイントは課題認識。
課題認識なくして改善はあり得ないということでしょうか。
なぜ阪神はV字回復したのか?(角川oneテーマ21)
2013年に発売された『なぜ阪神はV字回復したのか?』です。
タイガースまさかの大躍進! 藤浪、西岡、マートン……絶好調の秘密。ここ数年不振続きで開幕前はそれほど期待されていなかった阪神タイガースだが、ふたを開けてみれば巨人と首位を争う大躍進。チームの何が変わったのか。その秘密を元監督の岡田彰布が探る。(紹介文より)
岡田監督の観察力や分析力を知ることのできる貴重な一冊です。
阪神タイガースという事例を冷静に分析して、好調の秘密を考察しています。
こうした分析と考察の積み重ねが、明日の勝利へと繋がっていくのかもしれませんね。
(2024/05/01 19:38:32時点 Amazon調べ-詳細)
動くが負け―0勝144敗から考える監督論 (幻冬舎新書)
2010年に発売された『動くが負け―0勝144敗から考える監督論』です。
岡田彰布は決して先には仕掛けない。彼は作戦において、常に相手の狙いを知ってから、それを上回る策を講じ、勝利を積み重ねてきた。それは最悪の展開を常に想定して、「完璧な準備」をしているからできること。スポーツ紙の片隅にある一人の選手の負傷記事から相手の意外な先発を察知し、裏の裏をかく。チームの結束を保つために、勝手な振る舞いをした不動の四番打者を開幕直前にスタメンからはずす。デビュー戦で自信をつけさせるために、新人投手は相手のローテーションの谷間にぶつける。かつて阪神を優勝に導いた名将の極意。(紹介文より)
ビジネスにおいて「戦略とは何か?」ということを考えさせてくれる一冊です。
岡田監督は、野球指導者として、本当に楽しく真剣に取り組んでいるんだと感じました。
「楽しく真剣に」、ビジネスでも必要な視点ではないでしょうか。
頑固力―ブレないリーダー哲学 (角川SSC新書)
2008年に発売された『頑固力 ― ブレないリーダー哲学』です。
阪神タイガース第30代監督・岡田彰布。彼の人生はまさに阪神とともにあった。阪神の寮を遊び場として育った少年時代。ドラフト1位で入団し、新人王を獲得。85年には、“伝説のバックスクリーン3連弾”の3発目を叩き込み、優勝への原動力となった。エリート人生を歩んできた男は、しかし不本意なかたちでオリックスへ放出される。だが指導者としての長い下積みを経て、男は猛虎の主となった。常に優勝を争った激動の5年間。寡黙な男が初めて明かす、ブレないリーダー哲学。(紹介文より)
岡田監督の戦略・戦術がいっぱい。
一般のビジネス界でも通用しそうなヒントが、たくさん見つかりますよ。
まとめ
いかがでしたか?
岡田監督の著作は、野球界のゴシップではなく、あくまでも指導者としての理論を説いたビジネス書です。
スキャンダルな暴露記事はありませんが、ビジネスに役立つ情報ならたくさん見つかります。
若い社員とのコミュニケーションに悩んでいる管理職の方にもおすすめですよ。
(2024/05/02 13:47:35時点 Amazon調べ-詳細)