庄野潤三『水の都』読了。
庄野文学のひとつの大きな流れとして「聞き書き小説」というジャンルがある。
自分の体験を書くのではなく、他者の体験を聞き取って書いた小説のことだが、庄野さんは、他者の体験を、まるで自分のことのように小説にしてしまう。
庄野さんの聞き書き小説の特徴のひとつは、特別の人の体験を聞き取るのではなく、できるだけ普通の人(いわゆる市井の人々)の話を聞き取っていること。
普通の人々の話の中に、普遍的な価値観や歴史的な価値観を見出そうとしているのが、庄野さんの聞き書き小説だ。
本作『水の都』では、丁稚奉公から叩き上げて来た大阪商人の生涯を通して、大阪という街の文化や庶民詩を描き出そうとしている。
庄野さんの聞き書き小説の、もうひとつの特徴は、小説を書くための手段であるはずの取材の工程そのものが、小説になってしまうということだ。
取材の対象者とどのように連絡を取ったとか、大阪までどのように移動して、大阪ではどのように過ごしたとか、そんなことも、庄野文学では小説の一場面になってしまう。
ドキュメント映画のメイキングシーンまで含めて、ひとつの作品として仕上げられている感じ。
結局、取材という行為を、そのまま作品化してしまうことで、聞き書きそのものが庄野さん自身の体験として昇華されているわけだから、聞き書き小説さえ、庄野文学ではひとつの私小説と呼ぶことができるかもしれない。
古い大阪の街なかの空気を吸って大きくなった人に会って、いろいろ話を聞いてみたらどうだろう
必ずしも商家に限らないが、古い大阪の街なかの空気を吸って大きくなった人に会って、いろいろ話を聞いてみたらどうだろう。おじいさんかおばあさんのいる家なら、なおいい。(庄野潤三「水の都」)
『水の都』は、庄野さんが、この作品を書こうと思いついた場面から始まる。
冒頭からして、メイキング映像のような小説なのだ。
すると「妻」が「悦郎さんに会ってみたらどうかしら」と提案をする。
「悦郎さんというのは、妻のひとつ年下の徒弟で、父親は小さい頃に亡くなったが、高麗橋で茶道具屋をしていたお祖父さんのあとを嗣いで、これまで商売を続けている。いまは芦屋にいる」人だという。
こんな具合に、「悦郎さん」を始めとする大阪の人々の回想が、それを聞いた庄野さん自身の体験として、小説は進められていく。
井伏鱒二の『珍品堂主人』が、骨董屋の主人が自分の半生を語る形で進められているのとは、まったくアプローチの方法が異なっている。
あくまでも、自分の経験したことを書くという庄野さんの強い信念が、そこにはあるような気がする。
だから、聞き書き小説を読んでいても、庄野文学に触れているという充実感は、いつもと何も変わらない。
そこに、庄野潤三の聞き書き小説の世界があるのではないだろうか。
書名:水の都
著者:庄野潤三
発行:1978/04/20
出版社:河出書房新社



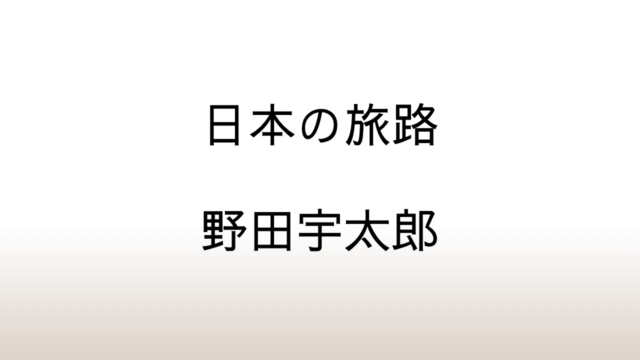
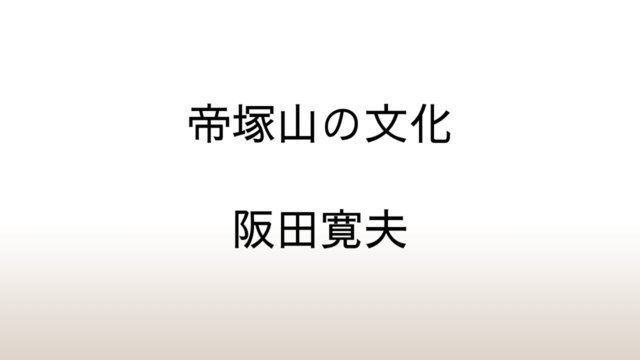


-150x150.jpg)









