庄野潤三『懐しきオハイオ』読了。
あとがきから引用する。
1957年(昭和32年)の秋から翌58年(昭和33年)の夏まで、庄野さんはロックフェラー財団の研究員として、奥様とともにオハイオ州ガンビアの林の中の教授住宅「白塗りバラック」で暮らした。
本書『懐しきオハイオ』は、初めて北米大陸の冬を迎えようとしていた最初のころを振り返って昔のノートを辿った『シェリー酒と楓の葉』(昭和53年・文藝春秋)の続編である。
『シェリー酒と楓の葉』と同じく「文学界」に掲載されたが、その連載は、1989年3月から1991年4月号まで、2年2か月間の長期に渡った。
すべての庄野文学作品の中で、最大最長の長編小説である。
驚くべきことは、1958年の留学体験を、ほぼ30年後の1989年から長期連載をしたということだろう。
バブルに沸く狂乱の日本で、庄野さんは黙々と30年前のアメリカの田舎町での暮らしを書き続けていたのだ。
まるで時代に抵抗するかのように粛々と、『懐しきオハイオ』は素朴だけれど温かい、ガンビアで出会った人々の姿を綴っていく。
1958年の12月31日で終わった前作『シェリー酒と楓の葉』の後を受けて、『懐しきオハイオ』は1959年の1月1日から始まる。
庄野夫妻は、同年7月21日にガンビアを離れているから、およそ7か月間の物語が、この作品の中で描かれている。
当時の詳細なノートを忠実に再現しているかのように、日々の記録が克明に描かれていく様子は、小説を超えて、まるでドキュメンタリー映画でも観ているかのようだが、庄野さんの描く物語は、明らかに庄野潤三という一人の作家の眼をフィルターとして描き出された物語だ。
それは、アメリカという国に対する社会批評でもないし、日本とアメリカとを秤にかけた比較文化論でもない。
我々が日本の日常で多くの人々とすれ違うように、庄野さんは異国のガンビア村で多くの人々とすれ違い、そこに交流を見出した。
アメリカだからとか外国人だからなどといった特殊な感情は、そこでは一切描かれていない。
ただ近所の人々と楽しく食事をして、隣町の友人の家へ遊びに行く。
それが、庄野潤三の留学体験だった。
『懐しきオハイオ』という小説を読んでいても、異文化の香りをいうものをまったく感じないのは、そんなところに理由があるのだろう。
描かれていることは、間違いなくアメリカの暮らしなのに、まるで、日本の田舎町で暮らしているかのように、庄野さんは堂々と、自然体で日々を過ごしていく。
とにかく目立つのは、友人たちとの食事の日々である。
毎日のように、誰かに夕食に招かれては、そのお返しにと誰かを夕食に招く。
特別な予定がない日にも、近所で暮らすミノーとジューンの夫婦が遊びにやってきて、食事をしたり、お茶を飲んだり、お酒を飲んだりしている。
庄野夫妻は、遠く日本を離れて寂しい、などと思う暇もなかったのではないだろうか。
日本の家族や友人たちからも頻繁に郵便が届いて、東京の様子を逐一知らせてくれるから、『懐しきオハイオ』では、しっかりと留守宅の様子も描かれている。
東京で留守番をしている「夏子」「龍也」「和也」の三姉弟が、ちゃんと物語の一部分を構成している。
仲良くしてくれたニコディムさんと最後の挨拶を交わしているとき、庄野さんの妻が、留守宅の子どもの写真をニコディムさんへプレゼントする場面、写真を受け取ったニコディムさんが「これがナツコ、これがタチア…」と言いかけたところで、妻が泣き出してしまう。
ニコディムさんは「泣いてはいけない、泣いてはいけない」と言いながら妻を抱いて、頬に接吻してくれるのだが、東京で留守番をしている子どもたちを含めて、まさしく家族ぐるみの交流が、ガンビア村の人々ともあったということなのだろう。
庄野さんが、ガンビア留学を書いたのは、『ガンビア滞在記』(1959年、中央公論社)が最初だけれど、『懐しきオハイオ』では『ガンビア滞在記』で書かれなかったエピソードがたくさん登場している。
特に、アメリカ国内での旅行の話は、『ガンビア滞在記』にはほとんどなく、むしろ、短編という形で過去に発表されてきたものが多いので、過去の短編作品で知られるエピソードが、『懐しきオハイオ』には多く含まれているようだ。
ところで、この『懐しきオハイオ』、読み始めてから読了までに、2週間以上かかってしまった。
その間、モームやサローヤンなど、多くの小説を読んでいたことは確かだが、庄野さんの作品を読み終えるまでに、これほど長い時間を要したのは初めてである。
最初の場面の記憶があやふやになっているので、できれば、もう一度最初から読んでみたいと思っている。
書名:懐かしきオハイオ
著者:庄野潤三
発行:1991/9/25
出版社:文藝春秋
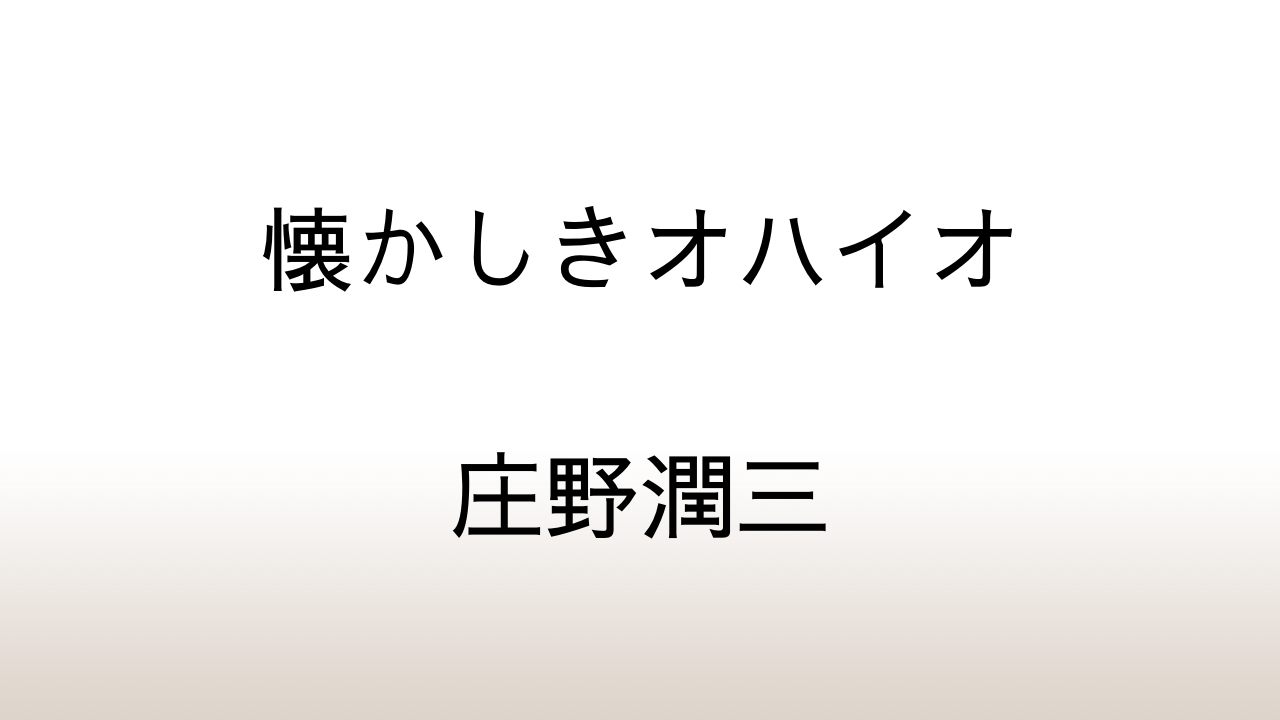
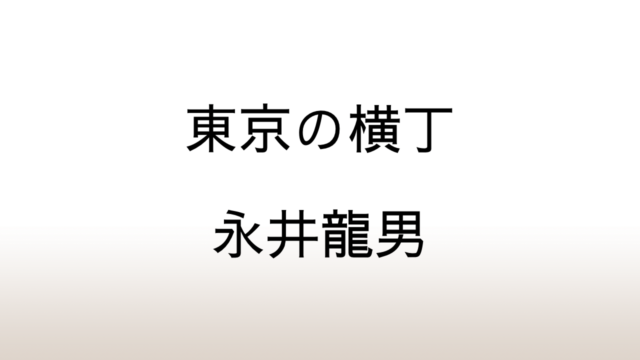
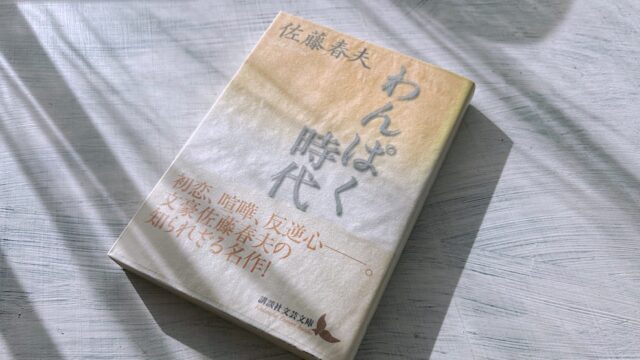

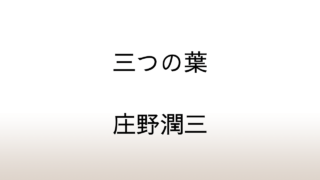

-150x150.jpg)









