「少女が大人になる時—その細き道」というテレビドラマがあります。
伊藤麻衣子主演の純愛ストーリーで、親友を裏切り続けた男女が、罪の重さに耐えかねて裏切りを告白するという、何やら重たい物語ではありました。
原作は、後に芥川賞を受賞する作家・高樹のぶ子「その細き道」です。
概要
『少女が大人になる時—その細き道』は、1984年(昭和59年)にTBS系で放送された連続テレビドラマで、原作は、高樹のぶ子さんの小説『その細き道』でした。
テレビドラマ『少女が大人になる時—その細き道』
テレビドラマの制作は大映テレビで、伊藤麻衣子のほか、金田賢一、利重剛、伊藤かずえ、松村雄基などが出演(全七話)。
大学入学のために単身上京した女子大生が、司法試験の勉強をしている二人の男子大学生と知り合い、三人の友人同士という関係を守り続けようとしますが、片方の男性と恋愛関係を持ちながらも打ち明けられずに、もう一人の男性を欺き続けるといった、純愛ラブストーリーとして描かれました。
原作小説『その細き道』
テレビドラマ『少女が大人になる時—その細き道』の原作は、高樹のぶ子さんの小説『その細き道』です。
高樹のぶ子さんは、1980年(昭和55年)に文學界新人賞候補となった後、『その細き道』を雑誌「文學界」に発表して小説家デビュー。
「その細き道」は、昭和55年(1980年)下半期の芥川賞候補となりますが、惜しくも受賞とはなりません。
ちなみに、この時の芥川賞候補作には、田中康夫「なんとなく、クリスタル」もありました。同年上半期には、村上春樹「一九七三年のピンボール」も候補作となっています。
高樹のぶ子さんは、その後、1984年(昭和59年)1月、『光抱く友よ』で、1983年下半期の芥川賞を受賞(笠原淳「杢二の世界」と同時受賞)。
テレビドラマ『少女が大人になる時—その細き道』が放送された時(1984年2~3月)は、原作者の高樹のぶ子さんが芥川賞を受賞した直後であり、話題性も十分のドラマだったと言えるでしょう。
なお、単行本『その細き道』は、1983年(昭和58年)9月、文藝春秋から刊行されています。
あらすじ
主人公の「中野加世」は、19歳の女子大生で、山口県内の高校を卒業して東京都内の女子短大に入学するために下宿生活を始めたばかり。
学校で親しい友だちを作ることもできず、孤独を紛らわすために山口県出身者の集まり(県人会)に参加しますが、その会場で司法試験合格を目指す男子大学生の「坪田精二」と出会います。
ちなみに、作者の高樹のぶ子さんは、東京女子大の短大を卒業しています。加世が通った大学も、東京女子短大がモデルになっていると思われます。
福井県出身の精二は、地元で政治家をしている父の代役として、この山口県の名士の集まりに参加していたのでした。
加世は、兄が妹を誘うような強引さで精二に呼び出されるようになり、少しずつ東京の暮らしに慣れていきます。
そんなとき、精二に紹介されたのが、精二の親友であり、精二とともに司法試験合格を目指す「阿部宏」でした。
宏よりひとつ年上の精二は、宏に「お前はどう見ても俺の弟に見える」「加世ちゃんは、お前の妹に見える」と言って、三人はまるで兄と妹のような関係を約束します。
東京での素敵な恋に憧れていた加世だったが、二人はまるで恋愛の対象ではありませんでした。
それは「学生運動の末端が新しい細胞を生み、親細胞から離反しては別のセクトを作っていた頃のこと」で、精二と宏は大学構内に立てられた立て看板を批判しながら「俺達はノンポリってのかな、心情三派ってのかな」「どっちでもないんじゃないの」などと話し合います。
その頃の三人の関係は、精二と宏が通う大学の近くにある「京」というコンパ屋のおばさんが、「あら、まあた三人なの、あんた達、仲がいいねえ」「本当に兄妹みたい」「だけどねえ、ほんと、あんたたち夢みたいだね」「仲が良すぎるってこと、何かこう、昔の小説みたいでさあ」などとうらやむほどでした。
「京」は本郷にあったので、精二と宏が通っていた大学は東京大学だったと思われます。京のおかみさんが言った「昔の小説」とは、いったい、どんな小説のことだったのでしょうか、、、
やがて、五月の初めに司法試験の短答式試験があり、二人とも失敗してしまい、宏は「来年が勝負だ」「留年も今年までだ」と悲壮感を漂わせます。
宏の実家は福井県の農家で、父が病気で動けないために、母と二人の弟が主に働いていたのです。
夏休みが終わって山口県から戻ってきたところで、加世は宏とともに精二の部屋へ食事に招かれますが、精二の部屋で料理の準備をしてくれた、まるで精二の姉のようにも見える若くて活動的な母親に、加世は圧倒されます。
中学生の時、テニスで母親に勝ったという精二の話を聞きながら、地方公務員の父や、病気で寝たきりになっていた祖父のことを思い出している加世。
精二の部屋を辞して、宏と二人で歩きながら、加世が「お金持ってると、人間って朗らかになれるのね」と言うと、宏は「金がないって平気で口に出せるのは幸せな方だ」と応えます。
宏の貧しかった子ども時代の話を聞いた後で、加世は宏と結ばれますが、宏は最後まで何かに躊躇しているようでした。
私ね—長い人生で一番正直になれるのは、今だ、って思う。正直にならなきゃいけないって思う。今、正直になれなかったら、この先、いくらでも嘘がつけそうで怖いの。(略)どんな女にも、一度はとことん正直な気持、とかね、澄んだ目を機会が与えられてると思うの。それが今なんだわ。こういう時のために、女だけ処女で生まれてくるんだわ。(高樹のぶ子『その細き道』)
すべてが終わった後で、宏は「精二は加世ちゃんと結婚するつもりだ」と打ち明けます。
散々女遊びをしてきた精二は、本気で加世ちゃんを愛しているからこそ、司法試験に合格するまで、加世ちゃんには決して手を出さないということを、宏に誓っていたのです
「衝動のまま突っ走って友達の大事なものを奪い、自分への制裁もできない男は、やはり負け犬だ」
宏と加世は、精二が司法試験に合格するまで、二人の関係は決して悟られまいと決意します。
三人は相変わらず兄妹のような関係を続け、加世は無邪気な妹を演じ続けますが、精二の何気ない一言一言が深い意味を持っているかのように思えてなりません。
精二のために隠しているはずの宏との秘密の関係が、いつしか加世には、二人の男性をもてあそんでいるだけようにも思えてきます。
宏が選び私が同意した道は、間違ってはいなかったかもしれない。だが、私達は失敗したのだ—。細く窮屈な道を全うするには、並々ならぬ心の緊張や覚悟が必要で、狎れあうことを潔癖なまでに遠ざけ、刃を自分達に向け続けるくらいの意志がなくては、思いやるために秘すなどということができるはずはなかったのだ。(高樹のぶ子『その細き道』)
題名の「その細き道」は、作品中の「細く窮屈な道」から。二人の関係を秘密にして、精二を欺き続けるという選択肢のことを意味しています。
いつか遠い将来「十九の自分に目をそむける老人にはなりたくない」「宏や精二にも、そんな思いをさせてはならない」と決断した加世は、冬のある日、直ちにすべてを精二に打ち明けるよう、宏を説得します。
数日後、加世の下宿を一人で訪れた精二は「俺は赦さない、赦したら、俺はおしまいだ」と言って、宏と加世の二人を罵倒し、そして、二人の前から姿を消してしまいました。
加世の「十九の自分に目をそむける老人にはなりたくない」という言葉は、夏目漱石の小説を思い出させます(『それから』から『門』へと続く作品群。主人公とその妻は、友人を裏切ったという罪を背負い続けて生き続けます)。
やがて、新しい夏が来て、宏は司法試験に合格しますが、精二が試験に落ちていたことを知って愕然とします。
精二が加代の前に姿を現したのは、加世と宏が一緒に暮らし始めたばかりの頃でした。
「君達と会うのは六カ月と十二日ぶりだ」と、精二が言います。
司法試験に不合格だった精二は、故郷の福井に戻って、勉強をし直すことにしたのです。
「精二は、私達を認めようとしている。こうして現れたからには、そうに違いない。決して赦すものかと言っていた彼が、この一年余りの時間を赦そうとしている」
そう考えた後で、加世はひとつの真実を悟ります。
生涯、精二という友人から、私達は逃げ出すことができないのだ。精二との繋がりをもって生きてゆくのだ、この重荷を、宏と二人で運び続けてゆく外はないのだと思った。私は、声を放って泣き出しそうになっていた。(高樹のぶ子『その細き道』)
三人の、新しい関係が始まろうとしていました。
読書感想と解説
この小説のテーマは「罪を償うこと」と「罪を赦すこと」の難しさだと思います。
「罪を償うこと」と「罪を赦すこと」の難しさ
宏と加世の罪は、精二に黙って肉体関係を結んでしまったことではなくて、むしろ、二人の関係を秘密にしながら、いつの間にか、精二の反応を探るようになってしまったという、その後の時間にあります。
清純な女性として描かれる加世が「三人で会うことに、最初のような、胸に針を刺すほどの痛みを自覚しなくなった」「私の甘えに反応する精二の昂りや、それを見ていても内側に押し込める外ない宏の嫉妬をかいま見て、面白がっていたものが、私のどこかにあったからではないか」「二つの心の上を転がりながら、どちらへともなく媚びていたものが、あったような気さえする」などと自己を追求していく場面は、この小説のポイントでしょう。
いざとなれば、宏の元へ逃げ込むことができる、そんな安全な場所から秘密を楽しんでいる自分を加世は激しく嫌悪し、「私の嫌な臭い」を振り払うために、すべてを打ち明けることを決心しますが、それは、もちろん、加世自身のためであって、精二を思いやる気持ちからではありません。
一方で「俺は赦さない、赦したら、俺はおしまいだ」と断言した精二が、最後に登場して、二人を赦したかのように見えますが、精二の登場は、それこそが二人の「罪」に対する精二からの「罰」なのだということを、加世は悟ります。
加世と宏は、生涯「精二に対する裏切り」という罪を背負って生きていかなくてはならない。
この作品では「償うことの難しさ」が、精二にとっての「赦すことの難しさ」とともに、克明に描かれているのです。
三人の三角関係と宏の裏切りは、夏目漱石の『こころ』にも似ていますが、「男女二人が罪を背負う」という意味では、やはり『それから』『門」の系統で考えた方が良さそうです。
少女から大人へと成長していく
精二が加世の下宿を訪れて「俺は赦さない、赦したら、俺はおしまいだ」と激しく罵った夜、「私を好きなようにすればいいのに」と思った加世の心の中にあったものは、精二への同情でも、精二に対する贖罪でもなく、それは明らかに加世自身が持つ性的な欲望でした。
『その細き道』では、少女が大人へと成長していく中で、自分自身の内に潜むものを、一人の女性が発見していく過程も、ひとつのテーマとなっています。
一見、清純で無邪気に見える加世ですが、肉体的な成長とともに、心の内側では大人の女の狡さを備えつつあり、そんな自分の狡さを「私の嫌な臭い」と表現して嫌悪するところに、少女の青臭さが感じられます。
清純な少女と狡猾な女性との間で揺れ動く様は、まさしく「少女が大人になる時」を描いたものと言っていいでしょう。
裕福な者と貧しい者
注目しておきたいのは、裕福な者と貧しい者との対比です。
作品中では、三人が大学構内の立て看板を見物に行って、精二が「俺達はノンポリってのかな、心情三派ってのかな」と、学生たちの活動を皮肉るシーンがあります。
恋愛小説の中で、この場面は時代背景を語る場面と読み取ることもできますが、「地方の政治家の息子である精二」と「東北の貧しい農家の息子である宏」との関係を考えたとき、大学紛争のエピソードは単なる時代設定以上の意味を持っているようにも思えます。
また、三人が並ぶときにはいつも「加世を挟んで左が宏、右が精二となる」ことが、わざわざ明らかにされていることも、何らかの暗示のように感じられないでしょうか(当たり前に考えると「左」は貧しい者の思想を暗示している)。
加世が宏と関係を持ったのは、精二の裕福で幸せな暮らしぶりを見た、その夜でした。
「お金持ってると、人間って朗らかになれるのね」という加世の言葉には、裕福な者に対する反発が込められているし、宏の貧しい子ども時代の話を聞きながら、加世は宏に抱かれたいという欲求を強くします。
加世の中の「貧しい者の側に立つ思い」が、宏と精二との関係に何らかの影響を与えたかもしれないということを、我々は忘れるべきではないような気がします。
テレビドラマと原作小説との違い
最後に、テレビドラマ『少女が大人になる時—その細き道』と原作小説との違いについて指摘しておきたいと思います。
テレビドラマ版は、基本的には原作小説のストーリーを忠実に再現していますが、「海野明子(伊藤かずえ)」と「一条信也(松村雄基)」の二人は、完全にドラマオリジナルの存在です。
中編小説を連続ドラマに仕立て上げる上で、話を膨らませる必要があったことと、この物語が「恋愛ドラマ」であることを強調する上で、二人の存在が必要になったということだと思います。
「恋愛ドラマであることを強調する必要があった」と書いたのは、そもそも、原作小説『その細き道』は、男女の恋愛をモチーフとしながらも、恋愛そのものをテーマとした文学作品とはなっていないからです。
先に述べたように『その細き道』のテーマは「罪と罰」であって、恋愛描写はモチーフでしかありませんが、アイドル主演のテレビドラマで、そんな複雑で難しいことをやっても視聴率には繋がらないので、シンプルな恋愛ドラマとして整理されたものでしょう(結果的に視聴率は低迷しますが)。
厳しいことを言えば、テレビドラマと原作小説との間ではテーマの齟齬が感じられますが、これは「テレビドラマあるある」なので、テレビドラマはテレビドラマとして楽しめばいいと思います。
加世が「罪の重さに耐えかねて、すべてを告白することを決意する」というテレビドラマの演出は、いかがなものかとは思いますが、、、(原作小説において、加世はそこまで単純な人間としては描かれていないし、内面に持った複雑で暗い欲望も、テレビドラマでは描かれていない)。
今さらながらに、原作小説は凄い作品だったんだなあと驚いています。
まとめ
ということで、以上、今回は、伊藤麻衣子主演のテレビドラマ『少女が大人になる時—その細き道』の原作小説について、全力で語ってしまいました。
皆さんも、ぜひ、原作小説を読んでみてくださいね。
書名:その細き道
著者:高樹のぶ子
発行年月日:1983/9/10
出版社:文藝春秋
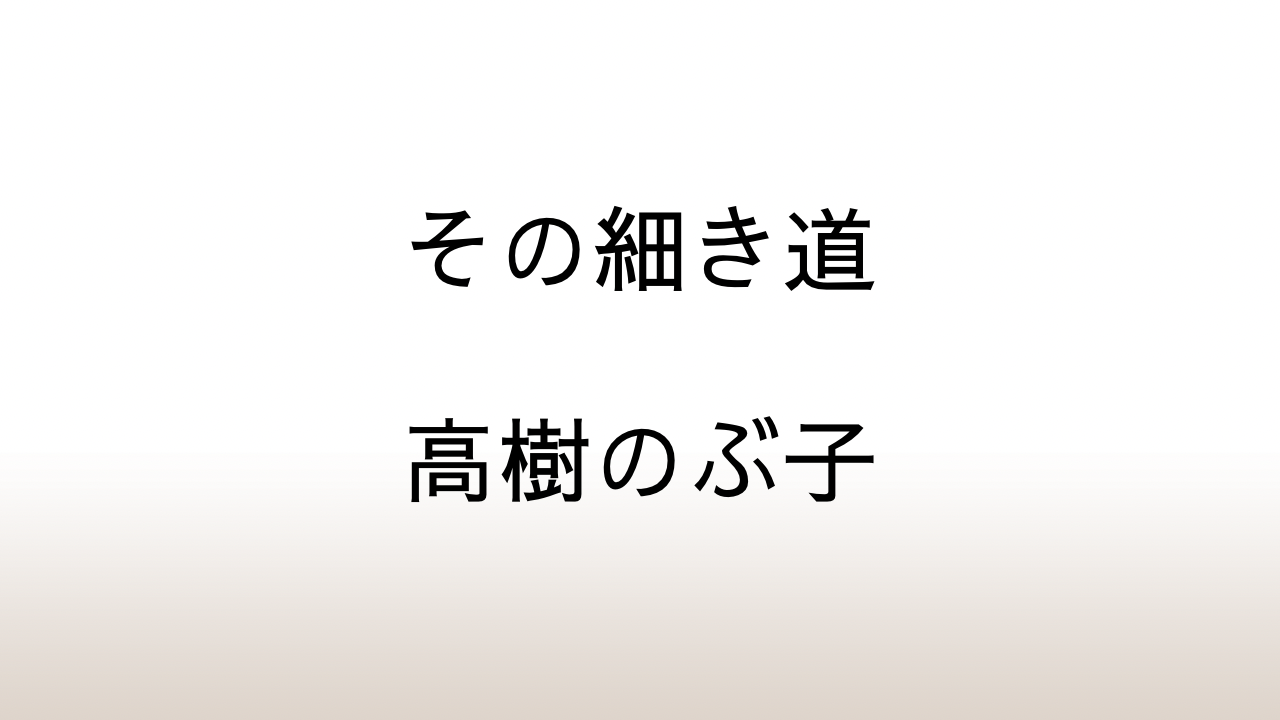
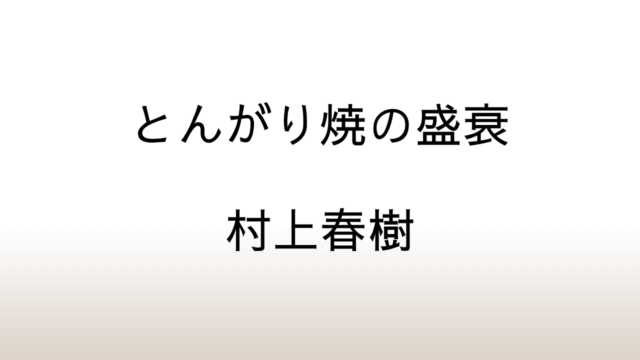




-150x150.jpg)









