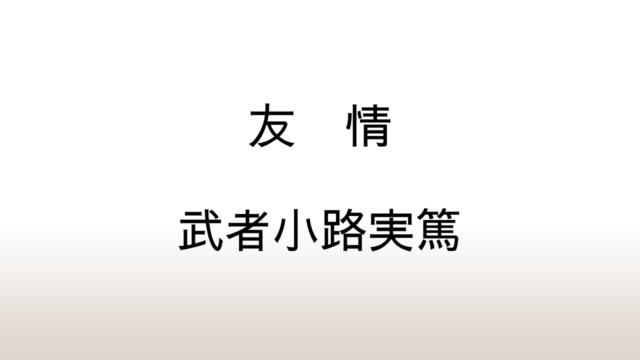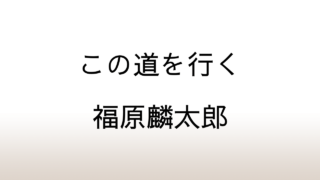井伏鱒二「還暦の鯉」読了。
本作「還暦の鯉」は、1957年(昭和32年)6月に新潮社から刊行された随筆集である。
この年、著者は59歳だった。
太宰治の褒め殺しに困惑する井伏鱒二
全部で37篇の随筆が収録されている。
講談社文芸文庫版では、巻末の「人と作品」を庄野潤三が担当している。
井伏文学の最も良き理解者の一人、と言っていい庄野さんの解説だから、おもしろくないはずがない。
『還暦の鯉』を井伏さんに頂いて、はじめて読んだとき、この「かに」と書いた女生徒の話が面白くて、何でもおかしみのある話を聞くのが好きな小学生の長女に私が話して、なぜおかしいかその訳を説明してやったら、長女がよろこんだことを思い出す。(庄野潤三「『還暦の鯉』の井伏さん」)
当時、石神井公園の麦畑の中の家で暮らしていた庄野さんは、自転車の後ろに長女(庄野夏子)を乗せて、ちょくちょくと荻窪清水町の井伏鱒二宅まで出かけていたという。
「人と作品」には、井伏鱒二と上林暁が将棋を指し、外村繫と青柳瑞穂がそれを見物している写真が掲載されているのもいい(昭和28年撮影)。
庄野さんの解説(というかエッセイ)を読んで、気持ちを盛り上げてから、井伏さんの随筆を読み始める。
表題作「還暦の鯉」は、東北方面へ鮠釣りに出かけたときの話で、ホテル鎌倉という温泉旅館の裏を流れている阿武隈川支流の白石川は、蔵王山の雪解け水で谷川が増水していて、ほとんど釣りにならなかったという話は、井伏さんに同行していた小沼丹も、自分の作品で書いているものだ。
「この鯉は、ここに来てから三十年たちます。ちょうど三十歳のときこの池に来たんですから、今年で六十歳になります」と長谷川さんが云った。「では、還暦の鯉でございますね」と、私は改めて悠然たる態度の鯉を見た。(井伏鱒二「還暦の鯉」)
翌日、上ノ山温泉の近くの長谷川さんという旧家を訪ねて、個人博物館を見学した一行は、裏庭の瓢箪池で大きな鯉とアカハラを目にする。
「還暦の鯉」というのは、そのときに見た大鯉の一匹で、短いけれども、紀行文の得意な井伏さんらしい作品に仕上がっている。
旅行記では、小沼丹や吉岡達夫と一緒に、富士川下流の下部川へ行き、不二ホテルという鉱泉宿に泊まったときの話もいい。
失敗した原稿を谷川へ投げ捨てながら、井伏さんは、一人の詩人を思い出していた。
やっとその仕事が終って石崖の上に這いあがると、ふと石川隆士という人の詩の句を思い出した。「渓流」という題の詩であるが、やはり谷川に紙ぎれを投げ棄てるところを書いたものである。しかし、石川君の場合は、書きそこねた原稿ではなくて温泉宿で無情な恋人宛に書いた恨みの手紙を破いて谷川に棄てる。(井伏鱒二「九月二十日記」)
井伏さんに同行して下部温泉へ行った話は、小沼丹も書いているし、井伏さんの弟子の一人だった石川隆士のことは、小沼丹の短篇小説「翡翠」に詳しい(『埴輪の馬』所収)。
▶ 小沼丹『埴輪の馬』古い記憶を乗せて回る走馬灯~最後の短篇集
ただし、小沼丹の小説では「翡翠(とり)になれ、翡翠(とり)になれ」とルビを振ってあるところ、井伏さんは「カワセミになれえ、カワセミになれえ」と記している。
宿に引き返した井伏さんは、同行の小沼丹に「紙ぎれは石川君のカワセミの詩のように都合よく川に飛ばないね。あれは嘘だ」と言ったそうである。
作家仲間の話としては、まだ元気だった頃の牧野信一にいじめられた井伏さんが、何度も(三回も)泣いたという話がある。
それでも牧野さんは私を捻るのを止さなかったが、谷崎さんが「なんだ牧野君、葛西善蔵の真似じゃないか。葛西そっくりだね」と云うと、牧野さんは口をつぐんだ。(井伏鱒二「牧野信一」)
牛込鶴巻町の喫茶店で油をしぼられているときは、たまたま通りかかった谷崎精二が助けてくれた。
久保田万太郎に連れられて行った浅草の料亭で捻られたときは、河上徹太郎が一緒だった。
「私はこてんこてんにやりこめられ、わあわあ泣きながら外に駆け出して」と、井伏さんは当時を回想している(恐ろしい、、、)。
一番弟子だった太宰治についての話もある。
1940年(昭和15年)7月12日の夜に、谷津の南京荘で大洪水に遭った話は「南京荘の将棋盤」に書かれている。
私は二階に駆けあがり、そのとき同宿していた亀井勝一郎の寝ている部屋に駆けこんだ。すると離れに泊っていた同宿者の太宰治夫妻が駆けこんで来た。太宰は畳の上にきちんとかしこまって、「人間死ぬときが大事だ。パンツをはいておいで」と細君に云った。(井伏鱒二「南京荘の将棋盤」)
しかし、より太宰治の人間性を示していると思われるのは「社交性」という一篇だ。
「青ケ島大概記」という実話ものを書いているとき、太宰治と中村地平が将棋を指しにやってきた。
将棋が終わって、中村地平が眠ってしまった後、太宰は井伏さんの執筆を少しだけ手伝って口述筆記をした。
そのときのことが「『井伏鱒二選集』後記」に記されている。
私はそれを一字一字清書しながら、天才を実感して戦慄した。私のこれまでの生涯に於て、日本の作家に天才を実感させられたのは、あとにも先にも、たったこの一度だけであった。「おれは、勉強しだいでは、谷崎潤一郎には成れるけれども、井伏鱒二には成れない」私は、阿佐ヶ谷のピノチオという支那料理店で酔っ払い、友人に向かってそう云ったのを記憶している。(太宰治「『井伏鱒二選集』後記」)
ところが、太宰の指摘する「一字一字清書しながら、天才を実感して戦慄した」という部分は、参考にした資料からそのまま抜き取った部分で、口述筆記を手伝った太宰治が、そのことを知らないはずはない。
無論、私は選集が出たときそれを読んだ。例の社交性によって不当の讃辞に似たものを書き並べているのだが、その選集が巻を追って出るごとに私はびくびくもので読んだのを覚えている。太宰君は嘘の話まで持ち出してお上手を云う。その手口を知っているからこちらはびくびくものである。(井伏鱒二「社交性」)
「何て意地の悪いいたずらを云うのだろう」とつぶやくところに、太宰の褒め殺しに困惑している井伏さんの姿が見えるようだ。
「傑作なんていうものが書けるとしたら僥倖だ」
自作の解説に類する文章は、作品理解の一助となるものだ。
名作「さざなみ軍記」を書くにあたり、井伏さんは平家物語を通読しているが、この本は吉岡達夫から借りてきた南蛮本平家物語抄だった。
当初の構想では、主人公の公達が生野あたりに疎開定住するというエンディングを考えていたが、やがて太平洋戦争が始まって、本当の疎開騒ぎの時代が来てしまった。
このころ疎開が流行した。そこで私の物語の公達が疎開すると、いかにも流行を真似て書くような気がしたので、あとは尻きれとんぼのまま終りということにした。もっとも戦争中は戦乱を悲惨だと書いては某筋から睨まれるので、触らぬ神に祟りなしの考え方も手伝っていた。(井伏鱒二「「平家」と自分に関すること」)
「さざなみ軍記」は、学校時代の知人(柿沢君の妹の同級生)の家に伝わる「先祖の書きとめた古い日記」がヒントになって生まれたと、井伏さんは明かしている。
戦争中に徴用された際の経験も、多くの作品に投影された。
私は戦争中に徴用されてマレーに行き、シンガポールの徴員宿舎で「花の町」という小説を書いて「東京日日」と「大阪毎日」に連載した。材料は当時シンガポールに進駐していた日本兵や徴員や、それに接触関係のあった華僑やマレー人の少年などとの交渉いきさつである。(井伏鱒二「「が」「そして」「しかし」」)
徴用中の体験については、長篇『徴用中のこと』に詳しい。
▶ 井伏鱒二「徴用中のこと」太宰治に見送られて出発したシンガポールが陥落した日
「花の町」の前々年には「おこまさん」を書いている。
この小説を書く前々年には、私は甲州の釣宿で「少女の友」という雑誌に連載する「おこまさん」という作品を六回ぶん書いた。そのころ私の書いたもののうちでは、枚数が長いという点で自分には印象の深い作品だが、これが芳しくない出来であったことを自分で自分に弁解する理由は幾つか挙げられる。(井伏鱒二「「が」「そして」「しかし」」)
戦前のバスガールを主人公とする『おこまさん』(1940)は、今、読んでも楽しい物語である。
▶ 井伏鱒二『おこまさん』甲府のバスガールが主人公の戦前少女小説
1985年(昭和60年)から1986年(昭和61年)にかけて『井伏鱒二自選全集』が出たとき、収録の選に漏れた作品は少なくない。
先の「青ケ島大概記」や「おこまさん」なども、やはり収録されることのなかった作品である(意外と読者の読みたい作品が入っていない)。
この随筆の中で「私は自分の参考にするため、手づるを求めて尊敬する某作家の組版ずみの原稿を雑誌社から貰って来た。十枚あまりの随筆である」と書いてあるのは志賀直哉のことで、後の対談においても、井伏さんは、志賀直哉の校正原稿の話を持ち出している。
自分の希望するのは、文体の浄化というよりも、書きたい材料に巡りあわすことである。以前、私は学生のとき友人仲間の古参と見られている人の影響を受け、小説を読むときには筋書を読んでは駄目、書くときには筋書で書いては駄目だと思いこんでいた。映画を見ても、すぐ筋書を忘れるのが本当だと思っていた。(井伏鱒二「「が」「そして」「しかし」」)
「映画を見ても筋書きを覚えてるようじゃだめだ」と諭したのは、横光利一だったらしい。
当時は葛西善三に人気のあった時代で、小説は筋書きで読ますものではない、といったような風潮があったのだろう。
「現在では私は筋書が欲しい」「材料を見つけることも才能のうちに入れられる」と、井伏さんは綴っているが、井伏鱒二の文学を理解する上で、この「「が」「そして」「しかし」」という随筆は、是非とも一読しておくべき作品だろう。
井伏文学という点では「記者のいろいろ」にも注目したい。
私にしてみると、悪循環だろうが何だろうが、百も二百も短篇を書いているうちに、たった一度でも僥倖で快心の作が出来ればもうそれでいい。傑作なんていうものが書けるとしたら僥倖だ。宝くじを引くようなものである。(井伏鱒二「記者のいろいろ」)
「井伏鱒二は、作品をたくさん書く。それはべつに偉いと思わないが、駄作を書かないのはたいへん偉い」と言ったのは谷崎精二だが、その井伏鱒二にして「傑作」を生み出すことは容易ではなかった。
「傑作なんていうものが書けるとしたら僥倖だ」という言葉には、文学の難しさを知り抜いているからこその真理がある。
もちろん、井伏さんは、最初から「傑作を書こう」などとは思っていなかったのだ。
読者を楽しませることのできる文学は、傑作ばかりとは限らない。
そこに、井伏鱒二という作家の稀な存在性があるのではないだろうか。
書名:還暦の鯉
著者:井伏鱒二
発行:1992/10/10
出版社:講談社文芸文庫
文芸エッセイの世界をより深く知りたい方へ
大人の随筆の世界をもっと知りたい!という方に、おすすめの記事を用意しました。
アナクロで粋な昭和エッセイの世界を極めてみませんか?
大人のための随筆(エッセイ)案内
昭和文学を中心に、大人のための随筆(エッセイ)を集めました。
教養ある「粋」な大人になりたい方に、超おすすめのマニアックな文芸世界です。
▶ 大人のための随筆(エッセイ)案内|教養ある大人が嗜むべき名作の歩き方ガイド