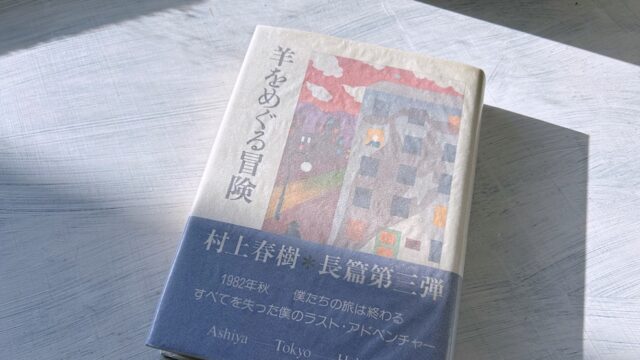村上春樹「街と、その不確かな壁」読了。
本作「街と、その不確かな壁」は、1980年(昭和55年)9月の『文学界』に発表された中篇小説である。
この年、著者は31歳だった。
なお、全集を含め、作品集には収録されていない。
元カノとのセックスが忘れられないでいる男のモノローグ
本作「街と、その不確かな壁」は、壁に囲われた街へ行った<僕>が、<君の影>と出会い、恋をしながらも、<君の影>と別れて街を出るまでの物語である。
一般的に、村上春樹の小説には意味不明の部分が多いことが特徴であるが、本作は、著者の伝えたいことが、作品中にきちんと書かれている。
僕はかつてあの壁に囲われた街を選び、そして結局はその街を捨てた。それが正しかったのかどうか、いまだに僕にはわからない。(村上春樹「街と、その不確かな壁」)
「壁に囲われた街」は、<僕>のかつての恋人自身であり、<僕>は彼女を選び、彼女を捨てた、という過去を持つ。
だから、<僕>が街の図書館で読む「古い夢」は、彼女との思い出であり、彼女との思い出に浸りながら、<僕>は「たまらなく君に会いたかった。君を抱きしめ、そして君と交わりたかった」と、元カノへの思いを鮮明にしている。
あるいは「壁」は、元カノの女性自身=子宮の象徴と読むこともできる。
<僕>が壁の中へ入る行為は、恋人とのセックスそのものだから、<僕>は彼女の肉体を思い出しながら、彼女との思い出を忘れられないでいるわけだ。
要約すると、「街と、その不確かな壁」は、元カノとのセックスが忘れられないでいる男の孤独と未練によって構築された妄想、ということができるかもしれない(身も蓋もない言い方になってしまうが)。
「元カノへの未練」を小説にするため、村上春樹は、壁に囲われた街や金毛の獣たちを登場させて、感傷的なまでに美しい言葉を並べているのだが、残念ながら、それ以上の深まりがない。
この作品が、一切の作品集に収録されることなく、幻の作品となってしまったことには、そんな理由があるような気がする。
『風の歌』や『ピンボール』と異なった世界観
「街と、その不確かな壁」の前に村上春樹が発表している作品は、『風の歌を聴け』(1979)と『1973年のピンボール』(1980)の長編小説2編に、「中国行きのスロウ・ボート」(1980)という短篇小説1編、計3作品である。
しっかりとした枚数のものとしては、『風の歌』『ピンボール』に続いて3作目ということになるが、作品としての毛色は、鼠シリーズの前2作品とは、かなり異なっている。
もしも、僕が村上春樹のリアルタイムの読者であって、当時、この小説を雑誌で読んでいたとしたら、正直に言って、がっかりしたかもしれない。
それは、「街と、その不確かな壁」の作品としての完成度に問題があるということではなく、『風の歌』や『ピンボール』と異なった世界観を受け入れることが難しかったことが想像されるからだ。
現代になって当時の作品を読み返してみると、「街と、その不確かな壁」は、しっかりと村上春樹の作品だということが分かる。
だけど、1980年の時点で、村上春樹は、やはり『風の歌』や『ピンボール』の村上春樹だったのだ。
結局、村上春樹は「街と、その不確かな壁」を捨て、1982年(昭和57年)、『羊をめぐる冒険』を発表して、『風の歌』の世界観にケリをつける(鼠三部作の完成)。
そして、1985年(昭和60年)、「街と、その不確かな壁」をベースに使った長編小説『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』により、新たな世界観の創造に成功する(第21回谷崎潤一郎賞受賞)。
後世の読者として、この流れはまったく必然的に思われるが、著者自身の中では、様々な葛藤があったのかもしれないと、「街と、その不確かな壁」を読み終えて感じた。
村上春樹の作品を全部読んでしまったという人には、図書館で借りて読むだけの価値があるのではないだろうか。
作品名:街と、その不確かな壁
雑誌名:文学界 1980年9月号
著者:村上春樹
出版社:文藝春秋