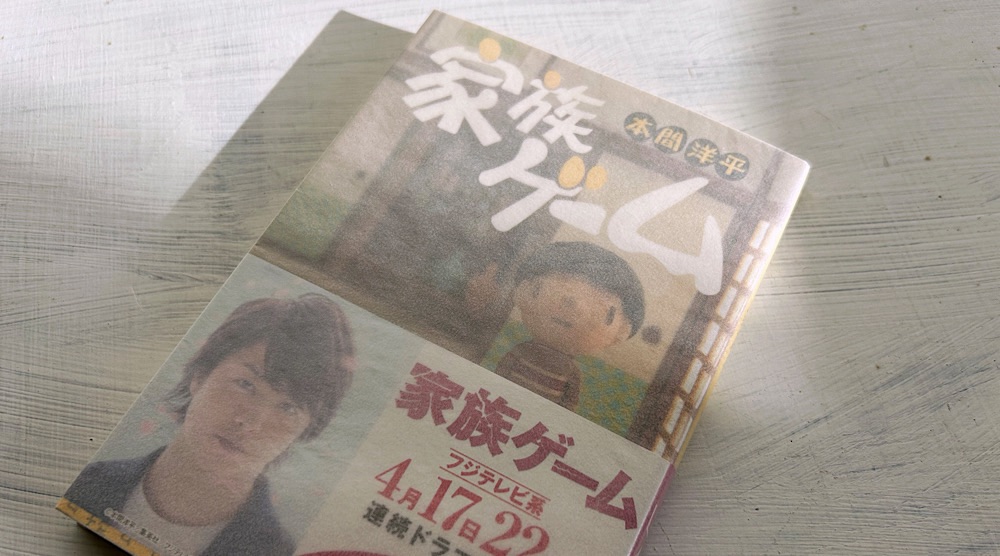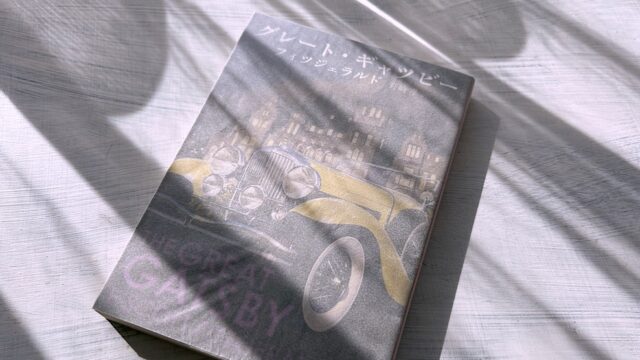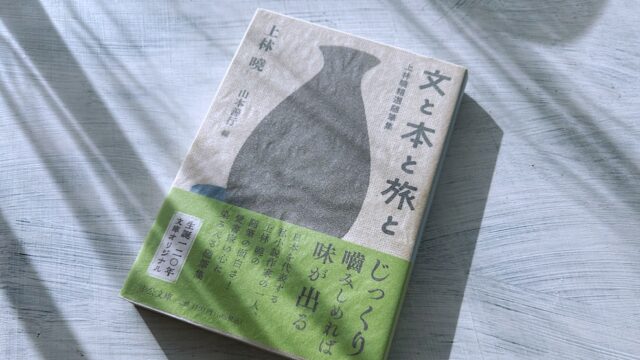本間洋平「家族ゲーム」読了。
本作「家族ゲーム」は、1981年(昭和56年)12月『すばる』に発表された長篇小説である(初出時の作品タイトルは「枡の中に駒が並んで」)。
この年、著者は33歳だった。
単行本は、1982年(昭和57年)1月に集英社から刊行されている。
1981年(昭和56年)、第5回すばる文学賞受賞。
1982年(昭和57年)、鹿賀丈史主演テレビドラマ『家族ゲーム』原作小説。
1983年(昭和58年)、松田優作主演映画『家族ゲーム』原作小説。
1983年(昭和58年)、長渕剛主演テレビドラマ『家族ゲーム』原作小説。
2013年(平成25年)、櫻井翔主演テレビドラマ『家族ゲーム』原作小説。
現代社会を象徴的に描いた80年代の社会小説
冒頭、劣等生の弟(沼田茂之)が、将棋の駒を激しく振る場面がある。
両腕を振りながら、比較的大きなそのボール紙に駒を投げ出し、王将二枚だけ表になると一枡黒く塗りつぶす。投げ出しては拾い、拾っては投げ出し、同じ試みを繰り返していく。しかしまだ、一列も黒く塗りつぶされていない。(本間洋平「家族ゲーム」)
現実逃避のために弟が熱中しているゲームは、もちろん、この物語の主人公である沼田家(4人家族)を投影したものだ。
落ちこぼれのいじめられっ子である弟(茂之)にフォーカスされがちだが、この物語は、沼田家という団地族の一家を描いた物語である。
「家族ゲーム」(つまり「沼田家ゲーム」)という遊びの中で、家族は、誰もがプレイヤーであり、誰もが「駒」でもある。
弟が振る「王将二枚」は、兄(沼田慎一)と自分自身(茂之)であるとともに、父や母でもあったかもしれない。
ゲストプレイヤーとして、沼田家に闖入してきた家庭教師(吉本)は、「沼田家ゲーム」の中では「特殊アイテム」として機能する(ゲームの結果を変えるまでには至らなかったが)。
最終場面近く、志望校に合格した弟が登校拒否になったとき、家庭教師がゲームを総括している。
「ああ、やっぱりね、おれ、何とかしてあげたいけど、一時的に強制しても、同じことなんだなあ。……結局、家庭のいう枠のなかでね、それぞれの人たちが、互いに作用し合って、生きてきて、その結果、茂之君が、今のように、育ってきたわけなんだから」(本間洋平「家族ゲーム」)
5人目の家庭教師として登場した吉本は、鉄拳制裁により、無気力な弟の学力を向上させることに成功したが、沼田家そのものを変えることはできなかった。
沼田家を変えるためには、父や母もまた、変わる必要があったのだ。
吉本が、そのことに気づいたのは、志望校の変更を自分から行おうとしなかった弟を、学校の職員室でボコボコにしたときである。
「失敗だった、おれのやり方は、……おれは、やっぱり、受け入れられなかったんだなあ、……」(本間洋平「家族ゲーム」)
ゲストプレイヤーの吉本もまた、この「沼田家ゲーム」の敗北者だった。
誰一人として勝利者のいないゲーム、それが、沼田家の「家族ゲーム」だったのだ。
もっとも、団地で暮らす沼田一家は、この団地の象徴であり、あるいは、現代社会の象徴にすぎない。
この物語で描かれているものは、現代社会そのものの敗北だったからだ。
弟の部屋には、零式戦闘機(いわゆるゼロ戦)のポスターが貼ってある。
「おい、茂之、ゼロ戦って、操縦者の防備と燃料タンクの防備は、いっさい省略されただろう、だから、攻撃しているときはよいけど、いったん守勢にまわったら一発でアウト」(本間洋平「家族ゲーム」)
太平洋戦争では、日本海軍のヒーローとして活躍したゼロ戦も、決して万能ではない。
「新幹線もそうだろう、速いのは結構だけど、ちょっと何かあるとすぐアウト。日本人の造りだすものって、一つの機能だけ重視して、その他はおかまいなし。どこか余裕がないんだ」(本間洋平「家族ゲーム」)
兄(慎一)が非難しているのは、もちろん、自分たちの両親であり、現代の日本社会である。
それは、「勉強さえできればいい」(突き詰めると、「受験さえうまくいけばいい」)と信じている、日本の学歴社会への警告だ。
弟(茂之)が愛用している天体望遠鏡も、限られた視野しか持たない現代人の投影として読むことができる。
「ところで、Z大学へ七年、いってるんだって? いったい何、やってるんだい」(略)「いや、これといって、別に、……」「まったく、Z大学で、七年じゃ、……親が泣いてるだろう」(本間洋平「家族ゲーム」)
(三流私大の)Z大学へ7年間も通っている家庭教師(吉本)は、(少なくとも沼田家の父や母にとって)現代社会の落ちこぼれだが、彼は、救いようのなかった弟の成績を上げてみせる。
三流私大の家庭教師が、落ちこぼれの成績を上げて、進学校へ合格させるという構図は、既に、学歴偏重の現代社会に対する、鋭い皮肉だ。
「どこへ行くんですか」ぼくはアフリカ旅行のパンフレットを見ながら訊いてみた。「ちょっとシルクロードへ行って、できれば、北アフリカの沙漠も、まわってみたい、と思ってるんだどね」(本間洋平「家族ゲーム」)
現代社会のアウトローである吉本は、自身が大学生であり、家庭教師でありながら、学歴社会の中で生きようとはしていない。
「とにかく、朝起きてから、夜寝るまで、毎日同じじゃあ、飽きちゃうじゃないか。テレビや映画だって、毎日毎日同じもの見てたら、気が狂いそうになるだろう。食べるものだってそう、会う奴だってそう、……少しぐらい眼先を変えたいじゃない」(本間洋平「家族ゲーム」)
異端児・吉本の生き方は、両親の期待どおりエリート社会への道を歩む兄(慎一)に、新しい価値観を持たせるきっかけとなった。
特殊アイテム「吉本」の投入は、「沼田家ゲーム」にとって、実は、危険な賭けだったのだ(結果として、最悪の手となった)。
この物語は、父・母・兄・弟という四人の家族によって構成される「沼田家」をモデルに、互いを「駒」として駆け引きしながら生きる現代社会を象徴的に描いた、80年代の社会小説である。
いじめられっこの中学生が主人公だからといって、安易に、この物語を「青春小説」とは呼びたくない。
家族ゲームの主人公は、父でもあり、母でもあるのだから。
現代社会の「家族ゲーム」に勝者はない
一方で、体罰も厭わずに弟(茂之)の成績を上げていく家庭教師(吉本)は、現代(80年代)管理教育の象徴でもある。
「テストを言わなかった分、五発、宿題を忘れた分、五発、計十発」ハート型になった細い棒の先が、弟の厚い肉のなかに食い込み、弟はそのたびに、うえっ!という奇声を発する。(本間洋平「家族ゲーム」)
1970年代後半から1980年代にかけて、中学校を中心として「荒れる学校」が社会問題化する日本では(いわゆる「校内暴力」の時代)、教師による体罰を容認する徹底した管理教育が推奨された。
鉄拳制裁で、弟(茂之)の成績を上げる家庭教師(吉本)の手法は、明らかに、80年代日本の学校教育を象徴するものだ。
「殴らなきゃ駄目だ。殴るのは、いいことだよ。今までの奴らは、殴らなかったから、駄目だったんだよ」(本間洋平「家族ゲーム」)
「殴らなきゃ駄目だ」という父の言葉は、体罰を歓迎する世の中を反映している。
あるいは、それは、激しい校内暴力を放置してきた学校教育に向けて発せられた言葉だったかもしれない。
武田鉄矢主演『3年B組!金八先生』でも体罰は容認されているように、肉体と肉体とがぶつかり合う体罰は、ある意味「人間的な指導方法」として受け容れられていたのではないだろうか。
もっとも、現代社会の闇を生み出す根源は、やはり、家庭教育である。
「どう思います、今度の人?……ん」「なにが?」母に向けた父の眼には、驚くほど表情がない。ぼくは嚙み合わない二人の会話を、黙って聞いていた。(本間洋平「家族ゲーム」)
「家族ゲーム」は、夫と妻による、駆け引きのゲームである。
弟はぼくの顔を見ながら大声で笑った。ぼくらは父と母のつくった秤にのせられ、絶えず目盛の動きを観察される。弟の笑い声の大きさは、その目盛の動きを示すものだった。(本間洋平「家族ゲーム」)
ゲームの中で、互いは、それぞれの「駒」にすぎない。
いかに、子どもたちを進学校へ送り込むかというゲームの中で、夫婦は、互いの駆け引きを繰り返していたのだ(世の中は、それを「子育て」と呼ぶ)。
「どいつもこいつも、馬鹿野郎で、俺は、そんなガキども、育てた覚え、ねえぞ!」(本間洋平「家族ゲーム」)
「A大にいかなけりゃ、意味がねえぞ」と言い続けてきた父は、登校拒否になった兄弟を見て、「そんなガキども、育てた覚え、ねえぞ!」と、過去の積み重ねを否定してみせる(ゲームオーバー)。
「あら、……そんな、……無理やり、だなんて、……」母は跡切れ跡切れの言葉とともに、眼を見開きぼくの心を覗こうとするように、訝し気な視線を向けてきた。「誰も、強いたことなんて、ありませんよ。母さんは、世間の教育ママとは、違います」(本間洋平「家族ゲーム」)
一方で、「勉強は、あたしたちのためじゃなくて、自分のためでしょ、自分の」と言い続けてきた母は、「慎一、……お願いだから、……母さんのために、……学校へ、行っておくれ」と泣き崩れる(ゲームオーバー)。
二人の駆け引きの積み重ねが生み出したもの、それが、登校拒否となった、二人の高校生だった。
もちろん、二人は、現代社会のルールに従って、現代社会の「家族ゲーム」に向き合ってきたにすぎない。
二人にとって、(三流私大の家庭教師のように)現代社会の「家族ゲーム」から降りるという選択肢は、もはや存在しなかったのだ。
後半、ゲームに破れた家庭教師が、「あいつは糞で、徹底的に、外側へ出てこられなくなったんだ」と呟く場面がある。
生徒たちは一斉に弟を見つめた。そのとき、液状の汚物が流れ出る。躰中の力が抜けたのだ。(本間洋平「家族ゲーム」)
授業中、教室で糞を垂れた事件は、その後も、弟(茂之)の自信を回復させることはなかった。
「あいつは糞で、徹底的に、外側へ出てこられなくなった」のだ(外傷性ストレッサー)。
しかし、トラウマ(心的外傷)を抱えているのは、果たして、弟だけだったのだろうか。
ぼくは自分のことを考えてみた。外側へ出られないのは、弟だけではない。(本間洋平「家族ゲーム」)
兄(慎一)は、予想が立たなければ、外側へ出ることを、最大限に避けようとする人間になった。
あるいは、それは、父や母にも言えることだったのではないだろうか。
若い頃に苦労して、小さな自動車整備工場を持つに至ったという父と、若い頃に夢中だった絵と文学をあきらめて、自動車整備工の夫と一緒になったという母と。
外側へ出られないのは、弟だけではなかったのだ。
現代社会の「家族ゲーム」に勝者はない。
弟は躰を震わせ駒を投げ出すこともせず、腕と手のひらを振り続けている。考えることも、まわりの現実も、すべてそれで消そうとしているのだろう。(本間洋平「家族ゲーム」)
物語は、その始まりと同じように、弟(茂之)が将棋の駒を振り続ける場面で終わる。
まるで、ゲームから逃れることのできない家族を象徴しているかのように。
書名:家族ゲーム
著者:本間洋平
発行:1984/03/25
出版社:集英社文庫