ツルゲーネフ「ベージンの野」読了。
「ベージンの野」は、庄野潤三『エイヴォン記』の第二回目で登場する、ツルゲーネフの短篇小説である。
あらすじとしては、猟の帰りに道に迷った「私」が、馬の群れの番をしている百姓の子どもたちと一夜を過ごすという物語。
ポイントは三つで、ひとつめは、夕暮れから夜明けにかけての自然描写が非常に美しいこと。
「朝が始まりかけている。暁の紅はまだどこにもさしていないが、東の空はもう白みかけている。ぼんやりながらも、あたりのものが何もかも見えるようになった。淡い灰色の空が明るくなり、冷たくなり、青くなっていく」は、一夜が明けた瞬間の描写。
ふたつめは、一緒に夜を過ごした五人の少年たちの描写がリアルで親しみのあること。
彼らのある者は裕福であり、ある者は貧しく、ある者は器量よしで、ある者ははなはだふるわないが、「鉤鼻で、間のびがしていて、弱視で、つまりその顔はどことなく愚鈍な、病的な懸念といったものを表していた」のように、著者は一人一人の少年のキャラクターを丁寧に構築していく。
もっとも、この小説の最大のポイントは、そのような著者の表現力にあるのではない。
「ベージンの野」最大のポイントは、一夜を通して語られる少年たちの会話の中で、少年たちの暮らす村で流布している様々の奇妙な噂話である。
ワーシャのお母さんは、ワーシャが水で死ぬということが分かっていて、ワーシャが川遊びに誘われることを極度に警戒していたのに、お母さんが乾草を掻き寄せている隙に、どうしてか川で溺れて死んでしまった。
ワーシャのお母さんが狂ってしまったのは、つまり、ワーシャの死んだ場所に寝転んで、ワーシャがいつも歌っていた、あの歌を歌い、それからさめざめと泣きながら神様に恨み言を言うようになったのは、それからだ。
「天のお知らせ」(日蝕のことを昔はこう呼んでいた)があったとき、女中部屋の料理人の婆さんたちは、ありったけの壺を持ち出して、かまどの中にぶちこみ、火箸で粉微塵に叩き壊してしまった、「世の終わりがやって来たんだから、今さら物を食う人もいなかろう」って言いながら。
先祖の日の夜に、教会の入口に立って、じっと街道を見ていると、その年に死ぬ者が教会の脇の道を通るというので、去年はウリヤーナ婆さんが教会の入口へ見に行ったが、ウリヤーナ婆さんが最初に見たのは、この春に死んだ男の子(フェドセーエフ)で、次に見たのが、なんとウリヤーナ婆さん自身だった。
ガヴリーナが、あんなふうに陰気な男になってしまったのは、水の精の誘いを断ってしまったから。
道に迷って森の中で眠っていたガヴリーナが、水の精に誘われかけて、とっさに十字を切ったとき、水の精は悲しい顔をして「私が泣いているのは、嘆いているのは、お前が十字を切ったからだ」「お前が十字を切らなかったら、一緒に生涯楽しく過ごせたのに」「私一人が嘆くようなことはしないさ。お前も生涯嘆くようにしてやるから」と言い残し、消えてしまったのだという。
少年たちは、村の誰かが幽霊や魔物に出会ったというような不思議な話を、次から次へと繰り出しては「こりゃおったまげた!」「それは不思議だなあ!」などと言い合っては身震いしている。
物語の語り手である「私」は、こうした少年たちの話に加わることもなく、何かの論評を加えることなく、ただ、会話の内容を聞きながら夜が明けるのを待ち続けたが、この作品は、こうした少年たちの会話を中心にして構成された短篇小説である。
そこには、不思議な伝説を通して語られる人間の生命のはかなさや人生というもの切なさがある。
庄野さんが、この物語を選んで紹介した気持ちが、分かるような気がした。
『猟人日記(上)』(岩波文庫・佐々木彰訳)は版元品切れ
「ベージンの野」は、『猟人日記(上)』(岩波文庫・佐々木彰訳・1956年)に収録されている。
ツルゲーネフの定番作品ではあるが、岩波書店の公式サイトでは「品切れ」と表示されており(いわゆる「版元品切れ」の状態)、「絶版」でこそないものの、書店での入手ははなはだ困難と思われる。
管理人が古本屋で見つけてきたものは「1989年1月17日・第14刷」で、数はそれなりに出ているから、古書店やインターネットで探せば入手は可能だろう。
庄野さんの読書体験を再現しようと思うと、書籍の入手の段階で、かなりの困難を伴うことが多い(岩波文庫も「品切れ」が多くて苦労する)。
入手の難しいものは、図書館を利用するなど、柔軟な対応が必要になりそうだ。
書名:猟人日記(上)
著者:ツルゲーネフ
訳者:佐々木彰
発行:1958/05/06
出版社:岩波文庫
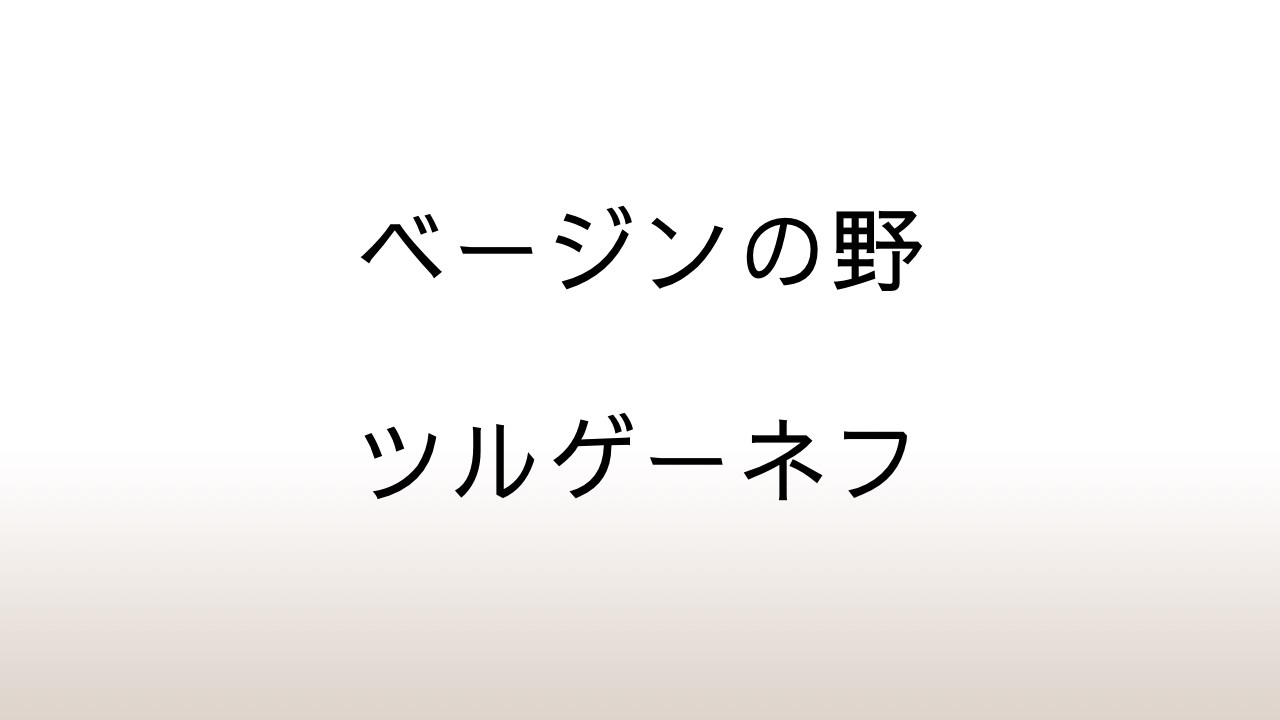
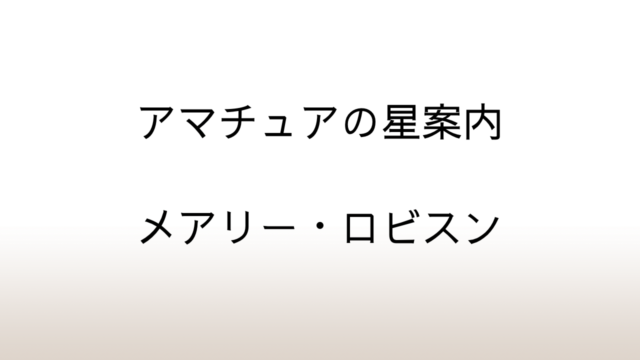
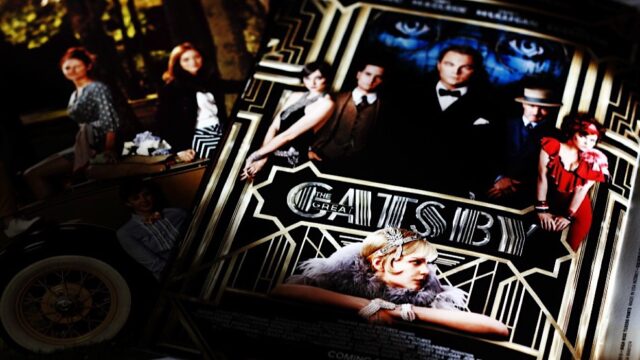

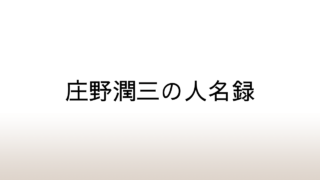
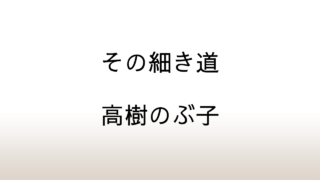
-150x150.jpg)









