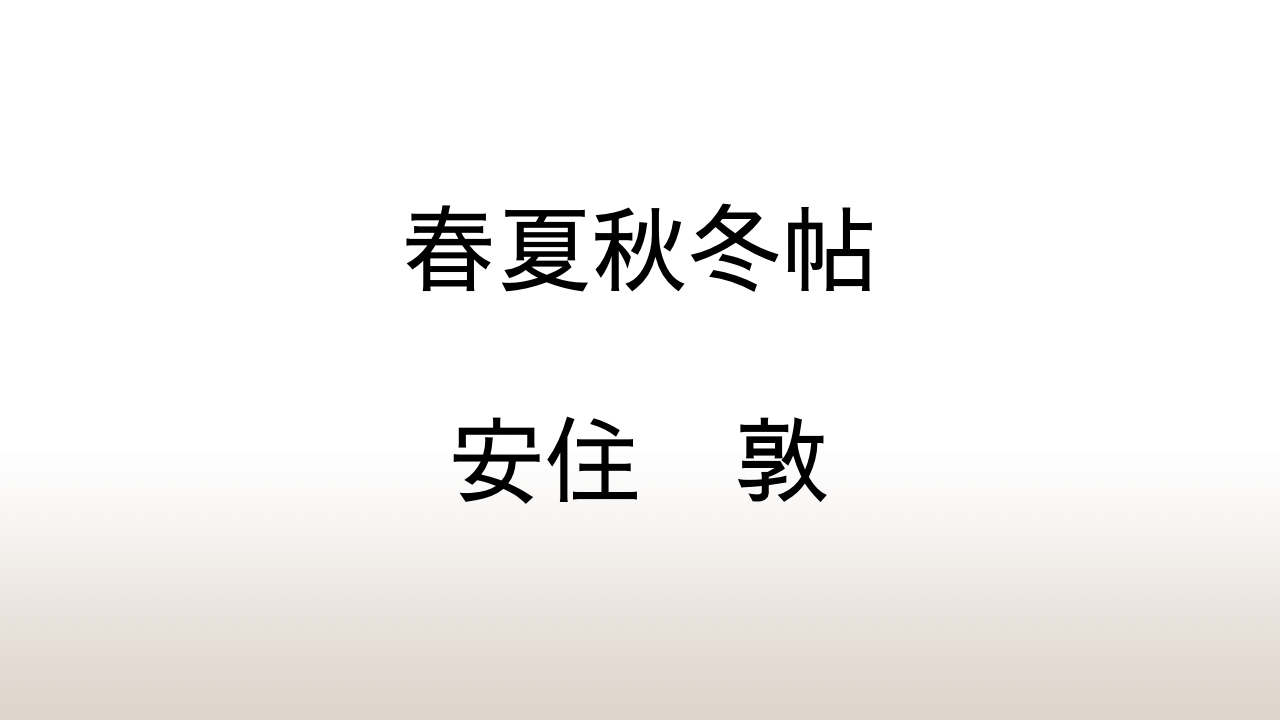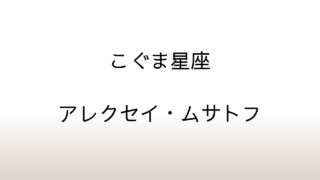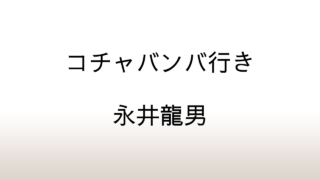安住敦「春夏秋冬帖」読了。
本書「春夏秋冬帖」は、1967年(昭和42年)に刊行された随筆集である。
この年、著者は60歳だった。
1967年(昭和42年)、日本エッセイストクラブ賞受賞。
主宰・久保田万太郎の思い出
どの作品も見開き2ページの中にきちんと収まっている。
右端にタイトル、文末に発表年月。
「あとがき」を読むと、俳誌『春燈』へ編集後記代わりとして載せていた「柿の木坂だより」を収録したものらしい。
ほぼ原稿用紙三枚弱とあるから、随筆としては短いかもしれない。
しかし、随筆というものは、短い方が楽しめるものである。
俳誌へ毎月載せていたものだから、季節の話題が多い。
季節の話題を身辺ドラマへと展開させているものもある。
最も多いのは、『春燈』主宰だった久保田万太郎に関するものだろう。
「流萬歳旦」(1966/01)は、久保田万太郎と過ごした元日の思い出を綴ったもの。
久保田万太郎が急逝したのは、1963年(昭和38年)5月のことだから、この随筆は、没後三回目の正月のものということになる。
戦後に過ごした鎌倉の家や、三隅一子と過ごした赤坂伝馬町の家のことが出てくる。
そこは虎屋の羊羹工場のコンクリート塀に添った袋小路の行きどまり、ささやかな、しかし、二、三坪の庭をもった家だった。表札には三隅と先生の字で書かれてあった。先生の傍にはいつも影の形に添うようにその三隅一子さんのものしずかな姿があった。(安住敦「流萬歳旦」)
「まゆ玉」(1964/01)も久保田万太郎の家で過ごした正月の話だし、「走り梅雨」(1965/05)は、久保田万太郎が亡くなった日の回想である。
中村汀女の『風花』の十五周年祝賀パーティーで、「今日は入れ歯がないから」と挨拶ではなく乾杯の音頭をとった久保田万太郎は、その夜、梅原龍三郎邸の夕食で、赤貝を喉に詰まらせて急死した。
「誕生日」(1963/11)は、1962年11月7日に銀座「辻溜」で行われた、久保田万太郎(73歳)の誕生日のお祝いのエピソードで、「歳寒」(1962/12)や「年越蕎麦」(1963/12)も、久保田万太郎や三隅一子の思い出に寄り添う内容のものとなっている。
敬愛していた主宰を偲ぶものが多いのは、当然とも言えるだろう。
俳句仲間たちの思い出
「弥生尽」(1960/06)は、安藤鶴夫『まわり舞台』に出てくる、高橋潤のことを綴ったものである。
高橋潤は「髭つけてみても端役やちろろ鳴く」「秋刀魚くふ貧しき芸をさらしきて」などの句を発表している俳優で、著者は安藤鶴夫の文章に強い共感を寄せている。
「高篤三」(1957/08)は、俳誌『春燈』を創刊した頃の思い出だが、高篤三は安住敦とともに、久保田万太郎主宰による俳句雑誌を夢見ていた、浅草の俳人である。
「浅草の風の中なる十三夜」の作品が遺されている。
高篤三は、1945年(昭和20年)3月10日の東京大空襲で妻子とともに亡くなってしまったので、『春燈』の創刊を知らない。
『春燈』創刊は、終戦直後の1946年(昭和21年)のことだった。
「秦豊吉忌」(1956/07)は、帝国劇場の社長だった秦豊吉の思い出。
春燈社の郵便箱(蜜柑箱を改造したもの)が台風で壊れたとき、安藤鶴夫の呼びかけで、新しいポストを作るための基金が集められた。
やがて、岩佐東一郎の音頭取りで「春燈ポストの会」が結成され、小島政二郎や岡田八千代、戸板康二、伊馬春郎、池田弥三郎などが集まったという。
秦豊吉は「春燈ポストの会」の発起人筆頭だったが、1956年(昭和31年)7月に亡くなっている。
「鹿島鳴秋」(1954/09)は、『お山のお猿』や『浜千鳥』などで知られる詩人・鹿島鳴秋が亡くなったという話で、安住敦は、かつて一度だけ、十和田操や那須辰造に紹介されて、鹿島鳴秋と会ったことがあった。
鹿島鳴秋の葬式は、その費用にも事欠く中で、ささやかに行われたという。
「田尻得次郎」(1964/09)は、バタヤ俳人・田尻得次郎が亡くなった話。
田尻得次郎は、石川桂郎『俳人風狂列伝』にも登場しているが、田尻得次郎の死を、安住敦はその石川桂郎から直接知らされたらしい。
追悼文のような話が多いが、それはそれで、戦後の俳壇事情を伝える貴重な資料になっていると思う。
楽しかったのは、パリ土産にマロニエの枯葉をもらう「枯葉」(1965/12)。
以前からマロニエに執心だった著者は、NHK国際局長の松井さんから、パリから持ち帰ったというマロニエの落葉をもらう。
松井さんはマロニエの木の下に車をとめ、車の屋根に上ってようやく手の届くところの枯葉を二、三枚もぎとってきたとのことだった。大型の外国雑誌の間に挟んでもってきてくれたそのマロニエの枯葉は、紅と褐色と、そしてまだところどころ僅かにのこっている緑色に染め分けられていた。(安住敦「枯葉」)
この話は、早稲田大学の同僚だった小沼丹のために、マロニエの葉を土産に持ち帰ったという村上菊一郎のエッセイを思い出させて愉快だった。
なお、NHKの松井さんは、<草一路>の号で『若葉』の同人だった人で、「ハンドバッグからとり出してマロニエの落葉なり」という句を、著者に見せたくれたという。
どの作品も短いが、短いからこその切れと余韻がある。
さすがに、優れた俳人の綴るエッセイというのは、まるで俳句のような味わいがあるものだと思った。
書名:春夏秋冬帖
著者:安住敦
発行:1967/08/20
出版社:牧羊社