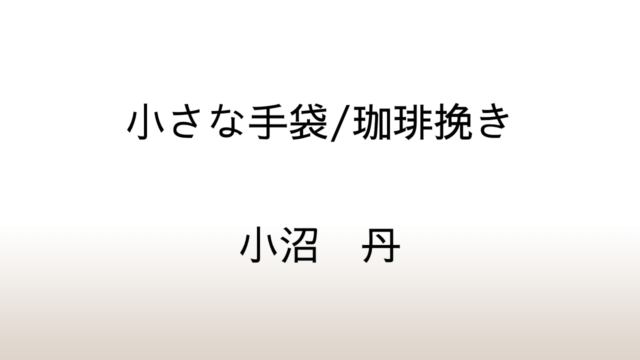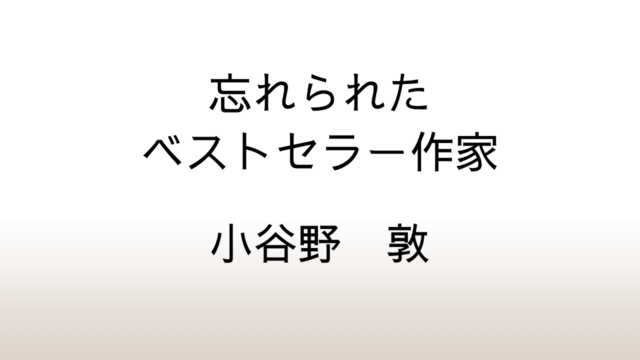山上たつひこ『がきデカ』第4巻読了。
本作『がきデカ』は、1974年(昭和49年)から1980年(昭和55年)まで『週刊少年チャンピオン』に連載されたギャグ漫画である。
連載開始時、著者は27歳だった。
少年チャンピオン・コミックス(第4巻)は、1975年(昭和50年)11月30日に刊行されている。
死者に生命のエネルギーを与える『がきデカ』的宇宙
自分の記憶の中にある『がきデカ』は、決して好きな漫画ではなかった。
近所の床屋さんに置いてあった『週刊少年チャンピオン』は、『ドカベン』や『ブラック・ジャック』や『750ライダー』を読むためのもので、『がきデカ』は、どんなに人気があっても、自分の対象ではなかった。
おそらく、僕には、ナンセンス・ギャグを理解するだけのスキルがなかったのだろう。
同時代にブレイクしていた『まことちゃん』(週刊少年サンデー)にも、自分はほとんど共感できなかったのだ。
だから、久しぶりに、チャンピオン・コミックスの『がきデカ』を読んで驚いた。
内容がおもしろいから驚いた、というだけではない。
当時、その作品を読んで笑っていた少年の自分がいたことを思い出して驚いたのだ。
少年時代、『がきデカ(第4巻)』は、間違いなく、我が家にあった。
そして、小学生だった僕は、この本を、自分の愛読書のように大切にしていたのだ。
一体、どこで記憶がねじ曲げられてしまったのだろうか。
最も鮮明な記憶として残っているのは、「初体験はこわいのじゃ!!の巻」である。
主人公(こまわり君)と友人(西城君)が、みどろヶ池で魚釣りをしていると、人間の白骨死体を釣りあげてしまう。
白骨死体が持っていた財布にお金が入っているのを見つけたこまわり君は、「二万円ほどもらおう」と言って、こっそりネコババしてしまう。
その夜、道に迷った二人は、見知らぬ農家に泊めてもらうが、そこで美しい少女と出会う。
少女は「お金を盗まれてこまっているのです」と泣いているが、それは、実は、昼間に釣り上げた白骨死体の幽霊だった、という物語である。
白骨死体を釣り上げ、道に迷い、幽霊の親子に襲われるなど、ほとんど『雨月物語』のような怪談ストーリーだが、『がきデカ』は、もちろん、ギャグ漫画である。
こまわり君は、幽霊の存在を受け容れつつ、恐怖心というものを一切持つことなく、死んだ人間を笑いのネタへと転換してしまう。
「わたしも長い間幽霊やっているけど、こんなアホな人間、初めて会ったわ~」「なにっ。幽霊にアホよばわりされるおぼえはないっ!!」(山上たつひこ『がきデカ(第4巻)』所収「初体験はこわいのじゃ!!の巻」)
ある意味で、こまわり君は、幽霊と対等の存在である。
そもそも、動物とだって(犬とか)対等の関係性を構築できるこまわり君だから、幽霊と対等であることに、何ら不思議はない。
固定的な関係性を超越したところにこそ、『がきデカ』の面白さはある(日常の破壊)。
しくしく泣いている美少女が、白骨死体へと変身していく場面はリアルで、思わず声を出して笑ったが、そのとき、僕は、少年時代の自分が、そのときも同じ場面を読んで笑ったことを思い出した。
僕は、決して『がきデカ』を嫌いなわけではなかったのだ(そもそも、家にコミックスがあったのだから)。
本来、女の幽霊は、こまわり君を霊界へと導いていく役割を担っているはずだが、『がきデカ』は、逆に、幽霊が人間界へと入ってきて(つまり、こまわり君と対等の関係となって)、およそ幽霊とは思われないナンセンス・ギャグを繰り広げる。
白骨死体をギャグのネタにするあたり、人間性の冒涜と読めないこともないが、幽霊は、既に幽霊性を失ってしまっているから、人間の尊厳を冒涜するような印象を受けることもない。
むしろ、死んだ人間に、生命のエネルギーを与えているものが、『がきデカ』的宇宙である。
『雨月物語』をギャグ漫画として昇華したものが、この「初体験はこわいのじゃ!!の巻」という作品だったのかもしれない。
日常の緊張感を笑い飛ばす『がきデカ』の哲学
コミックスを読んでいると、何度も少年時代に笑った場面を思い出した。
大人になった現在の笑いが、少年時代の笑いを取り戻したのである。
例えば、父親の郷里(四国の徳島)へ帰省する「できたところなのだ!!の巻」では、大きなムカデが現れる。
ムカデの恐ろしさは、庄野潤三『夕べの雲』でも詳細に描かれているが、ムカデを初めて見るこまわり君には、ムカデの恐ろしさが分からない(「なんだ、この虫ならさっき見たぞ」)。
大ムカデは、母親の太腿を這っていて、驚いた母親が恐怖の叫び声をあげる。
「動くなっ。動くとムカデがかむぞっ─。静かに。ぼくがとってやるから」「あ、あ、早くして~。パ、パンティの中にはいってこようとしているのよ」「う、うっ、す、すごいわねっ」(山上たつひこ『がきデカ(第4巻)』所収「できたところなのだ!!の巻」)
過度の緊張感を笑いに転化する力が、『がきデカ』にはある。
それは、「脱力感」という言葉では言い表すことのできない、緊張感を持った笑いである。
もちろん、素材としてのムカデが現代性を持っているか疑問だが、日常生活の中に潜む緊張感を、笑いへと転化するこまわり君のスキルは、人間関係が窮屈になった現代ほど、もっと評価されていい。
「好みの決定的瞬間っ!!の巻」では、ポラロイドカメラが素材として登場している。
モデルとなっているのは、ポラロイド社のボックス型で、表紙では「COLORPACK 69」「POLAROID AKITA CAMERA」のロゴが見える(正しくは「POLAROID LAND CAMERA」)。
ポラロイドカメラは、組立式のSX-70に人気があるが(なにしろカッコいい)、実用としては、手間のかからないボックス型が便利である(なにしろ中古価格が廉い。ただし、作中、こまわり君は「わーっ、一万八千円のポラロイドが──っ」と叫んでいる)。
ちなみに、「ポラロイドSX-70」は、『がきデカ』の連載が始まった1974年(昭和49年)発売で、ポラロイドカメラと『がきデカ』とは、同時代性を有しているとも言えるだろう。
このとき、友人(西城君)は、一眼レフカメラ(コニカ)を持ってきていて、「あはははは。ポラロイドなんて、しょせん、子供の遊びさ」と、こまわり君のポラロイドカメラを笑い飛ばす(つまり、そういう時代だった)。
緊張感の中に笑いを見い出すからこそ、『がきデカ』は、ナンセンス・ギャグの漫画だった。
むしろ、日常の中の緊張感を笑い飛ばしてしまうところにこそ、『がきデカ』という漫画の哲学があったのではないだろうか。
我々は、この「笑い」を忘れてはならないと思う。
書名:がきデカ(第4巻)
著者:山上たつひこ
発行:1975年11月30日
出版社:秋田書店(少年チャンピオン・コミックス)