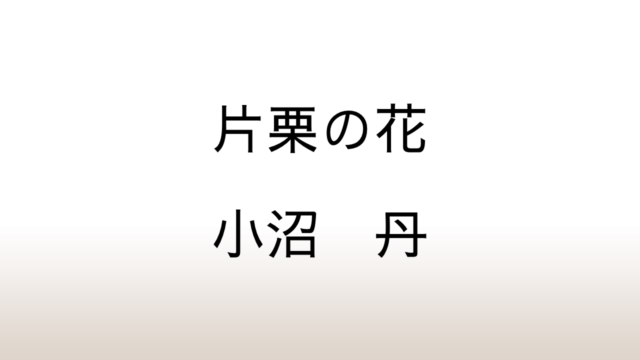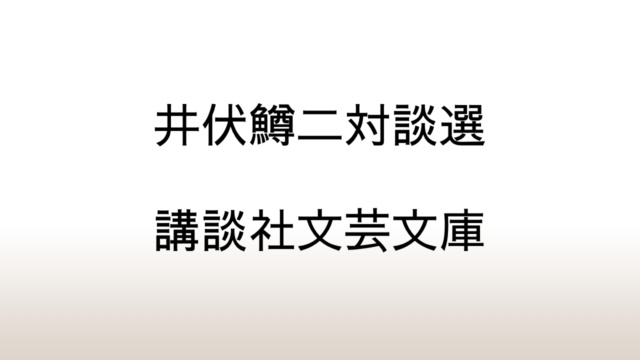聖日出夫『なぜか笑介』読了。
本作『なぜか笑介』は、1982年(昭和57年)から1991年(平成3年)にかけて、小学館ビッグコミックスから刊行されたサラリーマン漫画である。
初出は、1982年(昭和57年)~1991年(平成3年)『ビッグコミックスピリッツ』。
第1話発表時、作者は36歳だった。
働いて働いて働き続けたサラリーマンたち
2025年の「T&D保険グループ 新語・流行語大賞」の年間大賞に、高市早苗首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります(女性首相)」が選ばれた。
バブル世代には懐かしい言葉だったのではないだろうか。
本作『なぜか笑介』は、そんなバブル時代期に人気を博したサラリーマン漫画である。
真実一郎『サラリーマン漫画の戦後史』(2010)で、『なぜか笑介』は「島耕作になれなかった男」として紹介されている(なにしろ、『なぜか笑介』は『課長島耕作』と同時期に登場した)。
笑介シリーズは、とにかく「源氏の血」が濃い作品で、明るく元気な快男児という笑介のキャラクター造形は源氏鶏太のサラリーマン小説そのものだ。人柄主義が徹底され、人間関係の大切さが繰り返し強調される。(真実一郎「サラリーマン漫画の戦後史」)
『サラリーマン漫画の戦後史』では、戦後のサラリーマン漫画のルーツを、源氏鶏太のサラリーマン小説に見出している。
1950年代初頭から、サラリーマンを主役とした小説や映画が次々と登場し、大衆的な人気を獲得するようになった。その発端となったのは源氏鶏太という小説家の活躍だった。(真実一郎「サラリーマン漫画の戦後史」)
源氏鶏太が描いたのは、戦後日本の復興を支え、高度経済成長期を築きあげた「モーレツ社員」たちの実像である。
1970年代のオイル・ショックで、戦後のモーレツ経営は一時落ち着くが、1980年代に入って空前の好景気が訪れたとき、彼らは再び新しい姿となって復活した。
「24時間戦えますか?」と自らを鼓舞した「企業戦士」たちの登場である。
『なぜか笑介』は、主人公(大原笑介)を中心とした「企業戦士」たちの成長を、温もりのある人情ドラマで描いていく。
「新入社員マニュアル」とも題された『なぜか笑介』には、80年代サラリーマンに有益な金言や格言が多い。
「自分で納得して仕事をする奴がプロで、自分を納得させてから仕事をする奴はアマチュアだぞ!」「その仕事の成否を抜きにして、遅くまでガンバったからというだけで自分を納得させてないか!」「一生懸命さを逃げに使ったらダメだ!」(聖日出夫『なぜか笑介(10)』/「転機」)
地方の三流私立大学出身の主人公(大原笑介)は、大企業「五井物産」の落ちこぼれ社員である(落ちこぼれ社員になるはずだった)。
実は『なぜか笑介』には、前身ともなる読み切り物のシリーズ作品『多少難アリ』があった(『ビッグコミックスピリッツ』不定期連載)。
やがて、この作品が『なぜか笑介』の連載へと発展していくことになる。
笑顔がとりえのオチコボレ新入社員、大原笑介。同じアパート仲間の協力で、カンニング、偽装工作と大胆不敵な入社作戦を展開して、みごと一流商社、五井物産に入社。しかし、会社の中では劣等生、やはり、今ひとつさえないが……!?(聖日出夫『多少難アリ』)
一流大学出のエリート社員たちに囲まれて、笑介は自分らしい働き方を身に付けていく。
「オレ達みたいに、やめようと思っても、やめられない奴だっているわけだしよ」「やめられる自由のあるうちに、めいっぱいでかい仕事をしようぜ!」(聖日出夫『なぜか笑介(9)』/「辞表」)
彼を支えているのは、五井物産「食品3課」の仲間たちだった。
源氏鶏太流の「家族主義」を発揮して、彼らは難局を次々と乗り越えていく。
「世間じゃ専門バカになるなと言う人も多いが、ワシはそうは思わんよ!」「そう、どんな細いハシゴでも、昇り詰めれば下界は見えてくるもんだよ!」(聖日出夫『なぜか笑介(9)』/「スペシャリスト」)
温かいのは上司や同僚たちだけではない。
「室町食品」の重役(竹下取締役)を始めとする取引先の関係者たちも、笑介たち若いサラリーマンを導いてくれる。
「しかし、新入社員はいつもたいへんだね」「気ばかりあせったあたしの20代も、なんでこんな仕事をってよく思ったもんだよ」「しかし、土台のないところに家は建たんし、30代にどの程度の仕事ができるかは、20代の過ごし方で決まるからね!」(聖日出夫『なぜか笑介(4)』/「20代に何をすべきか」)
特に連載初期には、若手社員(新入社員向け)のエピソードが多かった(まさに「新入社員マニュアル」である)。
「どんな社会人をめざそうが、20代は体力、頭を使ってガンバって生きるのが30代だしな」(聖日出夫『なぜか笑介(4)』/「20代に何をすべきか」)
そこにあるのは、日本における普遍的なビジネスマン像だったかもしれない。
「部下は上司を選べないかわりに、上司も部下を選べないのがサラリーマンだよ!」「我々は、その中でうまくやっていくしかない!」「入社二年目のキミに、ボクは四番打者を期待していない」(聖日出夫『なぜか笑介(4)』/「人間関係」)
上司と部下との理想的な関係は、常に彼らのテーマだった。
「なーに、迷惑なんかが怖くて、上司も務まらなんしね」「そう、そうだよ、大原クン。迷惑をかけずに生きてきたヤツなんて、けっしていないしね!」(聖日出夫『なぜか笑介(7)』/「根回し」)
時には、森川課長の奥さんまで登場して、若手社員に格言を与えてくれる。
「そりゃ、休日、道ですれ違っても、上司は上司、部下は部下に変わりなくてよ」「でも、上司の家を訪ねた時ぐらい、部下の立場を越えて、甘えてほしい思ってるものなのよ」「仕事上のつきあいだけでなく、上司だって普段着の時ぐらい、人生の先輩でいたいんだから!」(聖日出夫『なぜか笑介(6)』/「休日」)
源氏鶏太の小説と違うのは、この物語には「明らかな悪人」という人たちは登場しないことだ。
すぐに怒る森川課長や、嫌みのマントヒヒ(高山係長)など、一見「敵役」と思われる上司たちも、時に厳しく、時に優しく、若い彼らを導いてくれる(彼らはまさしく指導者だった)。
ビジネス社会全体が、まるで一つの家族であるかのように、互いが互いを支え合っている(いわゆる「疑似家族」)。
「どんなにエラくなっても、忘れちゃダメよ!」「自分の仕事に愛情を持つことを! そして、自分を育ててくれた人たちを!」(聖日出夫『なぜか笑介(9)』/「スペシャリスト」)
物語の根底に流れているのは、仕事(=会社)に対する深い愛情だ(「愛し続けていきたい会社ですよ、五井物産は!」)。
「そ、そうなんだよ、大原くん! 男はとことん満足のいくまで仕事をしておくべきなんだよ!」「サラリーマンにとってのライフ・ワークは、自分の仕事だけなんだよ!」「たとえ出世なんて運次第とわかっていてもな!」(聖日出夫『なぜか笑介(3)』/「ライフ・ワーク」)
仕事に(会社に)愛情を注ぐことのできない男たちは、出世することができない。
会社を愛するということは、つまり、自分の職場を愛するということでもあった。
「これでよくわかったでしょ? 歯車一つが欠けても会社がつぶれることだってあることが!」「仲良くすることがね、チーム・ワークじゃないのよ」「友情と信頼だけが、チーム・ワークをつくりあげるのよ!」(聖日出夫『なぜか笑介(3)』/「チーム・ワーク」)
サラリーマンの目標は、明確に「出世」だった(木下人事部長が教えてくれた)。
「サラリーマンである以上、出世をめざすのは当然だよ」「権力欲のみの出世欲なら困るけど、責任あるポストにつかないと、自分が本当にやりたい仕事はできないし、自分の人生を充実させるためにも、しっかり出世しなきゃね」(聖日出夫『なぜか笑介(28)』/「昇進」)
人事課の美人OL(今日子さん)も、笑介にとって大きさ存在だった(最終巻で二人はゴール・イン(結婚)する)。
「笑介クン、OLは、入社2年間が勝負なのよ!」「どれだけステキな彼と社内結婚できるかの!」(聖日出夫『なぜか笑介(4)』/「OL(オフィス・レディ)」)
男性社員顔負けの実力者(花園さん)は独身のまま、仕事で生き抜くキャリア・ウーマンである(後日譚である『社長大原笑介』では取締役に昇進した)。
美人OL(今日子さん)は、早い段階から大原笑介の才能を見抜いていたらしい(さすが人事課社員だ)。
「出世できるわよ、笑介クン!」「だって、出世する男の条件は、OLから好かれることなのよ!」(聖日出夫『なぜか笑介(4)』/「OL(オフィス・レディ)」)
男女雇用機会均等法が施行された時代(1986年)、女子社員の生き方は、新しい時代を意味するものでもあった。
食品3課のマドンナ(花園さん)は、新しい時代を生きる女子社員像として、重要な役割を果たしていく(活躍する女性像)。
「わたしの務めたこの何年間でも、多くの人が辞めていったわ」「自分の役割を演じきれずに、それも本当につまらない理由でね」「ねえ、今日子さん、人生そのものが回り舞台よ。ガンバって名女優になってみない? この五井物産という大舞台でね!」(聖日出夫『なぜか笑介(7)』/「給湯室」)
男たちがサラリーマン社会の中心だった時代を、花園さんは一人で生き続けてきた。
「オンナ」を武器にすることなく、男たちと対等の舞台に立って(「ただ女性にとって一番問題なのは、女性だからっていうだけで、仕事にハンディのあることが多いことよね」)。
「あたしよりもっと仕事のできる女たちが、うちの会社にもいっぱいいるしね」「みんながみんな、腰かけじゃないってことを会社がわかるまで、一歩ずつガンバるしかないじゃない」「そう、ハイヒールをはいたプロたちが、21世紀に役員の半分をうめつくすまでね」(聖日出夫『なぜか笑介(8)』/「ベテランOL」)
女性管理職が少なかった時代を、彼女たちは生きていた。
「女性活躍の時代」と呼ばれる、少し前の時代を。
それは「お酒」が重要なコミュニケーション・ツールという時代でもあった。
「でもね笑介くん、今、求められてるサラリーマンはね、できる男より、できた男なのよ、わかる?」「人間のできたサラリーマンなら、酒席だって最低限の気くばりぐらい忘れないのよ!」「酒席をしらけさせるサラリーマンなんて最低よ!」(聖日出夫『なぜか笑介(3)』/「酒」)
高度経済成長期以降、「飲みニケーション」こそがコミュニケーション構築の柱だと、(日本中の)誰もが信じていたはずだ。
「実は、わたしも昔は一滴も飲めなかったんだよ」「残念ながら、今日子クンみたいなお酒の先生はいなかったが、十数年かかって、なんとか仕事の味も酒の味も覚えてきたよ」「その頃は、酒さえ飲めれば、取引相手を仲良くなれるんじゃないかと思っていたがね」「しかし、ビジネスマン同士の強い絆は、ビジネスを通してこそ、仕事でお互いの全力を出し合ってこそ生まれてくるものさ!」「それがわかってからかな。仕事を成しとげたあとの一杯が、心底ウマイと感じ始めたのは……」(聖日出夫『なぜか笑介(8)』/「のみにケーション」)
新入社員の失敗あり、出世レースあり、女性の活躍推進あり、飲みニケーションあり。
サラリーマンに必要な知識を、80年代の若者たちは『なぜか笑介』で学んだ。
「働いて働いて、ひたすらに働き続けること」が当たり前だと信じていた時代を、そうやって彼らは(我々は)生きてきたのだ。
もしかすると、それは、高市首相が目指す「新しい時代」(働く時代)を予言していたのかもしれない(歴史は繰り返す)。
バブル時代のトレンド漫画
本作『なぜか笑介』は、80年代という時代を映す「トレンド漫画」でもあった。
登場人物たちのさりげない会話の中にも、80年代のトレンドが見える。
「うわあ、じゃ、笑介クン、うまく休みがとれそうなの?」「フーン、『笑介ちゃんが水着に着がえたら』ってわけ?」(聖日出夫『なぜか笑介(22)』/「計画」)
ホイチョイ・プロダクションズ原作、原田知世主演の映画『彼女が水着にきがえたら』は、1989年(平成元年)の公開(まさにバブルの絶頂期だ)。
中山美穂がモデルらしい「タレント・ショップ」や、宮沢りえがモデルらしいアイドルのCM起用も、当時を象徴している。
中山美穂は、原宿のタレント・ショップ『オーブ・ジャポン』を経営。
宮沢りえの芸能活動は、1985年(昭和60年)、明星食品「チャルメラ」のCM活動から始まった。
満員電車の中で痴漢と間違われたときには「セクシャル・ハラスメント」という言葉が登場している。
「んもう、笑介ちゃん、いまどきセクハラを知らないなんて遅れてるわよ」「セクハラって、職場の内外で上司や顧客が職権を乱用して部下の女性なんかに、エッチをせまったり、性的いやがらせをすることよ」(聖日出夫『なぜか笑介(24)』/「セクシャル・ハラスメント」)
もちろん、現代において「痴漢」は性犯罪であり、「セクハラ」では済まされないだろうが。
バブル時代らしい流行語にも敏感だった。
「さーさ、小森ちゃん、今夜は遠慮なく飲んでよ」「もし飲みすぎたら、人畜無害のアッシー君(笑介ちゃん)に送らせるからねー!」(聖日出夫『なぜか笑介(24)』/「風邪」)
「アッシーくん」に「メッシーくん」。
90年代に入る頃には「ファジーくん」も登場した。
「ファジーですよ、ファジー。あいまいなって意味のFUZZYですよ」「自己主張の強い段階の世代や、感性は鋭くても殻にとじこもりやすい新人類に代わって、90年代のニュータイプとして誕生したファジー君ですよ」(聖日出夫『なぜか笑介(26)』/「ファジー君」)
「おたく族」が登場したのも、やはり、この時代である。
「じゃ、酒井クンって、いま流行のおたく族なのかもね」「相手の名前をちゃんと言わないで、おたく、おたくって言うことで、他人との関わりを避けようとする青少年が増えてきてるのよね」(聖日出夫『なぜか笑介(25)』/「おたく」)
ジェネレーション・ギャップさえも、新しい時代には必要だったかもしれない。
「単に仕事ができる人間なら、いまでもいくらでもいるのだから……。願わくば、新人類はいつまでも新しさを失わない新人類のままでいてもらいたいね」(聖日出夫『なぜか笑介(13)』/「新人類」)
1980年代に入って登場した新人類も、今や定年退職を迎える時代となった(なにしろ、連載から30年以上が経過しているのだから当たり前ではあるが、、、)。
ちょっとした会話表現さえも、80年代っぽい。
「笑介クン、今夜、ビールする?」(聖日出夫『なぜか笑介(26)』/「女の武器」)
連載前半(80年代前半)には、ビジネス・マニュアルが中心だったストーリーが、連載後半(80年代後半)には、時事ネタ中心の物語へと変化していった。
かつて新入社員だった彼らが、係長級へと昇進するタイミングを迎える中で、物語としての『なぜか笑介』も成熟しつつあったのだ。
最近、話題となることも多い「消費税」が導入されたのは、1989年(平成元年)のことである。
「消費税なんかもそうだが、いまの時代こそ、いままでやったことのないことに挑戦して、克服していかなきゃならんことの多い時代だからね」「そう、いつの時代も、人は体験を通して新たな能力を身につけるんだしね」(聖日出夫『なぜか笑介(21)』/「消費税」)
空前の好景気を背景に、日本中がアグレッシブだった。
日本を支えていたのは、高市首相が提唱する「働いて働いて働いて」という言葉どおりに生きるサラリーマンたちである。
サラリーマンは、戦後社会の主役だったのだ(当時は「リーマン」と呼ばれた)。
「今日も明日も完徹になりそうなんだけど、日曜日は死ぬほど寝るから、いーの」(聖日出夫『なぜか笑介(21)』/「研修旅行」)
「完徹」という言葉も、最近では死後になりつつあるらしい(完全に徹夜すること。一睡もしないこと。つまり「オール」。当時の人々はオールで仕事していたのだ)。
「24時間、働けますか?」の時代、大原笑介も、やはり立派な「企業戦士」だった。
「先月は、何日徹夜した?」「えーと、この夏のお中元商戦用に、一週間に四日は会社の仮眠室で寝ましたよね」(聖日出夫『なぜか笑介(21)』/「研修旅行」)
会社で徹夜するのも、休日出勤も、当たり前の時代だった(どこにも不思議はなかった)。
「宮仕えは、自分で休みを決めるより、仕事が休みを決めるほうが多いからね」(聖日出夫『なぜか笑介(15)』/「息抜き」)
思えば、それは「働くこと」のインセンティブが明確な時代だったのだろう。
24時間働き続けるだけの収入と社会的地位が、しっかりと(明確に)約束されていた(そうでなければ誰も頑張らない)。
だからこそ、「ヤング・エグゼクティブ(ヤンエグ)」が、バブル時代の若者たちにとって憧れの職業になり得たのだ(みんな早く管理職になりたかった)。
「ボクらの時代は、ただガムシャラに働くことが、上級管理職(ヤング・エグゼクティブ)につながる道だったけどね」「仕事とプライベートを使い分ける時代か……。それだけ、日本がリッチになったのかもしれないね」(聖日出夫『なぜか笑介(12)』/「エグゼクティブ」)
「リッチ」という言葉が、日常会話の中で普通に使われていた。
遠くない将来に「管理職離れ」の時代が来るなんて、当時は誰も予想しなかったに違いない。
「失われた30年」を通して、「管理職」が失ったものは、あまりにも大きい。
「札幌南高校」卒業生である聖日出夫の作品には、北海道がよく登場した。
「そうそう、今年の北海道といったら、6月3日から「世界・食の祭典’88」という巨大イベントが、150日間の会期で催されるのよね」「今年ブームの地方博の中で最大規模のイベントで、五井物産も協賛してるし、あんた担当の室町食品も参加するのよね?」(聖日出夫『なぜか笑介(17)』/「出張」)
1988年(昭和63年)に開催された「世界・食の祭典」は、横路孝弘知事率いる横路道政の大失策として、今に語り継がれている(なにしろ、企画チームの責任者が、責任問題の中で自殺に追いこまれた)。
バブル時代にも、光と影があったのだ。
そして、バブル経済の崩壊とともに『なぜか笑介』も姿を消した。
係長に昇進した大原笑介に必要なものは、もはや「新入社員マニュアル」ではなかったからだ。
暗黒の(失われた90年代)に、彼は『だから笑介』の主人公として再登場する。
そこには、あの華やかな「80年代の物語」はなかった。
80年代、それは、本当の意味で(夢のような)特別の時代だったのだ。
今、高市首相が叫んでいる「働いて働いて働き続けていく」社会を実現するためには、何よりも経済的な裏付けが必要だろう。
働いた分だけ生活が「リッチ」になり、ゴージャスな海外旅行が当たり前だった、あのバブル時代のように豊かな経済的保証が。
まさか、戦後の復興時代のように「働いて働いて働き続けていく」時代を、誰も求めてはいないとは思うのだけれど。
書名:なぜか笑介
著者:聖日出夫
出版社:小学館(ビッグコミックス)