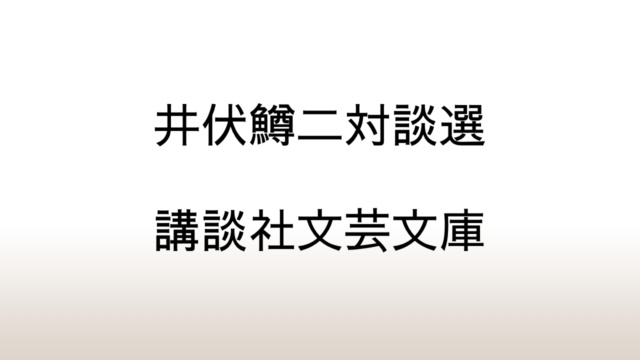久住昌之・谷口ジロー『孤独のグルメ』読了。
本作『孤独のグルメ』は、1997年(平成9年)に扶桑社から刊行されたグルメ漫画である。
この年、原作者(久住昌之)は39歳、作画(谷口ジロー)は50歳だった。
テレビ東京系ドラマ『孤独のグルメ』は、2012年(平成24年)放送開始。
『孤独のグルメ』は何がおもしろいのか?
原作漫画『孤独のグルメ』を読んでいると、切ない気持ちになる。
なぜなら、このグルメ漫画は、人がみな孤独であることを思い出させてくれるからだ。
「孤独のグルメ」の「孤独」とはいわゆる「お一人様」のことではない。
「孤独のグルメ」の「孤独」とは、人間が孤独であることの「孤独」なのだ。
例えば、浅草の甘味処「松むら」で「豆かん」を食べながら、主人公(井之頭五郎)は孤独を感じている。
「なんていうか……違うな」「ここは自分のような商売とはまったく違う時間が流れている」「おそらく自分はこんなふうには生きられないだろう」(久住昌之・谷口ジロー「孤独のグルメ」)
井之頭五郎の孤独は、居場所のない疎外感である。
その疎外感は、人間が生きていく上で避けて通ることのできないものだ。
そして、青年期から中年期への移行期間に、こうした疎外感は特に強く現れてくるものらしい。
中年時代を迎えた彼らは、いつでも何か(どこかに)忘れ物をしたような思いにとらわれていた。
西荻窪の自然食レストランでも、彼は、忘れていた「何か」を思い出そうとしている。
「なんだか懐かしい店だな」「学生の頃にこういう店に入ったことがあるような気がする」(久住昌之・谷口ジロー「孤独のグルメ」)
学生の頃の居場所は、既に大人になった彼の居場所ではない。
そこに、彼の(そして我々の)疎外感がある。
「うわ…なんだ、このホウレン草」「固くて臭くて……まるで道端の草を食っているようだが」「マズくない!」「けっしてマズくないぞ!」「ああ、うまい! なんだか懐かしい味だ」「そうだ、これは子供の頃、キライだった味だ」(久住昌之・谷口ジロー「孤独のグルメ」)
子どもの頃には、両親の待っている家があった。
大人になった今、彼は、この社会を一人で生きていかなければならない。
それが、大人になるということである。
独身であるとか妻帯者であるとか父親であるとか、そういうことは問題ではなかった。
独り者でも家族持ちでも、大人になった男とは常に孤独な存在なのだ。
主人公(井之頭五郎)は、現代社会を生きる孤独の象徴である。
そして、彼は、食べることによって、自分の孤独と向き合っていた。
渋谷の「餃子専門店 太河餃」にライスはない。
彼にとって「ウチはライスやってないんだ」というセリフほど、寂しさを感じる言葉はなかっただろう(激しく同意!)。
「素朴だなあ」「屋台の焼きそばとも、また全然違うんだけど…」「これはこれで」「そうか…」「ビールやなにかが合うような気はする」「この油っぽい感じが…」「このどこか野暮ったい味って…いい意味で取り残された渋谷のようだ」(久住昌之・谷口ジロー「孤独のグルメ」)
野暮ったい味の「取り残された渋谷」は、井之頭五郎自身でもある。
青年から中年へと年を取っていく中で、彼は自分自身の居場所を探し続けていた。
「あのストリップ劇場の向かいに一軒、うまいラーメン屋があったぞ」「ストリップか……」「観てみようかな…十年ぶりぐらいに」「どんな気分だろう」(久住昌之・谷口ジロー「孤独のグルメ」)
もちろん、彼は既に、ストリップ劇場で喜ぶような若者ではない。
同時に、青春時代の思い出を求めてストリップ劇場に入るほど、中年世代を受け容れる年齢でもなかった。
言ってみれば、井之頭五郎は「モラトリアムな中年世代」なのだ。
秋葉原の街でも彼は、自分自身の居場所を探していた。
「この街には ”食欲” というものが欠乏している気がする」「この街自体が、電気製品の内部みたいだ」(久住昌之・谷口ジロー「孤独のグルメ」)
『孤独のグルメ』のおもしろさは、自分探しのおもしろさである。
うまい飯屋を探しながら、井之頭五郎は、自分自身をも探していたのかもしれない。
井之頭五郎はなぜ「下戸」なのか?
井之頭五郎の孤独を際立てているのは、彼が「下戸」であるということである。
酒の飲めない彼は、酒によって自分をごまかすということができない。
朝の赤羽で、井之頭五郎は「飲み屋」という異世界へと迷いこむ(「酒は飲めないけれど、酒の肴はなんでも好きだ」)。
「青りんごサワー?」「鯉こく?」「常連……?」「いま、本当に9時半なのか?」「俺は…夢でも見ているようだ」(久住昌之・谷口ジロー「孤独のグルメ」)
酒の飲めない彼が、泥酔や酩酊という「あちら側の世界」に飲みこまれてしまうことはあり得ない。
つまり、彼は下戸であることによって「こちら側の世界」に留まっているのである。
もちろん「あちら側の世界」にとって、酒の飲めない彼は異端児だった(「俺ってつくづく酒の飲めない日本人だな……」)。
ここにも彼の孤独(=疎外感)がある。
「酒飲み天国」とまで呼ばれた日本において、下戸は居場所を失ったマイノリティーである。
酒の飲めない下戸にとって、会社の宴会ほど苦しい「自分探しの旅」はない(それはただの「苦行」だ)。
だからこそ、井之頭五郎は「会社」という集団に属することなく、フリーの輸入雑貨商で生きる道を選んだのだ。
会社という組織の中では生きていくことのできない彼は、現代日本のアウトローである。
「川崎に焼き肉が似合うということが、今日よくわかったよ」「まるで、俺の体は製鉄所。胃は溶鉱炉のようだ」「うおン」「俺はまるで人間火力発電所だ」(久住昌之・谷口ジロー「孤独のグルメ」)
孤独な主人公は、徹底的に自己対話に集中していく。
まるで、現実世界から遠く逃れていこうとしているかのように。
「デパートの屋上って…変わらないんだなあ」「この雰囲気」「下がすぐ駅だなんて信じられないよ」「都会のエアポケットみたいだ」「そうか」「都会のぐしゃぐしゃから逃げたければ、ここに来ればいいんだな」(久住昌之・谷口ジロー「孤独のグルメ」)
井之頭五郎は、社会のエアポケットで生きる、孤独なフリーランサーである。
インターネットでグルメ情報を収集することも、SNSで誰かと繋がることも、彼には必要なかった。
彼は、常に自分自身の孤独と向き合いながら生き続けていたからだ。
「モノを食べる時はね、誰にも邪魔されず、自由で、なんというか、救われてなきゃあダメなんだ」「独りで静かで豊かで……」(久住昌之・谷口ジロー「孤独のグルメ」)
自由に生きるということは、つまり、孤独に生きるということだった。
孤独な主人公にとって、食事とは(魂の)救済行為でもある。
だからこそ、彼は、食べることをないがしろにはできなかったのだ。
本作「孤独のグルメ」は、マイノリティーとして生きることを決意した男の、救済の物語である。
孤独でない大人の男など、世の中には一人もいないとするならば、大人の男にとって「ひとり飯」は、時に必要なものなのではないだろうか。
書名:孤独のグルメ
著者:原作/久住昌之、作画/谷口ジロー
発行:2000/02/29
出版社:扶桑社文庫