寺田博「昼間の酒宴」読了。
本書は「文藝」や「海燕」で編集長を務めた寺田博の初めての随筆集である。
随筆集と言っても、文芸誌編集者の雑文なので、作家との交流や書評に関するものが多い。
例えば、表題作「昼間の酒宴」は吉田健一との交流を回想したもの。
毎週木曜日の昼過ぎ、神田神保町のビヤホール「ランチョン」で吉田健一氏とお目にかかるようになったのは、昭和四十五年ごろからであったろうか。その年の「文藝」七月号に掲載した『瓦礫の中』が各紙の文芸時評その他で絶賛を博し、次に私は、どうしても氏の長編小説の一挙掲載をしたいと思い、その週に執筆された三、四十枚の原稿を頂くことをその分の原稿料をお支払いすることのために、毎週出かけていった。(寺田博「昼間の酒宴」)
吉田健一には、原稿は原稿料と引き換えに手渡すことと、依頼を受けた枚数の原稿用紙の最後の枡目でぴたりと終るように書くことだった。
どうやら、吉田健一は、酒場で原稿料を受け取ると、その原稿料でその場にいる全員分の飲み代を支払っていたらしい。
「ランチョンの会」には、寺田博のほか、「ユリイカ」の清水康や「すばる」の安引宏が常連メンバーがだったが、少しずつ増えていって、筑摩書房の風間氏、集英社の大波加氏、番町書房の田村氏、小沢書店の長谷川氏などが顔を揃えるようになった。
英文学者で翻訳家の野崎孝なども、頻繁に同席してらしい(サリンジャー『ライ麦畑でつかまえて』で有名)。
生ビール三、四杯を空にした頃、吉田健一は「そろそろリプトンにしましょうか」と店主を呼び、リプトンティーにサントリーオールドをダブルで計量したものを注いで飲み干したという。
当時、吉田健一は中央大学大学院で講義を持っていたから、二時を過ぎるとさっと立ち上がり、立ち上がろうとする編集者たちに「そのまま、そのまま」と声をかけて、颯爽とタクシーに乗り込んで消えたそうだ。
吉田健一の文章は長い上に句読点が少ないので、あまり積極的に読んでいないのだけれど、こういう文章を読むと、今度は、その小説を読んでみようかという気持ちになってくる。
このとき、吉田健一が書き上げて『文藝』昭和四十六年三月号に一挙掲載された作品は『繪空ごとである。
井伏鱒二「横光利一は才能のない人だったよ」
「昼間の酒宴」では、こうした作家の横顔やブックレビューのほかに、寺田博が担当したインタビューも収録されている。
津島佑子や安岡章太郎も興味深いが、おもしろいのは、何と言っても井伏鱒二へインタビューしたときのものである。
話題が同時代作家へと及んだとき、横光利一の話になって、井伏さんは「荻窪にいた。額田六福の隣の家にいた。それからあれは偉くなったんだ」「つき合いはないが、知ることは知っていた。僕の同窓だから」などと話をした後で、横光利一は菊池寛と親しくて、「川端康成よりも信頼されていたろう」と振り返っている。
「才能はどうでしょうか」「(井伏)才能はないね」「『機械』とか評価は高いですね」「(井伏)『機械』は有名だったが、駄目だ。非常に買われたんだがね。菊池さんが少し酒に酔っていたのかな。才能のない人だよ、ほんとうに」(寺田博「みんな一生懸命書いた—井伏鱒二氏に聞く」)
「菊池さんが少し酒に酔っていたのかな」というところが楽しい。
この井伏さんのインタビューは非常に長いもので、井伏さんと同時代を歩んできた小説家がたくさん登場するので、昭和文壇史に関心のある方にはお勧めだ。
なお、安岡章太郎のインタビューは短篇小説をテーマにしていて、この中に<第三の新人>の盟友・庄野潤三の名前も登場している。
(安岡)僕は、庄野(潤三)の初期のやつ、『噴水』もしくは『舞踏』というのが好きでね、つまり優れた資質そのものが真っ直ぐに出ている。よかったな。それから吉行で言えば、『鳥獣虫魚』。(寺田博「短篇の魅力—安岡章太郎氏に聞く」)
こういうのを読むと、久しぶりに、庄野さんの初期の作品が読みたくなってくる(笑)
書名:昼間の酒宴
著者:寺田博
発行:1997/1/30
出版社:小沢書店




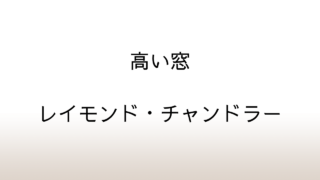
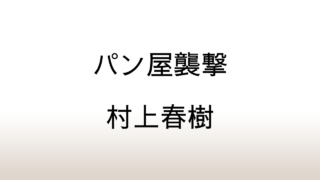
-150x150.jpg)









