阪田寛夫「受けたもの 伝えたいもの」読了。
本書は、日本キリスト教団の雑誌「信徒の友」に連載された随筆「私に届いた言葉」を収録したエッセイ集である。
タイトルは「信徒の友夏期セミナー」の主題から。
心にしみ入る言葉となった「夕べの雲」
阪田寛夫が敬愛する作家といえば、まずは庄野潤三である。
本書では、庄野さんの代表作『夕べの雲』が紹介されている。
「夕べの雲は小説の題名となった為に、作品の内容と分かちがたく結びついて、心にしみ入った言葉となりました」と、阪田さんは言う。
ある夏の日、多摩丘陵の一つの丘のてっぺんに住む小説家が、家のすぐ下にある浄水場の芝生に寝ころがって、空を見上げておりました。小説家の名は庄野潤三。その時四十三歳で、間もなく『日本経済新聞』に連載を始める小説の題を考えている最中でした。(阪田寛夫「夕べの雲」)
芝生に寝転がりながら空に浮かぶ雲を眺めていると、ちょっと目を離した隙に、雲はもう違う色の別の雲になっている。
今の今まであったものが、もうなくなっている。
刻々と移り変っていく雲は、そのまま新聞連載小説の作品タイトルとなった。
「いまそこに在り、いつまでも同じ状態でつづきそうに見えていたものが、次の瞬間にはこの世から無くなってしまっている具合を書いてみたい」と考えたからである。
そうして、『夕べの雲』では、何気ない日常生活の中の「今」を、スケッチのように描き出した。
庄野さんにとって、作家人生の大きな転機ともなった代表作は、多くの愛読者を獲得し、友人・阪田寛夫も、その一人となったのである。
ただ「現在」を愛し、慈しむという庄野哲学
実は、阪田寛夫と庄野潤三は、民間会社で同僚だったという経歴を持つ。
私が庄野さんと初めて話を交わしたのは、右のエッセイ(夕刊新大阪「わが文学の課題」)発表の二年後で、一九五一(昭和二六)年九月のことでした。その秋十一月に電波を出す大阪の民間放送(ラジオ局)に就職して、配属された部署の上司が庄野さんなのでした。小学校、中学校の先輩で顔は見知っていましたから、ふしぎな出逢いにびっくりしました。(阪田寛夫「夕べの雲」)
当時の庄野さんについて、阪田さんは「恰幅も姿勢もよく、ワイシャツの袖をまくり上げて、その時せっせと手紙を書いておられました。ずいぶん勤勉で、言語明晰で、健康な人だと思いました」と回想している。
懐かしい庄野さんの思い出が続いた後で、話は冒頭の『夕べの雲』へと戻っていく。
五人家族が楽しく暮らす山は、やがて大規模な団地の造成で姿を大きく変えていくのだが、刻一刻と変化していく世の移り変りを、著者はただ無抵抗に受け入れていく。
そこには、すべてのものは移ろうものだという、庄野さんの人生哲学が反映されているからだ。
時の流れに逆らうのでもなく、世の移り変りに嘆くのでもなく、ただ「現在」を愛し、慈しむ。
それが、庄野さんの生き方であり、庄野文学に共通して流れている通奏低音である。
子どもらの声も幻の声かも知れず、「いつも家の中で聞える子供たちの声や細君の声も、もしそんな風に考えるなら、同じように彼の耳に聞えた」と作者は述懐します。それは『方丈記』のような無常を唱えるのではなく、この世での生活がどんなに懐かしいかと低い声でたたえる歌なのでした。(阪田寛夫「夕べの雲」)
おそらく、阪田さんは、庄野さんのそんな自然体の生き方に憧れていたのではないだろうか。
書名:受けたもの 伝えたいもの
著者:阪田寛夫
発行:2003/9/20
出版社:日本キリスト教団出版局
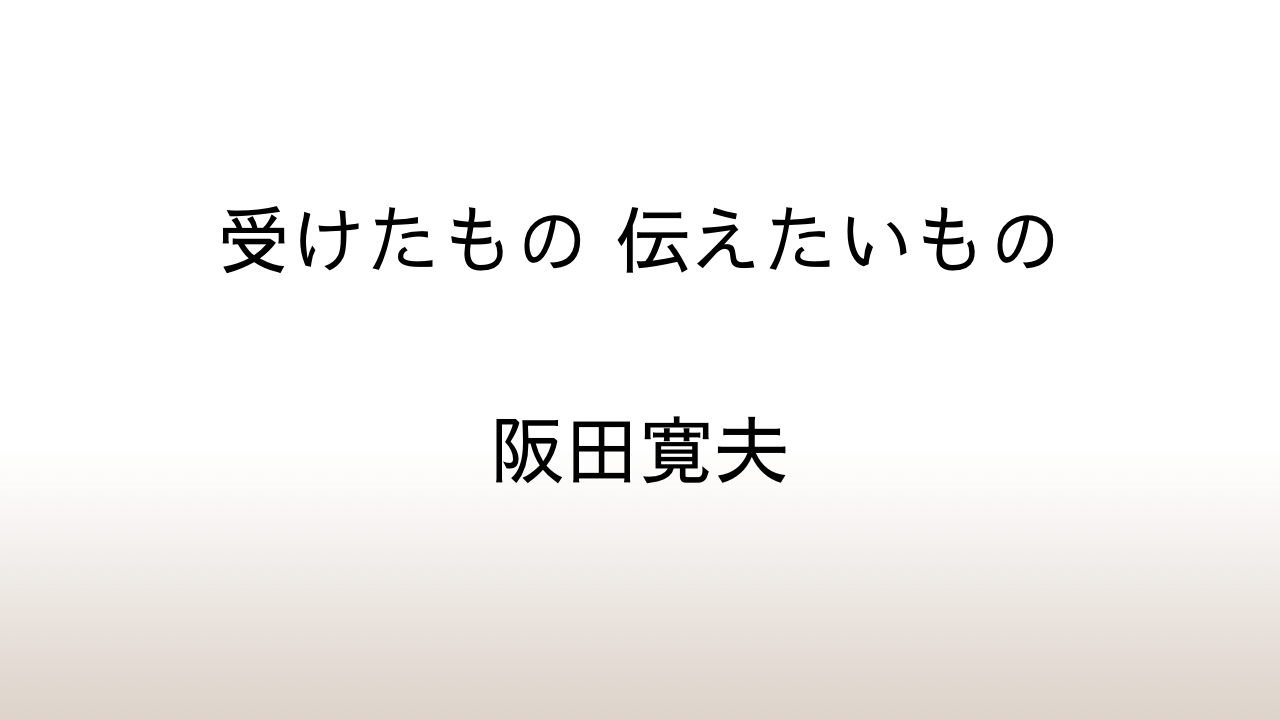
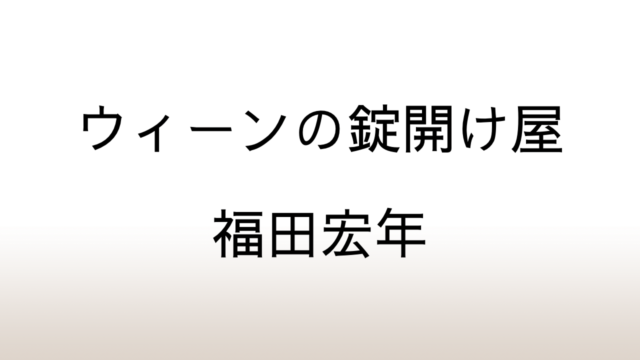
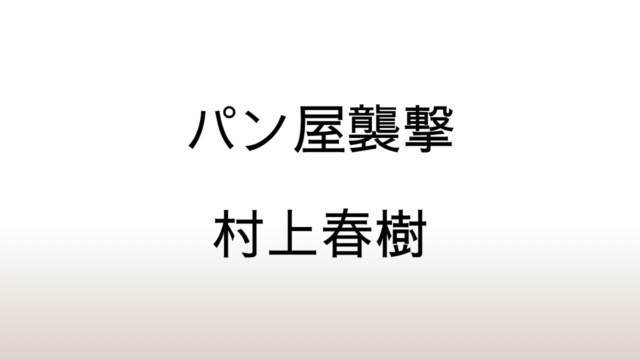

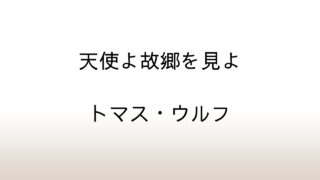
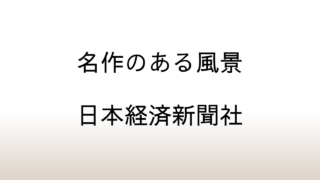
-150x150.jpg)









