和田芳恵「おもかげの人々」読了。
本作は、昭和32年(1957年)から昭和33年(1958年)にかけて、雑誌『婦人朝日』に連載された「名作のモデルを訪ねて」を書籍化したエッセイ集である。
近代日本の文学作品に登場するヒロインのモデルを取材
小説はフィクションだが、小説の登場人物には、モデルとなった実在の人間がいる場合がある。
本書は、近代日本の文学作品に登場する女性(主にヒロイン)のモデルと思しき人物を取材して、その近況を伝える内容となっている。
例えば、日本の自然主義文学の礎石として知られる田山花袋の『蒲団』は、家庭を持った中年の作家が、自分の女弟子に惹かれる気持ちを、性欲中心に赤裸々に描いた作品だが、作家の女弟子<横山芳子>のモデルとなったのが岡田美知代である。
本作では、美知代の経歴に詳しく触れて、田山花袋の家庭で暮らすことになったときの状況を事細かに綴っている。
このとき、花袋は、数えの三十四歳で、夫婦生活も六年目になり、とっくに倦怠期にはいっておりました。花袋は、二十九で利佐子と結婚するまで童貞をまもっていたような人ですが、抑圧した性欲からくる妄想には悩まされていたのです。それに、妻の妊娠から花袋の性生活は阻害されていたのです。(和田芳恵「おもかげの人々」)
日本の自然主義文学では、自分の性生活を明け透けに描くことが、その特徴とされていたが、本作においても、田山花袋と岡田美知代の関係は、かなり綿密に描写されている。
また、耽美派の作家として有名な谷崎潤一郎の代表作『痴人の愛』は、若い女性に振り回される中年男性の悲しい姿を描いた物語だが、そのヒロイン<ナオミ>のモデルとされているのが、神戸市在住の和嶋せい子である。
せい子は、著者の取材に対して、質問も写真もてんで受けつけようとはせず、「だめよ」「だめだめ」の一点張りで、取材班をかなり困らせたらしい。
「痴人の愛」のナオミから、その当時、ナオミズムという流行語が生れました。ナオミ・イコオル・せい子ではありませんが、ナオミズムは、貞操観念のない女性の変態性欲を指しています。その実態は、ひとりの女性の、多くの男性たちとの性的乱交を意味します。(和田芳恵「おもかげの人々」)
実際、せい子は取材に対して、「私は、若いころは、いろんなことをやった。いろんなこともあったさ。しかし、早く卒業してしまったからね」と答えており、大正末期に「イット」と呼ばれたモダンガールの匂いを漂わせている。
もう一人、島崎藤村の代表作『新生』は、作家の<岸本>が、姪の<節子>と肉体関係を持ち、節子を妊娠させてしまう物語だが、節子のモデルと呼ばれているのが、島崎こま子である。
本作では、藤村と別れた後のこま子の生活も詳しく紹介されているが、取材に答えたこま子の言葉が印象的である。
私は、こま子と別れ際に、「なにか、自分の過去を顧みて、こう生きたらよいというような、なにか、若い人に伝える言葉があったら……」と申しますと、こいつ、自分が後悔でもしていると思ってやがるなと、この人は感じとったらしく、「私は間ちがっていなかった。正しい道として生きてきたのです」と、少しはげしい口調で早口に答えました。(和田芳恵「おもかげの人々」)
創作のモデルが、まるで小説の登場人物そのもののよう
小説にモデルがあったとして、モデルはモデルであって、小説の登場人物ではない。
しかし、本作では、創作のモデルが、まるで小説の登場人物そのものであるかのように、赤裸々に解体されていく。
プライバシーの侵害とか名誉棄損とかいう範疇をとっくに越えていると思われるくらい、その内容は激しく衝撃的だ。
今の時代には、到底無理な企画だろうが、こうしたモデルに対する取材が、文学作品に対する理解を深めてくれたことも、また事実なのかもしれない。
何より日本の近代文学が、作者の実体験を重視しているという創作スタイルが、このルポルタージュからは読み取ることができる。
近代文学にあって、読者は明らかに、作品中の登場人物を作者自身としてとらえ、作品中のドラマを作者自身の体験したこととして理解していたのだろう。
こうした傾向は、自然主義文学が台頭してきた時代にあっては、特に顕著なものになったと思われるが、それは自然主義文学以外のジャンルにおいても同様であった。
取材班は、取材拒否を恐れて、あえて事前のアポ取りをせずに突然押しかけたり、写真撮影を拒否された場合に備えて盗み撮りする手順を整えたりと、その取材過程においても、現代ではコンプライアンスに反すると思われるものも多い。
今になってみると、無茶苦茶なルポルタージュだが、文学的緊張感を、これほどまでに感じる作品も、そうそうないだろうなあと思った。
書名:おもかげの人々──名作のモデルを訪ねて
著者:和田芳恵
発行:1976/
出版社:光風社書店
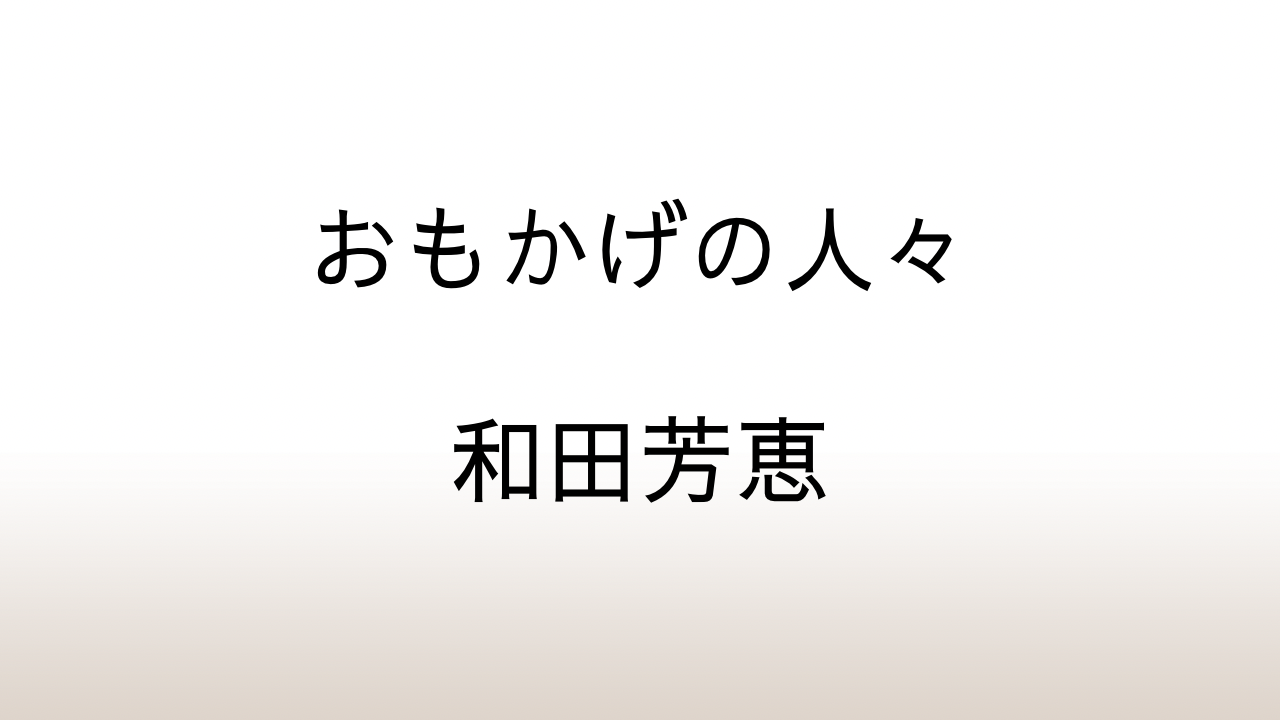


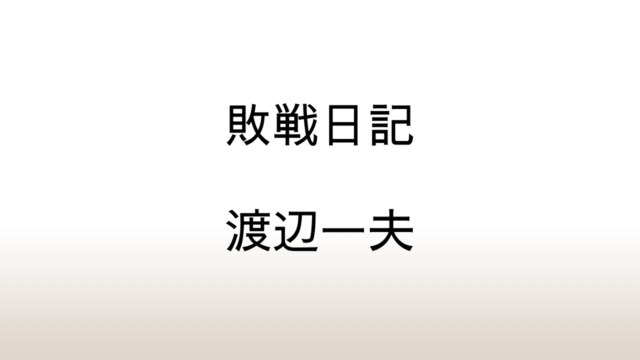
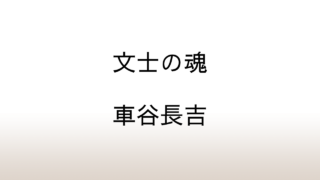

-150x150.jpg)









