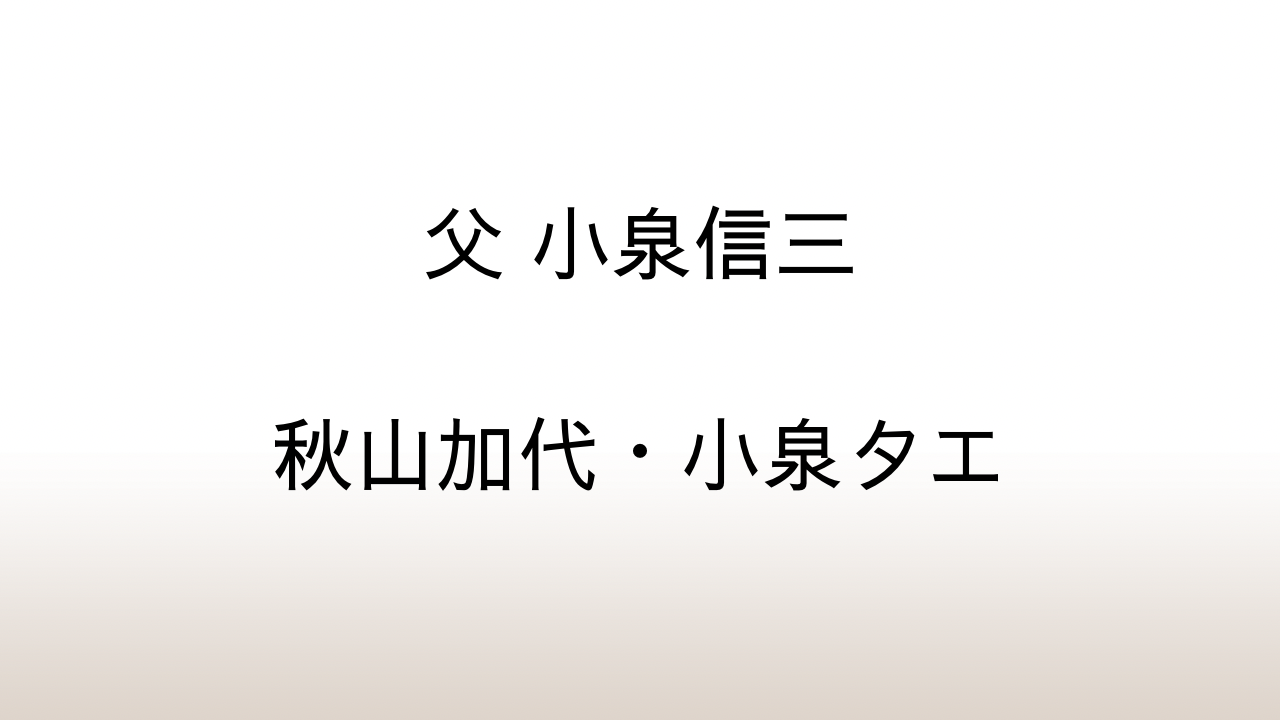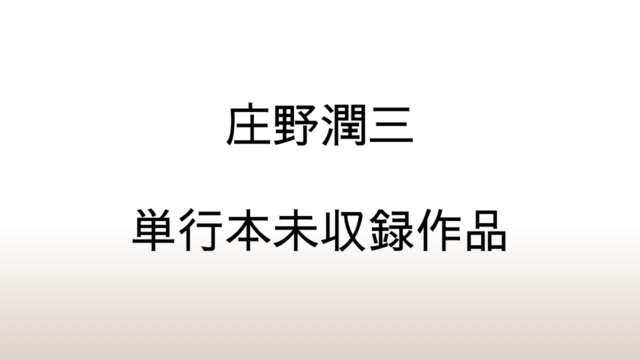秋山加代・小泉タエ「父 小泉信三」読了。
本書「父 小泉信三」は、1968年(昭和43年)に刊行されたエッセイ集である。
空襲の記憶と火傷の痕
姉妹二人による共著で、父・小泉信三の回顧録である。
小泉信三を知る上で貴重なエピソードが多いが、真っ先に注目したいのは、小泉信三の顔に、生涯の傷痕を残すことになる、空襲の記憶だろう。
アメリカ軍の焼夷弾の直撃を喰らった小泉邸は、その夜のうちに焼け落ちてしまうが、はじめ、消火活動に当たった小泉信三は、家の中で炎に巻き込まれてしまう。
全身火傷の重傷を負ったものの、生命を取り留めただけでも奇跡的なことだったのかもしれない。
「お前たち、おれが死んだら、眼と口はすぐ縫いつけて、とじさせてくれよ」と父はよく言った。父が亡くなった直後、私はすぐそれを思った。しかし、眼を母が撫で、父の愛した姪やその他の親しい方々が撫でると、縫わなくても、父のまぶたは、きっちりと閉じられた。(秋山加代「空襲と父の負傷」)
火傷から月日が経った後、「父の顔は、やけどのあとの方が本物」のようにさえ、感じるようになったそうである。
もう一つ、注目しておきたいのは、妹・タエの夫<準三>が、膵臓炎で危篤に陥ったときのエピソードだ(昭和41年の話)。
旅先の父に電話をかけて、準三の急病を伝えたとき、信三は「ああ、どうか、どうか」と言ったまま絶句したという。
妹が不幸になったら、父はどんなに悲痛な晩年を送らなければならないか。考えていると、恐ろしさがひしひしと迫って、家に帰ってからも、胸許がつまって息苦しかった。(秋山加代「最後の誕生日」)
このときのことは、準三の妻・タエも綴っている。
準三は、タエと二人で、鎌倉の句会に参加した翌日(4月30日)、激痛を覚えて入院するのだが、そのときの句会で選に入った準三の作品を、タエが信三に報告した。
「それはシャボン玉の句で、”灯台の子は一人吹くしゃぼん玉”……」と言い足した時、父が「可哀想」と低い声で言い、すすりあげて泣き出した。私は、父があわてた動作で箸を置き、手を目に当てるのを、変に落着いて見ていたように覚えている。(小泉タエ「別れ」)
結局、準三は、どうにか一命を取り留めるのだが、予想だにせず、その直後(5月11日)、信三が急死してしまう。
人生の不思議を感じないではいられないエピソードである。
小泉信三の素顔をスケッチする
本書では、日常の小泉信三の素顔をスケッチした、貴重な作品も多く、エッセイ集としては、むしろ、そうした素描的な作品に楽しめるものが多い。
例えば、『味の味』に発表した「食卓」は、小泉信三の食生活について紹介したもの。
食後は必ず甘い物をとった。「サムスィングスヰート」と湯呑みをもって食卓を離れながらいって、大てい食後は書斎で食べた、羊羹、カステラ、ナッツの入ったチョコレート、京都の大納言、岐阜の栗きんとん。どういう考えからか、必ずほんの一口残した。(秋山加代「食卓」)
イギリスに留学していた頃の名残りなのか、小泉タエは「食べる物がパンのせいもあって、朝の父は少し英国人に似ていた」と綴っている。
果物のジュース、半熟卵、トースト、ママレードや蜂蜜、紅茶。目の前の卓に並んでいるそれらを、ホテルでメニューにしたがって運ばれてくるときのように、順々に食べる。このほかにチーズやレバーペーストなどが加わることもあった。(小泉タエ「晩年の日常」)
2人の娘にとって、イギリス帰りのダンディな父は、自慢の父であったのだろう。
回想の中にも、亡き父親に対するリスペクトが感じられる、凛としたエッセイ集だと思った。
書名:父 小泉信三
著者:秋山加代・小泉タエ
発行:1968/10/20
出版社:毎日新聞社