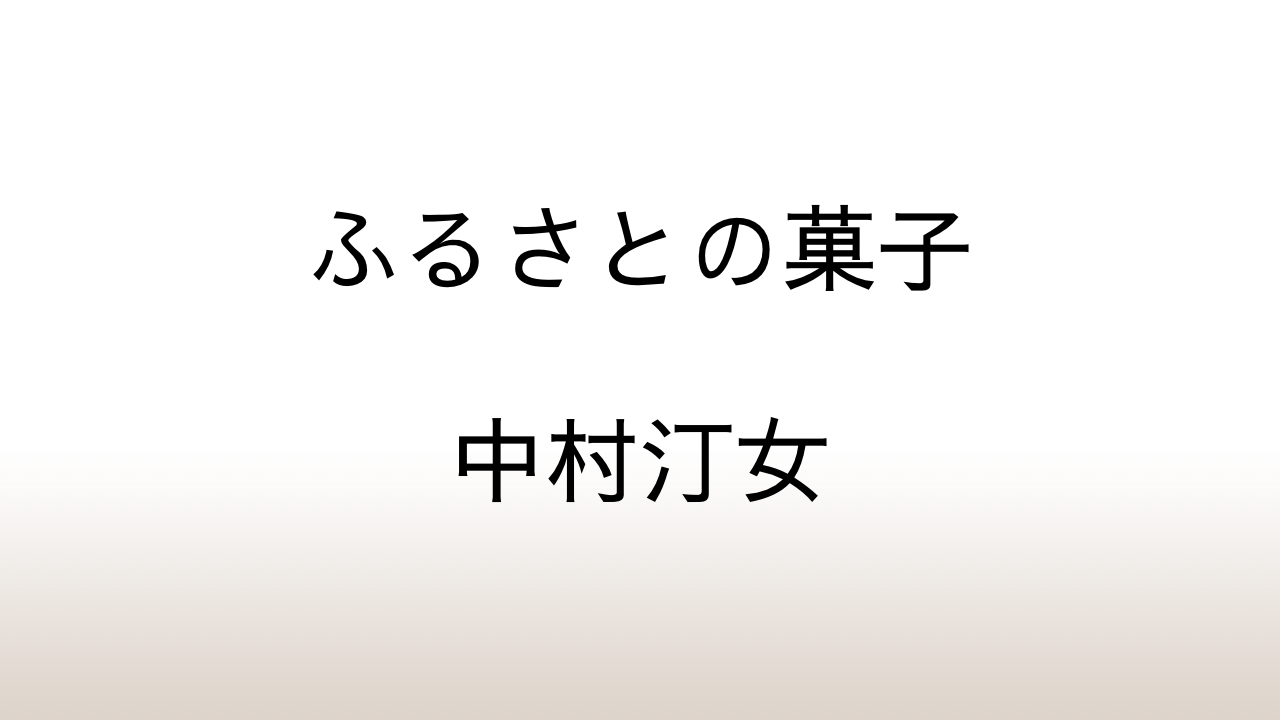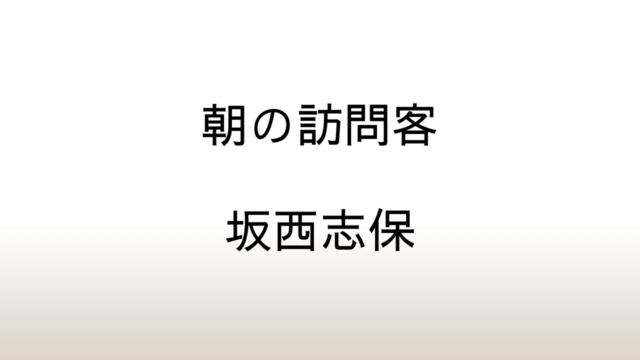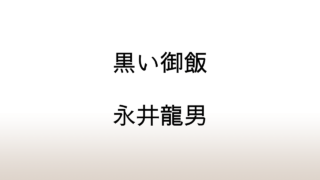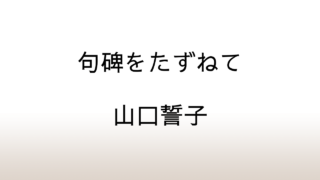中村汀女「ふるさとの菓子」読了。
本書「ふるさとの菓子」は、1955年(昭和30年)に刊行された随筆集である。
この年、著者は55歳だった。
なお、初出は『婦人朝日』『婦人画報』とある。
文学で全国菓子めぐりを楽しむ
本書は、俳人・中村汀女が、全国各地名産の菓子を紹介する随筆集である。
ひとつのお菓子に短い文章と俳句が添えられていて、読んでいるだけで全国菓子巡りをしているような気持ちになる。
例えば、新潟県高田市にある大和屋惣兵衛の「笹あめ」は、こんな感じ。
熊笹の一枚ずつに一なすりの飴がたたんでる。ぷんと笹の香がして、これこそまぎれのない飴の味。二言三言興じているうちに忘れたように解けるので、また遠慮ない手を延ばして、つい顔を見合わせながら、ひどく愉しい。嵩ばらず身綺麗なこの素朴な包装はいつもでも自慢していい。漱石の「坊っちゃん」で、きよばあやは「越後の笹飴が食べたい」と言っているが、この薄手のなめらかなふくみ心地を、きよも好きなのだろう。(中村汀女「ふるさとの菓子」)
夏目漱石の『坊っちゃん』の話が出てきて、そうか、清の食べたかった越後の笹飴は、この飴のことだったのかと気付く。
四国の学校への赴任が決まって、坊っちゃんは東京を離れるのだが、土産に「越後の笹飴が食べたい」という清に、坊っちゃんは「越後の笹飴なんて聞いた事もない、第一方角が違う」と考える、あの場面だ。
戦後も、昭和30年代くらいまでは、地方都市には地方都市の独自色があった。
『ふるさとの菓子』という作品が成立しているのも、全国各地に個性豊かなお菓子があったからこそだろう。
鎌倉駅通にある豊島屋の「鳩サブレー」は、俳人・久保田万太郎がこよなく愛したことでも有名。
「これやこの鎌倉みやげ花ぐもり」「鎌倉の春としまやの鳩さぶれ」という二句に続いて、短い文章がある。
久保田万太郎先生の、この二句を入れた、和紙のすっきりした包装に、ぱっと鎌倉の春光が来る。材木座のお宅、拭き込んだ長火鉢のあるお部屋で鳩サブレーは、先生が気軽にこの句に筆をとられたかと思うと私もいい気持である。(中村汀女「ふるさとの菓子」)
コロナ禍前に、鎌倉で鳩サブレーを買ったとき、今も包装紙に久保田万太郎の俳句が載せられているのを見て感動した。
歴史というのは、こうして積み上げていくものなんだと、納得したような気がする。
お菓子から季節感を拾う
ふるさとのお菓子は、地方にばかりあるのではない。
東京名物のお菓子も少なくなくて、例えば、銀座にある空也の「空也もなか」などは、東京を代表する銘菓だろう。
種の焼も秋の日ざしの色。稔りの色。つぶし餡の中に光り輝く小豆の誘惑。あれだけたっぷりの餡をふくんで、びくりともしない種ものの手ざわりの好ましさ。谷崎、小島、舟橋諸氏、播磨屋も常連と聞くが、老舗の味はさすがにありがたい。(中村汀女「ふるさとの菓子」)
谷崎潤一郎、小島政二郎、舟橋聖一の名前が見えるが、いずれも、食には大いなる関心を寄せた文士たちである。
文豪の名前におもねるお菓子ではなく、名だたる文豪も共感を寄せたお菓子ということなのだろう。
著者は俳人だから、季節感のすくいとり方が絶妙に上手い。
「種の焼も秋の日ざしの色。稔りの色」と、空也もなかからさえ季感を拾っているのかと、驚いてしまう。
本書の後半は、お菓子を離れて、幅広く食べ物の季節感と向き合う随筆がまとまっている。
「心の花圃」では、またまた、久保田万太郎の俳句が登場していてうれしい。
それは「べんとうのうどのにつけの薄暑かな 万太郎」という作品である。
先日のいとう句会、四国の旅行から馳せつけられた久保田万太郎先生の作。そのうどの香りと味に旅情おのづからなるものがあり、改めてうどのすきとおるような白い色を好ましく思い浮べたけれど、庭隅に年々、手軽く採れる季節のものに、私たちはずいぶん深く励まされ、いたわられている生活のようである。(中村汀女「ふるさとの菓子」)
俳句は、人の営みと向き合う文学なのかもしれない。
本書『ふるさとの菓子』は、そうした基本を思い出させてくれる、ほのぼのとした随筆集だ。
書名:ふるさとの菓子
著者:中村汀女
発行:1955/6/10
出版社:中央公論社