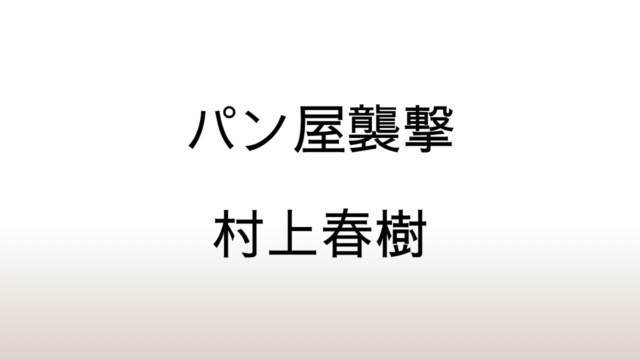小沼丹『埴輪の馬』読了。
本作『埴輪の馬』は、1986年(昭和61年)9月に講談社から刊行された短篇小説集である。
この年、著者は68歳だった。
小沼丹にとって、最後の短篇小説集で、収録作品及び初出は次のとおり。
「煙」
1980年(昭和55年)7月『群像』
「ゴムの木」
1981年(昭和56年)3月『新潮』
「十三日の金曜日」
1981年(昭和56年)6月『海』
「連翹」
1982年(昭和57年)1月『文芸』
「大きな鞄」
1982年(昭和57年)2月『文学界』
「翡翠」
1982年(昭和57年)5月『海燕』
「散歩路の犬」
1982年(昭和57年)11月『文学界』
「夕焼空」
1984年(昭和59年)1月『海燕』
「トルストイとプリン」
1986年(昭和61年)2月『海燕』
「童謡」
1974年(昭和49年)1月『群像』
「埴輪の馬」
1976年(昭和51年)3月『文芸』
小沼丹最後の短篇小説集
本作『埴輪の馬』には、全部で11篇の短篇小説が収録されている。
生前に刊行された小沼丹の短篇小説集としては、本書が最後のものとなった。
小説以外の著作としても、本書の後には、1992年(平成4年)に刊行された随筆集『清水町先生』しかないから、本書は、小沼丹にとって最晩年の作品集だったということになる(1996年11月、78歳で逝去)。
収録作品11篇のうち9篇は1980年代の最新作で、表題作「埴輪の馬」と「童謡」の2篇は、1970年代の古い作品となっている。
小沼丹の短篇小説は、特別のストーリーのない思い出話が中心だが、単なる昔語りとはならない小説的な面白さがある。
それは、小沼丹の短篇小説が、一見複雑なコラージュ作品のように、立体的な構造となっているからだろう。
ひとつの作品は、主要なエピソードと枝葉のエピソードという、複数のエピソードによって構成され、さらに、それぞれのエピソードは、時間軸ごとに切り分けられて、パズルのピースのような断片となる。
小沼丹の小説の特徴は、時間軸ごとに切り分けられた複数のエピソードが、複雑な配列で再構築されているというところにある。
だから、ひとつのエピソードが、突然、次のエピソードを呼び込んだかと思うと、昔話の中で、さらに昔の話が語られたりしていて、読者は、自分が、今どこにいるのかということを把握することが難しい。
作品を最後まで読み通したとき、初めて全体像が理解できるわけで、読者は「なるほど」と腑に落ちるのだが、こうしたプロットで読ませるテクニックは、エンターテイメント小説の時代に培われたものと思われる。
野球のピッチャーに喩えると、「複数のエピソード」という左右(横)の配球と、「時間軸」という上下(縦)の配球を、小沼丹は変幻自在に組み合わせてくる。
さらに、エピソードによって、球種はストレートだったり、変化球だったりと、緩急を付けてくるから、バッターたる読者が、煙に巻かれてしまうのも当然だろう。
剛速球のストーリーでグイグイと読ませるタイプの作家ではないが、一球一球の配球を計算しながら、最終的に読者を追い込んでいくピッチングが、つまり、小沼丹の短篇小説ということになるのではないだろうか(ひと言で言うと、曲者のピッチャーということになる)。
煙 │ 植木屋の親爺の思い出
「煙」は、戦後すぐの頃に出会った「植木屋の親爺」を中軸に、「近所の交番の警官」や「近くへ越してきた友人(天狗太郎こと、将棋記者の山本亨介)」「古い友人である眼科医」などを登場させながら、懐かしい思い出を最構築した作品である。
特別のストーリーはないものの、複数のエピソードが、時間軸を切り離してバラバラに配列されているので、困惑しつつも読者は、思わず引き込まれてしまう(これを「魅惑」というのかもしれない)。
さらに、現代から過去への導入が、巧妙に仕組まれているのは、小沼丹必殺の「魔球」みたいなものだろう。
ちろちろ燃え上る焔とか、風にながれる煙を前に立っていると、知らない裡に昔も今も区別が附かなくなって、どこにいるのか判らなくなる。みんな、煙と消えてしまう。(小沼丹「煙」)
煙に巻かれているうちに、読者は時間の感覚を失ってしまう。
時間の感覚を失うという快感が、小沼丹の短篇小説にはある。
近所の小川の水車や米軍の将校宿舎、中島飛行機会社の工場(武蔵境にあった)、国鉄スワローズ(1950年設立)の本拠地だった幻の野球場など、さりげなく語られる武蔵野市の昔話もいい。
なお、旧中島飛行機工場跡地に建設された「幻の球場」こと「武蔵野グリーンパーク野球場」は、1956年(昭和31年)に閉鎖された(開催試合はわずか七試合のみ)。
ゴムの木 │ 米原さんと次女(秋子)の思い出
「ゴムの木」は、いわゆる「大寺さんもの」として最後の作品となった。
大寺さんが初めて登場するのが、1964年(昭和39年)の「黒と白の猫」だから、最後の作品まで、実に20年以上の時間が経過したことになる。
ストーリーの中心となっているのは、大学の同僚(米原さん)の思い出と、次女(秋子)の昔話だが、二つのエピソードが複雑に配置されて、この物語を立体的な文学作品としている。
「──米原さんが亡くなったのは、何年前だったかしら?」「──もう十年ぐらいになるんじゃありませんか?」「──もうそんなになりますか……」河は日夜流れて、愁人のために少時も止ることが無い。米原さんに最后に会ったのはいつだったろう?(小沼丹「ゴムの木」)
この米原さんの思い出が、いつの間にか、大寺さんの次女<秋子>の思い出へとつながっていく。
かつて、米原さんは「秋子を養子にしたい」と言い出したことがあったのだ。
米原さんの思い出から離れて、次女の話へと展開していくように見せながら、主役であり、舞台回しでもある「ゴムの木」が、二人のエピソードを巧みに繋ぎ合わせていく。
いつだったか、大寺さんの娘の秋子が、ちっぽけな男の子を連れて大寺さんの家に遊びに来たとき、何かの弾みで思い出したのだろう、「──ウエンズさんに頂いたゴムの木、どうしたかしら? まだ、あります?」と訊いた。「──あれだ」と大寺さんが教えてやると、「──まあ、驚いた。あんなに大きくなったの?」と眼を丸くした。(小沼丹「ゴムの木」)
成長したゴムの木と小さな男の子(秋子の子どもだろう)が、時間の経過を示しているが、詳しいことには触れられていない。
昔話をしているのに、具体的な時間が示されていないのは、「あれは何年前のことだった」という話ではなく、「昔昔あるところに、、、」と言って始まる昔話のような曖昧さを感じさせることになる。
あるいは、読者はそんなところにも、不思議な割り切れなさを感じてしまうのではないだろうか。
そして、そんな割り切れないところこそが、小沼丹の小説の魅力ということなのだろう。
次女(秋子)は、『椋鳥日記』で主人公(小沼さん)と一緒にロンドンへ滞在する、次女「李花子」がモデル。

同僚(米原さん)は、ドイツ文学者だったと思われる(「ドイツに辛夷は無いでしょう?」)。
十三日の金曜日 │ 二羽の文鳥の思い出
「十三日の金曜日」は、かつて飼っていた文鳥の思い出に、学生時代の友人の記憶などを織り込んだ作品である。
戦争が終って三、四年経った或る年の二月頃だったと思う。その頃はまだ吉祥寺の駅に陸橋があったが、或る日、その陸橋からプラットフォームに降りて行ったら、停車中の下り電車の窓際の席に、何某が澄して坐っていた(小沼丹「十三日の金曜日」)
ど真ん中ではないエピソードにこそ、小沼丹の技が光る。
「巴里帰りの友人に貰った珈琲挽き」は随筆「珈琲挽き」(『珈琲挽き』所収)に、文鳥と喧嘩をする山鳩は短篇小説「山鳩」(『山鳩』所収)に登場するなど、他の作品とのリンクを楽しむことができるところは、小沼文学の、もう一つの醍醐味となっている。

連翹 │ 先輩作家・小山清の思い出
「連翹」は、作家・小山清の思い出を綴ったものだが、清水町先生(井伏鱒二)や太宰治、横田瑞穂、吉岡達夫などが登場して、文壇史的にも興味深い内容となっている。
小山清はもちろん、太宰治に関するエピソードにも注意が必要だ(「この頃、私は先輩を訪問しても、なるべく早く失礼しようと心掛けています」)。
甲州の御坂峠に太宰治の文学碑が建つことになったとき、その敷地と石を見に行こうと、清水町先生に誘われて、小山清や吉岡達夫と一緒に随いて行った話もある。
年譜でいうと、1953年(昭和28年)7月の「山梨県御坂峠に井伏鱒二らと太宰治文学碑の敷地の下見に出かけ」とあるやつだろう。
ちなみに、前年(1952年)に、御坂峠を越えて波高島へ遊んだときの話は「凌霄花」に詳しい(『山鳩』所収)。
小山清の妻が自殺したとき、葬式の準備をする人がいないというので、吉岡達夫が某出版社の石井君と二人で近くの寺へ行って頼んだという話も貴重だ。
小山清が亡くなったのは、1965年(昭和40年)3月6日のこと。
大学入学試験の採点が終わって荻窪で飲んでいると、清水町先生が四、五人連れで入ってきた。
何か会でもあったのかと思って、「──今夜は何ですか?」と訊くと、「──小山君の所へ行って来たんだ」と先生が云った。続いて吉岡が、小山さんが今日死んだんだ、と云ったからたいへん驚いた。何だ、君は知らなかったの? と先生は云われたが、無論、何も知らない。(小沼丹「連翹」)
小山さんの家の庭に黄色の花がたくさん咲いていたらしい(「──そりゃ、連翹じゃないかな。あれはいま頃咲くから……」)。
「何だか、大きな黄色の花環が見えたような気がする」という一文で締めくくるあたり、何気ない昔話を小説に変えてしまう小沼丹らしいテクニックだ。
小山清は享年53歳。
小沼さんは、この年、47歳だった。
大きな鞄 │ 学生時代の友人(関口)の思い出
「大きな鞄」は、学生時代の友人(関口)の思い出を綴った作品。
蓬髪で、大きな鞄を抱えた関口は、長篇青春小説『風光る丘』に登場する「福島虎之助」のモデルとなった人物だ。

同じく、学生時代の友人として登場する「金井」は、玉井乾介がモデルになっていて、早朝の雑司ヶ谷霊園を散歩する話は、別の作品でも描かれている。
関口が死んだと判ったのは、戦争が終って三、四年経ってからだと思う。昔の友人の一人に聞いて知った。最初、死んだと聞いて、戦死したのだろうと思ったら、何の病気か知らないが、「――病気で死んだそうだ」と友人が言った。(小沼丹「大きな鞄」)
学生時代の友人の思い出を書いた作品は、シリーズものとして、まとめることができるかもしれない。
翡翠 │ 学生時代の友人(石川隆士)の思い出
「翡翠」は、学生時代の友人(石川隆士)に捧げられた追悼小説で、石川は「市川」という名前で描かれている。
主人公(小沼丹)は、清水町先生(井伏鱒二)の紹介で、市川と知り合うのだが、その頃、市川は「二十世紀の憂鬱を独りで背負い込んだ顔」をしていたとある。
二人は『海燕』という名前の同人誌を始めようとするが、ロシア人(ブブノワさん)に書いてもらった表紙絵を紛失したため、雑誌の名前は『胡桃』に変更された(この辺の話は、「胡桃」に詳しい(『木菟燈籠』所収))。

作品タイトル「翡翠」は、石川隆士の書いた詩に由来している。
石川の詩では、「渓流」と云う題の詩が記憶にある。多分、「早稲田文学」に載ったような気がするが自信は無い。作品が手許に無いのではっきり想い出せないが、谷川に向って書き損じた手紙を千切って捨てる、捨てながら紙片に、「──翡翠になれ、翡翠になれ」と呼び掛けるのである。(小沼丹「翡翠」)
この詩のことは、井伏鱒二も、「仲人」という随筆に書いていて、石川隆士は「房木君」という名前で登場している(井伏鱒二と石川隆士とは同郷で、戦後に石川隆士が結婚したとき、井伏さんが仲人になった)。
井伏鱒二は、「九月二十日記」でも、石川隆士の「翡翠」を引用しているから、この詩を気に入っていたのだろう(『還暦の鯉』所収)。

1981年(昭和56年)の1月、小沼さんの出版記念会(『小沼丹作品集』か『山鳩』だろう)で久しぶりに再会したとき、石川は何となく元気がないように思われた。
ちなみに、随筆「長距離電話」(『小さな手袋』所収)で、石川は、名古屋の新聞社に勤務していることが綴られている。

小沼さんの出版記念会のために、名古屋から荻窪までやってきたらしい。
石川と会って話をしたのは、それが最後になった。
今年の正月の二日、石川の奥さんから電話があって、石川が死んだと知らせて来たからたいへん驚いた。何でも去年の夏ごろから入院していたらしい。病気は脳出血で、元日に死んだそうだが、「──元旦にお知らせするのもどうかと思いまして……」と奥さんが云った。(小沼丹「翡翠」)
「どこか遠くの方から、翡翠になれ、翡翠になれ、と云う声が聞えて来るような気がした」と続いているところが、小沼スタイルというやつだが、物語は「翡翠」では終わらない。
ブラジルのサン・パウロにいる金井からの手紙に、ブラジルはやぽたんとか云う大木が一杯に花を付けていて、紫がかった夾竹桃も満開だと書いてある。
「一体、紫色の街とはどんな感じがするものかしらん? やぽたんの花とは、どんな花な
のだろう?」と、まるで石川の死をはぐらかすようにして物語が終わるところは、小沼丹の熟練の技ということだろう。
散歩路の犬 │ 関前界隈の移り変わり
「散歩路の犬」は、主人公の散歩コースを通して、時代の移り変わりを描いた作品である。
具体的な記述はないが、主人公(物語の語り手)が小沼丹であることを考えると、この散歩コースは、武蔵野市関前ということになるだろう。
つまり、本作「散歩路の犬」は、関前界隈の移り変わりを描いた作品ということになる。
この小説を片手に、実際に関前辺りを歩いてみたら、きっと楽しいかもしれない(ただし、1982年の作品だが)。
大体、木そのものが無くなっているのだから、枝がある筈が無い。いつ伐ってしまったのかしらん? 何だか知らない裡に、いろいろ変って行くようである。それから、「――あの犬も知らない間に消えてしまったな……」と歩きながら独言を云った。(小沼丹「散歩路の犬」)
散歩路を離れて、荻窪「後家横丁」の飲み屋「きらく」の女将が亡くなったエピソードが挿入されているところもいい。
試みにその女に「──きらくってどこだっけ?」と訊いてみたら、女は此方の顔を見て、「──きらくさんは亡くなりました」と云ったから吃驚した。(小沼丹「散歩路の犬」)
案外、主軸ではない、こうしたエピソードに、重要な意味が込められているのかもしれない。
夕焼空 │ 学生時代の級友(吉田)の思い出
「夕焼空」は、学生時代の級友(吉田)の思い出を綴った作品。
電車に乗って上野の近くを通ったときに見た遠くの赤い夕焼け空から、主人公(物語の語り手)は古い友人を思い出す。
本作「夕焼空」は、懐かしい日々の記憶の物語だ。
遠くの赤く染った空を見ながら、何か想い出せそうで想い出せない中途半端の気分でいたのだが、その二人の話声を聞いたら、不意に、遠い昔に行ったことのある或る病院を想い出した。それが上野の近くにあったことは知っているが、どの辺だったかとなると全然判らない。何故、そんな遠い昔の記憶が甦ったのかしらん?(小沼丹「夕焼空」)
小沼丹の小説では、なにかしらタイム・スリップのきっかけとなるものが登場する。
そして、それが作品タイトルと密接な関わりを持つことが多い。
この作品の場合、「夕焼空」がタイム・マシンのような役割を果たしている。
主人公(物語の語り手)は、吉田に頼まれて、上野にある病院に入院中の若い女のもとへ手紙を届ける。
「あの女」が、吉田とどのような関係にあったのか、最後まで明かされないが、昭和初期の東京の雰囲気が郷愁を誘う、青春の一篇だ。
短い物語のクライマックスは、死んだ友人と酒を酌み交わす夢の場面である。
あるいは、吉田の奴、酔い過ぎたかもしれないと思って「おい、しっかりしろ」と声をかけると、いつの間にか吉田がいない。
もちろん、死んだ人間が最初からいるはずもないのだが、ここに、主人公の喪失感がある。
突然、「──あの女はね……」と云い出した。どの女かと訊くと、上野の病院にいた女だと云うから、漸く何さんに就いて詳しい話が聞けると思う。「──あの女はね……」「──うん」「──あの女はね……」空回りするレコオドのように、あの女はね……、ばかりで一向に先に進まないから焦れったい。(小沼丹「夕焼空」)
一体、同じ記憶を共有している人間の死というのは、生き残った人間にとって、常に大きな喪失感を与えるものなのではないだろうか。
「一体、いつ帰ったのかしらん?」と言って、語り手は物語を締めくくるが、もちろん、彼が「帰ったのではない」ことは、語り手自身が誰よりも理解をしている。
古い友人を失ったことで生まれた、心の中の小さな隙間。
そんな隙間を埋めるような作品を、小沼さんは書き続けていたのかもしれない。
トルストイとプリン │ 吉岡達夫とヨーロッパ旅行の思い出
「トルストイとプリン」は、1972年(昭和47年)にオーストリアのザンクト・アントンを訪ねたときの思い出を交えた短篇小説である。
当時、小沼さんは、早稲田大学の在学研究員としてロンドンに滞在中で、日本からやってきた吉岡達夫とともに、キュウタイからインスツブルクを経て、チューリッヒへと小旅行をしている。
「トルストイとプリン」に「友人」として登場するのが吉岡達夫で、ザンクト・アントンへ行く前に訪れたインスツブルクという街での思い出を綴った紀行随筆「山の中にある町」という随筆では、吉岡達夫が本名のままで登場している(『福寿草』所収)。

また、ザンクト・アントンで木彫りのマリア像を買った話は、既に「マリア像」という随筆に書かれている(『珈琲挽き』所収)。

本作「トルストイとプリン」が小説的技巧を持っているのは、懐かしい旅の記憶に、現在の入院生活が組み合わされているからだろう。
1984年(昭和59年)年末、小沼さんは、糖尿病による心筋梗塞のため、武蔵野市の西窪病院へ入院するが、このとき、見舞いに訪れたのが、かつて一緒にヨーロッパを旅行した吉岡達夫だった。
この友人とは、昔一緒にヨオロッパ旅行をしたことがあるからだろう。「――早く元気になれよ。また一緒に外国旅行をしようや。あれは愉快だったなあ……」友人は、そんなことを云って、それが切掛で昔の旅行の想い出話をした。(小沼丹「トルストイとプリン」)
生涯で最も多くの思い出を共有した友人(吉岡達夫)に捧げる作品。
なお、吉岡達夫には『仏蘭西「田舎」遺聞』(1981)などの作品がある。

童謡 │ 太った女性を愛した信州の叔父の思い出
「童謡」は、信州の叔父の思い出を綴った作品。
年譜によると「母方の小林家は信州南佐久郡にあり、青沼村の名主を務めた家柄」とある。
背は低いが太っていて、「痩せた女性は不美人」だと考えている叔父の家で、小学校時代の主人公(小沼丹だろう)は、半年間ほど暮らしていたらしい。
頭のどこかが変になって、何でもすぐ忘れてしまう病気にかかった叔父は、間もなく死んでしまった。
ある晩酒を飲んでいたら、同席の若い一人が童謡を歌った。何気無く聞いていると、遠くの方から洋傘を持った叔父が歩いて来て、にこにこ笑った。その向うにちかちか光る千曲川の川波も見えたようである。おや、と思ったら不意に眼の前に雲がかかって、みんな見えなくなってしまった。(小沼丹「童謡」)
伯父を舞台回しとして、信州の小学校で知り合った同級生(三公)や、片腕のない美人のお神さんなど、幼少期の思い出が語られていく。
埴輪の馬 │ 井伏鱒二と弘光寺を訪ねた日の思い出
表題作「埴輪の馬」は、「埴輪の馬」を買おうと突然に思いたった主人公が、埼玉県「弘光寺」まで出かける話だが、「埴輪の馬」そのものは重要なテーマではない。
かつて、清水町先生(井伏鱒二)をはじめとする仲間たちと弘光寺へ出かけたときの思い出が、この物語の大きな柱となっているからだ。
年譜でいうと、1951年(昭和26年)10月にある「井伏鱒二らと埼玉県岡部町針ヶ谷の弘光寺を訪ね、出迎えた消防自動車に乗る」と記されている部分だろう。
つまり、この物語は、小沼丹が、初めて弘光寺を訪ねたときの思い出話が、主要なストーリーとなっているのだ。
真面目そうな若い運転手が直立不動の姿勢でお辞儀をすると、先ず清水町先生が衆人環視の裡に俯き加減に運転席の隣に坐った。途端に見物人の一人の子供が大声で、──あっ、村長さんだ。と叫んだ。(小沼丹「埴輪の馬」)
本堂の奥に古ぼけたかごが二挺置いてあった話や、座敷で宴会をしている最中に住職が行方不明になった話などは、長篇青春小説『風光る丘』にも挿入されている(井伏鱒二は「多良鯉三先生」として、弘光寺の住職は、「運徳寺」の住職、通称「ベラフォンテ和尚」として登場)。

念のため、年譜を参照すると、1975年(昭和50年)12月として「弘光寺を訪ね、和尚の紹介で名人の工房から埴輪の馬を買い持ち帰る」と記されている(本作「埴輪の馬」発表は1976年3月)。
このとき、自動車を運転してくれたのが<夏川君>で、<夏川君>は最初に清水町先生と一緒に弘光寺へ行ったときのメンバーの一人の弟だった。
無職の某君と書いた兄の夏川君は、現在では或る会社の社長で、なかなか忙しいらしく長いこと会っていない。しかし、兄の夏川君を想い出したら、昔、一緒に消防自動車に乗った人の弟の運転する車で同じ弘光寺へ行く、それは別に偶然ではない筈だが、そのときは何だか偶然のように思われて面白かった。(小沼丹「埴輪の馬」)
小沼丹が弘光寺を訪れるのは、これが三度目で、二度目は1960年(昭和35年)4月のところに「井伏らと弘光寺を再訪、長瀞に遊ぶ」とあった。
なお、講談社文芸文庫の裏表紙に「表題作『埴輪の馬』では、埴輪様式の土器の馬を購入のため、師井伏鱒二や友人と出かける」とあるのはおかしい。
井伏鱒二と出かけたのは昔のことで(1951年と1960年)、1975年(昭和50年)に埴輪の馬を購入するために出かけたときは、、夏川君ただ一人が一緒だったのだから。
まとめ │ 小沼丹の記憶は、多くの読者の記憶でもある
本書『埴輪の馬』は、「小沼丹最後の短篇集」と呼ぶにふさわしい作品集である。
すべての作品に、過去の記憶の断片がちりばめられていて、作品集全体が、古い記憶を乗せて回る走馬灯のようだ。
思うに、小沼丹は(特に晩年は)やがて消え去ってしまうだろう「記憶」を書き残しておくために、小説を綴っていたのではないだろうか。
言ってみれば「文化的終活」である。
あるいは、小沼丹という作家は、生涯をかけて、小説という終活作品を書き続けていたのかもしれない。
結果として、一人の作家の死とともに消え去るはずの記憶は、多くの短篇小説として後
世に受け継がれることになった。
小沼丹の記憶は、多くの読者の記憶でもあるのだ。
書名:埴輪の馬
著者:小沼丹
発行:1999/03/10
出版社:講談社文芸文庫