庄野潤三「紺野機業場」読了。
本作「紺野機業場」は、石川県小松市安宅にある小さな織物工場を舞台とした長編小説である。
1969年に芸術選奨文部大臣賞を受賞している。
この年、庄野さんは48歳だった。
人々の暮らしの積み重ねが、日本という国を描いていく
庄野潤三は、庶民の暮らしを通して、日本を描くことにこだわり続けた作家である。
日本の中に生きる人々を描くのではなく、人々の暮らしの積み重ねが、日本という国を描くことに繋がっていった。
本作『紺野機業場』は、そんな庄野文学の、ひとつの完成形であると言っていい。
一人の人間の半生が日本という国を描き出すまでに、とにかく、庄野さんは徹底的に話を聴いている。
物語の主人公は、織物工場を経営する紺野友次である。
紺野は、我が半生を語りながら、一族の人々を語り、安宅の人々を語り、北陸の人々を語る。
安宅の伝承を語り、己の信仰を語り、病を語る。
祖父母の話は江戸期にまで遡るし、我が半生の中には、日露戦争や太平洋戦争が登場する。
人と人との繋がりが、やがて大きな物語を構築していく。
庄野文学の特異なところは、他者に取材した話を作家がまとめるのではなく、あたかもドキュメンタリー映画の生フィルムを観るかのように、取材の過程を含めて再現されていることだろう。
著者のねらいは、あとがきの中に書かれている。
それも歴史という風な改まったものでなしに、聞き手の人間がその町へ訪ねて行く度に、いろんな話を順不同に書きとめるという形にしたい。身内の者でもなければ興味の無いと思われることでも、遠慮なくしゃべって貰う。むしろそういう話を聞きたい。云わば炉辺談話の積み重ねのようなものであるが、その中から「日本」が浮び上らないとも限らない。(庄野潤三『紺野機業場』)
このあとがきを、庄野さんは「長い間、質実な心持で生きて来た(そうでない人も無論いる)田舎町の人の生活の流儀から、先ず教わりたい気がする」という言葉で締めくくっている。
都会の作家が田舎まで出かけて行って話を聞いてやる、そんな上から目線がない。
むしろ、神妙な面持ちで(ただし、日本酒で酔っぱらいながら)、庄野さんは田舎で生きて来た人たちの話に聞き入っているのである。
作家と地域の人々との温かい交流
本作『紺野機業場』は、いわゆる聞き書き小説である。
安宅で織物工場を営む主人公の、取りとめもない回顧録とも言える。
「安宅の水戸つかえ」や「のた越しのぼら」など、安宅の伝承に着目すれば、これは貴重な民俗史の記録になる。
一方で、主人公の半生に着目すれば、これは庶民にスポットを当てた評伝ということになる。
主人公の織り成す交流から考えると、安宅という町を舞台にした庶民史になる。
縦糸と横糸とが複雑に絡み合って美しい模様を描いている。
おもしろいのは、こうした話を聞きとるための取材の過程が、作品の一部として、生き生きと描かれていることである。
紺野氏は、そばにいるおばあさんから話を聞き出しては、私に分るように云い直してくれた。おばあさんは耳が遠いし、そこへ工場の音がするので、紺野氏はおばあさんに聞く時、顔をそちらへ寄せて、よほど大きな声を出した。例えば、「ばあちゃん、ばあちゃん。雨は降ったがや」という風に。(庄野潤三『紺野機業場』)
この作品が、単なるルポタージュではなく、文学作品として高い気品を漂わせているのは、こうした取材のやり取りそのものが、安宅で生きる人々を描くことに成功しているからだろう。
庄野さんの聞き書き小説の楽しさは、作家と地域の人々との温かい交流にある。
そう考えると、こんな小説は、やはり庄野潤三という小説家にしか書けなかったのだ。
書名:紺野機業場
著者:庄野潤三
発行:1969/11/12
出版社:講談社
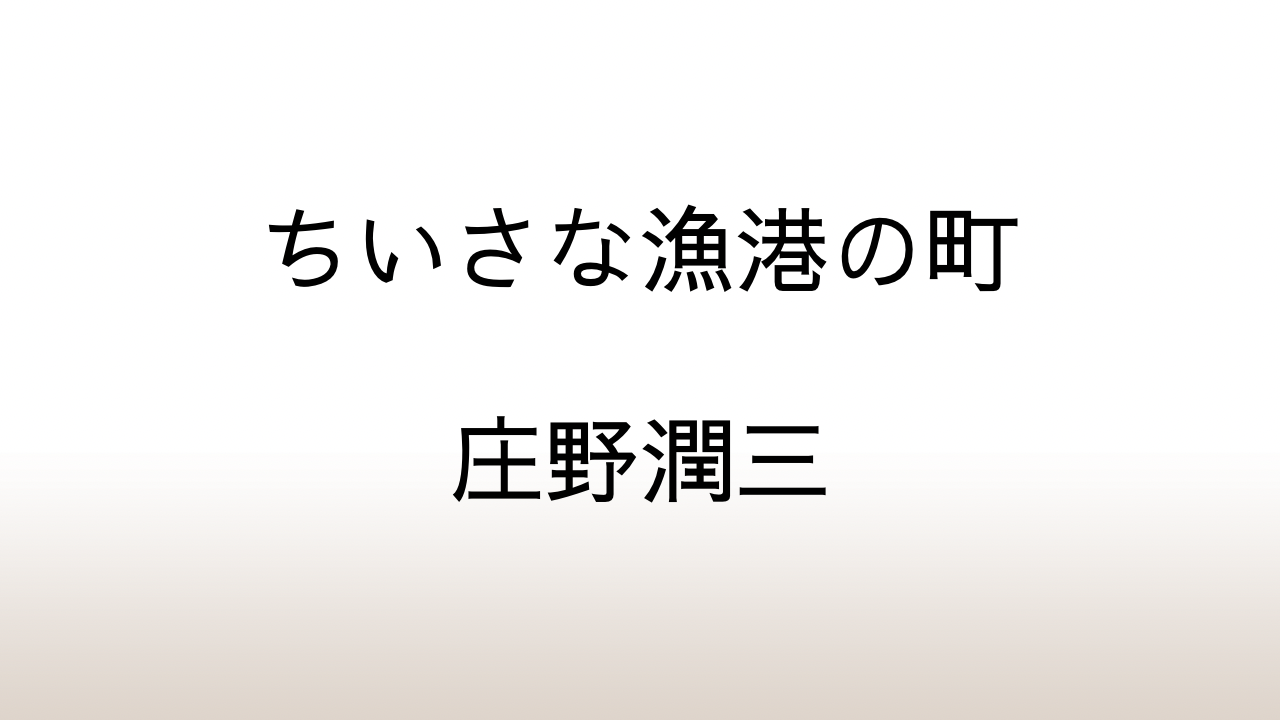


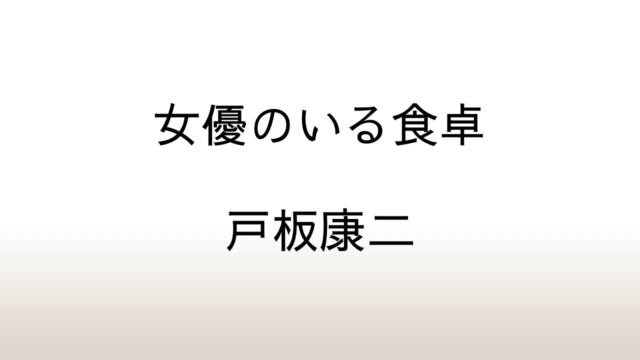
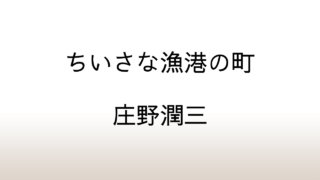
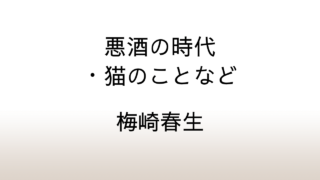
-150x150.jpg)









