内田樹「もういちど村上春樹にご用心」読了。
本書は、<村上春樹ファン>を自認するフランス文学者が書いた、村上春樹に関する書評やエッセイを集成したものである。
筆者にはもともと『村上春樹にご用心』という著作があるのだが、そのうち特に重要と思われるものと、その後に発表したものを再構築する形で『もういちど』が製作された。
新曲が何曲か含まれているベスト・アルバムのようなものだとは、著者自身の解説。
同じく著者が「これは村上春樹さんへのファンレターです」と言っているように、ここに収録された書評やコラムは、ほとんどすべてが村上春樹作品に対する全肯定的な姿勢によって綴られたものだ。
ある特定の文学者の作品を、ここまで全面的に肯定するなんて、かなり熱狂的なファンでなくてはできないことだろう。
そして、すべてのコラムに底流しているものは、「村上春樹の作品は、どうして世界中の人々に支持されているのか」という、一つの大きなテーマである。
おそらく、本書の著者にとって、村上春樹が世界中で支持される理由を解明することは、村上文学の魅力を解明することと同じ意味を有しているのだろう。
村上春樹の新作が出るたびに、著者はその書評の中で、この謎に挑み、これまでに幾多の仮説を積み上げてきたが、もちろん、それほど簡単に謎は解明したりしない。
どうして村上春樹の作品は世界中で読まれているのか。
いろいろな仮説が呈される中で、いちばんしっくりきたのは、世界の人々は、村上春樹が描く「存在」に共感したのではなく、その「欠落」に共感したとする説だ。
どうして村上春樹はこれほど世界的な支持を獲得し得たのか? それは彼の小説に「激しく欠けていた」ものが単に八〇~九〇年代の日本というローカルな場に固有の欠如だったのではなく、はるかに広汎な私たちの生きている世界全体に欠けているものだったからである。私たちが世界のすべての人々と「共有」しているものは、「共有されているもの」ではなく、実は「共に欠いているもの」である。(内田樹「激しく欠けているもの」について)
著者の主張を、ちょっと村上春樹的に例えてみると、読者は村上春樹の作ったドーナツの味や触感に共感するのではなく、<ドーナツの穴>に共感している、ということだ。
味覚や触感に対する好みは多様で、世界中で共感を得ることは難しいかもしれないが、ドーナツの穴は国境を越えて普遍的であり、世界中の人々が、ドーナツの真ん中に生まれた「欠落」に共感したと考えると、村上春樹の作品が世界中で支持される理由がなんとなく分かるような気がする。
文学を論じるときに大切なことは、この「なんとなく分かるような気がする」という部分で、全部が簡単に分かってしまっては、つまらない文学作品ということになってしまいかねないし、あまりにも何も分からないと、読む価値がない作品ということになってしまう。
村上春樹の作品は、大抵の場合、よく分からないからこそ、むしろ良い作品だという評価
へと繋がっていく。
本書『もういちど村上春樹にご用心』を読みながら、そんなことを、つくづく感じた(というくらい、本書にも何を言っているか分からないような、難解な話が多い)。
『羊をめぐる冒険』と『長いお別れ』と『グレート・ギャツビー』
そうした中、本書でも特に分かりやすいと感じたのは、『羊をめぐる冒険』は『長いお別れ』(レイモンド・チャンドラー)のリメイクであり、『長いお別れ』は『グレート・ギャツビー』(スコット・フィッツジェラルド)のリメイクだとする仮説である。
管理人は(という多くの人が)、『長いお別れ』を読みながら『羊をめぐる冒険』に似ているなと感じた(はずだ。ちなみに、管理人にとっては『羊』が先で『長いお別れ』が後だった)。
構造もディティールも『羊』は『長いお別れ』のオマージュだったから、似ていると感じて当たり前なんだけれど、村上春樹の解説本というものを読まない管理人にとって、それはなかなか斬新な発見だった。
そして、『ギャツビー』を読んだときに『羊』に似ていると感じたことも、やはり偶然ではなかった。
『羊をめぐる冒険』も『長いお別れ』も『グレート・ギャツビー』も兄弟のような作品なのだから、当然といえば当然である。
チャンドラー、フィッツジェラルド、村上春樹、彼らの底流にあるもので、僕が一番惹き付けられたのは、嫌な人が出てきてなにかをした場合でも、「なんでこの人はこういうことをするのか」って、できるだけフェアな視点に立ってその人の事情を理解しようとする姿勢です。(【特別対談】柴田元幸×内田樹『村上春樹はからだで読む』)
思うに、村上春樹の作品は、鋭い文学論ではなくファンレター的な書評で読む方がすっきりするようだ。
書名:もういちど村上春樹にご用心
著者:内田樹
発行:2010/11/30
出版社:アルテスパブリッシング
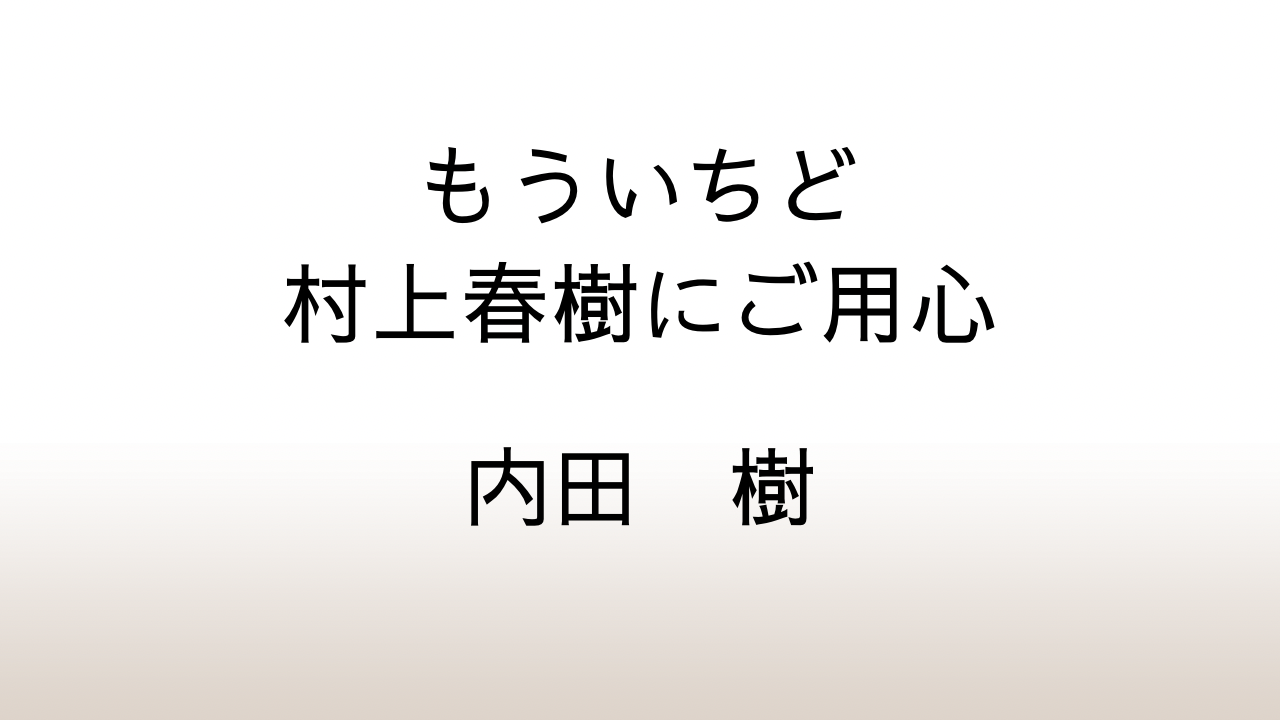

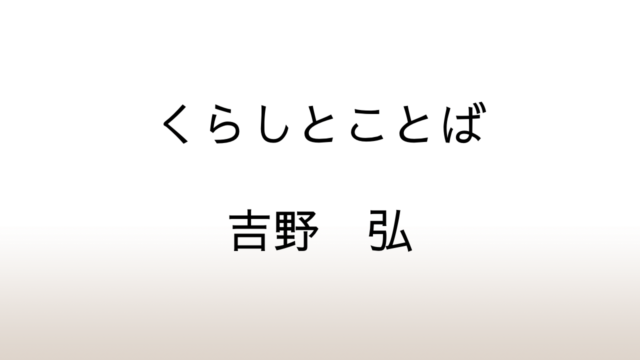
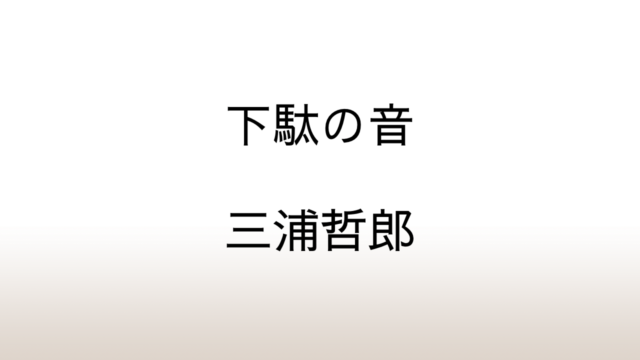

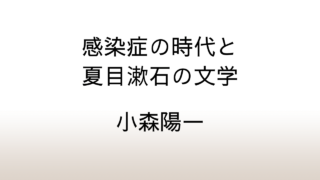
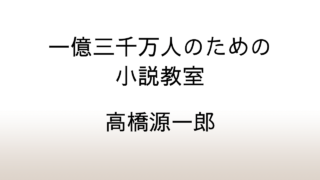
-150x150.jpg)









