庄野潤三「庭の小さなばら」読了。
題名に「庭の小さなばら」とあるが、特別に「バラの花」の本というわけではない。
自宅の庭に小さなばらが咲いている庄野夫妻の日常をスケッチ風に描いた小説で、庄野さんの晩年のライフワークとなっていた「夫婦の晩年シリーズ」の作品である。
「夫婦の晩年シリーズ」については、本作中でも触れられていて、「子供がみな結婚して、孫の数も八人になった、家に二人きり残された夫婦が、いったいどんなことをよろこび、どんなことをたのしんで暮してゆくかを書くというのが、私のテーマであり、その第一作の『貝がらと海の音』(新潮社)が出てから、年月たった。文芸誌への連載という形の私の仕事はとぎれず続いてゆく。この「文學界」の「山田さんの鈴虫」が第六作となる」と書かれている。
さらに、「そうして「山田さんの鈴虫」に続く新潮社の「波」の「うさぎのミミリー」が、来月から始まろうとしている」とあって、この「夫婦の晩年シリーズ」を書き続けることに対する庄野さんの情熱が伝わってくる。
ちなみに、本作「庭の小さなばら」が「群像」に連載されたのは、2002年(平成14年)1月号から12月号だが、本作で書かれている内容は、2000年(平成12年)5月から2001年(平成13年)1月までの庄野家の出来事である。
連載当初から登場している「フーちゃん」も、本作では中学2年生となった。
フーちゃんに限らず、庄野さんの夫婦の晩年シリーズでは、既出のエピソードが何度も繰り返し登場しているのが特徴である。
ひとつのエピソードを連載のどこに組み込むかといったような構成上の計画性よりも、書きたいことを書きたいままに書くという執筆姿勢が、如実に表れているのではないだろうか。
僕(ブログ管理人)の場合、「エイヴォン」というバラが登場するたびに、「エイヴォンといえば、イギリスの田舎を流れている川だ。ほら、『トム・ブラウンの学校生活』のなかで、トムが学校の規則を破って釣りをする川が出て来るが、あの川の名がエイヴォンだよ」と言いながら、そのとき連載を始めようとしていた長編随筆のタイトルを『エイヴォン記』としたというエピソードが大好きで、「ほら、『トム・ブラウンの学校生活』のなかで、、、」という回想が出て来ないと、「夫婦の晩年シリーズ」を読んでいる気がしない。
この『エイヴォン記』に関する回想は、本作『庭の小さなばら』でもしっかりと登場しているので、何だか安心した心持ちになる。
もはや予定調和とさえ言っていいほど、庄野さんの晩年の作品は安定的である。
今も庄野さん晩年の作品が「静かなブーム」などと言われるのは、この安心できる予定調和に秘密があるのではないだろうか。
心の安らぎと安定を求める気持ちに、庄野さんの作品はしっかりと応えてくれる。
「夫婦の晩年シリーズ」は、本作で第八作目となるが、最初の頃の作品に比べると、文章のリズムはかなりゆったりとしてきている。
文学が作者の生活のリズムと連動していることを感じさせてくれている、そんなことを思った。
生まれ故郷へ帰っていく子どもたち
本作では、庄野さんの長女(夏子)の長男(和雄)夫婦の引越し先が決まったというエピソードが出てくるが、和雄夫婦の引越し先が「餅井坂」だったというところが楽しい。
結婚して庄野家を出た長女夫婦が最初に居を構えたのが、この餅井坂で、例えば、昭和47年に連載されていた『野鴨』という長篇小説の中では、黍坂(餅井坂がモデル)で暮らす長女が、生後二か月の長男を連れて実家を訪ねるシーンが出てくるが、このときの「生後二か月の長男」が和雄のことである。
あのときの赤ん坊が結婚して夫婦となって、かつて自分が生まれた街「餅井坂」へと戻ってくるという話は、偶然とは言え、文学の素晴らしいところだと感じた(実際には、決して偶然ではなくて、ある意味での必然性を伴ってはいるのだが)。
一貫して家族をテーマとした小説を書き続けてきた庄野さんだからこその物語ではないだろうか。
書名:庭の小さなばら
著者:庄野潤三
発行:2003/4/10
出版社:講談社
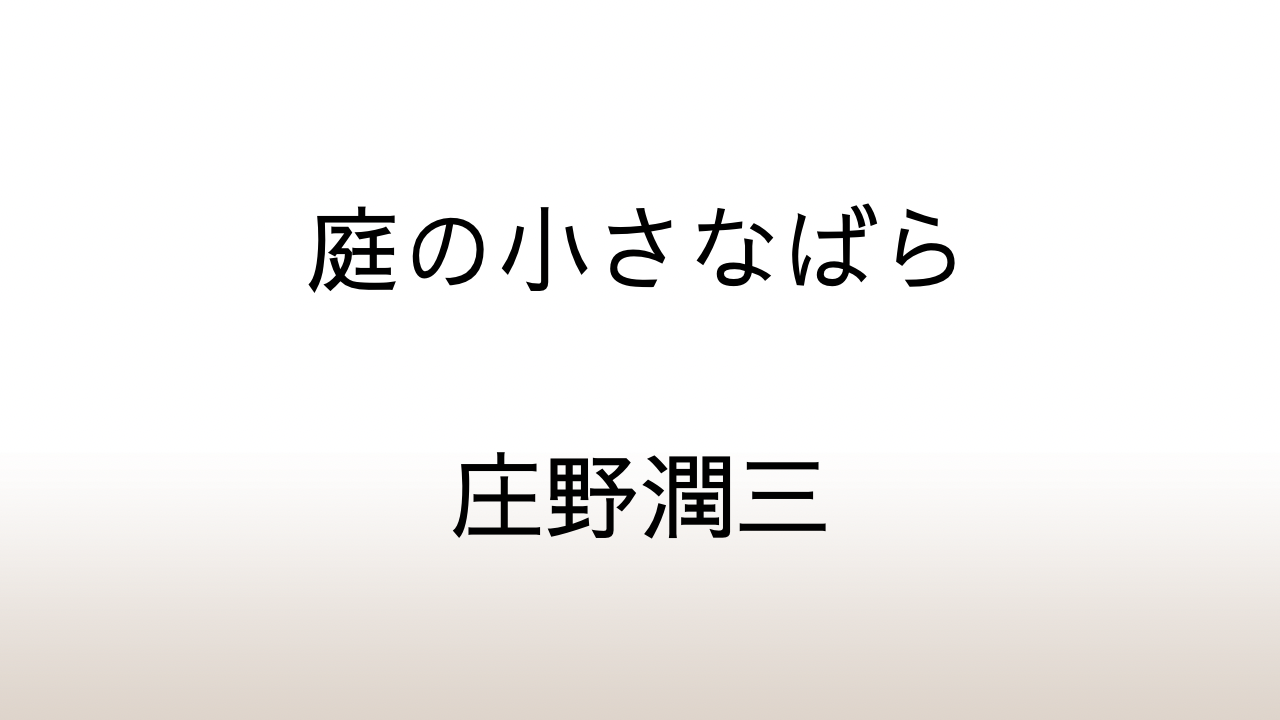


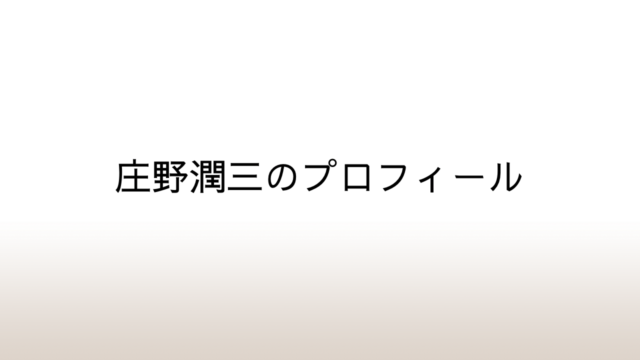

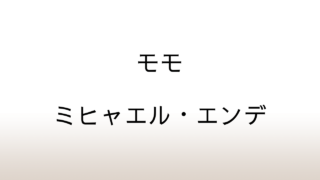

-150x150.jpg)









