チェーホフ「シベリヤの旅」読了。
本作「シベリヤの旅」は、1890年に発表された、シベリヤ訪問のルポルタージュである。
この年、著者は30歳だった。
人生は思ったとおりになるものではない
本作「シベリヤの旅」は、冒頭こんな書き出しから始まっている。
「シベリヤはどうしてこう寒いのかね?」「神様の思召しでさ」と、がたくり馬車の馭者が答える。(チェーホフ「シベリヤの旅」)
チェーホフと馭者のやりとり、殊に「神様の思召しでさ」という馭者の言葉は、このシベリヤの旅を象徴するものとなっている。
人生は思ったとおりになるものではない。
日本の作家・庄野潤三も、「シベリヤの旅」の冒頭に登場する、この馭者の言葉を好んで引用した。
そういう意味で「シベリヤの旅」は、純粋なルポルタージュ作品というよりは、著者の体験を素材にした文学作品と言った方が的確かもしれないが、ここで、作品のジャンルにこだわってみたところで仕方ない。
「シベリヤの旅」は、ロシアの人間が、遥か異国のシベリヤまで旅をする物語である。
それは、ひと言「旅」という言葉でまとめてしまうには不十分過ぎるくらいに、過酷な旅だった。
通常、旅行記と言えば、滞在先の話題が中心になりそうなものだが、「シベリヤの旅」では、シベリヤへ向かう旅が、どれだけ過酷な移動を伴うものかということが中心に描かれている。
悪路と水害の連続で、チェーホフを乗せた馬車は何度も事故に見舞われながら、シベリヤを目指して走り続けた。
この旅は、チェーホフの心身に、かなりの苦痛を与えたものと思われる。
人生を諦めた人々に対する同情と憐憫
こうした移動の苦労と同時に描かれているのが、旅の途中で出会った人々の荒んだ暮らしである。
いましがた追抜いた百姓たちは、黙りこくっている。天幕馬車について、よろよろする足を引き摺りながら、どの顔を見ても鹿爪らしく何か一心に考え込んでいる風だ。……私はそれを見て心に思う、──「よくない生活と見たら潔くそれを振り切って、生まれ故郷も生れた古巣も棄てて行けるのは、非凡な人間だけなのだ、英雄だけなのだ……」(チェーホフ「シベリヤの旅」)
苦難に満ちた移動を除けば、チェーホフの関心は、周囲の人間に対して向けられているようだ。
そして、ほとんどのコメントはネガティヴなものであって、人生を諦めた人々に対する同情と憐憫によって綴られている。
明治時代、内地から北海道へ向かう人たちは敗残者だと言われたらしいが、シベリヤへ向かう人たちの気持ちも、同じようなものだったのだろうか。
もっとも、北海道への移住には何かしらポジティブな発想が伴っているものだったが、シベリヤでの生活に明るい材料を見出すことはできないらしい。
下等な居酒屋、家族風呂、公然乃至秘密の夥しい魔窟などは、孰れもシベリヤの人間の大好物であるが、これを措いてはどの町にも何一つ遊び場所はない。秋や冬の夜長を、追放者は自分の部屋に坐って過ごすか、ヴォトカを飲みに土地の古顔の所へ行く。二人でヴォトカを二本ビールを六本も倒すと、例によって「ひとつ繰り込むかね」と来る。言わずと知れた魔窟へである。(チェーホフ「シベリヤの旅」)
考えようによっては、こういう世界の果てみたいなところでも、狭いながらにちゃんと社会が成立しているということが不思議のようにも思える。
何より、こんなところへわざわざ出かけて行った、チェーホフという作家のメンタルの強さはさすが。
世の中にまだ、本当の意味での冒険が残されている時代だった。
作品名:シベリヤの旅
著者:チェーホフ
訳者:神西清
書名:シベリヤの旅(他三篇)
発行:1942/11/25改版
出版社:岩波文庫
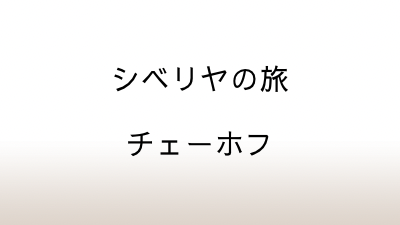


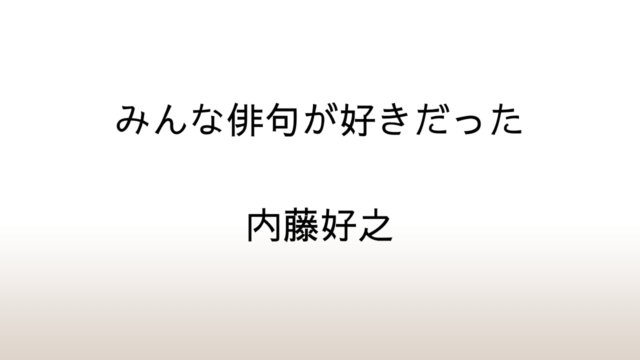

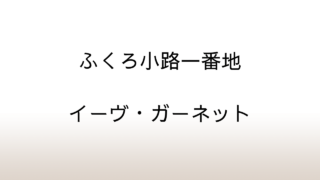
-150x150.jpg)









