庄野潤三「行きずり」読了。
本作「行きずり」は、1965年(昭和40年)3月『文学界』に発表された短編小説である。
この年、著者は44歳だった。
作品集としては、1965年(昭和40年)12月に筑摩書房から刊行された『丘の明り』に収録されている。
朧げな記憶の断片というあやふやなスケッチ
庄野一家が、神奈川県生田の「山の上の家」で暮らし始めたのは、1961年(昭和36年)4月のこと。
間もなく、庄野さんは、生田を舞台とする家族の物語を書き始め、『つむぎ唄』『鳥』『夕べの雲』といった著作を発表する。
こうした「山の上の家」黎明期に発表された短編小説を集めた作品集が『丘の明り』で、「行きずり」は、「冬枯れ」と「まはり道」の間に収録されている。
この「冬枯れ」「行きずり」「まはり道」は、いずれも生田周辺の地域で実際に体験した話を素材としていて、長編小説『夕べの雲』の周辺情報を知ることのできる作品となっている。
本作「行きずり」は、大きく三つの章で構成されていて、最初に出てくるのが、「下の道」で三人の男と一緒になったときの話である。
私の家の向いにある水道局の浄水場では、一昨年の九月から工事をしている。大きな赤松や欅が生えていた山をすっかり崩して、低く平らにしてしまって、そこに新しい沈殿池をこしらえることになった。(庄野潤三「行きずり」)
物語の語り手である<私>は、「下の道」のお菓子屋の前の郵便箱まで手紙を出しに出かけた帰り道で、男たちと一緒になったのだった。
物語は、行きずりの男たちの会話を中心に構成されているが、水道局の工事関係者らしいとは推測できても、そもそも見知らぬ人たちである。
会話の前後の流れも分からないから、<私>は、ただ聞いたままに、男たちの会話を再現していく。
続く二つ目の章は「私の住んでいるところからひとつ東京寄りの駅のフォームで乗換の電車を待っていた時に会った二人連れの男」の話である。
「その駅は遊園地のある駅」で、「東京から急行電車に乗って来ると、ここが二つ目の停車駅」になる。
ちなみに、この駅は、小田急小田原線「向ヶ丘遊園駅」と思われる。
<私>も二人連れの男も、東京から反対の方へ行く電車を待っているところだったが、男たちの会話の詳しい内容は、やはり分からない。
私が覚えている言葉は、二つだけある。ひとつは、「もうここまで来たら、もとへ引き返すわけにはゆかない」という意味の言葉であった。(庄野潤三「行きずり」)
<私>の朧げな記憶の断片だけが、あやふやなスケッチのように描かれている。
誰かが書き留めておかなければ忘れられてしまう日常風景
最後の章は、東京の下町で鰻屋をしている人から聞いた話である。
この鰻屋さんと同町内に<私>の知人で写真家の人がいて、二人ともお父さんの代からそこに住んでいる。
<私>は、写真家の人に誘われて、鰻屋さんがすっぽんを料理するところを見学することになった。
こうして私たちがさまざまな色とかたちをした内臓を見ている時であった。同じ俎の少し離れたところにひとつだけ、置き忘れられたようにしてあったすっぽんの首が、不意にあくびをした。一回、二回と口をあけて、最後に思い切り口をあけたかと思うと、ぱくっと閉じた。これでおしまい、という風に、あとは永久に口を閉じたきりであった。(庄野潤三「行きずり」)
このとき、鰻屋さんは、青ギス釣りをする人たちの話をしてくれた。
どの話も断片的であって、特別の物語性はないが、むしろ、そこに、この物語の意味があるような気がする。
誰かが書き留めておかなければ、やがて忘れられてしまう日常風景。
そういうものに、庄野さんは惹かれたのではないだろうか。
そして、どの話にも、読者の関心を引き出す仕掛けがあり、世間話の面白さといった趣を醸し出している。
よく夢のように過ぎる、というが、僅か四年の間であるのにそのうちの何年目になるのか、見当がつかないというのは心細い気がする。いかにも私がぼうっとして月日を過しているようである。しかし、思い出せないのだから仕方がない。(庄野潤三「行きずり」)
「四年の間」とあるのは、<私>が今の家へ引っ越してから、もうすぐ四年になろうとしていたからである。
四年の間に生田の町は、庄野文学の礎となる素地をちゃくちゃくと磨きつつあったらしい。
作品名:行きずり
著者:庄野潤三
書名:丘の明り
発行:1975/04/25(新装版)
出版社:筑摩書房
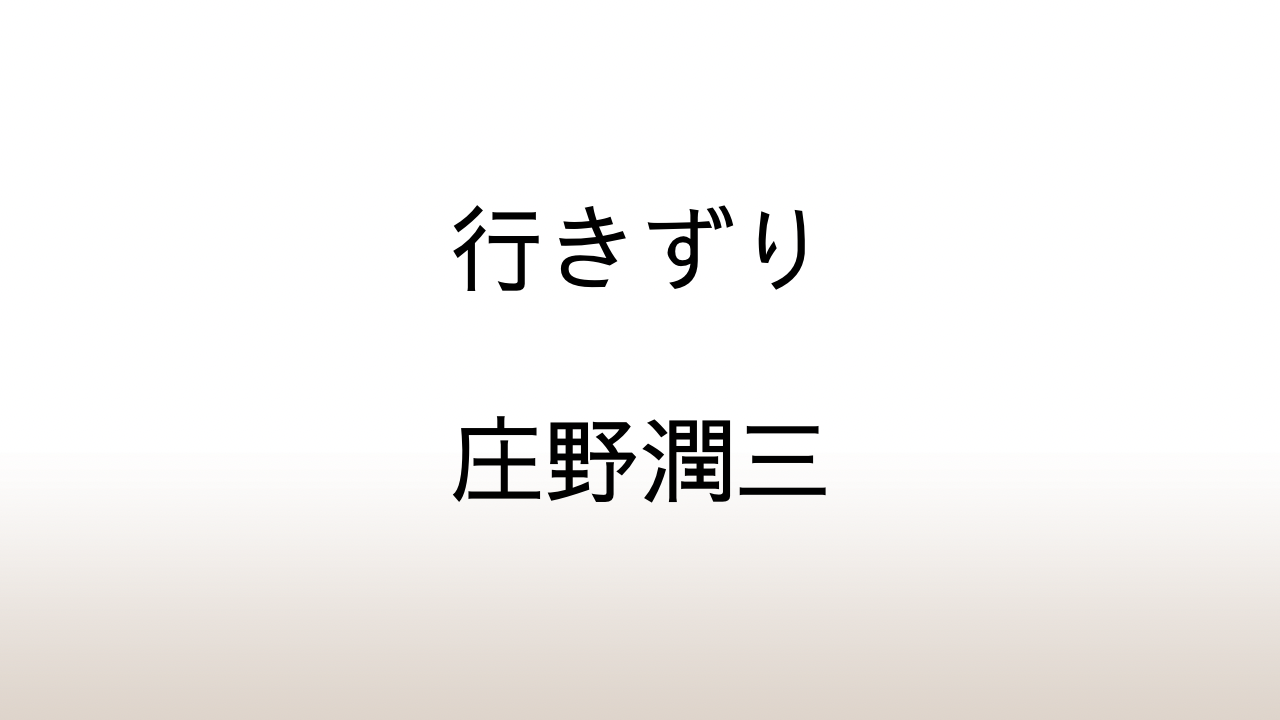






-150x150.jpg)









