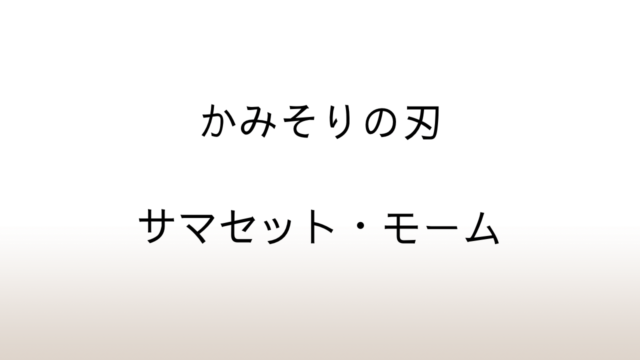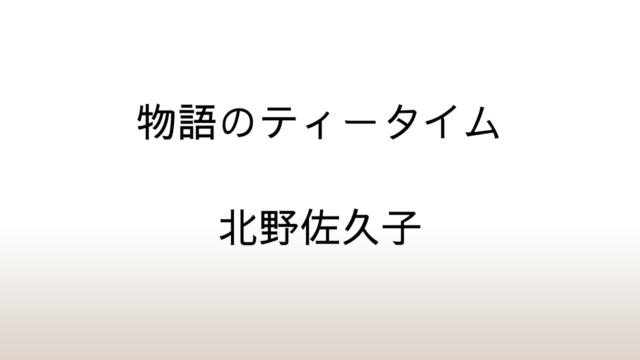レフ・トルストイ「アンナ・カレーニナ」読了。
本作「アンナ・カレーニナ」は、1875年(明治8年)から1977年(明治10年)まで『ロシア報知』に連載された長篇小説である。
連載開始の年、著者は47歳だった。
単行本は、1878年(明治11年)に刊行されている。
アンナ・カレーニナが自殺した理由を読み解く
ロシアの文豪・トルストイの代表作と言われる『アンナ・カレーニナ』は、不倫の末に駆け落ちしたことで、貴族社会から弾き出され、苦悩の自殺を果たした人妻(アンナ・カレーニナ)を主人公とする恋愛小説である。
村上春樹は『アンナ・カレーニナ』が大好きだったらしく、初期の短篇小説『眠り』(1989)では、この小説を重要なモチーフとして用いている(短篇集『TVピープル』収録)。
私は最初の一週間かけて『アンナ・カレーニナ』を続けて三回読んだ。読みなおせば読みなおすほど、私は新しい発見をすることができた。その長大な小説には様々な発見と様々な謎が満ちていた。(村上春樹「眠り」)
阪神・淡路大震災の後に発表された『かえるくん、東京を救う』(1999)でも、『アンナ・カレーニナ』は重要な謎として引用されている(短篇集『神の子どもたちはみな踊る』収録)。
「ひとりで闘います」とかえるくんはしばし考えてから言った。「ぼくが一人であいつに勝てる確率は、アンナ・カレーニナが驀進してくる機関車に勝てる確率より、少しましな程度でしょう」(村上春樹「かえるくん、東京を救う」)
いずれも短篇小説だが、引用元の『アンナ・カレーニナ』を読んでいないことには、物語の真意を理解することが難しい仕掛けになっている。
『眠り』の主人公である人妻が言っているように、本作『アンナ・カレーニナ』は「様々な発見と様々な謎に満ちた」長篇小説なのだ。
基本は確かに恋愛小説だが、時代の転換期にあったロシア社会の矛盾や、生と死、宗教のあり様など様々なテーマが、それぞれに重要な立ち位置を持って提示されている。
タイトルにもなった人妻(アンナ・カレーニナ)の物語と同時並行的に、田舎の貴族青年(リョーヴィン)を主人公とするもうひとつの物語が進行していく構成もいい(個人的にはリョーヴィンの物語の方が好きなほど)。
二つのプロットは絶妙に絡み合いながら展開していくので、長大な小説ながら飽きる場面もなく、最後まで一気に読ませられてしまうあたり、さすがに世界の名作といったところだろう(『眠り』のように一週間で三回は不可能だとしても)。
「様々な謎」の中でも最大の謎は、美貌の不倫妻(アンナ・カレーニナ)は、なぜ、自殺しなければならなかったのか?ということだ。
アンナの自殺は、彼女の初登場の場面から、既に不吉な兆候として暗示されている。
婦人たちは客車に逆戻りし、ヴロンスキーとオブロンスキーは事故の詳細を確かめようと、人々の後についていった。警備員が一人、一杯機嫌だったのか、それともひどい寒さのために服を着込みすぎていたせいか、後退する列車の音を聞き損ねて、轢かれてしまったのである。(レフ・トルストイ「アンナ・カレーニナ」望月哲男・訳)
ペテルブルグ線の駅で下車した直後に轢死事故があったことを知ったとき、彼女は「悪い兆候だわ」とつぶやく。
それは、間もなく不倫相手となる青年(ヴロンスキー)と出会った直後のことで、この事故が、やがて訪れるアンナの自殺を予告するものであることは間違いない。
そもそも、アンナの自殺の直接的な動機は、不倫相手(ヴロンスキー)との仲が落ち着いてきた(冷めてきた)ことにあった。
「そうだ、死ぬんだ!……夫の恥や不名誉も、セリョージャの恥や不名誉も、わたしのおそるべき恥辱も、死ねば全部が消える。死んでしまえば、あの人だって後悔して、わたしを哀れんで、愛して、わたしのために苦しんでくれるだろう」(レフ・トルストイ「アンナ・カレーニナ」望月哲男・訳)
アンナには、大物官僚の夫(アレクセイ・カレーニン)と、一人息子(セリョージャ、8歳)という家族があったが、愛人(ヴロンスキー伯爵)と情熱的な恋に落ちたことから、家族を捨てて、駆け落ちしてしまう。
アンナにとって理想の筋書きは、夫(カレーニン)と正式に離婚して、一人息子(セリョージャ)を引き取り、愛人(ヴロンスキー)と再婚することだったが、世間体を気にするカレーニンは、アンナとの離婚に応じようとしない(この物語で、離婚争議はストーリー上の大きなテーマだ)。
「わたしとおまえの人生はひとつに結びついている。しかも結びつけたのは人間ではなく神だ。この絆を断つことができるのは犯罪のみであり、その種の犯罪は重い罰をもって報いられるのだ」(レフ・トルストイ「アンナ・カレーニナ」望月哲男・訳)
当時、結婚は「神によって結ばれる絆」と考えられていたから、離婚のハードルは、かなり高かったらしい。
「不貞」も離婚要因の一つではあったが、不貞の罪を犯した者は、二度と再婚することはできない。
不貞の妻(アンナ)が再婚するためには、「夫(カレーニン)が不貞を働いた」という虚偽の申告を必要とするわけで、策略家カレーニンにとって、そもそも恋愛結婚でもなかったアンナに対し、それほどの自己犠牲を払う理由も考えられなかっただろう(なにしろ、アンナとの結婚は、カレーニンにとっても、アンナ側の伯母から強いられた政略結婚だったのだから)。
「なるほど! だがわたしはとりあえず表向きの体面は保ってもらうよう要求する」カレーニンの声は震えだした。「わたしがその、自分の名誉を守る措置を取り、それをきみに伝えるまでは」(レフ・トルストイ「アンナ・カレーニナ」望月哲男・訳)
本来であれば、貴族社会から隠れ、(田舎の農村あたりで)ひっそりと生きていくべきだったかもしれないが、ヴロンスキーもアンナも、華やかな貴族社会から離れることはできない。
アンナは、堂々と社交の場に再登場するが、当時の貴族社会は、家族を捨てて駆け落ちした不倫妻(アンナ)を受け入れるほど寛容ではなかった。
行き場を失ったアンナの唯一の拠り所は、愛人(ヴロンスキー)だけとなるが、エネルギー溢れる青年(ヴロンスキー)こそ、隠遁生活をしているわけにはいかない。
アンナが自分に対する服従的な愛情を求める一方で、ヴロンスキーは、男性の自由と権利を主張したことで、二人の精神的な距離は少しずつ遠いものとなっていく。
「あの人は別の女を愛している。それはもっとはっきりしている」自分の部屋に入りながら彼女は思った。「わたしが欲しいのは愛だ。でも愛はない。だとしたら、全部おしまい」(レフ・トルストイ「アンナ・カレーニナ」望月哲男・訳)
その最終的な結末が「鉄道自殺」ということになるのだが、自殺直前のアンナは、ほとんど病的なまでに自分自身を見失っている(精神を病んでいたと思われるほどに)。
アンナの悲劇は、不倫の愛と社会的な地位の両立、さらには息子(セリョージャ)との同居という、相反するものをすべて望んだことにある。
もちろん、当時の社交界において、不倫は決して特別なものではなかった(そもそも、この物語は、アンナの兄オブロンスキーの浮気が発覚する場面から始まっている)。
高貴な人妻と不倫することは、将来ある青年たちの大きな野望とさえ思われていたらしいが、それは、あくまでも「恋愛遊戯」であって、貴族社会のたしなみとして、秘めやかに行われるべきものだった(たとえ、公然の秘密であったとしても)。
しかるに、アンナは、貴族社会の因習を嘲笑うかのように、不倫相手の子どもを出産し、家族を捨てて駆け落ちしてしまう。
自由に(自分に正直に)生きることこそアンナの生き方だったし、それは、やがて訪れるだろう「新しい時代」を予言するものでもあったかもしれない。
しかし、転換しつつある時代の中で、アンナは、古い社会に押しつぶされてしまった。
大切なことは、彼女が、自分自身との折り合いをつけることができなかった、ということである。
人は誰も、自分の好きなように生きていくことはできない。
社会との折り合いをつけるために、自分の中の自分自身と折り合いをつけながら生きていくのが、我々の人生だが、アンナは、あくまでも自分に対して正直に、自分にとって真実のままに生きようとした。
それは、欺瞞に満ちた社会への抵抗であり、だからこそ、アンナ・カレーニナは、自由に生きる女性の象徴として、我々の中で記憶されているのである。
ある意味、アンナ・カレーニナの伝説は、彼女自身の自殺によって初めて完結したと言うことができるかもしれない。
「あそこだ!」貨車の陰、枕木の上に撒いてある石炭まじりの砂を見つめながら、彼女は自分に言い聞かせた。「あそこの、ちょうど真ん中に跳び込むんだ。そうすればあの人を罰して、そしてみんなからも、自分からも自由になれるんだ」(レフ・トルストイ「アンナ・カレーニナ」望月哲男・訳)
驀進してくる機関車は、彼女自身だ。
アンナ・カレーニナは、自由に生きようとする彼女自身の自我によって轢き殺されたのである(村上春樹『かえるくん、東京を救う』は、この文脈から読み解くことができる)。
なぜなら、アンナの自殺は、絶望の果ての自殺であると同時に、彼女自身を貫くための自殺でもあったからだ。
第7部でアンナが自殺した後、第8部では変わり果てた姿のヴロンスキーが戦争へ出兵する場面が描かれている(「めっきり老けて苦悩の色を宿したその顔は、まるで化石のように見えた」)。
ヴロンスキーはコズヌィシェフの手を固く握りしめた。「まあ、戦争の道具としては、ぼくでも何かの役に立てるでしょう。しかし人間としては、すでに廃墟のようなものですよ」(レフ・トルストイ「アンナ・カレーニナ」望月哲男・訳)
ストーリーは「アンナの自殺」によって完結していたかもしれないが、作者にとって必要だったのは、むしろ、最後の第8部だったのかもしれない。
アンナの自殺を読み解く鍵は、やはり、第8部の中にこそあると思われるからだ。
アンナの自殺が「鉄道自殺」でなければならなかった理由
それにしても、アンナの自殺は、なぜ、「鉄道自殺」でなければならなかったのか?(モルヒネを服用していたアンナは、いつでも服毒自殺できる環境にあったはずなのに)。
その答えは、もう一つのプロット、リョーヴィン(初登場時で32歳)の物語の中に読み解くことができる。
だから鉄道が、期待されたように農業の振興に寄与するどころか、逆に農業に先行する形で工業や金融業の発達を招き、農業の発達を止めてしまったのだ。(レフ・トルストイ「アンナ・カレーニナ」望月哲男・訳)
農業振興に情熱を傾けるリョーヴィンにとって、鉄道を始めとする交通機関の発達は、農業の発展を阻害する要因でしかなかった(南部鉄道と複数の銀行の提携による信用相互合同代理委員会の委員の職を求めるオブロンスキーは俗物の象徴)。
最新文明を代表する機関車は、つまり、リョーヴィンにとって「邪悪なもの」の象徴である(「まったく、鉄道はすっかりうまい汁を吸い取ったあげく、いつわりの輝きを恵んでくれるわけだ」)。
そもそも、リョーヴィンは、アンナと対をなす主人公だから、「機関車」が二つの物語をつなげる鍵になっていると読んでいい(アンナとリョーヴィンは第7部で接触する)。
「あなたにね、駅へ行っていただきたいんですよ」棒切れの先端をむしりながら、リョーヴィンは暗い声で言った。(レフ・トルストイ「アンナ・カレーニナ」望月哲男・訳)
都会の生活を嫌悪し、嫁(キティ)を口説こうとした客(ヴェスロフスキー)を追い出すリョーヴィンも、また、自分に対して正直に生きようとする、不器用な人間の一人だった。
もしかすると、リョーヴィンは、アンナの分身だったかもしれない(別の人生を生きる分身)。
さらに踏み込んで言えば、リョーヴィンは、アンナの生まれ変わりであり、アンナは、リョーヴィンの転生した姿だったと考えることもできる(似たような生き方をしている二人が、なぜ、別々の人生を歩むことになったのか? それは、まるでシミュレーション・ゲームのようだ)。
邪悪な象徴としての機関車は、アンナの物語では、アンナ自身の不幸の影を携えて登場する。
ひげをぼうぼう生やした老人が、鉄のうえにかがみ込み、意味のないフランス語の単語を唱えながら、何かをしている。そしてアンナは、いつもこの悪夢を見る時と同様、その小柄な百姓が彼女のことをまったく無視しているくせに、なんだか恐ろしい鉄を使ったその作業を、まさに彼女目当てに行っているのを感じた。(レフ・トルストイ「アンナ・カレーニナ」望月哲男・訳)
アンナが自殺する直前まで登場する醜い老人は、機関車の化身であり、アンナを死の世界へと誘う死神を具現化した姿だ(「この醜い男には、どこか見覚えがあるわ」)。
そして、この醜い老人を生み出したのも、やはり、アンナ自身だった。
ヴロンスキーと出会った直後に遭遇した轢死事故は、彼女の中で不吉な予言として記憶され、彼女の罪の意識とともに成長していく。
アンナは、彼女自身の罪の意識により、死神(醜い老人)を生み出し、自らを死の世界へと追い込んでいったのだろう(機関車という邪悪な文明の機械に、その姿を託して)。
「ここはどこ? わたしは何をしているの? なぜ?」彼女は身を起こして飛びのこうとした。だが何か巨大なもの、容赦ないものが彼女の頭をドンと突き、背中をつかんで引きずっていった。「主よ、すべてをお許しください!」(レフ・トルストイ「アンナ・カレーニナ」望月哲男・訳)
ヴロンスキーの母親は、息子の人生を台無しにした悪女として、アンナを強く非難する(「ええ、あの女は、いかにもあんな女にふさわしい最期を遂げましたよ。死に方まで、下品で卑しいんですから」)。
このとき、コズヌィシェフ(リョーヴィンの兄)が言った言葉は象徴的だ。
「裁くのはわたしたちの仕事ではありませんよ、伯爵夫人」ため息をつきながらコズヌィシェフは言った。(レフ・トルストイ「アンナ・カレーニナ」望月哲男・訳)
裁くのはわたしたちの仕事ではない──。
この言葉こそ、本作『アンナ・カレーニナ』の献辞として掲げられた言葉に対応するものだっただろう。
「復讐するは我にあり、我これを報いん」(レフ・トルストイ「アンナ・カレーニナ」望月哲男・訳)
アンナは、神によって裁かれたのであり、同時に、自分自身によって裁かれたのだ。
アンナ亡き第8部では、リョーヴィンもまた、生きる意味をつかみかねて苦悩していた。
この力から逃れることが必要だった。そしてその手段は、各人の手の内にあった。悪に依存している状態にけりをつけるのだ。その手段はただ一つ、死ぬことだった。(レフ・トルストイ「アンナ・カレーニナ」望月哲男・訳)
自らの自殺に脅えながら、それでもリョーヴィンは生き続けた。
彼を苦悩から救い出したのは、一人の農民(フョードル)の言葉である。
「わかりきったことですよ。正しく、神さまの教えどおりに生きるだけです。人はいろいろですがね。でもたとえば旦那さまだって、人を傷つけるようなことはなさらないじゃないですか……」(レフ・トルストイ「アンナ・カレーニナ」望月哲男・訳)
自殺した者と生き延びた者。
人生の光と影を描いた物語こそ、『アンナ・カレーニナ』という長篇小説だったのだろう(冒頭でオブロンスキーが「人生がこんなにも多様で、魅力的で、美しいのも、すべて光と影の両方があるからなんだよ」と言っていたように)。
この作品は、明治期の日本文壇にも大きな影響を与えた。
大きな満足感をもって『アンナ・カレーニナ』を読了した。これは読む者に衝撃を与えるほどの力強さと、涙を流させるほどの美しさを併せ持った、実に素晴らしい作品だ。その調子の高さ、断固とした判断、それにすべてを包む同情といった点で、ダンテの『神曲』に十分匹敵し得るというのが僕の印象だ。(有島武郎「観想録 第十一」)
ヨーロッパ留学から日本へ帰る船中で(1907年)、『アンナ・カレーニナ』を読み終えた有島武郎は、この物語にいたく感動し、やがて、オマージュ作品とも言うべき長篇小説『或る女』(1919)を完成させる(外国へ向かう船の中で不倫する人妻の物語)。
不遇の人妻(波多野秋子)と不倫関係に陥り、行き詰った末に心中した有島武郎の人生には、どこか、アンナ・カレーニナ的なものが影響していたのかもしれない。
書名:アンナ・カレーニナ(全4巻)
著者:レフ・トルストイ
訳者:望月哲男
発行:2008/07/20
出版社:光文社古典新訳文庫