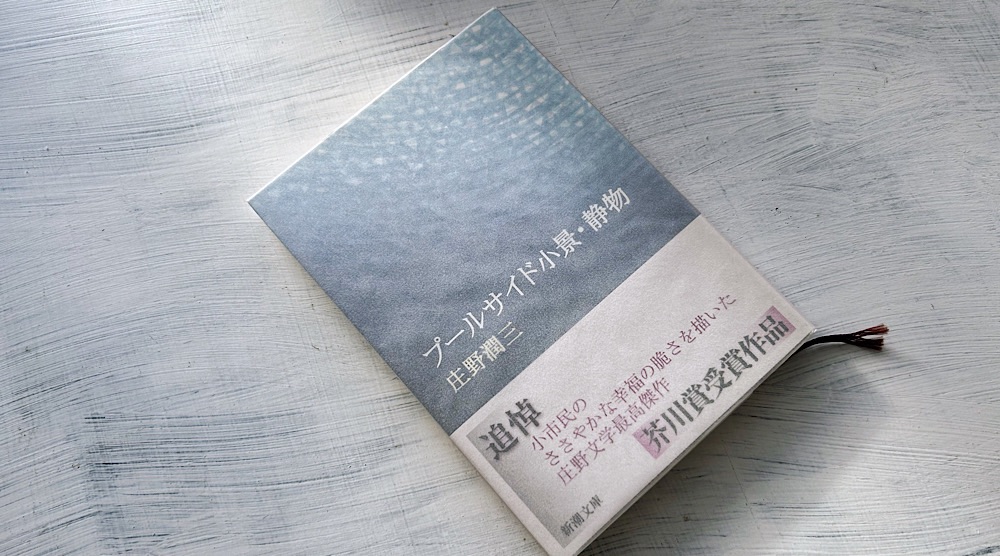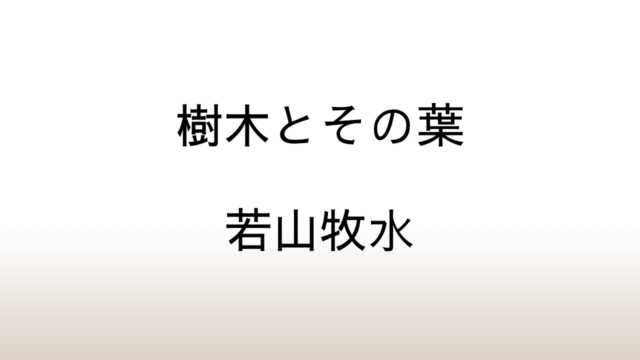庄野潤三「五人の男」読了。
本作「五人の男」は、1958年(昭和33年)12月『群像』に発表された短篇小説である。
この年、著者は37歳だった。
作品集としては、1960年(昭和35年)10月に講談社から刊行された『静物』に収録されている。
『小川洋子の陶酔短編箱』に登場した庄野潤三
『小川洋子の陶酔短編箱』の中で、庄野潤三「五人の男」が取り上げられている。
垂直であれ平面であれ、とにかく移動を拒否しているのは「五人の男」たちだ。彼らは庄野潤三さんの記憶の中にどっしり根を下ろしている。名前も知らず、会ったことさえないにもかかわらず、男たちの根は深く、切り倒したとしてもすぐにまた新芽を出す。彼らは絶対に枯れない樹木なのだ。(小川洋子「私の陶酔短編箱」)
葛西善蔵や泉鏡花、梶井基次郎、木山捷平、井伏鱒二、武田泰淳、武者小路実篤らと並んで、庄野潤三の名前があることの不思議。
著者・小川洋子の心をとらえたものは何か?
もし彼ら五人の中の一人と逢びきするとしたら誰がいいだろう、と私は空想する。漢字に弱いあの人がいいか、それともがらがら蛇を愛するあの人か…。しかもただの逢びきではない。荒神様の前でズロースについて語り合うのだから、やはり肝の据わった男でなければ成り立たない…。(小川洋子「私の陶酔短編箱」)
本作「五人の男」の魅力は、まずは、そのミステリアスなタイトルにあるのだろう。
この時期の庄野さんは、まるでミステリー小説みたいに謎めいた作品タイトルを好んだらしい(この年の8月、一年間のアメリカ滞在から帰国したばかりだった)。
さらに、作品自体も、かなり謎めいている。
ストーリーとも言えないような、男5人の日常的スケッチが並べられているだけで、説明も補足もない。
脈絡のない物語の中から、読者は何を読み取ればいいのだろうか?
僕が、この作品から読み取ったもの、それは、家庭を支えて生きていかなければならない男性という存在の、悲壮な孤独感である。
最初の男は、主人公(物語の語り手)の隣の下宿に住んでいる「五十くらいと思っても差支えなさそうな人物」である。
この男が部屋の中で祈るのである。私が勤めから帰って来る頃には、それがもう大抵始まっている。もしもまだ祈り始めていない時は、長い膝を両方の手で抱くようにして、じっと坐っている。(庄野潤三「五人の男」)
男が、何に対して祈っているのか、それは分からない。
彼は、ただ、ひたすらに祈り続けているだけだ。
私は正直に云うと、その姿が眼に入る度に喜びを感じるのだ。この気持はいったい何と説明すべきものだろうか? 私が不思議に思うのは、彼があのひと間に家族もなしに暮していながら、少しも哀れげに見えないことだ。(庄野潤三「五人の男」)
隣の家の人の話では、彼は「普通の会社」へ行っているそうだ。
二番目の男は、バスの中で見た、若い男である。
男は、若い女と一緒で、「二人にとって致命的と思われるような失策について」話し合っていた。
「難しい字ならとも角、誰でも知ってる字だのに」女は自分の連れを責めているのだった。男はすぐには返事をしなかった。私は二人の方を見ないようにしていた。「誰でも知っている字だのに」(庄野潤三「五人の男」)
どうやら、男は「愛媛(えひめ)」という漢字を読むことができなかったらしいが、それが、どのような場面で起きたことか、愛媛という漢字を読めないことで、どのような結果になってしまうのか、それは書かれていない(おそらく主人公にも分からない)。
ただ私に分ることは、その時彼がこの字を読めなかったのは取り返しのつかないことであり、男の失策が彼等を不幸にさせているということであった。女が男を責めても、男が恐い声を出して女を黙らせても、彼等の不幸は無くなりもしなければ軽くもならないのであった。(庄野潤三「五人の男」)
男は、女に対して、何か指示するようなことを言いながら、女と一緒にバスを降りていった。
三番目の男は、父の知人で、主人公が中学生の頃に(戦争前の時代に)、よく家へ遊びに来ていたD氏である。
体兵肥満で斜視だったD氏は、シカゴの市中で昼間、二人のギャングを地面に叩きつけたということなどを、愉快そうに話して聞かせた。
戦後、D氏に初めて会ったのは、主人公が復員してから、四、五年も経った頃である。
すっかりと痩せて、元気のなくなったD氏は、喘息治療のために、ソ連で発明された冷凍植皮という手術を受けたという。
その手術をやっているのは、私たちの住んでいた都市では共産党の有力な拠点と見なされていた病院であった。「喘息を治すのに、共産党だって何だって、そんなことは君、何も関係のないことですよ」とD氏は云い、私の同意を求めるように顔を見つめた。(庄野潤三「五人の男」)
D氏の喘息はかなりの重症で、彼が持っていた水産加工会社の経営も、戦後二年くらいは何もできなかったらしい。
病気を治すためには、どんなものにでもすがりつこうという気迫が、D氏の言葉には漂っている。
「今度、その皮を貼る時、うまくくっつくんですか?」私は余計なことを質問した。D氏はちょっと慌てた様子で口ごもったが、「いや、それはちゃんとくっつくようにしてくれるのでしょう。何か方法があるのでしょう。え! くっつかないことには君、手術したことにならんのですからね」と云って笑った。(庄野潤三「五人の男」)
手術の効果は書かれていない。
ただ、D氏の皮膚は、うまく元通りにくっついたものの、冷凍中に少し縮んだらしく、わずかながら隙間ができたということだった。
必死に生きてきた男たちの祈り
四番目の男であるN氏は、郷里の中学校で教師をしていた当時に、父の教え子だった人で、四人の中では一番親しい間柄だった。
戦後、満州から復員したN氏は、小さな川のふちの一軒家に家族と住み、父も長兄も亡くなった主人公の家を、時々訪れた。
庄野潤三の長兄(鷗一)は昭和23年に、父親(貞一)は昭和25年に、それぞれ他界している。
ある日、自転車で通勤していたN氏の眼に、小さな虫が飛び込んできたという。
ひどい激痛を、しばらくは酒の酔いでごまかしていたが、三日目に、とうとう医者へ行った。
医者は真赤に腫れ上ったN氏の右の眼の球を見て、飛び込んだ虫は小さな蛾で、羽根についた鱗粉に猛毒を有するものだと云った。「このまま放って置くと、失明するところでした」と医者が云ったのにはN氏は驚いた。(庄野潤三「五人の男」)
思わぬ災難のために、N氏は会社を十日間休んだが、その九日目に大きな事件が起きた。
大雨が降って、水かさが増している近くの川で、四つになる男の子が溺れたのだ。
N氏は、男の子を見つけて水から引き揚げたが、既に意識はなく、心臓も動いていなかった。
身体の表面に死斑が現れたのを見て医者が引き上げてからも、N氏は、男の子の腕を動かしたり、胸を強く擦ったりしていた。
最後に、N氏は、男の子の足を両手でつかんで逆さまにして、思い切り振り回した。
その時、子供の身体から「くっ」というような声が聞えた。そして、その「くっ」という声でみんなが死んだと諦めていた四つの男の子の心臓がもう一度動き始めたのであった。(庄野潤三「五人の男」)
五番目の男は、ガラガラ蛇に自分の手を咬ませて実験をした、アメリカの爬虫類学者の話である。
その男の話を、主人公は「戸外運動」という狩猟専門の雑誌のグラビアで見たのだ。
それは、「ガラガラ蛇はいかに攻撃してくるか? 咬まれた時の手当はどのようにすべきか?」という企画で、雑誌に掲載された実験の経過を、主人公は克明に再現していく。
これ以上開きようがないくらいに開かれた蛇の口が、次にそれを閉じる力の激しさを見る人に想像させる。そして最初の写真では自然にひろげられていた彼の右手の指が、ここでは反射的に縮められようとしている。(庄野潤三「五人の男」)
ガラガラ蛇に右手を咬まれた男は、左手で応急処置を行った。
咬まれた右手と腕は二倍の太さに膨れ上がり、二時間の間、彼は、苦痛と失神と猛烈な吐き気に苛まれたという。
しかし、彼を苛んでいる苦痛も失神も吐き気も私には推し量ることが出来ず、ただ咬まれたあとにかぶせられて、指の中ほどから突き出ている物が、間違って生えた角か何かのように見える。(庄野潤三「五人の男」)
やがて、男が回復したことを伝える雑誌記事を紹介して、主人公の話は終わる(つまり物語が終わる)が、その終わり方は、いかにも呆気ない。
読者は、突然、小説世界の外に放り出されてしまったように感じるかもしれない。
しかし、五人の男の話を読み終わった後には、何か物悲しいような、切ないような余韻が残る。
それは、必死に生きてきた男たちの祈りだ。
おそらく、五つの話の中心になっているのは、死んだ子どもが生き返ったというN氏の話で(四番目の男)、次に、喘息治療で冷凍植皮の手術を行ったというD氏の話が来る(三番目の男)。
ここには、なんとしても家庭を支えて生きていかなければならないという、家長としての男の厳しさがある。
「愛媛」という漢字を読めなかった男(二番目の男)にも、一緒にいた若い女(妻だろうか)を支えなければならないという悲壮感があった。
もちろん、同様のことを、主人公は、ガラガラ蛇に咬まれた男(五番目の男)にも感じたことだろう。
異なっているのは、50歳くらいで独身生活をしている隣の男(一番目の男)だけだ。
最初に主人公は、「私が不思議に思うのは、彼があのひと間に家族もなしに暮していながら、少しも哀れげに見えないことだ」と言った。
背負うもののない男の人生を、主人公は見て取ったのだ(それが正解かどうかは別として)。
男は、おそらく、男たちのために祈り続けているのだ。
川で溺れた息子を救出した父親や、喘息治療に打ち込む会社社長のために。
それは、同時に、世の中を生きる、すべての男たちのために祈ることでもある。
もしかすると、主人公は(物語の語り手、つまり、著者自身を意味する)、最初の男の祈りに、自分自身の祈りを投影していたのではないだろうか。
それは、家庭を支えて生きる、すべての男たちへの応援メッセージである。
裏を返すと、この頃の主人公には、家族を支えて生きていかなければならないという、家父長としての重圧感があったはずだ。
その重圧感が、男たちの悲壮感への共感となり、彼らを励ます応援歌へと、物語を構築させたのである。
本作「五人の男」は、庄野潤三作品の中で、決して有名な作品とまでは言えないものの、新潮文庫に長く入っていることで、多くの読者の眼に触れてきた作品だ。
もしかすると、この物語に励まされたという読者が、僕の他にもいるのではないだろうか。
作品名:五人の男
著者:庄野潤三
初出:1958年(昭和33年)12月『群像』
書名:プールサイド小景・静物
発行:2002/05/25 改版
出版社:新潮文庫