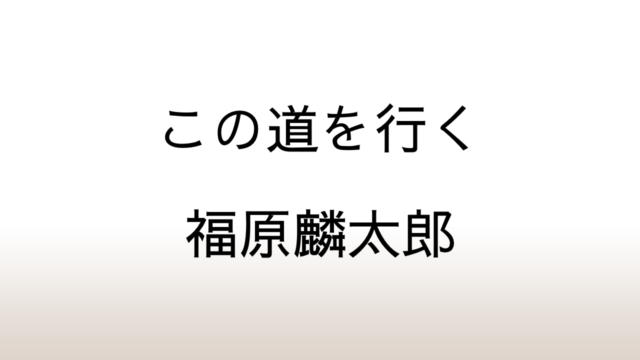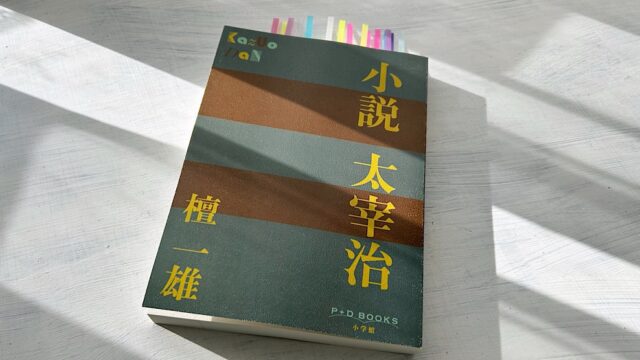庄野潤三展記念トークイベント「おとうくん、おかあくんの思い出」参加。
本イベントは、神奈川近代文学館にて開催中の企画展「没後15年 庄野潤三展――生きていることは、やっぱり懐しいことだな!」の記念イベントとして、2024年(令和6年)7月13日(土)に開催されたものである。
定員200名(満席)。
入場整理番号付きチケットは1,000円(一般)だった。
夏葉社と今村夏子で「夏まつり」?
2024年(令和6年)4月上旬。
神奈川近代文学館の公式サイトにて、企画展「没後15年 庄野潤三展――生きていることは、やっぱり懐しいことだな!」の発表と同時に、記念トークイベント「おとうくん、おかあくんの思い出」の開催がアナウンスされた。
定員200名は、企画展が始まって間もなく満席となり、当日の会場は、満員御礼の大盛況だった。
有料イベントは、当日9時30分から展示館1階のミュージアムショップで、入場整理番号付きのチケット(1,000円)を販売するとのこと。
気持ち早めの11時30分に現地入りし、ミュージアムショップの窓口に並んでチケットを購入すると、入場整理番号は60番台だった。
窓口では、展覧会の図録や、庄野千寿子さんの新刊『誕生日のアップルパイ』を一緒に購入
する来場者も多かったらしい。
イベント開始まで、館内のカフェ「鮨喫茶すすす」で時間を潰そうと思っていたけれど、予約で満席だったので、すぐ近くにある大佛次郎記念館の「ティールーム霧笛」でコーヒーフロートを飲んで人心地つく。
イベントは13時30分開演だが、13時の開場までに集まってくださいとのことで、12時30分頃、展示館2階ホール前のロビーへ移動し、ソファで寛ぐ。
一階の入り口では、夏葉社代表の島田潤一郎さんが、本日の主役・今村夏子さん(庄野潤三の長女)の到着を待ち構えていた。
開場時間が近づくにつれて、ロビーはたくさんの来場者で賑やかとなる。
ほぼ9割以上が年配の女性で、この層が、庄野潤三の「静かなブーム」を支えている人たちなのだろう。
13時に開場となり、入場整理番号順に10人ずつ入場が始まる。
自分は60番台、7番目の入場グループで、ステージが見やすい席に座ることができた。
13時30分、定刻どおりイベントが始まり、島田代表に続いて今村夏子さんが入場。
会場内は、最初から温かい雰囲気の拍手で包まれる。
冒頭、島田代表から「夏子さんの講演会は、これが最後かもしれない」との言葉があり、夏子さん本人からも「講演会のような仕事は、今回で最後にするつもり」という挨拶があった。
「まるで親戚の集まりみたい」とは言いながら、一人の主婦として、多くの聴衆の前で話をするということには、想像以上の負担があったのだろうか。
島田代表のリードに合わせて、夏子さんから、庄野潤三や千寿子夫人の思い出が語られていく。
講演会というよりは、本当に親戚が集まっている場で、懐かしい昔話をしているような、ほのぼのとした雰囲気だ。
庄野夫妻のなれそめに続いて、若き日の千寿子夫人の苦労話が始まると、会場内に共感の空気が広がっていく。
島田代表の話にもあったが、現在の「庄野潤三の静かなブーム」を支えているのは、千寿子夫人や長女・夏子さんに向けられる強い共感だ。
夏子さんは、庄野さんの執筆活動を「町の豆腐屋さんと同じ家内制工業」と呼んだけれど(もともとは千寿子夫人の言葉らしい)、庄野潤三という一人の作家を支える妻や娘の献身的な姿勢が、同世代の女性たちから強い支持を得ているということだろうか。
それは、庄野文学が、庄野一家という家族の支えによって成立したという「家族主義」への熱い共感とも言えるかもしれないし、あるいは、家族の支えを、そのまま小説として可視化した庄野文学は、主婦の存在を肯定的に描いているという意味で「主婦の文学」だったと考えることもできる。
千寿子夫人や長女・夏子は、庄野文学において、それぞれ一人の主婦として活躍しているし、長男・龍也は妻・あつ子ちゃんの支えによって、次男・和也も妻・ミサヲちゃんの支えによって、それぞれ父親としての責務を果たしているのであり、むしろ、庄野文学のプロットそのものが、理想的な家庭像としての「家内制工業」を描いているとも言える。
「平穏な家庭は、強力な父親の存在によってのみ成立しているのではない」という家庭観が、庄野文学の土壌にはあるということを、夏子さんの話から気付くことができたが、これが、この日最大の収穫だったような気がする。
庄野一家の物語は、作品の中で永遠に残る
夏子さんの話の中で、とりわけ印象的だったのは、庄野夫妻がアメリカのガンビアに滞在した一年間のことだ(昭和32年から33年にかけて)。
日本に残された子どもたちは、長女9歳、長男5歳、次男1歳6か月。
祖母(千寿子夫人の母親)が面倒を見てくれるとは言え、この一年間は、夏子さんにとって「人生の<青の時代>だった」という(パブロ・ピカソの苦悩の時代になぞらえたもの)。
ガンビア時代の一年間は、庄野さんにとって、重要な文学的土壌となったことに間違いはないが、その経験は、家族の犠牲があってのものだったらしい。
『明夫と良二』(1972)の講談社文芸文庫版巻末に収録された「著者に代わって読者へ」の中でも、夏子さんは、両親のガンビア時代を回想している。
留守宅には母方の祖母が来てくれましたが、明るくスポーツマンでいつもおもしろいお話をしてくれる父と、空想力豊かな母が突然いなくなり、我家は太陽と月が一ぺんに沈んでしまったようでした。私は父からの手紙を心待ちにし、上の弟はさみしさをいたずらでまぎらわし、下の弟はおばあちゃんにしがみついて離れませんでした。三人の姉弟の生まれて初めての試練でした。(今村夏子「かけがえのない家族との日々」)
名作『ガンビア滞在記』(1959)を支えたのは、千寿子夫人だけではなかった。
作品にこそ登場しないものの、日本で両親の帰りを待つ三人の子どもたちも、また、『ガンビア滞在記』を支える陰の功労者だったのだ。
ここに、庄野文学が「家族の文学」と呼ばれる所以がある。
ガンビア時代を後年に回想した長篇小説『懐しきオハイオ』(1991)では、日本にいる3人の子どもたちの様子が、アメリカでの日常生活の中で、さりげなく織り込まれているが、離れていても、やはり、庄野一家は庄野一家だった。
子どもたちの犠牲の上に、自分の文学があることを、庄野さんは、誰よりも痛切に感じていたのではないだろうか。
石神井公園時代の庄野さんが、幼い夏子さんを連れて、井伏鱒二の自宅を訪ねた思い出も懐かしいし、文士仲間の旅行に参加して、志賀直哉を訪ねたときの様子は、スナップ写真としても残されている(夏子さんは、河盛好蔵の膝に抱かれて、井伏鱒二と一緒に写っている)。
ひときわ、会場が盛り上がったのは、長男・龍也さんが、聴衆席からステージ上へ乱入した瞬間だろう。
龍也さんは、会場内の聴衆にコーラス指導を行いながら(♪汗をかいたので一休み~(ダカダカダン!))、かぐや姫の「うちのお父さん」を熱唱(「うちのおとうくん」として)。
もちろん、この演出は、『うさぎのミミリー』(2002)の良雄の結婚式で、長男が披露するものだ(良雄は夏子さんの次男)。
もう一つのハイライトは、長女からこの日の余興をたのまれていた長男が、次男一家らを集めて歌ったかけあいの歌。「うちのとうちゃん」というのであったか。はじめにリハーサルをやった。長男が手を振ってサインを送ると、グループは「カタカタカタ」という。別のサインを送ると「カーカー」という。さて本番になると、みんな長男のサインに合せて、あるいは「カタカタカタ」といい、「カーカー」といい、それがうまく合って会場の盛大な拍手を受けた。(庄野潤三「うさぎのミミリー」)
夏子さんは「うちのエンターティナーです」と言っていたけれど、会場の雰囲気を一瞬で変えてしまうような、龍也さんのパワーは、ある意味で、この日のトークイベントのハイライトでもあった(ちなみに、長男・龍也さんは、今年で73歳)。
次男・和也さん(フーちゃんのお父さん)は、庄野さん他界から3年後の2012年(平成24年)のクリスマス、56歳の若さで<がん>のため亡くなっており、かつての五人家族の時代を知るのは、今や、夏子さんと龍也さんの二人だけとなった。
一番好きな作品として、夏子さんは、五人家族時代の原点とも言うべき『夕べの雲』(1965)を挙げていたけれど、なんだかんだ言って、庄野文学は、やはり、五人家族の物語である。
「自分たちのしてきたことを、父は、絶対に消えない形で残してくれた」という夏子さんの言葉が、家族全員の思いを代弁しているのではないだろうか。
千寿子夫人が亡くなったとき、そのお葬式で、遺族は、百人一首の坊主めくりをして盛り上がったという(「ボンズコール」)。
明るく、前向きに生きる姿勢は、庄野さんの遺した大きな財産だったのかもしれない。
「山の上の家」も、いつまで維持できるか分からない状況の中(税金も高いので)、「もし、仮に家がなくなったとしても、庄野一家の物語は、作品の中で永遠に残る」と語った龍也さんの言葉が、妙に胸に残った。
最後に夏子さんの残した言葉は「普通の主婦に戻ります」(「金時のお夏」に戻ります)。
可能性だけの話をすれば、父・幸田露伴の思い出を綴って作家となった幸田文のように、夏子さんも、また、著述業の道を選ぶことは可能だったかもしれないが(なにしろ、多くの手紙が、庄野文学に残されている)、夏子さんは、あくまでも、一人の主婦として全うする道を選んだ。
それは、娘として、主婦として、庄野文学を支えてきた女性にとって、あるいは、必然的な帰着だったのかもしれない。
夏子さんは、既に、庄野文学の登場人物の一人として、たくさんの作品を発表してきたのだから。
15時、定刻どおりにイベントは終了。
夏子さんを見送る満場の拍手は、庄野文学に力をもらった読者からの、感謝とねぎらいのメッセージだった。
会場を後にする来場者に向かって挨拶をする夏子さん(と龍也さん)を囲んで、2階フロアーが、いつまでも賑やかだったことは言うまでもない。

(2026/03/03 19:47:20時点 楽天市場調べ-詳細)