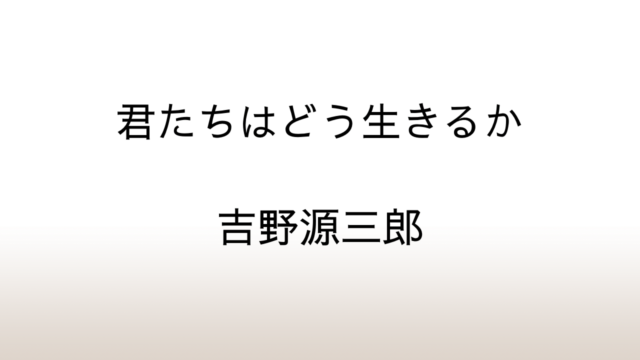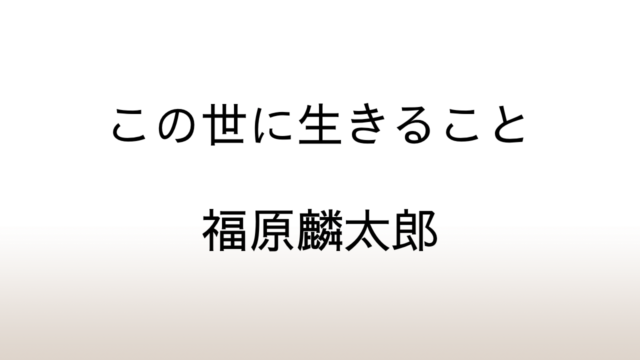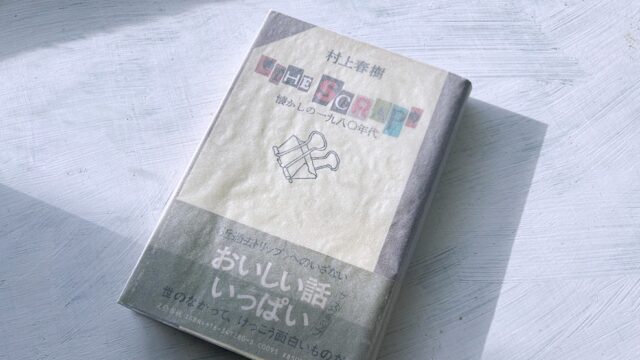辻仁成「ピアニシモ」読了。
本作「ピアニシモ」は、1989年(平成元年)12月『すばる』に発表された長篇小説である。
この年、著者は30才だった。
1989年(平成元年)、第13回すばる文学賞受賞。
単行本は、1990年(平成2年)1月に集英社から刊行されている。
鬱屈した少年が逆ギレするまで
作品タイトル「ピアニシモ」は、「きわめて弱く」を意味する音楽用語である(pp)。
存在をギリギリまで消して生きる(「もっともっと存在を消さないと、誰かが火をつけてくるだろう」)。
それが、現代社会を生き抜くために必要な、少年たちの知恵だった。
消えないように、消さない程度に、そっとろうそくの炎のように存在できたものだけが、食いつないでいくことができるのだ。(辻仁成「ピアニシモ」)
本作『ピアニシモ』は、いじめられた転校生(中学3年生)が逆ギレする、反逆の物語である。
「だから、ガッコ行くのやめたんだよ」「そうね。それがいいわ」「いじめられるのが嫌で、鍵かけて、いちぬけた」(辻仁成「ピアニシモ」)
「いじめられるのが嫌で、鍵かけて、いちぬけた」は、もちろん、エコーズのデビュー・シングルからの引用だ(『Bad Morning』のB面曲)。
いじめられるのが嫌で
鍵かけて いち抜けた
そろそろ誰か心配して
あやまりに来る
Oh Visitor
エコーズ「訪問者(ヴィジター)」
居場所のない少年たちの孤独は、1985年(昭和60年)のデビュー以来、エコーズの重要なテーマであり続けた。
その世界観は、本作『ピアニシモ』においても再現されている。
例えば、夫婦愛に乏しい両親の姿は、デビュー・シングル『Bad Morning』に通じるものだろう(「あの二人の間には、ちゃんと愛が存在していたのだろうか」「今でもその愛は成立しているんだろうか」)。
働いてばかりの 無口なお父さん
朝早くでかけて 夜中に帰ってくる
すれ違いの Every day
エコーズ「Bad Morning」
転校を繰り返す主人公(氏家透)の姿は、「My protest song」でも描かれている。
団地の片隅で俺は生まれた
転校をくりかえし育った
見知らぬ街に送りこまれて
皆の前でおじぎをおぼえ
最初はいつもうまくいかずに
一人で遊ぶこつをみつけた
エコーズ「My protest song」
つまり、1985年(昭和60年)のデビュー以来、エコーズのリーダーとしての辻仁成が描き続けてきた世界の、ひとつの終着点が、本作『ピアニシモ』だったということになる。
もっとも、小説家・辻仁成は、行き場のない少年たちに、エコーズとは異なる未来を与えた。
ワァー。誰かが叫んでいる。それは僕の声にそっくりだ。絶叫する夜のマシーン。僕は、気がふれてしまったのかもしれない。落ちていたレンガで誰かの頭を殴る。反応のない痛みが、手のひらにも伝わってくる。「畜生、やってやる。畜生」(辻仁成「ピアニシモ」)
消えてしまわない程度に(ピアニシモ)息を潜めて生きていた主人公は、やがて爆発する。
彼の頭の中には、小さな亀裂が昔からあったのだ(「意識の中で無意識に削除していた小さな亀裂」)。
もう僕には、この亀裂を押さえることはできない。一人歩きを始めた小さな亀裂。(略)小さな亀裂の中に、矛盾や怒りや憎悪や拒否を全て封じ込め、ひたすら覆い隠してきた、はりぼての青春。(辻仁成「ピアニシモ」)
逆説的な言い方をすると、本作『ピアニシモ』は、鬱屈した少年が逆ギレするまでの経過を描いた、キレる少年の物語ということになる。
実際に「キレる子どもたち」が社会問題として表面化するのは、2000年代に入ってからのことだが、『ピアニシモ』で描かれているのは、紛れもなく「キレる子どもたち」だ。
繰り返される転校と陰湿ないじめ、仕事人間である父親の不在、気弱な母親の宗教狂い。
学校と家庭が、一人の少年を追い詰めていく過程を、この小説は丁寧に再現している。
キレ方の描写が十分ではないのは、この作品が、1989年(平成元年)に発表されたものであるということを意味している。
80年代的な管理教育の積み重ねを経て、抑圧された子どもたちの欲求不満は、90年代になって、陰湿ないじめという形で噴出する。
その延長線上で登場してくるのが、「キレる子どもたち」という新しい少年像だった(栃木県で女性教師が殺されたバタフライナイフ殺人事件は1998年)。
「ニュースでやっていたように、バットでぶっ殺してやろうか?」自分でも信じられないくらい、激しい興奮が全身を包む。もしも目の前にバットがあったなら、あの小さな母親の顔を粉々に砕いていたかもしれない。(辻仁成「ピアニシモ」)
神奈川県の金属バット両親殺害事件は、1980年(昭和55年)に起こった少年犯罪である(犯人は2浪の浪人生だった)。
既に、少年たちは「ピアニシモ」ではいられなかった。
机の足が床をする大きな音が教室を包み、全員がショーの始まりに生つばを飲んだ。ピストルズだけが演奏を続けていた。ゴッドセイブザクィーン。ゴッドセイブザクィーン。(辻仁成「ピアニシモ」)
彼らも、また、ジョニー・ロットンのように、大きな声で叫び出さずにはいられなかったのだ(当時の中学生がセックス・ピストルズを聴いたかどうかという問題は、ともかくとして)。
さとるは、正気を取り戻しながら、血で染まったこぶしを僕の方に突き出して、言い訳をするように吐き捨てた。「戦場なんだよ、ここは」(辻仁成「ピアニシモ」)
あるいは、これは、現代社会を生き抜く少年たちの姿を描いた作品だったかもしれない。
「♪信じられぬと嘆くよりも、人を信じて傷つくほうがいい~」みたいに悠長なことを言って過ごせる時代ではなかった(『3年B組金八先生』の「贈る言葉」)。
彼らは、学校という戦場で、命を賭けて戦っていたのだ。
「地獄にいます。引っ張り上げてくれる人、1000トリプルに来て下さい」(辻仁成「ピアニシモ」)
NTTの伝言ダイヤルサービスで知り合った少女(サキ)のメッセージは、あるいは、現代社会を生きる誰かのメッセージだったのかもしれない。
そして、「僕に似た誰かからのSOS」は、つまり、主人公自身のSOSでもあったのだ。
消えてしまいそうに生きている少年たちの「SOS」
サキの電話がすべて嘘だったことを知って、主人公は激しくキレる。
僕は僕から、遊離しなくてはならない。人間はあらゆるものから離れることによって、成長していく動物なのだから。(辻仁成「ピアニシモ」)
主人公の成長を意味するものは、彼自身が創り出したイマジナリー・フレンド(ヒカル)との決別だった。
イマジナリー・フレンドのひかるは、もちろん、もう一人の主人公自身である。
彼の独創性と自由なエネルギーが大好きだった。自分にはないものがヒカルの中にはほとんど存在したし、僕がやれたらいいな、してみたいな、ということを全て彼がやってのけてくれたのだ。(辻仁成「ピアニシモ」)
ヒカルは、おそらく、主人公自身の「意識の亀裂」の中に封じ込められた、彼自身の象徴だ。
やはり、ヒカルの存在は僕にしか見えないらしい。(辻仁成「ピアニシモ」)
亀裂が爆発して、本当の彼自身が噴出したとき、分身たるヒカルの存在に、もはや意味はない。
それを、主人公は「成長」と呼んだ。
あるいは、世の中は、それを「自己破綻(破滅)」と呼ぶかもしれない。
僕は自分のしていることが信じられなかった。まるでヒーローになろうとしているみたいでおかしかった。いつもヒーローを探す方の人間だったはずなのに、僕は今、ヒーローのペダルを踏んでいた。(辻仁成「ピアニシモ」)
激しく噴出する自我と自己葛藤。
「消えろ、消えろ、消えろ、消えろ、消えろ、消えろ、消えろ、消えろ、消えろ、消えろ、僕は一人でやってくんだ。お前にたよっていたら、本当に一人になってしまうだろうが。消えろ、頼むから消えてくれ」(辻仁成「ピアニシモ」)
「お前にたよっていたら、本当に一人になってしまうだろうが」という言葉は、一人では生きることが難しい現代社会に向けられた警告だったと読むこともできる。
1991年(平成3年)5月26日、日比谷野外音楽堂のラスト・ライブで、辻仁成は、客席に向かって「これからは一人でやってけよ!」と叫んだ(『JACK』の間奏)。
あるいは、それは、エコーズとともに生きてきた自分自身に対するメッセージではなかったか。
もしかすると、エコーズは、辻仁成という一人の音楽家が生み出した、彼自身のイマジナリー・フレンドだったのかもしれない。
辻仁成も、また、新しい自分を獲得するために、現代社会という戦場で戦っていたのだ。
「そうそう。チャリティーコンサートやったり、反核やったり、マジでなんとかしようとしている奴らはバカだよ。病気だよ。あいつら、宗教みたいで一番怖いよ」(辻仁成「ピアニシモ」)
ロックバンドに対する主人公の批判は、彼自身に対する自己批判でもある(当時は、反核や反戦のロック・ミュージックがトレンドで、各地のチャリティーコンサートに若者たちが集まっていた)。
裏を返すと、それは、彼ら自身の自己肯定だったとも言える。
「そんなことないよ」と、彼らは言ってほしかったのだ。
戦争もない平和で退屈する時代。その象徴があの日の丸だった。退屈ゆえに陰湿化していく僕らのジェネレーション。僕もヒカルも制服の詰め襟をきゅっと詰めて、心の再軍備を着実に進めていた。(辻仁成「ピアニシモ」)
「意識の亀裂」を爆発させた主人公は、イマジナリー・フレンド(ヒカル)と決別し、一人で生きていく道を選ぶ。
僕はあいつなしで強くならなくっちゃいけない。これからは、何があってもあいつを呼び出すことはできない。自分一人で、たった一人で、成長していかなくてはいけないのだ。(辻仁成「ピアニシモ」)
本作『ピアニシモ』は、現代社会を生きる少年の孤独を描いた物語である。
本当の意味での「成長」は、そこにはなかったかもしれない。
そこにあるのは、現代社会の中で消えてしまいそうに生きている少年たちの「SOS」だ。
やがて、訪れる「キレる子どもたち」の時代。
辻仁成は、もうすぐそこまで来ていた次の時代を、文学という形で予言していたのである。
書名:ピアニシモ
著者:辻仁成
発行:1992/05/25
出版社:集英社文庫