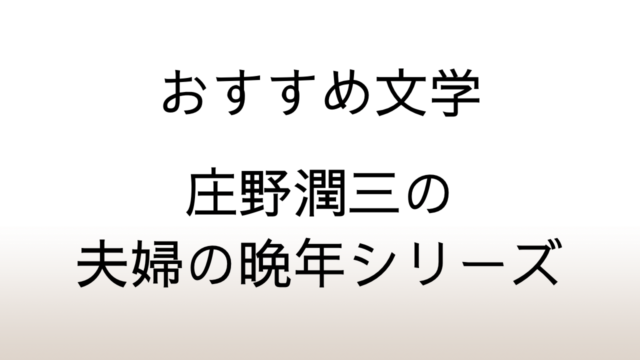アントン・チェーホフ『ワーニャ伯父さん・三人姉妹』読了。
本作『ワーニャ伯父さん・三人姉妹』は、2009年(平成21年)7月に刊行された、日本オリジナル戯曲集である。
収録作品及び発表年(初出)は次のとおり。
「ワーニャ伯父さん」
・1897年(明治30年)、『チェーホフ戯曲集』初出
・1899年(明治32年)、モスクワ芸術座にて初演
・この年、著者は39歳だった
「三人姉妹」
・1901年(明治34年)、モスクワ芸術座にて初演
・この年、著者は41歳だった
・2018年(平成30年)、乃木坂48メンバー主演舞台『三人姉妹』原作
生きることの悩みは、いつの時代でも普遍である
若き日の庄野潤三が、チェーホフ文学に傾倒していたことは、有名な話だ。
そのチェーホフについて、庄野さんは「むしろ取っつき難い作家である」と綴っている。
「桜の園」や「三人姉妹」でも、いいと思って読んではいるが、さてどれだけはっきりとした手応えを持ち合せて読んでいたのか、怪しいものであった。あった、とこう書いている現在でも、私はまだ同じような疑問を自分に対して覚える。(庄野潤三『自分の羽根』所収「チェーホフのこと」)
チェーホフの作品が難解なのは、「書いてあることは平易であるように見えて、人を感激させる要素をすっかり取り除いてあるためにそうならない」というところにあるらしい。
一見して分かりやすいように思える文学こそ、得てして、奥が深くて全容を理解するのに、時間がかかったりするものかもしれない。
本書に収録された『ワーニャ伯父さん』と『三人姉妹』は、いずれも「チェーホフ四大戯曲」に数えられる名作である(残りのふたつは『かもめ』『桜の園』)。
小説と違って、戯曲は芝居のセリフが中心だから、地の文(本文)が少ないだけ読みやすいかもしれない。
おまけに印象的なセリフが多いので、いわゆる名言が生まれやすいといった傾向もある。
そういう意味で、戯曲は取っつきやすいとも言えるが、『ワーニャ伯父さん』にしても『三人姉妹』にしても、扱っているテーマは大きくて重い。
なにしろ、ここで描かれている物語は「生きること」を主要なテーマとしているからだ。
一般に「生きること」と言うと、人生の前向きな側面を向いているように思われるが、チェーホフは「生きること」の悲劇を描いた。
チェーホフが亡くなる直前に書いた手紙に、次のような文章がある。
「君は人生とは何かと尋ねる。これはまさしく人参とは何か? ということに等しい。人参は人参だ。それ以上は誰もなんにも知ってはいないのだ」(中村白葉「チェーホフの偉さ尊さ」)
「それ以上は誰もなんにも知ってはいない」からこそ、チェーホフは人生を描き続けたのだろう。
生きることの悩みは、いつの時代でも普遍である。
それは、チェーホフ文学が普遍であるということの、ひとつの理由になっているかもしれない。
ワーニャ伯父さん
ワーニャ伯父さんは、ソーニャにとっての伯父さんである。
ワーニャの妹であり、ソーニャの母親であるヴェラは、娘を遺して亡くなってしまった。
ソーニャの父親(セレブリャコフ)は、若くて美しい後妻(エレーナ、27歳)を迎える。
セレブリャコフが、エレーナを連れて戻ってきたとき、家庭内に騒動が起きた。
本作『ワーニャ伯父さん』は、美しすぎる後妻エレーナをめぐる家庭内騒動を描いた、ドタバタ悲劇である。
47歳・独身の中年男性のワーニャは、人妻エレーナに恋をした。
さらに、セレブリャコフの要請で滞在中だった医師(アーストロフ、36歳)も、エレーナに恋をしてしてしまう。
この物語は、ワーニャ(47)とアーストロフ(36)という二人の中年男性を主人公とする悲劇だったのだ。
アーストロフ ぼくは腰を落として、こんなふうに両の目をおおって、考えるんだ。二百年、三百年後に生きる人たち、ぼくたちがいまこうして道を切り開いてやっている人たちは、ぼくらのことを、よく頑張ったとねぎらってくれるだろうか、と。(アントン・チェーホフ「ワーニャ伯父さん」浦雅春・訳)
現状に満足できないアーストロフは、あえて、200年後・300年後に目を向けて、虚しい現在の生活から眼を逸らそうとする。
アーストロフが見ている未来は、決して明るい未来ではない。
10年間働き続けて、すっかりと老け込んでしまった生活に、アーストロフは侘しさを感じている(「老け込んで、働きすぎてガタがきて、俗物になって、感受性もすっかり鈍くなって」)。
人生を侘しいものだと考えているのは、ワーニャも同じだった。
ワーニャ やつの後妻というのは、君たちも今しがた見かけたとおり、美人で聡明な女性だ。そんな女性が老年に差しかかった男に嫁いで、あたら自分の青春と美しさと自由と輝きを捧げているのさ。なんのために? どうしてなんだ?(アントン・チェーホフ「ワーニャ伯父さん」浦雅春・訳)
二人の中年男性に「気づき」を与えたのは、人妻エレーナである。
退職した大学教授(セレブリャコフ)が、いとも簡単に、若き美女(エレーナ)と結婚してしまったことで、二人は人生の虚しさを感じ、生きることに生き甲斐を見つけられなくなってしまう(要は「バカバカしくなった」)。
二人は、セレブリャコフに気遣うことなく、エレーナに愛の告白をするが、貞淑であることに誇りを持つエレーナは、なびきそうに見えて、なかなかなびかない。
ワーニャ どうして、俺は老いてしまったんだ? どうしてあの人はぼくのことを分かってくれないんだ? あの人の言い草だとか、怠惰なモラル、世界の破滅がどうのこうのという、あのたわけたものぐさな考え──何もかも虫唾が走る」(アントン・チェーホフ「ワーニャ伯父さん」浦雅春・訳)
「ぼくは自分自身を持てあましているんです」「人生は失われた、もう取り返しがつかない」「泡と消えた人生!」というワーニャの嘆きや、「ぼくにはあの遠くまでまたたいている灯りがないんです」「ぼくの人生はもう終わった、手遅れなんです」というアーストロフの嘆きは、この物語全体に流れる主調音だ。
やりたい放題のセレブリャコフにキレたワーニャは、拳銃自殺を図って失敗し、セレブリャコフを殺そうとして、また失敗する。
ワーニャ 待った、まだ終わっちゃいない! 貴様はぼくの人生を踏みにじったんだ! ぼくには人生なんてなかった! 貴様のせいで、ぼくは自分の人生の華の歳月を無駄にし、台なしにしてしまったんだ!(アントン・チェーホフ「ワーニャ伯父さん」浦雅春・訳)
好きな女性には振り向いてもらえず、かと言って死ぬこともできず、虚しく生き続けていかなくてはならないところに、中年男性ワーニャの悲劇がある。
ワーニャ なんとかしてくれよ! ああ、神様……。ぼくは四十七だ。六十まで生きるとして、まだ十三年ある。長いなあ! この十三年をどう生きればいいんだ?(アントン・チェーホフ「ワーニャ伯父さん」浦雅春・訳)
本作『ワーニャ伯父さん』は、生きることの苦悩を描いた物語である。
ワーニャ伯父さんの苦悩を結晶化するのは、恵まれない人生を送っていくだろう、姪っ子ソーニャだった。
【ワーニャ】ソーニャ、なんてつらいんだろう! このぼくのつらさがお前に分かればなあ! 【ソーニャ】仕方ないわ、生きていかなくちゃならないんのだもの!(アントン・チェーホフ「ワーニャ伯父さん」浦雅春・訳)
「ワーニャ伯父さん、もう少しの辛抱よ……あたしたち、息がつけるんだわ……。あたしたち、息がつけるようになるわ!」「息がつけるようになるんだわ!」というセリフで、物語は幕を閉じる。
それにしても「あたしたちの最期がきたら、おとなしく死んでゆきましょう」というソーニャの言葉は切ない。
中年の苦悩に共感を示す若い女性ソーニャこそ、この物語の、本当の主人公だったのではないだろうか。
誰しもみな「そろそろ疲れたなあ」という人生の瞬間を感じるときがある。
中年ワーニャの嘆きは、「そろそろ疲れたなあ」という人生の嘆きでもあるのだ。
40代・50代のビジネスマンに、一度は読んでもらいたい名作である。
三人姉妹
本作『三人姉妹』は、虚しさを抱き続けながら生きる三人の若い女性を描いた物語である。
長女(オリガ)は28歳、次女(マーシャ)は21歳、三女(イリーナ)は20歳で、このうちマーシャだけが既婚である(夫はクルイギン)。
美しいイリーナは、イケメンではない男爵トゥーゼンバフ(30歳手前)から求婚を受ける。
イリーナ 人生は美しいとおっしゃるけど、でも、もしそう思えるだけだとしたら! あたしたち、三人の姉妹には、人生なんてちっとも美しくなかった。まるで雑草のように、あたしたちをむしばんでしまっただけなの……。(アントン・チェーホフ「三人姉妹」浦雅春・訳)
イリーナは、ひたすら故郷であるモスクワへ移住することだけを夢見ている。
イリーナ 全部忘れていくの、毎日どんどん忘れていくの。なのに、人生はおかまいなく過ぎていって、けっして戻ってこない。けっして、あたしたち、モスクワには行けやしないのよ……。(アントン・チェーホフ「三人姉妹」浦雅春・訳)
行きたいけれど行けないモスクワは、三人姉妹の閉塞感を象徴する存在だっただろう。
三人姉妹と対照的に描かれているのが、長男アンドレイの嫁(ナターシャ)だ。
がさつで気遣いのないナターシャは、夫(アンドレイ)の上司(プロトポーポフ)と不倫を楽しみ、自分勝手な人生を謳歌する。
三人姉妹は、嫁の浮気にも気づかず、群会での出世ばかり気にする俗物となったアンドレイに失望を隠せない(「実際、兄さんも小物になったものね」)。
もちろん、アンドレイ本人も、自分の人生を手放しで喜んでいるわけではなかった。
アンドレイ ああ、どこに行ったんだ、どこに消えたんだ、ぼくの過去は? ぼくがまだ若くて快活で、頭がよかったあのころ、大きな夢や思想に胸をふくらませていたあのころ、現在と未来が希望に輝いていたあの過去はどこに消えたんだ?(アントン・チェーホフ「三人姉妹」浦雅春・訳)
アンドレイの嘆きは、『ワーニャ伯父さん』で主調音を成していたメロディと同じものだろう。
行き場のない閉塞感を感じていたのは、アンドレイもまた同じだったのである。
閉塞感を打ち破るため、イリーナはトゥーゼンバフとの結婚を決断するが、結婚直前になってトゥーゼンバフは、イリーナに思いを寄せる陸軍大尉(ソリョーヌイ)に殺されてしまう。
マーシャ あたしたちだけが残されて、新たに生活をはじめるのね。生きていかなくてはならないのね……生きていかなくては……。(アントン・チェーホフ「三人姉妹」浦雅春・訳)
ここで描かれているのも、やはり、閉塞感の中で生き続けなければならない、三人姉妹の苦悩だった。
どこにも行けない虚しさが、チェーホフの作品にはある。
オリガ ねえマーシャ、ねえイリーナ、私たちの人生はまだ終わりじゃないの。生きていきましょう!(アントン・チェーホフ「三人姉妹」浦雅春・訳)
彼らは、みんな、自己暗示でもかけるみたいに「生きていきましょう」「生きていかなければ」と叫び続ける。
そうでもしなければ、それは、生きていけない時代だったのだ。
しかし、彼らの言葉は、前向きな言葉のように見えて、実は、呪いの言葉でもある。
どこにもたどり着けない人生ほど、苦しいものはないからだ。
彼らの閉塞感は、おそらく、当時のロシア社会が抱いていた閉塞感でもあったのだろう。
見えない壁を打ち破るために、生きていかなくてはならない人々。
人生の閉塞感に混乱したときこそ、現代人は三人姉妹への共感を持つのではないだろうか。
書名:ワーニャ伯父さん/三人姉妹
著者:アントン・チェーホフ
訳者:浦雅春
発行:2009/07/20
出版社:光文社古典新訳文庫