庄野潤三「雉子の羽」読了。
本作は全部で171篇の短いエピソードで構成された長編小説である。
それぞれのエピソードは、「蓬田」とその妻、そして三人の子どもたちという、一家五人の家族によって語られる。
まるで、夕食の団欒の中で、それぞれが今日あったことを話し合っているような、そんな他愛ない話が、どこまでも積み重ねられてゆく。
読者によっては、これを小説と認めることに抵抗があるかもしれないが、僕はこの一風変わった実験的とも思える作品を、最初に読んだ時から自分好みだと感じていた。
舞台は1960年代(単行本の刊行は1968年)。
高度経済成長の中で、周辺環境が次々と変わってゆく、そんな時代だった。
五人家族は急速に街が移り変わってゆく中で、日々の日常生活を過ごしている。
それは、ヒバリの子やタニシ、川ニナ、アヒル、田植えなどといった、のどかな前時代的風景が生活の中で当たり前に登場する時代だった。
同時に、周辺の至るところで建築工事が始まり、いくつもの飯場が建ってはたくさんの土方が町を歩き始める、そんな時代でもあった。
1960年代、庄野さんがあえて、この高度経済成長の日本を作品として描こうとしていたのかどうかは分からないけれど、結果として、この小説には、高度成長期の日本が詳細に記録されることになった。
それは、政治的・経済的・ジャーナリズム的な記録ではない。
夫や妻や子どもたちが、町や電車や学校の中で見たり体験したりしてきた、等身大の日本社会の記録である。
この作品を読みながら感じるノスタルジーは、この作品が、昭和40年代の写真アルバムのような懐かしさを与えているからだろう。
オリンパスペンで撮影したストリートスナップ写真のようだ
実際、ここに収録されている計171篇の文章は、ひとつひとつがオリンパスペンで撮影したストリートスナップ写真のようだ。
35mmフィルムを使うハーフサイズカメラであるオリンパスペンが登場したのは、1959年(昭和34年)のことである。
この低価格で庶民派のコンパクトカメラは、1960年代の日常風景を気軽にスナップすることとなり、オリンパスペンで撮影されたフィルム写真が、多くの家庭の家族アルバムの中に並んだ。
本作「雉子の羽」に登場する作品ひとつひとつには、まるで昭和のハーフサイズカメラで撮影した写真のような味わいがある。
最も大きなポイントは、高価な一眼レフカメラで構図を吟味して絞り込んでいく写真ではなく、路上風景の何気ない一瞬を気軽にスナップしていく、その手法だろう。
もちろん、ハーフサイズカメラだから、24枚撮りフィルムで48枚の写真を撮ることができる。
気軽にたくさん撮影することができるから、必要のない写真も多くなる。
ハーフサイズカメラで撮った写真には、多くの写真の中からアルバムに貼るべき写真を選ぶ楽しさがあった。
「雉子の羽」でも同様に、撮影されながら収録されなかったエピソードというものが、きっとたくさんあったに違いない。
完璧な構図や1mm単位のピントが求められるわけではない。
いかに撮り続けてゆくかということが、路上スナップ写真最大のポイントであるから。
だから、僕はこの「雉子と羽」という長篇小説を、まるでスナップ写真で撮影された写真集をめくるような楽しさで読んだ。
写真集の中に数多く登場するのは、高度成長の日本を支えた「土方」の人々である。
変わりゆく街を描くために、おそらく庄野さんは意識して「土方」の姿をファインダーの中にとらえようとしていたはずだ。
あるいは、庄野さんは「土方」を主人公にした作品を書きたいと思っていたのかもしれない。
書名:雉子の羽
著者:庄野潤三
発行:1968/3/25
出版社:文藝春秋
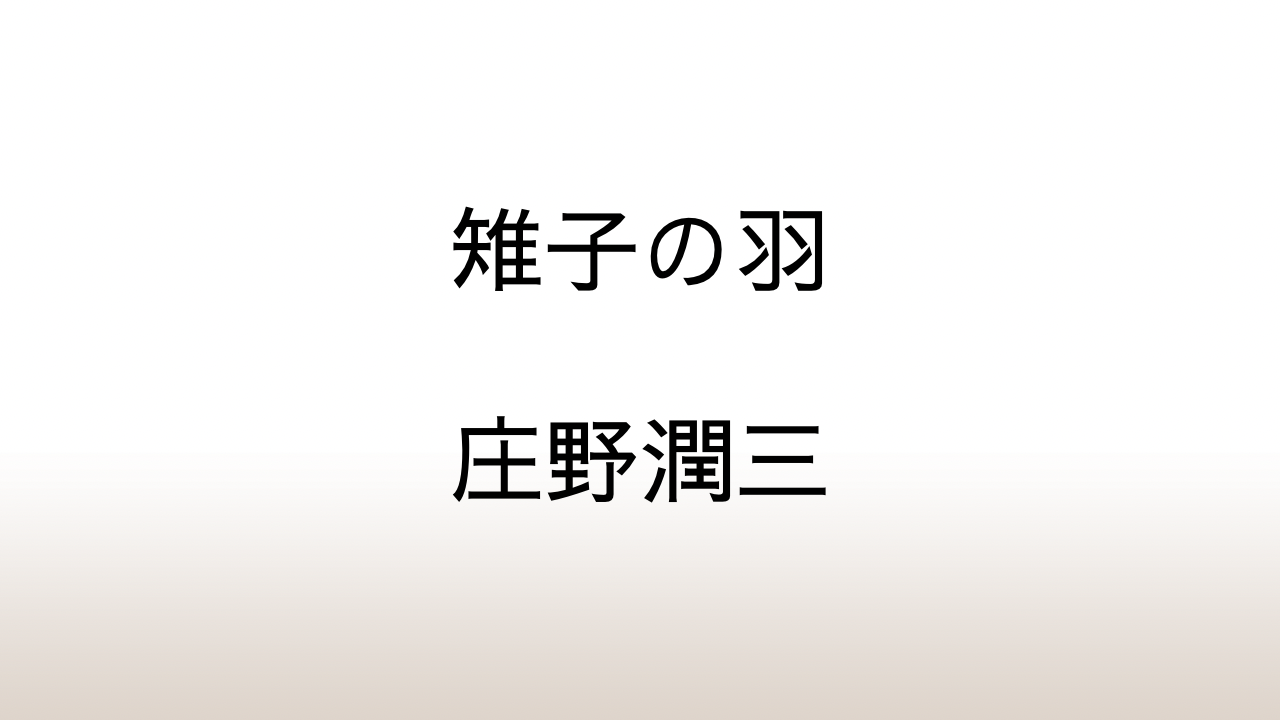
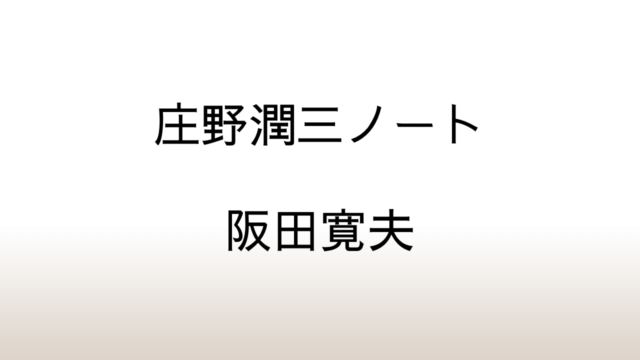

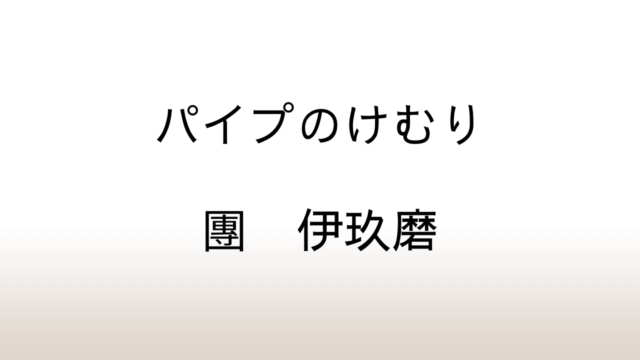


-150x150.jpg)









