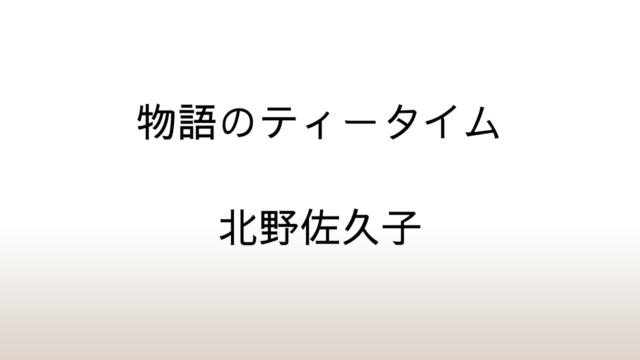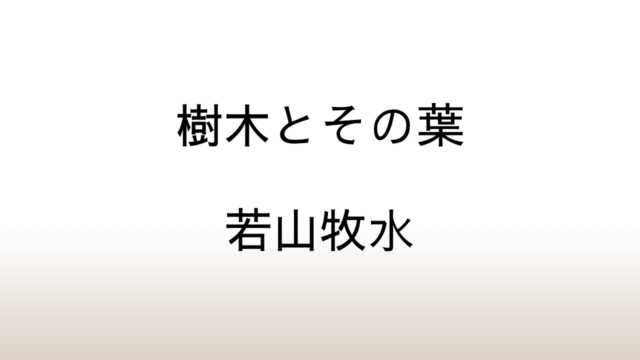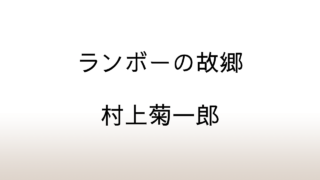サリンジャー「バナナフィッシュにうってつけの日」読了。
本作「バナナフィッシュにうってつけの日」は、1948年(昭和23年)1月『ザ・ニューヨーカー』に発表された短編小説である。
この年、著者は29歳だった。
作品集としては、1953年(昭和28年)にリトル・ブラウン社から刊行された『ナイン・ストーリーズ』に収録されている。

心に傷を負った帰還兵と現代社会との対立
「バナナフィッシュにうってつけの日」は、長篇小説『ライ麦畑でつかまえて』を代表作とするサリンジャーにおいて、最も有名な短編小説である。
そこで描かれているのは、きらびやかな通俗社会と、戦争で心に傷を負った若者との精神的な対比だ。
ニューヨークの広告マンが97人も泊まり込んでいるフロリダのホテルに、主人公(シーモア・グラス)は、妻(ミュリエル)と二人で滞在している(新婚旅行だった)。
メンタルを病んでいる夫を一人きりで放り出して、ミュリエルは、婦人雑誌のセックス記事を読んだり、指の爪にマニキュアを塗ったりすることに忙しい。
ホテルはニューヨークの広告マンが九十七人も泊り込んでいて、長距離電話は彼らが独占したような格好、五〇七号室のご婦人は、昼ごろに申し込んだ電話が繋がるのに二時半までも待たされた。(J.D.サリンジャー「バナナフィッシュにうってつけの日」野崎孝・訳)
ニューヨークの母親は、長距離電話でミュリエルの身を盛んに案じている。
彼女も、彼女の夫(ミュリエルの父親)も、頭のおかしいシーモアと一緒にいることは、ミュリエルにとって危険なことだと考えているのだ。
「ミュリエル、ちょっと待って、あたしの言うこと聞いてちょうだい」「なあに」そう言って娘は右脚に体重をかけた。「あの人がちょっとでも変な真似をしたり、変なことを言ったりしたら、すぐに電話してちょうだい──分るわね、あたしのいう意味」(J.D.サリンジャー「バナナフィッシュにうってつけの日」野崎孝・訳)
シーモアが、第二次世界大戦で心に深い傷を負った帰還兵であることは、随所で示唆されている。
「それでね。先生が言うにはね、そもそも陸軍があの人を退院させたのが完全な犯罪行為というものだって、そう言うんですって──嘘じゃないのよ」(J.D.サリンジャー「バナナフィッシュにうってつけの日」野崎孝・訳)
シーモアの精神の異常性について議論しながら、同時に、日焼けクリームやコートやファッション・ドレスについて語る二人の会話は、シーモアの健康(生命の安全)とファッションが同列に語られるという、現代社会の歪んだ価値観を意味している(「あんたあのブルーのコートの具合は?」)。
この物語のテーマは、俺たちは何のために戦ったのか?という、傷付いた帰還兵たちの心の叫びだ。
もちろん、シーモアの中には、「自分たちは、くだらない戦後社会のために戦ったのではない」という、深い葛藤があったことだろう。
シーモアの心の傷痕の深さと、俗物によって支配される現代社会の醜さとの落差こそが、主人公(シーモア)を追い込んでいったものの正体なのである。
シーモアが登場する前の、ミュリエルと母親との会話によって、読者は、シーモアが置かれている絶望的な状況を理解することができるだろう。
幼女シビルは醜い現代社会の象徴
一方、一人で出かけたシーモアは、ビーチで幼い女の子(シビル)と遊んでいる。
シビルの母親は、幼い娘にはあまり関心がないらしく、友人の女性とゴシップで盛り上がりながら、マーティニを飲むことに夢中だ(ここにも現代社会の象徴が描かれている)。
まだ四歳程度と思われるシビルは、シーモアが他の女の子(三歳半のシャロン・リプシャツ)と仲良くすることに激しく嫉妬する(「シャロン・リプシャツから聞いたけど、あんた、あの子をピアノの椅子にいっしょに坐らしてやったんですって?」)。
『ちびくろサンボ』に登場する虎を「たった六匹よ」と表現することからも分かるように、シビルは、現代社会を象徴する「満足できない女」として読むことが可能だ(「たった六匹だって?」「きみは六匹をたったって言うの?」)。
「今度はその子、押しのけてね」「その子って、誰を?」「シャロン・リプシャツ」「ああ、シャロン・リプシャツか。よくもそんな名前が思い浮かんだもんだ。記憶と欲望を混ぜ合わし、か(訳注 T.S.エリオット『荒地』冒頭の一句)」(J.D.サリンジャー「バナナフィッシュにうってつけの日」野崎孝・訳)
シーモアの言葉は、女の子の「シビル」という名前が、T・S・エリオット『荒地』からの引用であることを匂わせている。
なぜなら、「シビル」という名前は、『荒地』のエピグラムとして引用されているペトロニウス「サテュリコン」と関係が深いものだからだ。
「クーマエというところで一人の巫女が甕の中にぶらさがって暮していたのを実際に私は目撃したからだ。街の少年たちはいうのだ『巫女さん、あんたは何がしたいのだ』巫女はいつも答えた『わしは死にたいよ』」(T.S.エリオット「荒地」西脇順三郎・訳)
不死を望んだ巫女は、同時に若さを求めることを忘れたために老い衰えて、蝉のように萎んでしまい、甕の中にぶら下がって暮らしている。
巫女と訳されている言葉「sibyllam」は、「シビュラ(つまりシビル)」であって、シーモアと会話をしている少女(シビル)には、「わしは死にたいよ」とつぶやいた巫女の姿が投影されていると読むことができる。
さらに深読みすると、巫女であるシビルの存在(「わしは死にたいよ」)は、ラストシーンで描かれるシーモアの自殺を、あらかじめ予言していたものとさえ言えるかもしれない。
ちなみに、エリオットの『荒地』は、全五部から構成される長編詩で、「記憶と欲望を混ぜ合わし」のフレーズは、第一部「死人の埋葬」の冒頭で登場する(「四月は残酷な月だ」というフレーズが有名)。
四月は残酷極まる月だ / リラの花を死んだ土から生み出し / 追憶に慾情をかきまぜたり / 春雨で鈍重な草根をふるい起すのだ。(T.S.エリオット「荒地」西脇順三郎・訳)
「バナナフィッシュにうってつけの日」の前に発表された中編小説「逆さまの森」でも、エリオットの『荒地』は引用されていた。

3~4歳程度の少女との会話から「記憶と欲望を混ぜ合わし」という詩句へとつながっていく発想は突飛な印象を受けるが、醜い嫉妬心から独占欲を丸出しにするシビルの姿は、大人の女性と何も変わることがない(「今度はその子、押しのけてね」)。
主人公(シーモア)の目には、幼い女の子(シビル)までが、醜い現代社会の象徴として映っていたのかもしれない。
バナナフィッシュは俗物の象徴
シーモアが生きているのは、そんな俗物だらけの世界であって、ニューヨークの広告マンが(97人も)集まるフロリダの海岸は、現代社会の縮図である。
シーモアが語る「バナナフィッシュ」は、そんな現代社会にのさばる「俗物」を象徴するものだっただろう。
「シビル」と、彼は言った。「こうしよう。これからバナナフィッシュをつかまえるんだ。やってみようよ」「何をつかまえる?」「バナナフィッシュさ」と、彼は言った。(J.D.サリンジャー「バナナフィッシュにうってつけの日」野崎孝・訳)
バナナフィッシュは、穴の中のバナナを食べたいだけ食べて太ってしまい、穴の中から出ることができなくなり、やがてバナナ熱にかかって死んでしまう、悲劇的な魚である。
現代社会は、金儲けや不倫や酒やゴシップや浪費という「バナナ」に溢れた世界であり、そこで生きる人々は、金や酒やセックスを追いかけ回している「バナナフィッシュ」にすぎない。
戦争で心に傷を負って帰還したシーモアは、そんな現代社会に疲弊しているが、彼に寄り添う者は、どこにもいなかった。
悲惨な戦場から復帰した帰還兵の孤独が、ここにある。
ポイントは、シーモアの戦争体験が悲惨なものであればあるほど、俗物がのさばる現代社会との乖離は大きかった、ということだろう。
「ぼくの足は二つともまともな足なんだ。他人からじろじろ見られるいわれなんかあるもんか」と、青年は言った。「五階を願います」彼はそう言うと、ローブのポケットから部屋の鍵を取り出した。(J.D.サリンジャー「バナナフィッシュにうってつけの日」野崎孝・訳)
物語の最後で、シーモアは、若い妻のミュリエルを眺めながら拳銃自殺するが、その自殺は唐突で不自然のように感じられつつも、シーモアが暮らす社会とシーモアとの大きな乖離を考えたとき、むしろ必然的とさえ思われる。
居場所を見つけられない帰還兵は、「現代社会から逃避」するために、自殺するしかなかったのだ(それが、シーモアにとって、苦しみからの解放だった)。
主人公の苦悩は、作者(サリンジャー)自身の苦悩でもある。
サリンジャーが、従軍した若者たちの苦悩を描いた作品は、これが初めてではなかった。
サリンジャーの小説の主人公たちは、戦場と日常社会との違いの大きさに困惑し、混乱した(「他人」「ブルー・メロディ」「彼女の思い出」など)。

彼らが苦しんでいた背景は、「俺たちは、何のために戦ったのか?」という、戦争のアイデンティティを見失ったことである。
彼らが命をかけて戦い、守り抜いたものの正体は、セックスや金儲けがはびこる俗物的な現代社会だったと気がついたとき、彼らの絶望は、どれほど大きなものだっただろう。
「バナナフィッシュにとってパーフェクトな日」というのは、俗社会で生きる俗物どもにとって最高の日であり、逆読みすれば、そんな社会に順応できないシーモアにとって最悪な日だった、ということになる(だから死ぬしかなかった)。
野間正二『戦争PTSDとサリンジャー』は、シーモアの自殺の理由を、戦争によるPTSDに求めている。
シーモアは戦争によるPTSDに苦しむなかで、死にたいという願望/絶望をずっと抱いてきた。そういう願望/絶望を抱きつつも、妻と一緒にやって来た保養地で、シビルという可愛い少女に出会った。そのシビルに何かを感じたシーモアは、シビルに、生きつづけるための切っ掛けを見つけたいという、かすかな希望をもった。(野間正二「戦争PTSDとサリンジャー」)
自殺の原因を明確に書かなかったのは、戦争PTSDに対する理解の欠如を浮き彫りにするためだ。
作者(サリンジャー)が、第二次世界大戦のトラウマを抱えて生きていたことは、既に多くの作品から読み解かれており、「バナナフィッシュ」の主人公(シーモア)もまた、著者サリンジャーの投影であった。
戦争で深く傷付いた若者と、自分たちが楽しむことで手一杯の大人たち。
本作「バナナフィッシュにうってつけの日」は、そんな帰還兵と現代社会との対立を描いた物語だったのだ。
現代社会に救いを求めた若者のSOS
この小説を読むときに、いつも思うことは「狂っているのはどっちだ?」ということである。
物語としては、激しい戦闘で精神を病んだシーモアが、現代社会から弾き出される形で自殺してしまうが、シーモアは本当に自殺するしかなかったのだろうか。
主人公(シーモア)は、アメリカを代表して戦争に行き、国を守った若者である。
心に傷を負って帰ってきた帰還兵を、社会は守ってしかるべきだが、彼らは、自分たちの(快楽的な)生活を楽しむことに夢中だ。
シーモアの心に傷を負わせたのは「戦争」だったかもしれないが、その心の傷を一層深くしたのは、彼が戻ってきて生きている「現代社会」だった。
「そんな偉そうな口をきくの、やめてちょうだいよ、ミュリエル。あたしたちはあんたのことをとっても心配してんですよ。お父様なんか、実を言うと、昨夜あんたに帰って来いって電報を打とうかって──」(J.D.サリンジャー「バナナフィッシュにうってつけの日」野崎孝・訳)
シーモアにとって最も身近な現代社会とは、ミュリエルやミュリエルの母親やミュリエルの父親など、彼を取り巻く身内の人々である。
「バナナフィッシュにうってつけの日」は、一連のグラス家の物語群(いわゆるグラス・サーガ)最初の作品だが、残念ながら、この小説にグラス家の人々は登場しない。
次に、シーモアの自殺が触れられるのは『大工よ、屋根の梁を高く上げよ』(1955)だ。
好意的な四流批評家やコラムニストのうちで、ただの一人だって、シーモアの本当の姿を見てくれた者はいなかった。彼は詩人なんだ。本物の詩人なんだ。たとえ一行も詩を書かないにしても、その気になれば、耳の裏の形一つででも、パッと言いたいことを伝えることのできる男なんだ。(J.D.サリンジャー「大工よ、屋根の梁を高く上げよ」野崎孝・訳)
以後、サリンジャーは、シーモアの自殺の理由を解き明かすため、いくつもの作品を書き続けた(『フラニーとゾーイー』『シーモア─序章─』『ハプワース16、一九二四』)。
「シーモアが自殺したのは、三年前のちょうど今日だ。遺体を引き取りに僕がフロリダへ行ったとき、どんなことがあったか、君に話したっけか? 五時間びっしり、僕は飛行機の上で薄馬鹿みたいに泣いていたんだ」(J.D.サリンジャー「ゾーイー」野崎孝・訳)
「バナナフィッシュにうってつけの日」の中で、バディやブーブーといった兄弟がもう少し関わっていたとしたら、あるいは、シーモアの人生は、また違うものになっていたのではないだろうか?
読み方を変えると、傷付いた帰還兵を支えなければならない家族の存在こそ、この小説では問題提起されていたのかもしれない(現実として、あのグラース家でさえ、シーモアを救うことができなかったのだ)。
本作「バナナフィッシュにうってつけの日」は、救いようのない現代社会に「救い」を求めた若者の、SOSの物語なのである。
謎が多い作品として有名な「バナナフィッシュにうってつけの日」だが、この作品は、やはり、サリンジャーの代表作としてアメリカ文学史上に残るべき名作だろう。
そして、サリンジャーが一貫して描きたかったもの、それは、戦争によって傷付いた若者の心だったということも、やはり、忘れてはならないだろう。
サリンジャーは戦争と向き合い、戦争が残した傷痕を描き続けた作家だったのだ。
作品名:バナナフィッシュにうってつけの日
著者:J.D.サリンジャー
訳者:野崎孝
発行:1974/12/20(1988/1/30改版)
出版社:新潮文庫