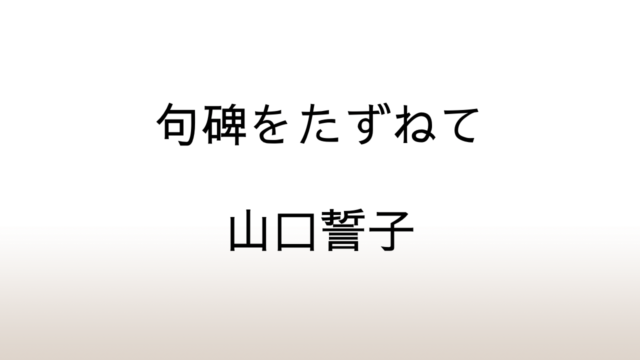鎌田敏夫「男女7人秋物語」読了。
本作「男女7人秋物語」は、1988年(昭和62年)10月9日から12月18日まで放映されたテレビドラマの原作(シナリオ)である。
キャストは次のとおり。
今井 良介(31)【明石家さんま】
神崎 桃子(28)【大竹しのぶ】
沖中 美樹(28)【岩崎宏美】
高木 俊行(34)【山下真司】
大沢貞九郎(32)【片岡鶴太郎】
島村 一枝(26)【手塚理美】
小泉ひかる(26)【岡安由美子】
横山 健(26)【柳葉敏郎】
工藤 波子【麻生祐未】
沖中 品子【堀江しのぶ】
ストラクチャーは夏目漱石『それから』
元祖トレンディードラマと呼ばれる『男女7人秋物語』のポイントは、大きく二つある。
ひとつは、物語の構造が極めてシンプルであること。
好き合っていた男女が理由あって別れて、様々な障害を乗り越えて再び一緒になるという構図は、夏目漱石『それから』に代表されるように、分かりやすい恋愛物語のひとつのパターンとなっている。
「やっぱりアメリカなんか行くなって言えばよかったな、良介」(鎌田敏夫「男女7人秋物語」)
主人公(良介)が恋人(桃子)をアメリカへと送り出したのは、「ノンフィクションライターになりたい」という桃子の夢を応援するためだった。
かつて、夢をあきらめたことのある良介にとって、桃子の無垢な夢は、自分自身の夢でもあった。
「おれは、お前の帰ってくるのを待っとったんやぞ。ずうっと待っとったんやぞ」「……」「お前から手紙が来るか、電話がかかってくるかって、毎日毎日、待っとったんやぞ」「……」「ほんまのこと言うとな、木更津に越したのも、お前のせいや」「……」「清洲橋のマンションにいると、お前のこと思い出してしようがなかった……今にもお前が帰ってきそうな気がした」(鎌田敏夫「男女7人秋物語」)
二人が乗り越えなければならない最大の障害は、アメリカで出会った男(健ちゃん)と一緒に帰ってきた桃子の裏切りである。
まるでライトビールのように爽やかだった『夏物語』と違って、続編『秋物語』のテーマは重い。
「軽かったな、あの頃は」「何が?」「毎日が……生きていることが……」「結構いろんなことがあったものな」「同じことが、だんだん重くなっていくんだって……それが年を取ることなんだって……」(鎌田敏夫「男女7人秋物語」)
『夏物語』で27歳だった桃子は28歳になっている(良介は31歳)。
『秋物語』の重さは、彼らの年齢の重さでもある。
出会いの物語だった『夏物語』に対して、『秋物語』は再生の物語だった。
二人の復活を支えたものは「ノンフィクションライターになりたい」という、桃子の夢である。
「お前、ノンフィクションのライターになる夢、どうしたんや?」「え?」「捨ててしもたんか、もう?」「今のとこやめてる……才能ないんだもの、私は」「なんで、そんなに簡単に捨てるんや!」「……」「おれは、お前の夢が実現するチャンスやと思て、アメリカに行かせたんやぞ。その夢をなんで、そんなに簡単に捨てるんや!」(鎌田敏夫「男女7人秋物語」)
「その夢をなんで、そんなに簡単に捨てるんや!」という言葉が、おそらくは、桃子の呪縛を解く魔法の言葉だった。
「どうして、あんなこと言ったのよ!」陸橋の上から、大きな声を出す。「どうして、あんなこと言ったのよ!」「何言うとるんや、あいつ!?」「どうして、あんなこと言ったのよ!」「ややこしいやっちゃなあ」(鎌田敏夫「男女7人秋物語」)
フェリー港の陸橋から絶叫する桃子の言葉は、桃子自身に対する叫びでもあっただろう。
混乱する桃子は、健ちゃんと別れて、良介とやり直すことを考え始めるが、二人の間に横たわる障害は大きい。
「桃子」「何?」「遅いよ」「……」「遅いんや、もう」(鎌田敏夫「男女7人秋物語」)
遅かったのは、桃子だけではない。
自分を裏切った恋人(桃子)を忘れるため、良介もまた、新しい恋人(美樹)と交際を始めたところだったからだ(「おれとお前はな、昔のおれとお前とは違うんや」)。
良介と桃子が復活するためには、健ちゃんと美樹という、それぞれの障害を乗り越えなければならない。
そして、相手(健ちゃんと美樹)の気持ちを考えたとき、「恋人を裏切る」という選択肢は、二人にとって確かに重すぎる選択肢だった(「神様が、私たちは一緒になってはいけないんだって言ってるような気がする」)。
本作『男女7人秋物語』は、厳しい試練を乗り越えて恋人関係を復活させた、アラサー男女の再生物語である。

誰もが前向きで一生懸命だった時代
本作『男女7人秋物語』もうひとつのポイントは、スピード感ある時代との共鳴である。
バブル時代のトレンディードラマというと、軽薄な印象を持つかもしれないが、『秋物語』の登場人物は、誰もがまっすぐで一生懸命だ。
例えば、一本気な美樹は、誰とでもすぐに性的関係を持ってしまう友人(一枝)のことが心配でならない(一枝は女性版「野上」として機能している)。
「まわりにいる男に、みんなモテたってしようがないじゃない、一枝」「……」「本当に好きな男に、好きになってもらわなきゃさ」(鎌田敏夫「男女7人秋物語」)
誠実な貞九郎も、一枝の誘惑に乗った良介を責める。
「バカだよ、お前は」「……」「好きでもないのに、そんなことになってどうするんだよ、この後」「……」「人生ってそういうもんじゃないよ」(鎌田敏夫「男女7人秋物語」)
この物語のバランスポイントは、おそらく貞九郎だ。
「人生ってそういうもんじゃないよ」という貞九郎の言葉は、この物語を通奏低音のように流れている。
だからこそ、一枝と貞九郎との対決は見応えがあるのだ。
「おれは、不死身の貞って言われてたんですよ、大学のボクシング部で」「え?」「打たれても打たれても、向かっていったから」「……」「慣れてるんですよ、おれは、人に傷つけられるのには……」(鎌田敏夫「男女7人秋物語」)
「不死身の貞」は、『秋物語』の象徴であり、スピード感ある時代の象徴でもある。
1980年代後半のバブル時代は、若者たちが元気な時代だった。
ハウンドドッグの大友康平が「負けるもんか! 負けるもんか!」と叫び、ザ・ブルーハーツの甲本ヒロトが「キスしてほしい! キスしてほしい!」と飛び跳ね、爆風スランプのサンプラザ中野が「♪走る走る俺たち~」と歌った時代。
若者たちは明るく前向きで、そして一生懸命だった。
『男女7人秋物語』の登場人物は、誰もがそれぞれに一生懸命で、そして、いつでも誰かのことを思いやっている。
「貞ちゃんに怒られちゃった」「貞ちゃん?」「不死身の貞よ」「……」「自分が不幸だからって、人まで不幸にするのは許せないって……」(鎌田敏夫「男女7人秋物語」)
不幸な女(一枝)の自己再生を促したのは「不死身の貞」だ(「私にとって、あいつは、ほんとに不死身の貞だった」)。
「美樹は……美樹は……、私のことも許して、あなたを好きになったのよ。その美樹を……あなたは、今になって捨てるっていうの!」(鎌田敏夫「男女7人秋物語」)
美樹や貞九郎のストレートな性格が、いつの間にか一枝にまで投影されている。
「私のところに来たりしたら、あのきれいな人に振られるよ」「不死身の貞は、来てくれって言われりゃ、どこだって行く」「……」「それが本気だろうと、本気でなかろうと……」(鎌田敏夫「男女7人秋物語」)
挫折することを恐れない「不死身の貞」こそ、バブル時代の象徴である。
そして、良介と桃子の復活を支えたものも、ためらわずに前へと進む、時代のドライブ感だった。
「お前は、悪い女やけどな……勝手な女やけどな……おれは、お前が好きなんや」「……」「やっぱり、お前が世界中でいちばん好きなんや」(鎌田敏夫「男女7人秋物語」)
もちろん、一途な美樹も、簡単にはあきらめたりしない。
「私は、あなたなんかより、ずっと今井さんのことが好きだった!」「……」「あなたなんかより、ずっと今井さんのことが好きだった!」「……」「アメリカに行ったら、すぐ男の人を作ってしまうような人よりも、私のほうがずっと今井さんのことを好きだった!」「……」「私は、ずうっとそう思ってた!」「……」「最初から、ずうっとそう思ってた!」(鎌田敏夫「男女7人秋物語」)
もちろん、美樹が愛したのは、自分を裏切った元カノさえも見捨てておくことのできない、そんな優しい良介だった。
そこに、美樹の苦悩があり、自己矛盾がある。
「どうして言い返さなかったのよって、桃子さんに言ってよ」「え?」「私は、あなたなんかよりずっと今井さんのことを好きだって、どうして言い返さなかったのよって……」「……」「好きな人は、一緒にならないとダメ」「……」「一緒にならないとダメよ」「……」「あなたは、今井さんのことを、そのくらいにしか好きじゃなかったのって、桃子さんに言っといてよ」「……」「今井さんにも、そう言っといてよ!」(鎌田敏夫「男女7人秋物語」)
自ら身を引いた美樹へ謝罪するために訪れた良介に向かって、美樹は、走り去る船の上からおどけて敬礼をする(ドラマのクライマックスシーン)。
「あの人のしてることで、本気のことなんかないですよ。男と女のことって、後で間違いやって分かっても、その時は、本気じゃないとつまらんのと違いますか?」「人を好きにならんと、人から好きになってもらおうと思ても無理や」(良介)
「努力して、人を好きになれるもんじゃないからね。そういうもんじゃないよ、人を好きになるっていうのは……」(貞九郎)
恋愛に全力で向かっていく誠実さが、この物語にはある。
こうした路線は、やがて「恋愛至上主義」として尖鋭化していくことになるが、少なくとも、一生懸命に生きている若者たちの姿が、この物語には描かれていた。
この物語が、現在でも共感を得る普遍的な作品となっているのは、若者たちが前向きで一生懸命に生きているからだ。
バブル時代、「まずは挑戦してみる」ということが、世の中のスタンスだったような気がする。
「失敗したらどうしよう」と悩むためらいは、ドライブ感ある時代の中では不要のものだった(おとなしいことが「暗い」という言葉で簡単に否定された)。
「一億総陽キャ」とも言える時代の高揚感が、こうしたトレンディードラマを生み出したのかもしれない(もちろん、実際には、陽キャと陰キャが混在していたが)。
一方、恋愛と全力で向き合うことができず、「8人目」になれなかった男が、桃子の恋人(健ちゃん)である。
「きみは、おれの気持ちなんか、どうでもいいんだよ」「健ちゃん!?」「おれの気持ちなんか、何とも思ってないじゃないか」「……」「おれが、きみにいてほしいことも、おれがきみを必要なことも、いなくては困るってことも、君は何にも考えてくれてないじゃないか」(鎌田敏夫「男女7人秋物語」)
健ちゃんの主張は、すべて「自分」が中心になったものだ(しかも、病気の母親とか兄貴夫婦とか、家族がややこしく絡んでくる)。
「桃子。おれは、お前の何だったんだ?」「……」「おれは、お前の何だったんだよ!」(鎌田敏夫「男女7人秋物語」)
興奮して桃子のブラウスを引き裂く健ちゃんは、自分のことしか考えることのできない自己中心的な男である。
ハンサムで男前の美樹に対して、モラハラ男の健ちゃんは、しかし、来るべき次の時代の主人公だった。
なぜなら、誰もが前向きだった時代は、やがて終焉を告げ、若者たちは全力で生きることを避けるようになるからだ(「失われた10年」の到来)。
健ちゃんは、全力で生きることをあきらめた、そんな次の時代の主人公だったのかもしれない。
障害を乗り越えて一緒になった良介と桃子は、『それから』の長井代助と平岡三千代だった。
世間の常識に逆らって結婚した二人は(略奪婚)、三部作の完結編『門』において野中宗助・御米(およね)として再登場する。
人生のドラマに最終回などなかったのだ。
「ひとつの人生が終わって、別の人生がはじまる。それから別の人生も終わって、三つ目の人生がはじまる、いつまでも続いていくのね」とは、ドストエフスキー『悪霊』に登場するリザヴェータの言葉だ。
あれから37年。
7人の男と女たちは、どのような人生を過ごしてきたのだろうか。
そして、間もなく人生の大きな節目を迎えようとしている、当時21歳だった僕たちも。
書名:男女7人秋物語
著者:鎌田敏夫
発行:1987/12/30
出版社:立風書房