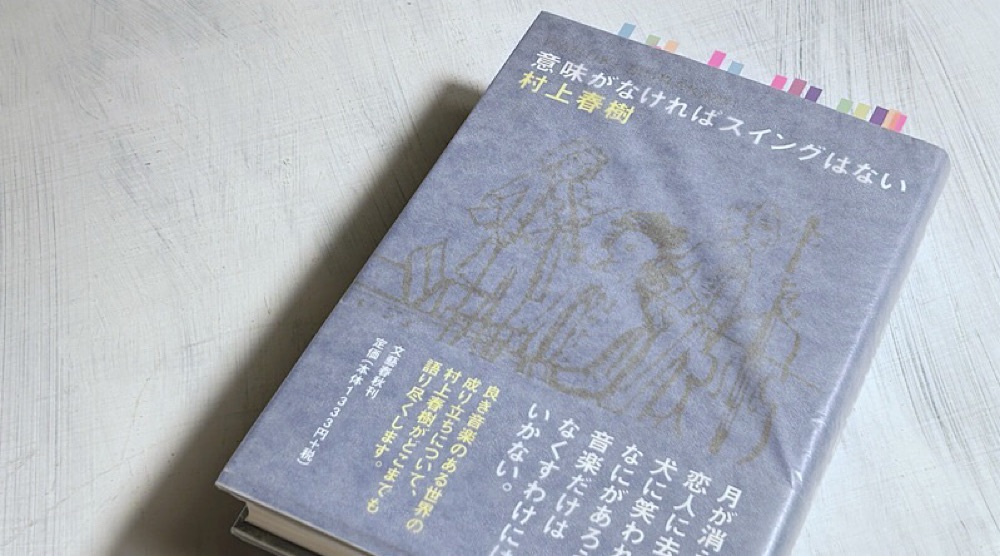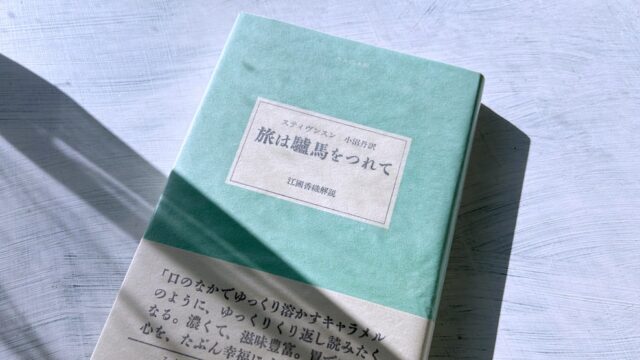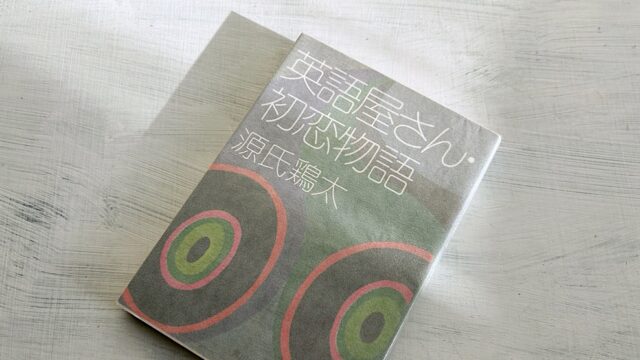村上春樹『意味がなければスイングはない』読了。
本作『意味がなければスイングはない』は、2005年(平成17年)11月に文藝春秋から刊行されたエッセイ集である。
この年、著者は56歳だった。
収録作品は次のとおり。
・シダー・ウォルトン―強靱な文体を持ったマイナー・ポエト
・ブライアン・ウィルソン―南カリフォルニア神話の喪失と再生
・シューベルト「ピアノソナタ第十七番ニ長調」D850─ソフトな混沌の今日性
・スタン・ゲッツの闇の時代1953-54
・ブルース・スプリングスティーンと彼のアメリカ
・ゼルキンとルービンシュタイン 二人のピアニスト
・ウィントン・マルサリスの音楽はなぜ(どのように)退屈なのか?
・スガシカオの柔らかなカオス
・日曜日の朝のフランシス・プーランク
・国民詩人としてのウディー・ガスリー
ブライアン・ウィルソンに投影された村上春樹という人生
本作『意味がなければスイングはない』は、音楽に関するエッセイ集である。
デビュー当時から、村上春樹の小説では「音楽」が重要な役割を担ってきた。
初期の作品では、アメリカやイギリスのポップ・ミュージックが盛んに登場している。
『風の歌を聴け』ではビーチボーイズが、『ノルウェイの森』ではビートルズが重要な役割を果たしたように。
もともとジャズ喫茶(ピーターキャット)のオーナーとして作家デビューした村上春樹だったから、当然のごとく、ジャズ・ミュージックも登場する。
『国境の南、太陽の西』は、スタンダード・ナンバー「国境の南」にインスパイアされた作品だ(小説の中では、ナット・キング・コールがこの曲を歌っている)。
さらに、村上春樹はクラシック音楽のレコード・コレクターとしても有名で、『1Q84』には多くのクラシック音楽が登場する(メインテーマはヤナーチェク 『シンフォニエッタ』だった)。
音楽との関係が深い小説家(村上春樹)が書いた音楽エッセイなんだから、当然おもしろいに決まっている。
多くの村上春樹ファンが、そう思っていたのが、本作『意味がなければスイングはない』というエッセイ集だった。
何より読み応えのあるのは、デビュー作『風の歌を聴け』から登場していたビーチ・ボーイズについてのエッセイ「ブライアン・ウィルソン」である。
初めてビーチ・ボーイズの音楽に出会ったのは、たしか1963年のことだ。僕は十四歳で、曲は「サーフィンUSA」だった。(村上春樹「ブライアン・ウィルソン―南カリフォルニア神話の喪失と再生」)
『ダンス・ダンス・ダンス』を読むまでもなく、ビーチ・ボーイズは村上春樹にとって特別な存在である。
謎の美少女(ユキ)と出会ったばかりの主人公は、カーステレオの音楽に合わせて、ユキと一緒に「サーフィンUSA」を歌う。
あの孤独な少女(ユキ)は、もしかすると少年時代の村上春樹自身だったのかもしれない。
60年代末期のタフな時代がやってきたとき、多くの若者がビーチ・ボーイズから離れていった。
ジミ・ヘンドリックスは、「もう誰もビーチ・ボーイズなんか聴かないぜ」と声高に宣言した。そのような嘲笑は、言うまでもなくブライアンを傷つけることになった。彼は、J・D・サリンジャーがそうしたのと同じように、自分だけの孤高な世界に向けてじりじりとあとずさりしていった。(村上春樹「ブライアン・ウィルソン―南カリフォルニア神話の喪失と再生」)
ビーチ・ボーイズから離れていったのは、中学校時代のクラスメート(五反田君)も同じだ。
その意味で、五反田君は、作者である村上春樹自身だったと言ってもいい。
しかし僕は自分がそのように、ビーチ・ボーイズの音楽を見捨ててしまっていたことを(あるいはすっかり忘れてしまっていたことを)、今になって残念に思う。彼らは当時、彼ら自身のひそやかな場所で、それなりに良質な音楽を必死に作り続けていたのだ。(村上春樹「ブライアン・ウィルソン―南カリフォルニア神話の喪失と再生」)
つまり、『ダンス・ダンス・ダンス』という小説は、登場人物の一人一人が、作者である村上春樹自身のペルソナであった、ということだ。
主人公は、「その後のビーチ・ボーイズ」の素晴らしさを、五反田君に説いている。
おそらく、ビーチ・ボーイズを見捨ててしまった自分自身としての五反田君に対して。
そして僕は、もしそう望めば、彼らとともに同時代を生きることもできたのだ。しかし僕はそれをしなかった。僕が『サンフラワー』と『サーフズ・アップ』を初めて耳にしたのは、ずいぶんあとになってからだった。(村上春樹「ブライアン・ウィルソン―南カリフォルニア神話の喪失と再生」)
ビーチ・ボーイズは(あるいはブライアン・ウィルソンは)、村上春樹の人生にとって、もはや外すことのできないパーツの一つになっていたらしい。
彼の文学を支えた、スコット・フィッツジェラルドと同じような存在として。
彼のペンは再び、美しい印象的な曲を次々と生み出すようになった。それはほとんど奇跡に近いことだった。「アメリカには第二章というものは存在しない」と、かつてスコット・フィッツジェラルドは書いた。しかしブライアン・ウィルソンの人生には、第二章が紛れもなく存在したのだ。(村上春樹「ブライアン・ウィルソン―南カリフォルニア神話の喪失と再生」)
村上春樹にとって、ビーチ・ボーイズは(ブライアン・ウィルソンは)、あまりにも大きな存在である。
評論家的視点から書かれている他のエッセイと比べて、本作「ブライアン・ウィルソン」に込められた重いは、あまりに重い。
このエッセイは、ブライアン・ウィルソンについてのエッセイであるとともに、村上春樹についてのエッセイでもあったのだ。
1963年に初めて「サーフィンUSA」を耳にしてから、長い歳月が流れた。ブライアンにとっても、僕にとっても、それはずいぶん重みのある歳月だった。(村上春樹「ブライアン・ウィルソン―南カリフォルニア神話の喪失と再生」)
その結果、このエッセイは、限られた枠の中に収まりきらない居心地の悪さを、読者に与えることになった。
ブライアン・ウィルソンに関しては、彼についてだけで一冊分の文章を書くべきだったのだ(あるいは『ダンス・ダンス・ダンス』のような物語として)。
とはいえ、このエッセイは、村上春樹の小説を読む者にとって、重要な意味を持つものであることに変わりはない。
ワイキキ・シェルのいちばん前の席に座った村上春樹は、ブライアン・ウィルソンの歌う「ラブ・アンド・マーシー」を聴いた。
とりあえず、僕らはここにいる。(略)それは誰がなんと言おうと、素晴らしいことであるように思える。少なくとも我々は生き延びているし、鎮魂すべきものをいくつか、自分たちの中に抱えているのだ。(村上春樹「ブライアン・ウィルソン―南カリフォルニア神話の喪失と再生」)
この一篇だけのために本書を買っても、決して損をしたとは思わないだろう。
思い入れが文学に与える影響というものを、我々はこのエッセイから知ることになるのかもしれない。
ブルース・スプリングスティーンへ送るエール
本書『意味がなければスイングはない』において、もう一篇、読むべき作品がある。
ハルキストはここで「ああ、スタン・ゲッツだな」と思うところだが(我々も最初はそう考えていた)、実は「スタン・ゲッツ」ではない。
確かに、スタン・ゲッツは、村上春樹の小説に何度となく登場するレギュラー選手だが、本書『意味がなければスイングはない』において、「スタン・ゲッツの闇の時代1953-54」は、どうにも脇役に徹していると言わなければならない。
それは、スタン・ゲッツに対する作者の情報量があまりにも多すぎて、限られたページ数の中では消化できていないという印象を与えるからだ。
この連載エッセイのコンセプトについては「あとがき」に触れられている。
一度音楽のことを、腰を据えてじっくり書いてみたいと、前々から考えていたのだが、なかなかそういう機会に恵まれなかった。具体的に言えば、ひとつのテーマについて原稿用紙五十枚から六十枚くらいのものを、シリーズとしてまとめて書きたかった。(村上春樹「意味がなければスイングはない」あとがき)
ポイントは「原稿用紙五十枚から六十枚くらいのもの」という部分で、多くの作品の場合、この枠内で美しくまとめられているのだが、とりわけ思い入れの強いミュージシャンについて語るには、このページ数は厳しい条件だったのではないだろうか。
それは「ブライアン・ウィルソン」でも感じたことだが、「ブライアン・ウィルソン」の場合、ワイキキのライブからスポット的に文章を掘り下げているので、何とかこの枠の中に収めることができた。
一方で「スタン・ゲッツ」の場合、「闇の時代1953-54」に焦点を絞っているとはいえ、伝記の引用を中心とした概略の紹介に留まっているような印象は拭えない。
書いていけばキリがなくなるから、ある程度のところで妥協したのではないか?という疑問が、読後につきまとうのだ。
その点、「ウィントン・マルサリス」で、おまけのように登場してきたチェット・ベイカーについてのコメントはいい。
『レッツ・ゲット・ロスト』は晩年のベイカーの姿を捉えた記録映像だから、もう身体は麻薬でぼろぼろだし、テクニックもサウンドも冬場のキリギリスみたいによれよれになっている。しかしそれにもかかわらず、ベイカーの演奏はまっすぐ心に届くのだ。(村上春樹「ウィントン・マルサリス」)
わずか数行のチェット・ベイカーに関する(おまけ的な)コメントは、20ページに渡るスタン・ゲッツに関するエッセイ以上に、多くのものを伝えてくれる。
あまりにもスタン・ゲッツを知りすぎているが故に、省くことのできない情報が、中途半端な形のままで文章になってしまったのだろうか。
それに比べると、本来、村上春樹的とは言えないはずの「ブルース・スプリングスティーン」に関するエッセイは素晴らしい作品となっている。
僕が初めてアメリカに行ったのは1984年の夏で、その目的のひとつは小説家レイモンド・カーヴァーにインタビューを行うことだった。アメリカに着いて空港からタクシーに乗ったとき、まず目についたのは、発売されたばかりのLP『ボーン・イン・ザ・USA』の巨大な広告看板だった。(村上春樹「ブルース・スプリングスティーンと彼のアメリカ」)
このエッセイは、小説家(レイモンド・カーヴァー)とロック・ミュージシャン(ブルース・スプリングスティーン)との共通点を検証する内容のエッセイである。
ブルース・スプリングスティーンを語るのに、レイモンド・カーヴァーを引用するという手法に、我々はまず驚かされることになる。
ワシントン州オリンピック半島にあるレイモンド・カーヴァーの家の居間で、二人で向かい合って彼の小説の内容について語りながら、僕はふとブルース・スプリングスティーンの「ハングリー・ハート」の歌詞を思い出すことになった。(村上春樹「ブルース・スプリングスティーンと彼のアメリカ」)
村上春樹は明らかに小説家であり、小説家としての視点から音楽にアプローチしている。
「ブライアン・ウィルソン」でも、作者は、J.D.サリンジャーやスコット・フィッツジェラルドを引き合いに出しながら、その音楽を読み解いていった。
そこに、小説家が音楽を読み解くことのおもしろさがある。
あたりまえだが「ウディ・ガスリー」に登場するのは、もちろん、スタインベックの『怒りの葡萄』だった(あたりまえすぎるが)。
小説家は、当然のごとく、ブルース・スプリングスティーンの歌詞に注目する。
救いのない町に生まれ落ちて
物心ついたときから蹴飛ばされてきた。
殴られつけた犬みたいに、一生を終えるしかない。
身を守ることに、ただ汲々としながら。
俺はアメリカに生まれたんだ。
それがアメリカに生まれるということなんだ。
(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・イン・ザ・USA」村上春樹・訳)
「俺はアメリカに生まれたんだ。それがアメリカに生まれるということなんだ」と、ブルース・スプリングスティーンは叫んでいる。
それは、もちろん、アメリカに生まれたことの不幸を、嘆き、悲しむ叫びだ。
ブルース・スプリングスティーンが「俺はアメリカに生まれたんだ」と叫ぶとき、そこにはいうまでもなく怒りがあり、懐疑があり、哀しみがある。俺が生まれたアメリカはこんな国じゃなかったはずだ、こんな国であるべきではないのだ、という痛切な思いが彼の中にはある。(村上春樹「ブルース・スプリングスティーンと彼のアメリカ」)
レイモンド・カーヴァーもまた、アメリカに生まれたことの不幸を書き続ける作家だった。
ワーキング・クラスの家庭に生まれ育った彼らは、アメリカの不幸について叫ばないわけにはいかなかったのだ。
そこに共通しているのは、アメリカのブルーカラー階級(ワーキング・クラス)の抱えた閉塞感であり、それによって社会全体にもたらされた「breakness=荒ぶれた心」である。(村上春樹「ブルース・スプリングスティーンと彼のアメリカ」)
似たような境遇から出発した彼らのうち、一人はロックスターとなり、もう一人は夭折の作家となった。
ブルース・スプリングスティーンは語っている。
「自分の知っていることを書き、自分の見たことを書き、自分の感じていることを書こう」と。
そしてカーヴァーもあるインタビューの中で、スプリングスティーンが述べたのと同じようなことを語っている。自分の知っていることを書け、と。「若い作家が、自分の知っていることについて書かないとしたら、彼はいったい何について書けばいいんだ?」(村上春樹「ブルース・スプリングスティーンと彼のアメリカ」)
作者(村上春樹)は、レイモンド・カーヴァーに抱いたものと同じ共感を、ブルース・スプリングスティーンにも抱いていた。
このエッセイは、だから生々しい匂いに満ち溢れている。
評論家・村上春樹ではない、生きている村上春樹の書いた、匂いたつようなリアリティに。
今でもスプリングスティーンの音楽を聴くたびに、春の日差しに照らされたアズベリーパークの光景をふと思い出す。僕が1970年前後、東京でなんとか生き残るための努力を続けていた頃、ブルース・スプリングスティーンもやはり同じように、このアズベリーパークの町で悪戦苦闘していたのだ。(村上春樹「ブルース・スプリングスティーンと彼のアメリカ」)
結局のところ、音楽エッセイというのは、個人的な思い入れに尽きるということだ。
評論家的な文章は、商業的な音楽評論家に任せておけばいい。
評論家には書けないものを書くからこそ、村上春樹が書くことに意味が生じるのである。
それから三十年以上の歳月を経て、我々はそれぞれにずいぶん遠い場所にまで歩を運んできた。うまくいったこともあるし、あまりうまくいかないこともあった。そしてこれからも生き残るために、それぞれの場所で、それぞれの闘いを続けていかなくてはならないはずだ。(村上春樹「ブルース・スプリングスティーンと彼のアメリカ」)
訂正しなければならない。
「ブライアン・ウィルソン」と「ブルース・スプリングスティーン」、この二つのエッセイを読むためだけに、本書を買う価値はある。
そういうことだ。
書名:意味がなければスイングはない
著者:村上春樹
発行:2005/11/25
出版社:文藝春秋