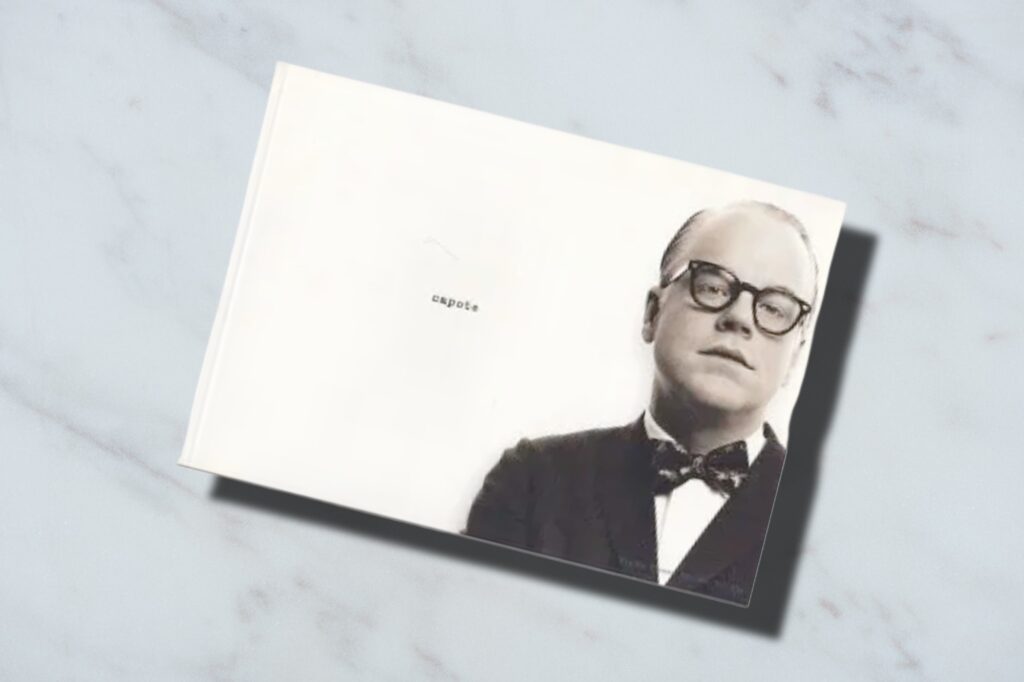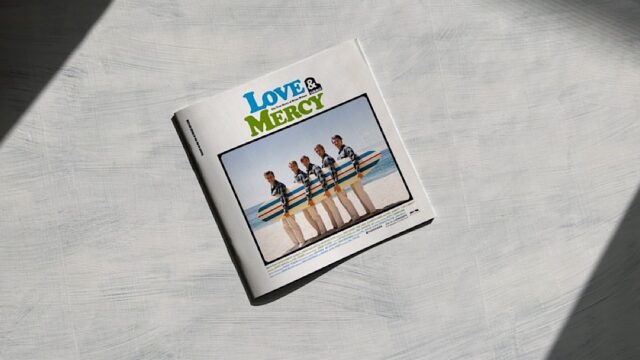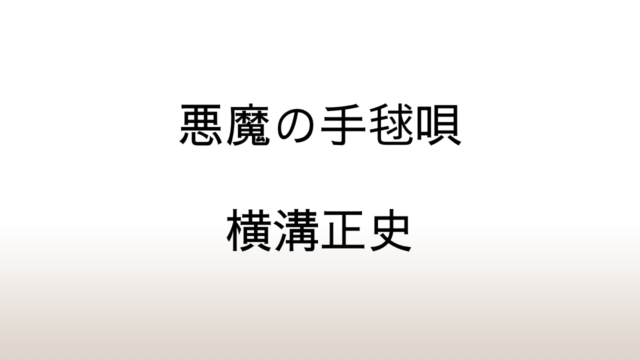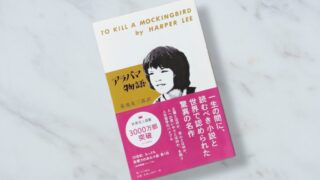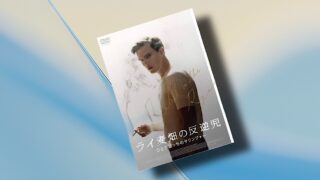映画『カポーティ』鑑賞。
本作『カポーティ』は、2005年(平成17年)に公開されたアメリカ映画である。
原題は「Capote」。
主演のフィリップ・シーモア・ホフマンは、この年、38歳だった。
第78回アカデミー賞「主演男優賞」受賞。
タイトル「冷血」が意味するもの
本作『カポーティ』は、作家(トルーマン・カポーティ)が、代表作『冷血』(1965)を完成するまでの経過をたどった伝記映画である。
「メイキング・オブ・『冷血』」と言っていいかもしれない。
『冷血』は、カポーティにとって、非常に重要な作品だった。
「じっと座って書いてなんかいられない。隣の部屋にチョコレートの箱があって、どうにも我慢できないみたいなものです。ここでいうチョコレートが小説(フィクション)の代りに事実(ファクト)を書きたいということでした」(ジェラルド・クラーク「カポーティ」中野圭二・訳)
カポーティが求めていたのは「真実を真実によって語らせる」という、文学への新たなアプローチだった。
1959年(昭和34年)11月16日付け『ニューヨーク・タイムズ』で「クラター事件」を知ったカポーティは、自分が「チョコレートの箱」を見つけたことに喜んでいたかもしれない。
『ニューヨーカー』の編集者(ショーン)に企画意図を説明して承諾を取り付けた後、カポーティは、幼なじみ(ネル・ハーパー・リー)と一緒にカンザスへ向かった。
ネルは彼女自身の作品である『アラバマ物語』をまだ出版はされていなかったが完成しており、二つ返事で引き受けた。(ジェラルド・クラーク「カポーティ」中野圭二・訳)
映画では語られていないが、カポーティが持参したトランクには、食料品が詰めこまれていた(「あっちへ行ったら食べるものがないんじゃないかと心配してたの」)。
担当刑事(KBI捜査官)アルヴィン・デューイの回想は、ジョージ・プリンプトン『トルーマン・カポーティ』に収録されている。
「初めて会ったとき、彼は小さな帽子をかぶり、大きなシープスキンのコートを着て、すごく長い、細いスカーフを床まで垂直に垂らしていた。靴はモカシンの一種。ここら中西部の記者の服装とは少々違っていた」(ジョージ・プリンプトン『トルーマン・カポーティ』野中邦子・訳)
保守的な中西部の田舎町(ガーデン・シティ郊外のホルカム)における取材は簡単ではなかった。
一度、すごく落ちこんで絶望的になり、何もかも投げ出してニューヨークへ帰るつもりだ、とネルに語ったことがあった。「ここの人間とは共感というものが得られない。てんで理解できないんだ」(ジェラルド・クラーク「カポーティ」中野圭二・訳)
映画は(物語は)、セレブが生きる大都会(ニューヨーク)と、残虐な犯罪に揺れる田舎町(ホルカム)とが対比する形で描かれていく。
そして、そこに「もうひとつの世界」が重ねられた。
犯罪者たちが生きる「闇の世界」である。
「あんなことをやる人間ってのは、どこか狂ったところがあるに違いない」ペリーはいった。「おれを一緒にしないでくれよ」ディックがいった。「おれはまともなんだから」(トルーマン・カポーティ「冷血」佐々田雅子・訳)
カポーティの『冷血』は、クラター一家四人を射殺して逃走した二人の「冷血」な男たちを描いている。
そこから浮かび上がってくるのは、「冷血」な犯罪者たちを生みだした「冷血」な社会の存在だ。
カポーティが二人の犯罪者たち(ペリー・スミスとディック・ヒコック)に惹きつけられていく様子を、映画は克明に再現している。
とりわけ、ペリーに対する共感は大きかった。
捜査官(アルヴィン)の妻(マリー・デューイ)は、「トルーマンはペリーがとても好きになった。ヒコックのことは好きじゃなかった」と証言している。
二人の関係は恋愛よりもっと複雑だった。おたがいのなかに、そこに自分がもしかしたらなっていたかもしれない人間を認めた、あるいは認めたと思った。(ジェラルド・クラーク「カポーティ」中野圭二・訳)
カポーティもペリーも人並み外れて身長が低く、家庭環境も酷似していた。
二人ともアル中の母親と不在の父親と養家に悩まされた。ペリーが送られた孤児院では、インディアンとの混血であることと寝小便のために軽蔑された。一方トルーマンは女性的であったがためにばかにされた。(ジェラルド・クラーク「カポーティ」中野圭二・訳)
主演俳優(フィリップ・シーモア・ホフマン)演じるカポーティは、現実のトルーマン・カポーティが抱えるコンプレックスを象徴的に表現している。
後年、彼は薬物やアルコールの依存症に苦しみ、薬物の過剰摂取により急死した。
人生においてさえホフマンは、あの「カポーティ」を演じ続けていたかのように。
トルーマン・カポーティは、殺人鬼(ペリー)の中に、自分自身を見つけた。
トルーマンは『遠い声、遠い部屋』の十三歳の主人公ジョエル・ノックスという虚構の人物のなかにもう一人の自分を投影した。そしてペリーのなかに、自分の影、自分の暗黒面、自分自身の積もり積もった怒りや傷が形をとって現れたのを認めたのだ。(ジェラルド・クラーク「カポーティ」中野圭二・訳)
担当捜査官(アルヴィン・デューイ)も、カポーティとペリーとの類似性に気がついていた。
「トルーマンはペリー・スミスの中に自分を見た。もちろん危険なタイプが同じだったわけではなく、子供時代が共通していたんだ。二人の子供時代は、ある意味で同じだった。身長もほとんど同じだったし、体つきも似通っていた」(ジョージ・プリンプトン『トルーマン・カポーティ』野中邦子・訳)
マリー・デューイ(アルヴィン夫人)は、次のように回想している。
「二人とも両親が離婚していた。トルーマンは奇妙だといっていたわ。人生の道を歩んできて、突然、分かれ道にさしかかる。右へ行っても、左へ行ってもいい。彼がいうには、この場合、彼は右へ行き、ペリーは左へ行ったのだと」(ジョージ・プリンプトン『トルーマン・カポーティ』野中邦子・訳)
社交界のアイドル(トルーマン・カポーティ)は、コンプレックスの塊のような人間だった。
奇妙な風貌で低身長の男は、声まで女性的であり、おまけにホモセクシュアルだった。
彼がペリーのような「暗黒の道」を生きなかったことは、ただ偶然でしかない。
だからこそ、彼は、ペリーの闇を掘り下げる作品に「冷血」というタイトルをつけたのだ。
それは、冷血な犯罪者を育んだ、冷血な社会の物語だった。
トルーマン・カポーティの葛藤
「冷血」は、犯罪者たちに取材するノンフィクションライター(つまり、カポーティ)を意味するものでもあった。
彼らが『冷血(イン・コールド・ブラッド)』というタイトルを知ったとき──それは彼らが殺害を計画していたことを三語で示していた──トルーマンは、その情報は間違っていると嘘をついた。しかし、彼らはだまされなかった。(ジェラルド・クラーク「カポーティ」中野圭二・訳)
ペリーは「『冷血』という題は、おれたちの良心にとってだけでも衝撃的だ」と憤慨したが、トルーマンは自分の嘘を押しとおした。
トルーマンは作家であり、事件を最後まで(つまり、彼らが絞首刑になるまで)取材を続けなければならなかったからだ。
新しい小説(『冷血』)が、自分の代表作になるだろうということを、もちろん、カポーティは知っていた。
目の前には、ほんの三、四十ページが欠けているだけのベストセラーが待ち構えており、それは彼の生活を根底から変え、彼を金持にし、何よりも欲しくてたまらなかったもの、すなわちアメリカ、どころか世界中で最もすぐれた作家の一人として認知されるという名誉が与えられることがわかっているだけに、彼の苛立ちはいっそうひどかった。(ジェラルド・クラーク「カポーティ」中野圭二・訳)
いつまで続くとも知れない審理の行方に、カポーティの緊張感は限界にまで達しつつあった。
「緊張と不安のまざり合った恐るべき状態に陥っています。ペリーとディックは連邦裁判所での裁判のやり直しを求めて訴えています。もしそういうことになったら、ぼくは完全に壊れてしまいそうです」(ジェラルド・クラーク「カポーティ」中野圭二・訳)
それは、カポーティにとって、まさしく「拷問」のような時間だったに違いない。
ペリーに「もう一人の自分」を見いだした作家(カポーティ)は、今や、犯人たちの死刑執行を今か今かと待ちわびる、一人のノンフィクションライターにすぎなかった。
ペリーとディックのとめどない上告は、トルーマンを単に陰鬱にし、不安に陥れただけではなかった。それは解決不能の道徳的ジレンマをもたらした。彼としては早く本を出したくてたまらなかったが、それはとりもなおさず、二人の痛ましい死を意味していた。(ジェラルド・クラーク「カポーティ」中野圭二・訳)
担当弁護士が「ペリーとディックが絞首刑を免れるだけでなく、本当に自由の身になるかもしれない」とほのめかしたとき、カポーティは本気で激怒したという(「なるほど、それで連中がまっ先にぶっ殺すのはあんたってわけだ」)。
弁護士の楽観的な推測が外れて、二人の絞首刑が確定したとき、カポーティの名作『冷血』が完成した。
死刑執行には、『ニューヨーカー』の編集者(ジョー・フォックス)が同行している(映画ではショーンになっていた)。
階段、輪縄、マスク。しかし、そのマスクが下ろされる前に、死刑囚は教戒師が差しだしたてのひらにガムを吐きだした。デューイは目を閉じた。ロープが首をへし折るドサッ-ボキッという音が聞こえるまで、その目は開けなかった。(トルーマン・カポーティ「冷血」佐々田雅子・訳)
捜査官(アルヴィン・デューイ)は、「自分は目を閉じてはいなかった」と証言している。
「誰も口をきこうとしなかった。トルーマンはただそこに立って見つめ、聞いていた。『冷血』では私が目を閉じていたと書かれているが、それは事実ではない。目は閉じていなかった。最初から見ていたし、最後まで見届けた。クラッター家の若い女の子のようすを見たあとでは、自分でレバーを引くことだってできた」(ジョージ・プリンプトン『トルーマン・カポーティ』野中邦子・訳)
編集者(ジョー・フォックス)の話によると、二人の死刑が執行された後しばらく、カポーティは泣き続けていたという。
「ニューヨークへ戻る飛行機で、私はトルーマンの隣に坐った。彼は私の手を握り、道中のほとんどを泣きつづけた。(略)長い旅だった」(ジョージ・プリンプトン『トルーマン・カポーティ』野中邦子・訳)
カポーティを励ましたのは、パートナーのジャックだった(映画ではネル・ハーパー・リーに置き換えられていた)。
あとでトルーマンは泣きながらジャックに電話をして、目撃した恐るべき光景を語った。ジャックは同情的ではなかった。「彼らは死んだんだ、トルーマン」彼は言った。「そしてあんたは生きているんだ」(ジェラルド・クラーク「カポーティ」中野圭二・訳)
彼らを殺したものは、もしかすると、自分たちだったのかもしれない。
冷血なノンフィクションライターは、『冷血』という作品を通して、「冷血な犯罪者」を育て上げた「冷血な社会」について訴えかけている。
大平原を疾駆していたのはもう一つのアメリカの姿、まずしく、住所不定の、できそこないのアメリカである。(略)被害者と殺害者の両方がアメリカの縮図だった──光と闇、善と悪なのだ。(ジェラルド・クラーク「カポーティ」中野圭二・訳)
ノンフィクション・ノヴェル『冷血』を、単なる「犯罪ルポルタージュ」として読んでしまっては、作者の意図を汲み取ったことにはならないだろう。
作者(カポーティ)は『冷血』の中で、「もしかしたら自分だったかもしれない男」の死を描き、彼を(自分たち)を破滅へと追いやった社会の闇をあぶりだした。
もとより、加害者たちを擁護するつもりはなかった。
彼はただ、彼らを(自分たちを)生みだしたアメリカ社会の「闇」にしっかりと向き合いたかっただけなのだ。
アメリカ人は、常にアメリカ社会と向き合い続けているものだ(ブルース・スプリングスティーンが「ボーン・イン・ザ・USA」を歌ったように)。
「冷血」という名のアメリカの闇は、冷血な犯罪者たちを生み続けている──。
それが、トルーマン・カポーティの出した結論だったのではないだろうか。
もちろん、犯罪者を利用してベストセラー小説を書き上げる彼もまた、アメリカ社会の闇のひとつの姿だ。
ペリーとディックが生きる牢獄も、クラター一家が葬られたホルカムの墓地も、セレブたちが集う社交界も、それはとりもなおさず「ひとつのアメリカ」である。
アメリカという闇の深さを、映画『カポーティ』は描き切った。
『カポーティ』に描かれるアメリカは、決して理想の国家たる「アメリカ」ではない。
映画は常に暗いトーンで描かれ、不穏な旋律を奏で続けている。
それは、厳しい家庭環境の中で育ち、社会の侮辱を受けて生きるカポーティ自身が見てきたアメリカの姿だった。
書名:カポーティ
著者:ジェラルド・クラーク
訳者:中野圭二
発行:1999/04/20
出版社:文藝春秋