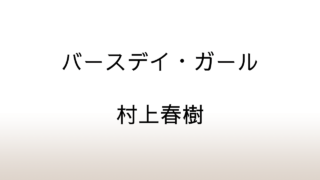山内義雄「遠くにありて」読了。
本書は、早稲田大学のフランス文学者として著名な山内義雄の随筆集である。
マルタン・デュガール『チボー家の人々』の翻訳者と言えば、すぐに分かるかもしれない。
意外にも山内先生は生前に随筆集を出していなくて、没後一年で企画された本書が最初の随筆集であったようだ。
全体の構成は「一 音楽のことなど」「二 本のはなし」「三 過ぎし日のこと」「四 友をしのんで」「暮らしの中から」となっていて、文学者なのに音楽の話題が一番最初に入っていることがおもしろい。
書名の「遠くにありて」は、冒頭に収録されている「遠くにありて思うもの」から来ている。
「「ふるさとは遠くにありて思うもの」とかつて室生犀星がうたっている。その「ふるさと」は、私にとって、まさに時間的にも空間的にもきわめて遠いものであることを思わずにはいられない」という文章で始まる、短い随筆だ。
故郷である佐渡郡八坂へ帰省したのは、今から四十年余りも昔、中学五年生のとき一度きりだったと書いてある。。
「音楽好きの音痴」は、若い学生に連れられて銀座裏にあった名曲喫茶へ行った時の話で、山内先生は「腰を下ろすところもないほど立てこんでいた客のすべてが小さなテーブルの上の一椀の紅茶を前に一様に首うなだれ、きわめて沈痛に電蓄から流れ出る音楽に聞き入っている姿」を見て驚き、ベートーヴェンの交響曲を三曲も立て続けに聞かされた末に「ここにいる奴らは皆馬鹿なのだな」だと考えるに至る。
若い頃に自分自身で何か楽器を覚えておくべきだったと後悔している山内先生にとって、鑑賞だけの音楽は「音楽好きの恐るべき音痴」となるらしい。
「まぼろしの京都」は、京都大学で恩師となった上田敏に関する思い出を書いたもので、新聞で「智恩院境内源光院焼く」という小さな記事を見た山内先生は、かつてそこに上田敏が暮らしていた頃のことを思い出す。
「上田先生ゆかりの源光院が焼けてしまい、こうして、京都へ行ったらぜひにと思っていた思い出がみんな焼けてしまった今、わたしにとって、京都もどうやらまぼろしになってしまった感が深い」という一文で締めくくられている、この随筆は、昭和40年に書かれたものである。
「颱風の眼」は、旧友であり詩人の木々高太郎が亡くなったときの話。
おたがい、そろそろ先の見える年齢になったことだし、そのうち身辺の俗用に何とか折り合いをつけて、ゆっくり話しあう機会をつくりたいと思っていた矢先、ぽっくり死なれてしまった。あれほど元気だった彼がと、まったく信じられないほどだったが、考えてみると、それもまたいかにも林君(木々高太郎)らしい死に方で、およそ「ご愁傷」なんていうじめじめした感じとは程遠く、闊達に「じゃあまたね!」とか何とか言って、手を振りながら遠ざかって行く感じだった。(山内義雄「颱風の眼」)
旧友の死を惜しむ愛情に満ちた、優れた追悼文である。
初めての随筆集ということで、戦後間もなくの頃から逝去まで、およそ30年近くの間に描かれた随筆が、テーマを問わずに収められていて、まさしく選集としての醍醐味を味わうことのできる一冊だと思った。
77歳のフランス旅行日記
本書の巻末には、山内先生が1971年に初めてフランスへ旅行したときの日記が収録されている。
随筆とは趣きの違うものだが、ひとつのフランス紀行が書けそうなくらいに充実していて、読んでいておもしろい日記だった。
Putney へのバスの帰りみち、その途方もない長さ、わびしい町はずれの感じ。右に左に古びた煉瓦の家並。横へ入る道の両側はずっと長く伸びた画一的な家並。小さな各々の家の入口には申し合わせたように白い柱。どの横町もすべておなじ感じ、たまたま並木のある横町があっても、画一的なおなじ家並から感じられる何とも侘しい感じ、こんなところによくも住んでいられると、その無神経さにおどろくばかり(二十五日)
車窓からのフランスの風景、どうやら日本の風景に似ていて大した感激も感じない。ただ、両側をやさしい並木にまもられた小流れの多いのにかつての日の荷風さんのことを想う(二十九日)
駅前旅館。窓から見下すとすぐ横手に駅が見える。ホテルの娘、日本が好きで来年出かけるという。(略)夜ふけて隣室で女客同士のどなり声。こちらからうるさいぞとどなったのにおどろいたか、ひっそりとなる(十一日)
いずれもフランス旅行というよりは、近所を散策しているかのような気楽さがある。
現実のフランスを生身で感じたままの言葉で書いた日記だからこそ、読んでいておもしろいと感じたのかもしれない。
書名:遠くにありて
著者:山内義雄
発行:1975/4/1
出版社:毎日新聞社
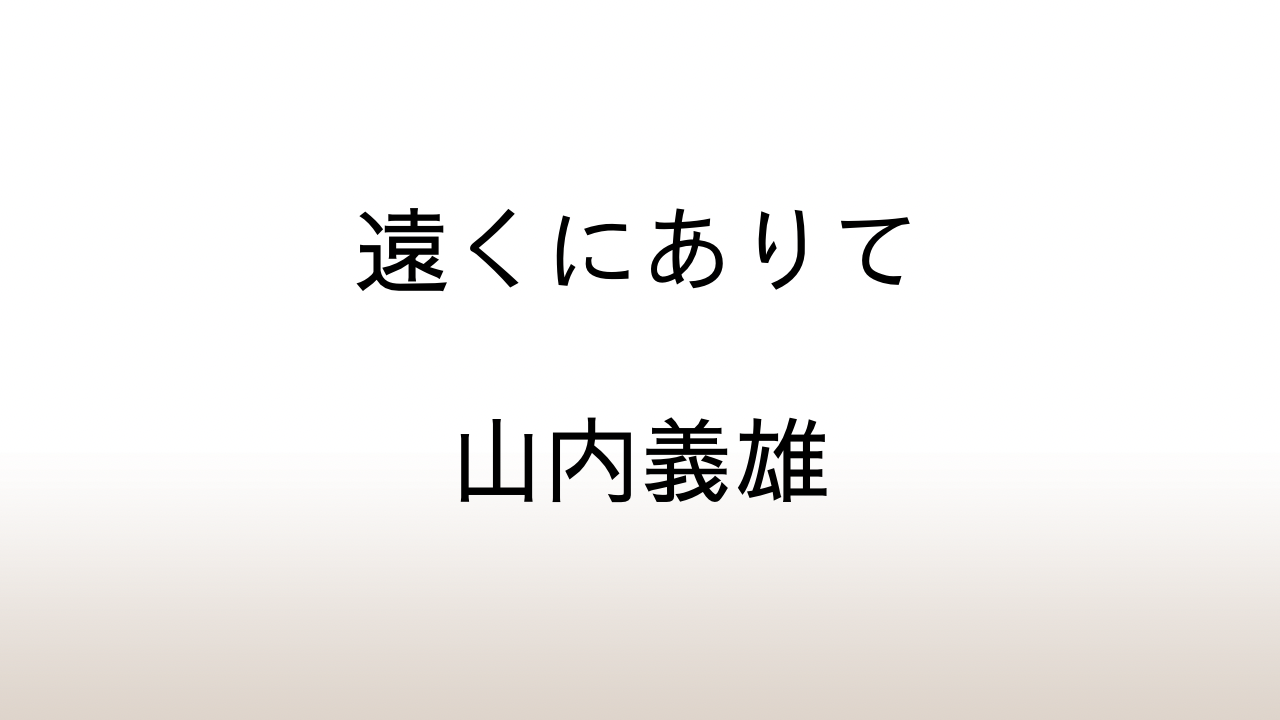
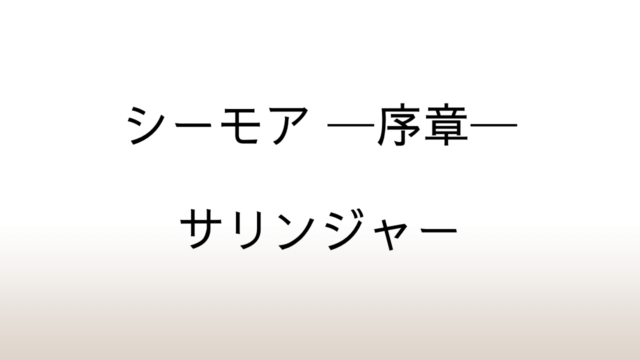


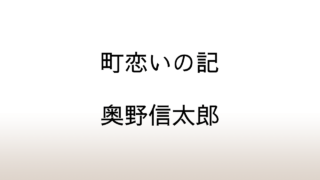

-150x150.jpg)