中村明「日本の一文 30選」読了。
井伏鱒二「珍品堂主人」の登場人物のモデルが小林秀雄だという話は、本書の中にも登場している。
東京荻窪の井伏邸を訪れた折、その作品に登場し、骨董は女に似ているという持論を展開する来宮という学者は、実は小林秀雄がモデルだと、作者自身の口からうかがった。「骨董も女も惚れていない人には一文の価値もない。惚れてるから夢中になる。彼、夢中だったからね」ととぼけると笑う井伏に、わかっていながら「どっちに夢中だったんですか、骨董の方ですか」ととぼけると、井伏は几帳面にわざわざ「骨董の方に」と念を押し、「小林君は昔、茶碗が欲しくて家を売ったり、それから刀の鍔に凝って、鍔は人間の象徴だとか一生懸命理屈つけて、方々に鍔を見に行く。今は勾玉かな」(中村明「日本の一文 30選」)
本書は、日本文学に登場する文章表現を引用しながら、日本語や文章テクニックについて解説することを目的としているものだが、随所に著者の個人的な体験の回想が織り込まれているので、随筆として読んでも楽しい。
井伏さんと会って話をしたときのことは、他にも紹介されていて、井伏さんの作品には、随筆か小説か迷うような作品の多いことを例に、著者が「小説と随筆との違いはフィクショナイズされてるかどうかってことだけですか」と訊ねると、井伏さんは「僕は初めから決めてるんだ、嘘を書いたら小説ってね」と即答した後で、「ただ、ほんとのことを書いても小説欄に入れた方がいいこともある。原稿料が随分違うんだ」と、いたずらっぽく笑ったという。
著者は、後日、鎌倉にある永井龍男を訪ねているが、雑誌で井伏訪問記を読んでいた永井さんは「井伏さん、あんたによくしゃべったね。将棋や釣りの話なら別だが」と驚いていたということも、井伏さんの人柄を伝えるエピソードである。
もっとも、本書は最初に書いたとおり、日本語の使い方や文章表現について解説することを目的としているのであって、文壇の四方山話が主ということではない。
例えば、小沼丹の「黒と白の猫」という作品の中から「しかし、猫は落着き払って、細君なぞ歯牙にも掛けぬ風情を示した。」という一文を紹介しながら、擬人的表現方法について具体的に解説していくのだが、「万物とともに生きようとした作家小沼丹の、おびただしい数のカテゴリー転換や擬人的な造形は、そのまま映像化できない典型的な例だろう」と、著者は指摘している。
無味乾燥の解説ではなくて、作家の人間性にまで踏み込んだ分析をしているところが、本書の一番の味わいということではないだろうか。
内容が優れていれば、おのずといい文章になる(庄野潤三)
そもそも、僕がこの本を購入したのは、庄野潤三の文章についての解説も掲載されているからだ。
それは「文章のふくらみ」という章の中で、庄野さんの「絵合せ」という作品の中にある「どうか、そんな気の早いことを二人で話さないで下さい—和子のいった「蚤」とは、どうやらそういう意味もあるらしい。」という一文が紹介されている。
結婚を目前に控えた長女・和子の部屋を、この後どのように使おうかと夫婦で話しているとき、突然、和子は「蚤が出る」と言った。
それは、自分は、まだこの家の娘なのだということを、暗に主張する和子の言葉なのだと、物語の語り手である父親は理解する、そんな場面だった。
この中で著者は、庄野さんの使う文章表現以上に、庄野文学の本質について細かい考察を行っていて興味深い。
ありふれた家庭の日常生活のひとこま、ひとこまを淡彩でデッサンする。その一枚ずつの絵と絵の間には、起承転結もなければ、因果関係のような論理的なつながりも一切なく、そこにあるのは流れる時間だけである。一見何でもないほんの些細なことを、ごく平易なことばでつづる作品が、どうして文学などという大それたことになるのか、長い間ふしぎだった。現実の生活から何をつかみだすか、そして、それをどう並べるか、インタビューでも、そういう話題に及ぶと、穏やかな顔にけわしい翳が走り、真剣な表情に変わる。(中村明「日本の一文 30選」)
インタビューの中で、庄野さんは、『静物』のころは「枝葉を取り去る、センテンスも短く短く、ということを考えすぎて気持ちの余裕がなかった」と内省した後で、「今はもう少し柔らかさ、しなやかさが出てきてると思う」と続けた。
著者が、そういう「ふくらみのある文章」というあたりに、庄野さんの理想とする文章の考えが集約されているということかと、重ねて問うと、庄野さんは「ふくらみというのはいい言葉だ」と認めた上で「彫琢した文章よりも内容が大事で、内容が優れていれば、おのずといい文章になる」と答えたそうである。
日本語の専門家さえも虜にしてしまう、庄野文学の奥行きの深さというものを感じた。
書名:日本の一文 30選
著者:中村明
発行:2016/9/21
出版社:岩波新書
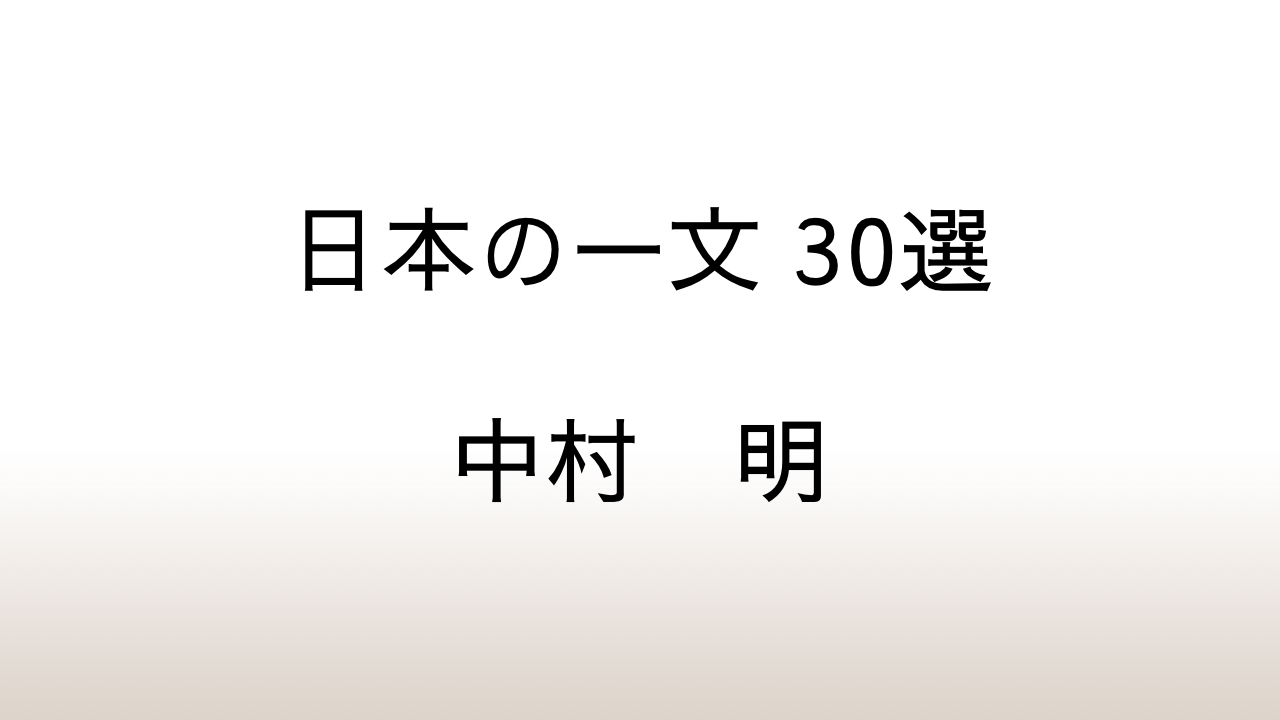
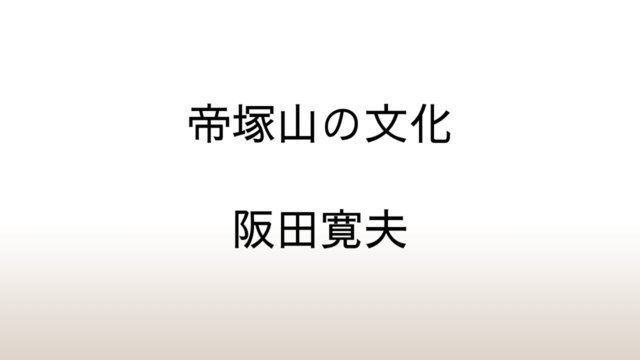




-150x150.jpg)









