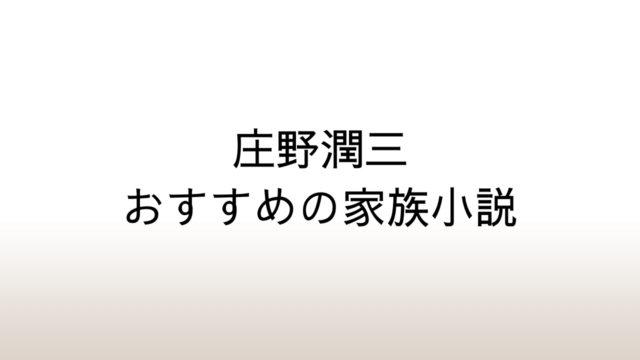太宰治「走れメロス」読了。
本作「走れメロス」は、1940年(昭和15年)5月『新潮』に発表された短編小説である。
この年、著者は31歳だった。
作品集としては、1940年(昭和15)6月に河出書房から刊行された『女の決闘』に収録されている。
信頼されることに対する恐怖心
「走れメロス」は、数ある太宰治の小説の中で、日本で最も有名な作品の一つである。
理由は、国語の教科書に全編が掲載されているからだ。
同じく太宰の代表作である『人間失格』は、タイトルは知っていても、作品を通読したことのある人というのは、決して数多くはないだろう。
そして、「走れメロス」は、読み終えた者に若干の違和感を抱かせるということでは、非常に印象に残りやすい作品でもある。
この作品の軸は二つあって、一つは、暴君ディオニスとメロスの関係、もう一つはメロスと親友セリヌンティウスの関係である。
邪悪な王様ディオニスは、「必ず戻ってくる」というメロスの約束を最初から信じていないし、メロスが約束どおりに戻ってきたことで、期待を大いに裏切られる。
一方、メロスとセリヌンティウスは固い信頼で結ばれているから、相手が約束を破るなんて夢にも考えていない。
この二つの関係が縦軸と横軸となって、物語を立体的に仕上げているのだが、太宰の作品としては、あらすじにかなりの無理があるようにも思える。
そもそも、この小説で、最も太宰治らしい場面は、メロスが約束を放り出して、何もかもあきらめてしまう部分である。
正義だの、信実だの、愛だの、考えてみれば、くだらない。人を殺して自分が生きる。それが人間世界の定法ではなかったか。ああ、何もかも、ばかばかしい。私は、醜い裏切り者だ。どうとも、勝手にするがよい。(太宰治「走れメロス」)
偽悪家の太宰にとって、これはいかにも太宰治らしい台詞である。
しかし、メロスは湧き出る清水を飲んだことで、命を吹き返す。
セリヌンティウスの弟子フィロストラトスに制止されても、メロスは走り続ける。
それだから、走るのだ。信じられているから走るのだ。間に合う、間に合わぬは問題でないのだ。人の命も問題でないのだ。私は、なんだか、もっと恐ろしく大きいものの為に走っているのだ。(太宰治「走れメロス」)
「もっと恐ろしく大きいもの」とは、セリヌンティウスとの友情であり、もっと突き詰めると、それは、「友だちから信頼されている」という事実である。
他人から「信頼されている」という事実ほど、太宰を恐れさせたものはないのだろう。
なぜなら、信頼を裏切り続けることこそが、太宰治という人間の生涯だったからである。
「走れメロス」で描かれているのは、美しい友情の物語ではなく、信頼関係で結ばれることに対する作者の恐怖心だったのだ。
王様や民衆の愚かさと、国家に対する怒り
「走れメロス」で、もっとも議論の的となるのが、暴君ディオニスが、最後にあっさりと改心してしまうところだろう。
散々庶民を殺してきたうえ、今まさにセリヌンティウスを処刑しようとしていたくせに、二人の友情に感動したからといって「わしも仲間に入れてくれ」は、さすがに、オッサン、どうにかしてるだろうって感じである。
さらに、「万歳、王様万歳」と感激する群衆も、あまりに単細胞で頭が悪すぎる。
「おまえらの望みは叶ったぞ。おまえらは、わしの心に勝ったのだ。信実とは、決して空虚な妄想ではなかった。どうか、わしをも仲間に入れてくれまいか。どうか、わしの願いを聞き入れて、おまえらの仲間の一人にしてほしい」どっと群衆の間に、歓声が起った。「万歳、王様万歳」(太宰治「走れメロス」)
読者は、ここに違和感を持つのだが、太宰が狙ったのは、まさしく、この違和感である。
この物語に描かれた愚かな王様と愚かな群衆を、太宰は、そのまま日本という国の中に見ていたのだ。
この小説が発表された昭和15年、日本は既に中国と戦争状態にあった。
翌16年には、アメリカを相手に戦争を始めようとしている時代である。
国家という存在に対し、小説家として太宰治は、きっと言いたいことが山ほどあったはずだ。
大日本帝国に対するシニカルな怒りは、惨めすぎるほどに滑稽な王様と民衆の姿として描き出される。
ただし、熱い友情の美談という見えないオブラートにくるまれた状態で。
ありがたい! 私は、正義の士として死ぬ事が出来るぞ。ああ、陽が沈む。ずんずん沈む。待ってくれ、ゼウスよ。私は生れた時から正直な男であった。正直な男のままにして死なせて下さい。(太宰治「走れメロス」)
溶けたオブラートの中から現れるのは、王様と民衆の愚かさと、そんな国家に対する怒りである。
だから、この「走れメロス」という小説は、「おかしい」と思う感覚こそ正解なのであって、これを友情の美談として素直に受け止められる人は、かなり幸せな人だと思う(それはそれで結構なことだけれど)。
大体、あの太宰治が、熱い友情の美談なんて書くはずがない。
もしも、これ(「走れメロス」)が志賀直哉の書いた作品だとしたら、太宰はきっとこう吐き捨てるだろう。
「げっ、恥ずかしい!」
「待つ身が辛いかね。待たせる身が辛いかね」
熱海の旅館に滞留している太宰を檀一雄が迎えに行ったとき、宿代を支払えなかった太宰は、壇を身代わりに置いて、東京の井伏鱒二のところへ金を借りに出かけた。
何日経っても戻ってこない太宰にしびれを切らした檀が井伏家へ乗り込むと、太宰は井伏さんと二人、悠々と将棋を指していたという。
キレた檀に向かって太宰が言った一言が「待つ身が辛いかね。待たせる身が辛いかね」。
これこそ、まさしく等身大の太宰治であって、「走れメロス」は、そんな太宰が描いた夢物語(ファンタジー)の世界である。

そもそも、太宰だって、そんなに美しい友情が実際に存在するとは考えていなかっただろうし、悪い人間がそんな簡単に改心するなんて思ってもいなかったに違いない。
「走れメロス」は、しょせんは小説の中だけで成立する架空の物語なのだ。
ただ、もしかすると、、、と思うのは、太宰は、実は自分自身こそが変わりたいと思っていたのではないだろうか?、ということである。
愛し合った女性との間で、互いに信じあうことのできる美しい純愛を、太宰は求めていた。
しかし、女性を信じきることのできない自分を、太宰は変えたいと願っていたのだ。
もしかすると、愚劣な王様の姿こそ、作者自身(太宰治)が投影されたものではなかったか。
愛する妻に裏切られた過去を持つ太宰だからこそ、そんな発想があってもおかしくはない、、、としたらおもしろいけれど、太宰だったら「変わる必要があるのは自分じゃなくて女の方だ」とか言い出しそうな気もする(笑)
まあ、そうやって読んでいくと「走れメロス」も、意外と悪くない作品だと思う。
作品名:走れメロス
書名:教科書で読む名作 走れメロス・富嶽百景ほか
著者:太宰治
発行:2017/04/06
出版社:ちくま文庫