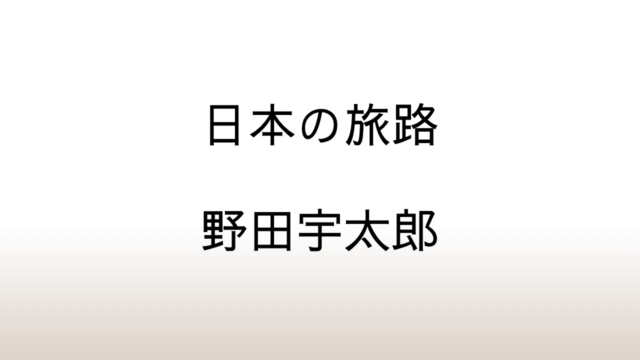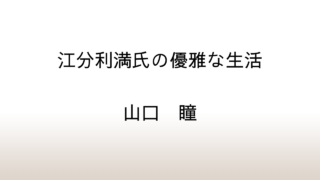若林勝「ズリ山」読了。
本作「ズリ山」は、1970年(昭和45年)に牧書店「新少年少女教養文庫」シリーズから刊行された児童向けの長編小説である。
赤平市の北炭赤間炭鉱がモデルだった
物語の舞台は、北海道の空知地方にある産炭地・赤平市である。
主人公は、炭鉱の「ズリ山」だ。
ズリ山とは、石炭と一緒に掘り出される不要なズリ石が積みあげられてできた山のことで、この物語は、ズリ山が、赤平の歴史をモノローグで綴る炭鉱児童文学となっている。
全体の構成としては、日本の大きな歴史の流れに沿って、赤平の町と炭鉱の発展と衰退を「ズリ山」の目線から描くものとなっている。
ちなみに、モデルになっているのは、1938年(昭和13年)に開鉱した北炭赤間炭鉱である。
かつて、赤平市内で教員として勤務経験のある著者は、取材を重ねて、この物語を完成させたらしい。
北海道の産炭地が、どのように生まれて発展して、そして衰退していったのかという歴史を俯瞰できるという意味では、優れた物語になっている。
ただし、炭鉱モノにはよくあることだが、庶民目線というよりは労働組合目線で庶民が語られている印象は強い。
炭鉱町の庶民の暮らしを克明に再現するというよりも、戦時中の朝鮮人労務者や中国人労働者(チャンコロ)など、炭鉱のネガティブな歴史に、著者の関心が高いことが感じられる。
真夏のある出来事だが……オレの隣の雑木山の中に、一枚の古新聞が捨てられていた。その古新聞に”ニッポンジン ケダモノ”と赤い血で書かれているのだ。そして、一人の若者が首をつり、むごたらしく死んでいるのだった。(若林勝「ズリ山」)
同様に、炭鉱事故と保安設備の問題なども取りあげられていて、内容は意外とマニアックである。
「友子同盟」のエピソードなど、炭鉱文化に触れた話もあるので、もう少し産炭地で暮らす庶民の生活について掘り下げられていると良かったのだが。
終戦後、朝鮮動乱の軍需を得て、赤平は「炭都」としてますます栄え、石炭は「黒いダイヤ」と呼ばれるようになる。
炭鉱町に近い農村から、「娘を嫁さやるなら、炭鉱にすんべ」という話が聞かれるようになってきた。「炭鉱は景気がよくなってきたからなあ」「炭鉱さ嫁に行ったら、野ら仕事をしなくてもいい、ただ遊んでいてもオヤジがたくさんお金をかせいでくれる」「そうだ、楽して金ため、ぜいたくもできるし」こんな話がかわされ、農村から炭鉱長屋へ嫁さんたちがやってきた。(若林勝「ズリ山」)
1950年代、この頃が、北海道の炭鉱の一番良かった時代なのかもしれない。
「炭都赤平」は、程なく斜陽の時代を迎えてしまうのだから。
町の未来は、町の人々自身が握っている
この物語で一番良かったシーンは、石油ストーブの台頭により、炭鉱長屋でも石炭ストーブから石油ストーブへの切り替えが進んだ話だ。
白毛がみえはじめた銀吉さんが、石油ストーブを前に、酒を飲みながら言うのだった。「石油ストーブって便利だなあ、まきはいらんし、エントツのすす掃除もいらん、しょっちゅう、石炭がなくなったかと心配もいらん……これじゃ、石油にかなわんなあ……」(若林勝「ズリ山」)
炭鉱夫が石炭ストーブではなく石油ストーブを使うという自己矛盾が、時代の移り変りを象徴している。
そして、銀吉さんの息子は東京の大学に進学し、東京の貿易会社に就職している。
町の子どもたちの親はみな、自分の子どもたちを炭鉱関連産業に就職させたいとは考えていなかった。
町の未来は、町の人々自身が握っているということを、当時の炭鉱町で暮らす人々には、うまく理解できていなかったのかもしれない。
むしろ、時代の方向性を的確に見定めていたという意味では、町の人たちは間違っていなかったのだけれど。
書名:ズリ山
著者:若林勝
発行:1970/12/20
出版社:牧書店「新少年少女教養文庫37」