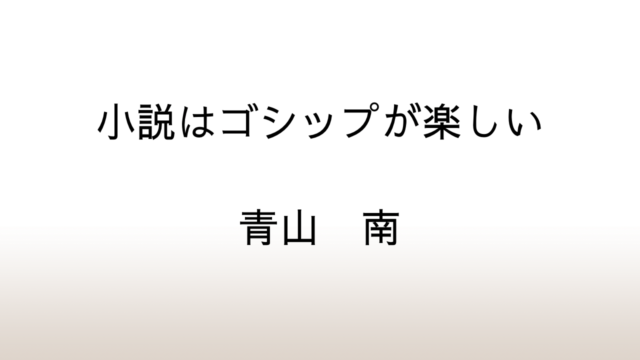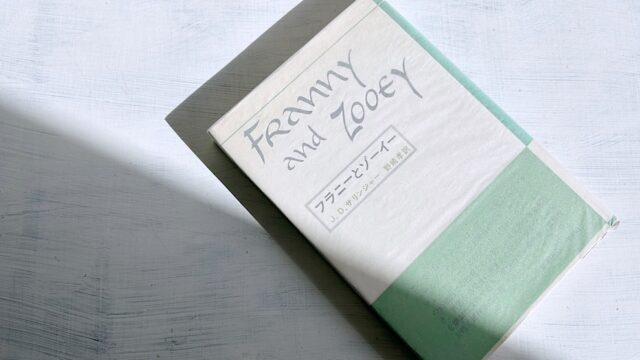干刈あがた『樹下の家族』読了。
本作『樹下の家族』は、1983年(昭和58年)10月に福武書店から刊行された短篇小説集である。
この年、著者は40歳だった。
収録作品及び初出は、次のとおり。
「樹下の家族」
1982年(昭和57年)11月『海燕』
1982年(昭和57年)第一回「海燕」新人文学賞受賞
「プラネタリウム」
1983年(昭和58年)2月号『海燕』
「真ん中迷子」
1983年(昭和58年)6月 書き下ろし
「雲とブラウス」
1983年(昭和58年)8月 書き下ろし
安保世代を蝕む「樺美智子」というトラウマ
安保闘争世代の安保闘争体験というのは、ある意味で、ひとつのトラウマ体験だったのではないだろうか?
第1回海燕新人文学賞を受賞した表題作「樹下の家族」を読むと、そんな気がしてくる。
特に、1960年(昭和35年)の安保闘争で亡くなった樺美智子に捧げる、最後の文章は鬼気迫るものがある。
美智子さん、その朝<今が大事なとき。今日は行かなければならない>と言って出かけて行ったという美智子さん。私はどこへ行けばいいのでしょうか。(干刈あがた「樹下の家族」)
本作「樹下の家族」は、家庭の中で疎外感を抱えて苦悩する主婦(37歳)の物語である。
二人の小学生の母親でもある主人公(ミチコ)は、仕事で帰ってこない夫の不在という孤独から逃れるために、見知らぬ男性(20歳)と夜の街を徘徊し、一緒に酒を飲む。
1960年(昭和35年)に生まれた青年は、1960年(昭和35年)に死んだ樺美智子の生まれ変わりとして機能している(「僕は人間に会いたいです。人間を深く知りたいです」)。
「一九六〇年、あなたが生まれた年。私は十七歳の高校生だった。六〇年安保闘争というのがあって、私は都立高校新聞連盟、略称コーシンレンの人達と、六月に入ってからデモに参加するようになったの」(干刈あがた「樹下の家族」)
機動隊との衝突が激しさを増し、高校生のデモ参加が中止となった、その夕方、東大の学生だった樺美智子が死んだ。
一人の女子大生の闘争死は、警察官を父に持つ女子高生に、強烈なトラウマを残していった。
美智子さん、あなたが考えていた革命とはどのようなものなのでしょうか。私もまたカクメイを考えています。もう一度<世の中>とか<人間>とかの言葉を臆面もなく使って、ものを考えたくなっています。(干刈あがた「樹下の家族」)
やがて、結婚をして妻となり、子供たちの母親となったとき、主人公は、樺美智子が抱いていた理想と現実生活との大きなギャップに苦しむことになる。
理想を抱いたまま死んだ樺美智子とは異なり、多くの安保世代は、理想と現実とのギャップに悩まなければならなかったのだ。
それは、樺美智子と同性である女性にこそ、大きな苦難だったのではないだろうか。
村上春樹『ノルウェイの森』で、主人公の良きガールフレンド(緑)は、大学入学後に参加したフォークソングのサークルで、性差別を体験している。
「ある日私たち夜中の政治集会に出ることになって、女の子たちはみんな一人二十個ずつの夜食用のおにぎりを作って持ってくることって言われたの。冗談じゃないわよ、そんなの完全な性差別じゃない」(村上春樹「ノルウェイの森」)
「革命」の真実に気づいた緑は、以後、闘争からドロップアウトしていくのだが、理想と現実との折り合いをつける技術こそ、彼らに求められるスキルだったのかもしれない(『ノルウェイの森』の登場人物たちは、そうした欺瞞を受容することができなかった)。
「樹下の家族」の主人公は、ワンオペ育児という現実の中で、理想に燃えた高校生時代を思い出している。
そして、闘いの中で死んだ樺美智子こそ、彼女にとっての理想であり、神格化された象徴だったのだ。
「樹下の家族」では、多くの象徴的な存在が登場する。
ジョン・F・ケネディが死んだ。円谷選手が死んだ。三島由紀夫が死んだ。エルビス・プレスリーが死んだ。克美しげるが死んだ。いや違った。克美しげるカムバックならず。ジョン・レノンが死んだ。(干刈あがた「樹下の家族」)
物語は、ジョン・レノンが殺された、1980年(昭和55年)12月の東京を舞台に繰り広げられる。
ジョン・レノンは、男性として育児に専念する「主夫生活」の象徴である。
ジョン・F・ケネディは、男性が公式の場で家庭の話などしなかった時代、1961年(昭和35年)の大統領就任演説で「私たちにも子どもが生まれる」と発言した。
二人のジョンは、政治や社会を、家庭や子どもたちの将来と結び付けて話すことのできる男性であり、その二人の死は(特にジョン・レノンの死は)、男性が家庭で暮らすことの難しさを象徴している。
走り疲れて自殺したマラソン選手(円谷幸吉)は、高度経済成長を生きた兄の姿に重なる(「幸吉は、もうすっかり疲れ切ってしまって走れません」)。
兄貴、私たちは今になって何を迷っているのだろう。マラソン武士道を守り、決してふり返ったりキョロキョロしなかった円谷選手。のようにゼニカネの長距離マラソンを走りつづけてきた兄貴。主婦道一直線で来た妹。兄貴の足をふと止めさせるものは何なのか。(干刈あがた「樹下の家族」)
「走った兄たちと伴走した妹たちは、今では夫たちと妻たち。四十歳前後の、ニッポンのオトーサンとオカーサンだ」とあるのは、つまり、安保世代である(作者は1943年、昭和18年生まれ)。
安保闘争で機動隊と闘った彼らは、60年代を忘れて、経済成長の波の中に飲み込まれていった。
ジョニー・リメンバー・ミーとうたった克美しげるは、カムバックする直前、女を殺して飛行場で逮捕された。女を殺したのは私かもしれない。リメンバー・ミーだって、六〇年代サウンドなんかもう沢山、と思っている多勢の私たちが、克美しげるをカムバックさせなかったのかもしれない。(干刈あがた「樹下の家族」)
「六〇年代サウンドなんかもう沢山」というのは、つまり、安保闘争なんてもうたくさん、という意味だ。
時代の先頭に立って走る彼らは、ウォークマンでクリスタルキングの「大都会」を聴いていたいと考えている。
1960年(昭和35年)の安保闘争から20年間、主人公は、樺美智子というトラウマを抱えながら、社会の中や家庭の中で戦い続けてきたのだ。
1960年と1980年との葛藤の中で生きる
作品タイトル「樹下の家族」は、若者の話の中に登場するインドの家族の姿に由来している。
「ある樹の下でぼんやりしている母子連れ」を見て、日本の旅行者は「家も荷物も何もなくて、ただぼんやりしているだけでも、その樹の下は家庭なんだなあ」と思う。
物質的な基準では図ることのできない家庭の幸福が、そこにはある。
1970年(昭和45年)、主人公が出産する数日前に、三島由紀夫が割腹自殺をして死んだ。
三島由紀夫が言ったのは「日本はこのままではダメになる」という言葉だった。
私たちには、戦中派とか戦後派とかの区別はよくわからない。わかるのは、真珠湾攻撃の日にセックスして子が生まれたとしたら、それは私たちの同級生ということ。そして私たちの中には真珠湾以前も<以後>もいるということ。(干刈あがた「樹下の家族」)
「妊娠四か月の子宮のしこり」を感じているとき、彼女は、赤坂山王病院の前の歩道を、七〇年安保闘争のデモ隊が行進するのを見た。
北朝鮮へ飛んだハイジャック機、沖縄闘争、赤軍派リンチ殺人事件、家のローン返済、実家の父母の離婚。
20年間の葛藤が、この作品には凝縮されている。
その葛藤は、主人公と同世代の女性たちが抱えてきた「社会的な葛藤」だった。
美智子さん、私は一人の妻としては夫を愛し、夫に寄り添っていきたい。(略)でも、夫と私との間で何かが違っている。たしかに夫は特別に仕事の好きな人間だけれど、その背後に彼をとりかこんでいる巨大な現代社会というものを感じるのです。(干刈あがた「樹下の家族」)
1960年と1980年との葛藤の中で、主人公は叫び続ける。
美智子さん! 美智子さん! と。
いいえ、私にはわかっているのです。女は、私は、全身女になって、<おねがい、あなた、私を見て。私が欲しいのは、あなたなの> と叫べばいいのです。美智子さん、私の前にもう一度、そう叫ぶ知恵と勇気のブルー・フラッグをはためかせてください。(干刈あがた「樹下の家族」)
ブルー・フラッグは、東大のスクールカラーの青旗のことで、安保闘争時、共産党の赤旗が林立する中、青い旗は、鮮明な印象を残したことだろう。
本作「樹下の家族」は、60年安保闘争を経験した女性の、80年家庭闘争を描いた物語である。
社会と闘った60年安保に対して、80年代の家庭内闘争は、自分自身との闘いだった。
経済成長とともに、男たちが家庭から遠く離れていく時代の到来を感じるが、間もなく、バブル時代になると、24時間働き続ける男たちは、家に帰ってこないことが当たり前となった(「亭主元気で留守がいい」の時代)。
そう意味では、同時収録「プラネタリム」も、家庭内における夫の不在を、主婦の目線から描いた作品である。
思春期の少年たちの母親である主人公は、育児の難しさを夫と共有することができない。
<ラムちゃん>は星から落ちてきた、髪の長い、ビキニの水着をつけているだけの美少女である。いつだったか、少年心理にうとい母親が不用意に「ラムちゃんの夢見ることある」と聞いたら、突然ナイフ眼になり、低い声で「ラムのことは二度と言うな」と言って、絵をズタズタに裂いてしまった。(干刈あがた「プラネタリム」)
子どもたちの難しさは、父親が不在であることの難しさでもある。
父親を愛しているからこそ、少年たちは、父親の不在に傷付いてしまうのだ。
SOS。キチヨリ ゼンセンニツグ。シキュウ キカンセヨ。SOS。キチヨリ ゼンセンニツグ。シキュウ キカンセヨ。──オウトウ ナシ。(干刈あがた「プラネタリム」)
主人公のメッセージは、11歳の長男が読むSF漫画や、ラムちゃんの登場する「うる星やつら」と共鳴している。
「シキュウ キカンセヨ」は、もちろん不在の夫に向けて発信された、妻からの「SOS」のメッセージなのだ。
高度経済成長がピークを越えて、日本が経済大国の仲間入りを果たそうとしていたとき、妻や子どもたちは、家庭の中で、夫や父親の不在に耐えていた。
日本の経済成長を支えたのは、そんな家庭の犠牲である。
戦争が、女たちに家庭内の孤独を強いたように、戦後の経済成長もまた、女たちに家庭内の孤独を強いていたのだろうか(しかも、高度成長期には核家族化が進んで、家庭内の孤独が一層深まっていた)。
腕を伸ばしても何にも触れず、返ってくるもののない暗黒空間に、三人は浮遊しはじめていた。星がゆっくりと回りはじめた。三人はその中心に向かって漂いながら、だんだん、だんだん小さくなり、極微小の宇宙塵となりつつあった。(干刈あがた「プラネタリム」)
本書『樹下の家族』に収録されているのは、家庭で生きる普通の主婦の叫びである。
もしかすると、こうした主婦たちの無言の絶叫こそ、1980年代という新たな時代を象徴していたのかもしれない。
作者(干刈あがた)は、1992年(平成4年)9月6日に、49歳で病死(胃がんだった)。
それは、80年代を駆け抜けるような作家人生だった。
書名:樹下の家族
著者:干刈あがた
発行:1983/10/15
出版社:福武書店