村上春樹「ねじまき鳥クロニクル」読了。
本作「ねじまき鳥クロニクル」は、1994年(平成6年)から1995年(平成7年)にかけて新潮社から刊行された長篇小説である。
なお、「第1部 泥棒かささぎ編」は、1992年(平成4年)10月から1993年(平成5年)8月にかけて『新潮』に発表されている。
連載開始の年、著者は43歳だった。
心の中に潜む「もう一人の自分」
この長い物語で描かれているもの、それは「自分の中にある心の闇」だ。
人は誰しも、自分の中に心の闇を抱えている。
あるいは、普段の自分とは違う「もう一人の自分」を抱えていると言うべきか。
「もう一人の自分」の正体を突き止めることは簡単ではなくて、「なにやら訳の分からないもの」が自分の中に潜んでいる、とでも表現した方が正確かもしれない。
「心の闇」は、そのまま「社会の闇」へとつながっていく。
ささやかな「裏切り」から「犯罪」、そして「戦争」まで。
本作『ねじまき鳥クロニクル』は、そんな人間の根源にある(そして、それは同時に社会の根源でもある)「闇」について書かれた物語だ。
ひとりの人間が、他のひとりの人間について十全に理解するというのは果たして可能なことなのだろうか。つまり、誰かのことを知ろうと長い時間をかけて、真剣に努力をかさねて、その結果我々はその相手の本質にどの程度まで近づくことができるのだろうか。(村上春樹「ねじまき鳥クロニクル(第1部 泥棒かささぎ編)」)
次から次へと現れる登場人物は、誰もが深い心の闇を抱えていて、それが、この物語を構成する大きなエピソードとなっている。
小説的構造としてみれば、本作は、いくつかの短編小説(あるいは中篇小説かもしれない)を重層的に組み合わせた、レイヤー方式の長篇小説だと言える。
それぞれのドラマの中では、もちろん誰もが主人公である。
夢と現実の区別がつかなかったり、肉体と意識が分離したりと、読んでいるこっちの頭の方が混乱してしまいそうになるが、冷静に考えると、心の中に暗い闇を抱えていない人間などいるはずがない。
「心の闇」としっかり向き合うことができるかどうか。
この物語では「それ」が試されているのである。
加納クレタは言った。「もちろん私たちは現実に交わっているわけではありません。岡田様が射精なさるとき、それは私の体内にではなく、岡田様自身の意識の中に射精なさるわけです。おわかりですか? それは作り上げられた意識なのです」(村上春樹「ねじまき鳥クロニクル(第2部 予言する鳥編)」)
僕たちに本当に必要なことは、心の闇の中に潜む「もう一人の自分」と、しっかり折り合いを付けながら生きていくことなのではないだろうか。
自分自身の中にある「壁」を抜けていくように。
心に不安を抱えて生きる人にとっての「救済の物語」
「ねじまき鳥」は、社会に生きる人間たちのネジを巻く鳥だ(誰もその姿を見た者はいない)。
彼らは人形が背中のねじを巻かれてテーブルの上に置かれたみたいに選択の余地のない行為に従事し、選択の余地のない方向に進まされた。その鳥の声の聞こえる範囲にいたほとんどの人々が激しく損なわれ、失われた。多くの人々が死んでいった。彼らはそのままテーブルの縁から下にこぼれ落ちていった。(村上春樹「ねじまき鳥クロニクル(第3部 鳥刺し男編)」)
ネジ巻き人形が動くのに意志は関係ない。
人形たちの意志に関わりなく、歴史は運命によって流され続けていく。
社会とは、たくさんのネジ巻き人形が動き回っている、小さなテーブルの上みたいなものなのだ。
ねじまき鳥を中心に、世界中で(そして様々な時代で)いろいろなドラマが生まれていく。
一見してそれらは、互いに何の関わりを持たないエピソードのように見えるけれど、実はすべてが少しずつつながっている。
そして、その物語の中心にいるのが、語り手である<僕(岡田亨)>と、妻<クミコ(岡田久美子)>、そして、久美子の実兄<綿谷昇(ワタヤ ノボル)>の3人だ。
本作のストーリー設定は、家出をして行方不明となった妻<クミコ>を探すという<僕>の物語だが、構図としては<僕>と<綿谷昇>との対決の物語と考えていい。
この二人の義兄弟の絶望的な不仲は、謎の占い師の予言やノモンハン戦争の記憶を引用して語られていくのだが、通奏低音のように物語全体に流れているのは、人間の心の中にある「深い闇」である。
井戸の底であれ、照明のないホテルの一室であれ、その闇は限りなく深い(実は、それらはみな同じものなのだが)。
僕は思うのだけれど、たしかに一人の君は僕から遠ざかろうとしている。君がそうするにはたぶんそれだけの理由があるのだろう。でもその一方でもう一人の君は必死に僕に近づこうとしている。僕はそれを確信している。そして僕は、君がここでなんと言おうと、僕に助けを求め、近づこうとしている君の方を信じないわけにはいかないんだ。(村上春樹「ねじまき鳥クロニクル(第3部 鳥刺し男編)」)
自分の中に「もう一人の自分」を抱えて生きることは異常なことではないし、特別のことでもない。
本作『ねじまき鳥クロニクル』は、心に不安を抱えて生きる人にとっての「救済の物語」であると同時に、心の闇を自覚していない人にとっての「気付きの物語」なのだ。
物語としては、前作『ダンス・ダンス・ダンス』(1988)の方がずっとシンプルで楽しかったけれど、文学作品としては『ねじまき鳥クロニクル』の方がずっと深くて考えさせられる。
そして、改めて読み返してみると、本作『ねじまき鳥クロニクル』は、その後の『海辺のカフカ』(2002)や『1Q84』(2009-2010)に比べて、ずっと親しみやすい小説であることに気づく。
それは、『ねじまき鳥クロニクル』が「一人称」で書かれた(<僕>によって語られる)最後の長篇小説だったからなのかもしれない。
もっとも、作者的に『ねじまき鳥クロニクル』の出来具合は、必ずしも満足のいくものではなかったのではないだろうか。
「第1部 泥棒かささぎ編」と「第2部 予言する鳥編」の一体感に比べて、「第3部 鳥刺し男編」は明らかに異質の物語という感じがするからだ(ストーリー的には、もちろん一つの作品なのだが)。
「第1部」と「第2部」が二階建ての建物だとしたら、「第3部」は、その隣に建てられたアネックス(分館)である──。
経営者もコンセプトも、そして名称までが同じであっても、「第3部」が後から補足された物語であるという違和感は拭い得ない。
もちろん「第3部 鳥刺し男編」によって、我々は『ねじまき鳥クロニクル』という物語の全貌を理解することができるわけで、「第3部 鳥刺し男編」があってこその『ねじまき鳥クロニクル』という物語ではあるんだけれど。
まあ、なんだかんだ言って、村上春樹という小説家にとって『ねじまき鳥クロニクル』が一つの到達点であったことは確かだ。
『ねじまき鳥』までの村上春樹と『ねじまき鳥』以降の村上春樹。
久しぶりに読み返して『ねじまき鳥クロニクル』は、やはり素晴らしい作品だと思った。
書名:ねじまき鳥クロニクル
著者:村上春樹
発行:2010/04/10 改版
出版社:新潮文庫
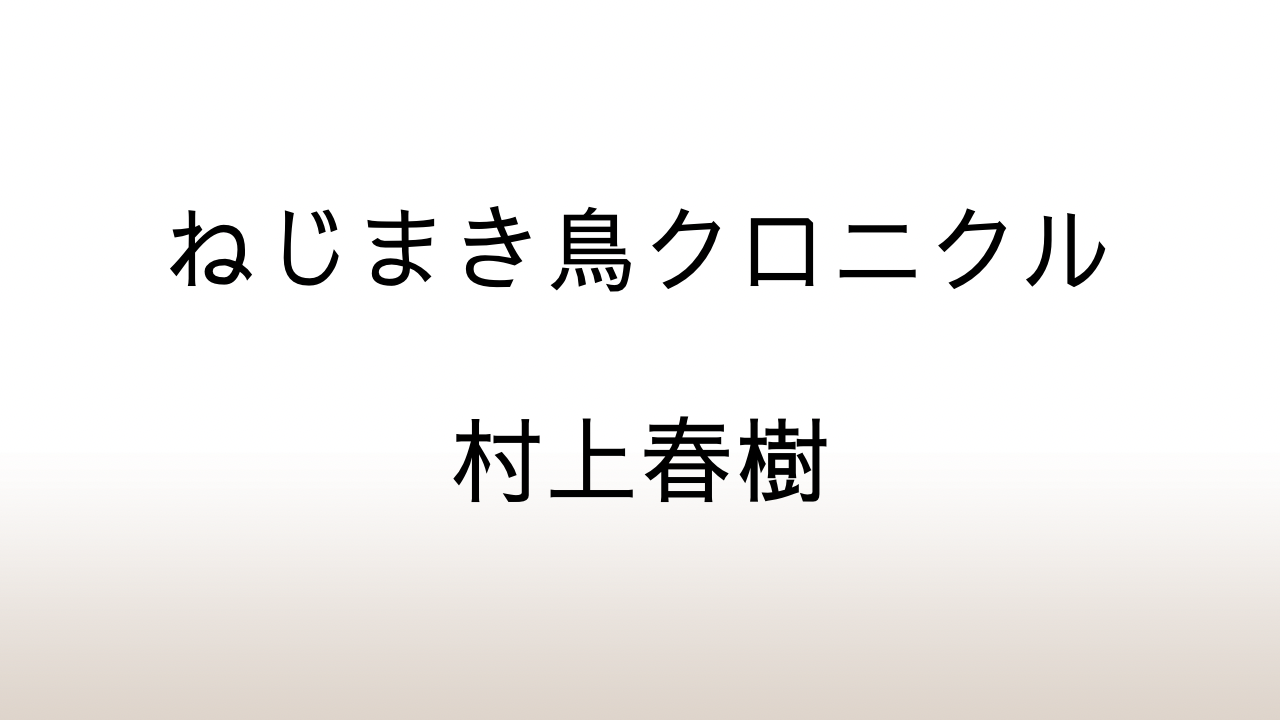
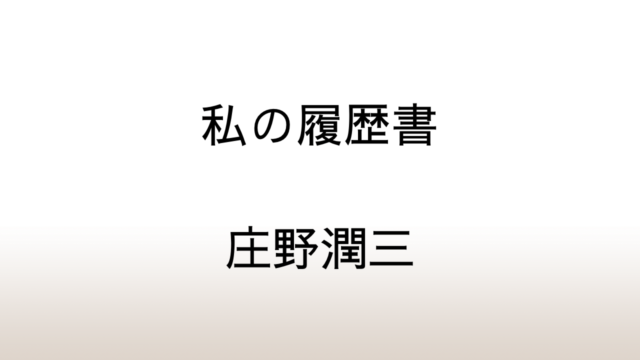


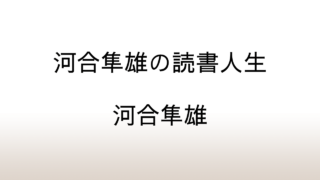

-150x150.jpg)









