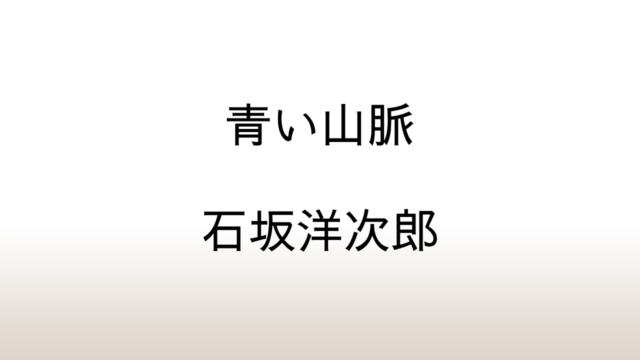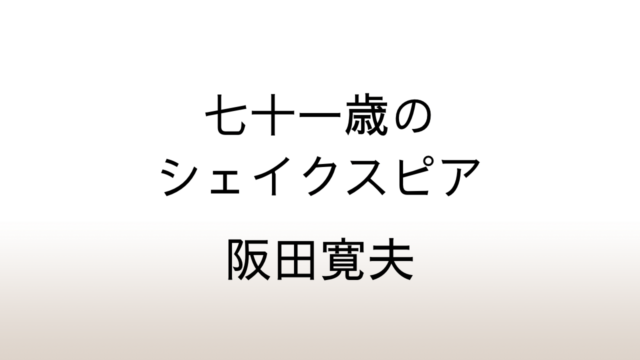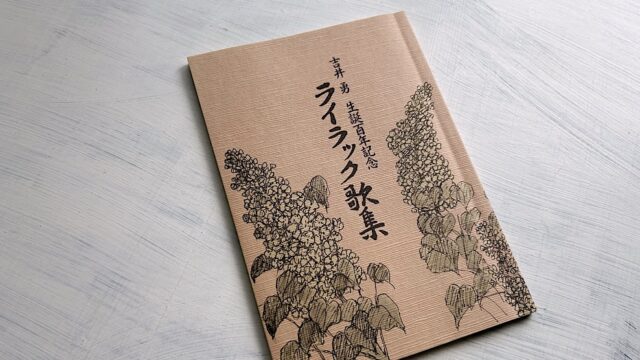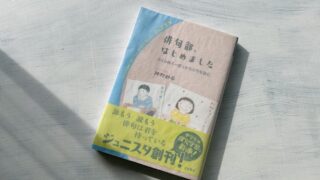シャルル=ルイ・フィリップ『小さな町で』読了。
本作『小さな町で』は、1910年(明治43年)に刊行された短篇小説集である。
著者(フィリップ)は、1909年(明治42年)に35歳で他界していた。
初出は、1908年(明治41年)9月~1909年(明治42年)9月『ル・マタン』紙。
なお、みすず書房(おとなの本棚)『小さな町で』には、1916年(大正5年)に刊行された続編『朝のコント』からも一部が収録された。
庄野潤三が愛読した作家・フィリップ
フランスの小説家(シャルル=ルイ・フィリップ)は、庄野潤三が愛読した作家として知られている。
フランスの作家シャルル=ルイ・フィリップは私の好きな作家の一人です。もし皆さんの中でまだフィリップの作品を読んだことがない人がいたら今すぐに本屋へ行って、文庫本の中からフィリップの名前を探し出し、何でもいいから見つけたものを買って来て読んでみて下さい。(庄野潤三「フィリップの手紙」/『野菜讃歌』所収)
フィリップは、パリ市役所の照明課に勤務する、しがない地方公務員だった。
役所に勤めながら、仕事が終わって帰宅した後に原稿を書いていたという。
しかし、私は会社勤めをしながら、文学をやろうとしている友人に云うことは一つしかない。(略)そうして、辛い時はパリの市役所に勤務しながら、夜、下宿でこつこつと小説を書いていたフィリップのことを思い、決して会社を止めてしまおうなどという無謀な考えを起してはならないと話す。(庄野潤三「文学を志す人々へ」/『自分の羽根』所収)
腸チフスにかかって死んだとき、フィリップは、まだ35歳だった。
本作『小さな町で』には、フィリップが亡くなる直前まで連載していた短い物語が収録されている。
もっとも、ここでいう「物語」とは、ワクワク・ドキドキするような「物語」ではない。
フィリップの物語は、小さな町に暮らす人々の生活を点描として綴った、いわゆるスケッチだった。
例えば「箱車」は、新しい箱車に乗って出かけた子どもたちが、思わず遠くまで行ってしまったため、日が暮れる中、必死に家へと帰り着く物語である。
キャトル=ムーランの四つ辻に来るか来ないうちに、日がとっぷり暮れた。まだまだ道は遠い。行きに歩いた分をそっくり引き返さねばならないのだ。泣いているのは、車のなかのちびたちだけではなかった。(シャルル=ルイ・フィリップ「箱車」山田稔・訳)
教科書にも掲載されている芥川龍之介の名作「トロッコ」は、フィリップの「箱車」にインスパイアされて生まれたものだと言われている。
大正から昭和初期にかけて、日本の作家は、フィリップの影響を大いに受けた。
人気作家・太宰治も例外ではない。
百姓、職工の芸術。私はそれを見たことがない。シャルル・ルイ・フィリップ。彼が私を震駭(しんがい)させただけである。(太宰治「碧眼托鉢」)
市井の人々の何気ない生活の中から人生を拾い上げる。
それが、フィリップの「物語」だった。
生まれたばかりの妹に嫉妬して死んだ少女(アリス)の物語がある。
「あたし、いちばん小さくなりたい! あたし、いちばん小さくなりたい!」その日の晩、彼女はきっぱりとこう言った。「赤ちゃんが死なないのなら、あたしが死ぬ」(シャルル=ルイ・フィリップ「アリス」山田稔・訳)
アリスは、自分の言葉を守る少女だった。
アリスは七つで、嫉妬のため死んだ。彼女は自分の小さな腰掛けに坐っていた。突然、横に転げ落ちた。見つけた者があわてて抱き起した。すでに死んでいた。(シャルル=ルイ・フィリップ「アリス」山田稔・訳)
フィリップの時代、まるで嘘みたいな「物語」が、市民の間で広まっていたのだろうか。
あるいは、美しい女たちに釣られるようにして、教会へ迷いこんでいった三人の労働者たちの物語。
すると、リペティ、リパトン、困り者のペティパトンが、他のふたりが引き止めるより早く立ち上り、上体をよろめかせながらまず笑ってから、こう叫んだのだ。「いちばん罪深い者、そりゃあ、わしですよ!」(シャルル=ルイ・フィリップ「いちばん罪深い者」山田稔・訳)
笑いの中から、庶民に対する共感の気持ちが滲み出ている。
ドメスティック・バイオレンスで、嫁を殺してしまった男(ルウロー)がいる。
要するに彼はかなり気分が落ち着いて、ひと息ついていたのだった。ところが九時が鳴ったころ、通りの上手に悪魔のしわくちゃ顔が、やけにはっきりと現われるのが見えたのだ。(シャルル=ルイ・フィリップ「犯罪の後で」山田稔・訳)
女房を殺した男の苦悩が、そこにはある。
「ルウローが女房を殺した!」たしかに、彼は世間で言うところの罪の重荷を自分ひとりで担えると思っていた。だが、ほかの連中はわかっちゃいないんだ、いやでたまらぬ女房を殺すってことがどんなことか。(シャルル=ルイ・フィリップ「犯罪の後で」山田稔・訳)
年を取りすぎて、働けなくなった男たちはどうすればいいのか。
それでもやはり、彼らはちゃんと心得ていたのだ。働けなくなったら、あとはどうすべきか。ロメはある朝、四時に身投げした。(シャルル=ルイ・フィリップ「自殺未遂」山田稔・訳)
働くことのできなくなった男たちに居場所はない。
こうした連中の真似をしないですむ方法は、探せばあるだろう。たとえば養老院の世話になるとか。だがそれは別の生き方というものだ。六十四にもなって、もう自分流の生き方が出来上ってしまっているのに、いまさら習慣を変えるのは容易ではない。(シャルル=ルイ・フィリップ「自殺未遂」山田稔・訳)
その瞬間は、いつか、誰にでも訪れるかもしれないものだ。
そこに、人生のはかなさがある。
死は、常に身近なものだった。
ああ、こんなものだったのか、死って。わかっていたら、もっと早くルプートル婆さんを呼びに行くんだったのに。近所の人たちに知らせた。テュルパン爺さんはいくら金がかかってもかまわぬと思った。(シャルル=ルイ・フィリップ「素朴な人々の死」山田稔・訳)
まさか、老妻が突然に亡くなるとは、テュルパン爺さんも考えていなかった。
ふだんは婆さんの顔にも、世の中の女房族同様、生活の色がにじみ出ていた。彼女はいつも家事や家の手入れのことを考えていた。何とかやりくりして恥ずかしくない暮らしをおくりたい、そのために多くの困難を乗り越えねばならぬ。そうした苦労の跡があらわれていた。(シャルル=ルイ・フィリップ「素朴な人々の死」山田稔・訳)
貧しい生活の中にも、人々は自分たちなりの幸福を見出そうと努力していたのだ。
そうでもしなければ、彼らは生き続けていくことができなかったから。
人はいつか死ぬ。そのことをテュルパン爺さんはもちろん知っていた。しかし自分の妻の死ぬ日がその「いつか」になろうとは思ってもいなかった。(シャルル=ルイ・フィリップ「老人の死」山田稔・訳)
妻が死んだことで、テュルパン爺さんの幸福な暮らしも終わりを告げた。
ふと、その手が止まった。まったく不思議だった。食べる気がしないのだ。腹はへっているのか、いないのか。へっているようだ。ただ何か足りなくて、食べる気になれないのである。(シャルル=ルイ・フィリップ「老人の死」山田稔・訳)
人生とは、まったく不思議なものだ。
婆さんに先立たれたテュルパン爺さんは、自然な気持ちで婆さんの後を追った。
「だめなんだよ。何かわしの頭を下へ下へと引っ張るものがあってね」三日目に彼は死んだ。膝に両肱を突いた姿勢を頑として変えようとせずに。足の間にはテュルパン婆さんが横たわっていた。(シャルル=ルイ・フィリップ「老人の死」山田稔・訳)
その不思議な人生を、フィリップは庶民の暮らしの中に見つけた。
本作『小さな町で』は、20世紀初頭のフランスの小さな町に生きる人々の生活を綴った物語集である。
まるで嘘のような話の中に、我々は不思議な人生というものを感じないではいられないだろう。
貧しい人々の暮らしの中から剝き出しにされた人生
古本屋で買ってきた本の中には、新聞の切り抜きが挟まっていた。
川上弘美が書いた書評である。
乾いた笑いを誘うそっけない文章に、まず引き込まれる。残酷さとすれすれの諧謔がスリリングである。とんとんと進んで、しかし最後私は足を掬われたように、泣かされてしまった。(川上弘美「小さな町で」/『朝日新聞』発行日不詳)
古本には、こういう嬉しいオマケが多い。
これは何なのだろうと思う。シンプルなのだ。けれど鋭い。(略)フィリップという凝縮された人生を駆け抜けるように送った作者でなければ、表現しえなかったものである。(川上弘美「小さな町で」/『朝日新聞』発行日不詳)
わずか35歳で亡くなったフィリップは、老人を描くのがうまい。
「ねえ、先生、このわしに、幸せになれなんておっしゃったのが間違いですよ。わしみたいな一生働きづめの者は、どうしたらいいかわかりませんもの。わしは年をとりすぎましたよ、先生、年をとりすぎました」(シャルル=ルイ・フィリップ「ある生涯」山田稔・訳)
その街では、誰もが人生と向き合いながら生きていた。
体が痛むので、ボネ爺さんは道具を使うのがつらかった。しかし、なんとか自分の仕事は片づけることができた。彼は道が完成する前に死んだ。働けなくなる前に死ねて幸せだった。(シャルル=ルイ・フィリップ「ある生涯」山田稔・訳)
人生を浮き彫りにするという意味で、庶民の暮らしは最適だったのかもしれない。
ふたりは乞食の身ではあったが、その境遇を受け入れていた。これでもまだ生きる手だてがあるのだから、他の人間よりも不幸というわけではないのだ。(シャルル=ルイ・フィリップ「ふたりの乞食」山田稔・訳)
貧しい人々の暮らしには、剝き出しの人生がある。
一九〇〇年、パリで万国博覧会の開かれた年の秋に、サンテュレルの爺さんは死んだ。(略)顔に息を吹きかけた。まだ死んだとは思いたくなかった。死んでからもう五分はたっているのに、まだ息を吹きかけていた。(シャルル=ルイ・フィリップ「ふたりの乞食」山田稔・訳)
彼らは、必死で人生と向き合っていた。
「殺したな」後から入って来たバティストが言った。(略)「やつらはどいつもこいつも同じだ。怖くて死ぬのさ」(シャルル=ルイ・フィリップ「ふたりの泥棒」山田稔・訳)
懐かしい恋人に再会した大人たちの人生。
「ポール、引き止めはしないわ。奥さんが心配しているかもしれないし」「ああ、そうだな。かわいそうに女房のやつ、今晩おれが何を考えているか知ったら、もっと心配するだろうな」(シャルル=ルイ・フィリップ「再会」山田稔・訳)
彼らは、それぞれに選んだ人生を歩き続けていくしかない。
もちろん、彼らだけが、特別の人生を生きているわけではなかった。
後戻りできないものが、つまり、人生だったというだけのことだ。
フィリップの物語は、あたりまえの人生を、我々の前にさらけ出してみせているにすぎない。
「でもね、たった一日で結婚なんかできないよ。じゃあんたは、このまますぐにわたしを連れて行くつもりなの?」「そうだよ」とギャゼは言った。「式を挙げるまで、わたしのところに住むのさ」(シャルル=ルイ・フィリップ「求婚」山田稔・訳)
出合いがあり、別れがある。
それは、いつの時代も、どこの町でも、変わることのない永遠の物語だ。
100年以上も昔に書かれたフランスの物語に、我々が共感できる理由が、そこにある。
庄野潤三は、誰よりも普通の人生を愛する作家だった。
普通の人生を描いたフィリップの作品に、庄野さんが共感したことは、必然と言えば必然だだったかもしれない。
それは、庄野さんが師と慕う井伏鱒二の場合も同じだった。
庄野潤三『ガンビア滞在記』(1959)を読んだ井伏さんは、フィリップの『小さな町で』を思い出したという。
これを読みながらつい私はフィリップの「小さい町」を思い出した。しかし庄野君の見せてくれたガンビアは珍しく楽しい町であった。(井伏鱒二「著者へ<庄野潤三『ガンビア滞在記』>」)
井伏鱒二や庄野潤三が愛した作品。
そう添えるだけで、本書『小さな町で』が持つ魅力を伝えることができるのではないだろうか。
本作『小さな町で』は、庶民の暮らしを通して描かれた人生の物語である。
もしかすると、現代日本では見つけることの難しい人生の素顔が、そこにあるかもしれない。
書名:小さな町で
著者:シャルル=ルイ・フィリップ
訳者:山田稔
発行:2003/12/10
出版社:みすず書房(大人の本棚)