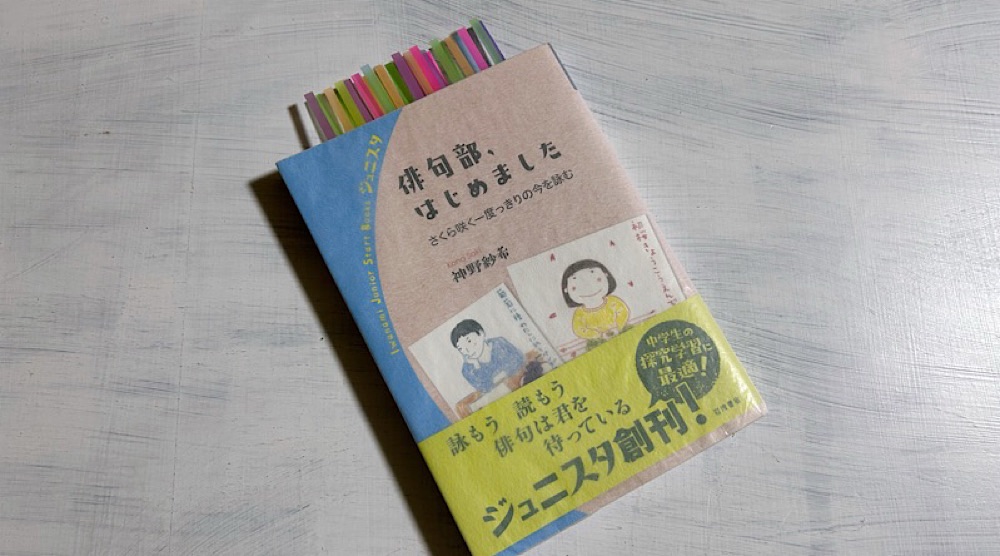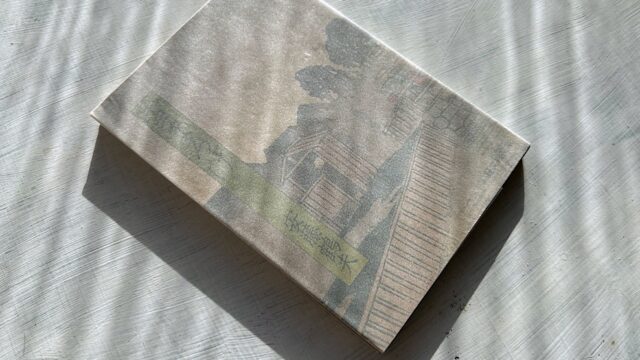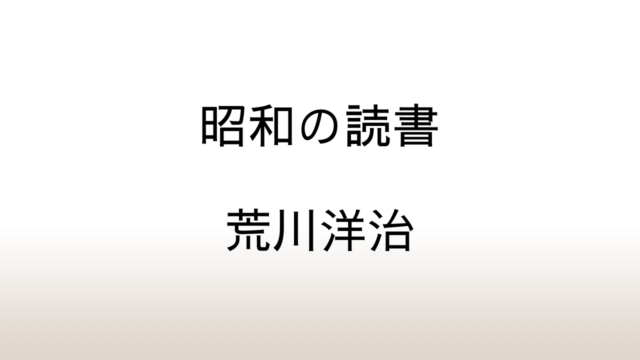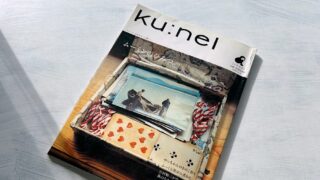神野紗希『俳句部、はじめました』読了。
本作『俳句部、はじめました』は、2021年(令和3年)3月に岩波書店から刊行された俳句入門書である。
この年、著者は38歳だった。
俳人・神野紗希の高校生デビュー
NHK-Eテレ『きみと磨く、17音〜俳句甲子園2025〜』を観た。
印象に残る作品があった。
天牛の歩き尽くして飛びにけり 帯谷到子
俳句は、いかに記憶に残るかということが重要な文学である。
2001年(平成13年)の俳句甲子園にも、そんな作品があった。
カンバスの余白八月十五日 神野紗希
本書『俳句部、はじめました』の著者であり、後の俳人・神野紗希の作品である。
このとき、著者は高校3年生。
「白」と「青」が兼題だった。
「白」には、未知という連想がはたらくのだなあ。「白紙」のイメージをふくらませ、絵を描くカンバスを思いつきました。うーん、まっさらの白紙もいいけれど、描かれている途中もまた、想像をかきたててくれそう! 句帳に「カンバスの余白」と書きつけたとき、ふと、続いて言葉が出てきました。(神野紗希「俳句部、はじめました」)
ヒントを与えてくれたのは、正岡子規の「夏嵐机上の白紙飛び尽くす」である。
この年、俳句甲子園は、終戦記念日直後の8月19日に行われた。
私にとっての余白。そう考えたとき、祖父の戦争の話を、ふと思い出しました。カンバスの余白のように、私にとっての「八月十五日」にも、ついぞ埋められない余白があるのではないか、と。(神野紗希「俳句部、はじめました」)
最初から俳句に興味があったわけではなかった。
なにしろ、高校1年生のときは、放送部の大会に参加するために、俳句甲子園の取材をしていたのだ。
その日、神野紗希は運命的な出会いを果たす。
いわしぐも進路相談室の窓 作者不詳
発表された作品への、強い共感だった。
その句を見た瞬間、「この句の中に私がいる」と思いました。(略)私も、この気持ち、知ってる。(神野紗希「俳句部、はじめました」)
俳句に魅了された著者は、学校を舞台に俳句を作り続けていく。
起立礼着席青葉風過ぎた 神野紗希
俳句との出会いは様々だ。
教科書に掲載されている作品を読んだだけでは知ることのできない感動が、俳句にはある。
本書『俳句部、はじめました』では、俳句の魅力を、俳句甲子園出身の著者が、中学生にも分かりやすい言葉で説明してくれる。
俳句は、なぜ楽しいのか?
俳句の練習は、とにかくたくさんの作品(できれば秀句)に触れることである(これを「鑑賞」という)。
小説と違って十七文字で構成される短詩の俳句は、短時間で数多くの作品に触れることが可能だ。
良い作品を鑑賞することは、実際に自分で俳句を作る際の力になる。
俳句鑑賞は、作句のための基礎練習なのだ。
野球の投手が、ピッチングフォームの研究をする前に、ジョギングや筋トレをして、肉体を作るのと同じような基礎練習が、俳句にもある。
本書では、著者の感性によってチョイスされた俳句が(秀句が)、たくさん収録されている。
ランボー全集全一巻や青嵐 榮猿丸
榮猿丸は、今年59歳のベテラン俳人である。
全集は書いたものをすべて収録するので、ふつうは何巻かにわたりますが、ランボーの詩業は約五年間、ほんのわずかでしたから「全一巻」におさまります。青嵐は、夏の青葉を吹き渡る強い風。この句も一冊の本がそこにあると詠んだだけです。それでも「全一巻」「青嵐」という現実のものごとが、全速力で駆け抜けた詩人の青春を象徴しています。(神野紗希「俳句部、はじめました」)
少ない言葉で構成される俳句は、解釈の難しい文学でもある。
先生も浴衣になっている夜だ 丸田洋渡(第十九回俳句甲子園)
逆に言うと、俳句は解釈の幅が広い、自由な文学ということになる。
「浴衣」は夏の季語です。お客に屋台の出る、夏祭りでしょうか。近くの花火大会? 修学旅行先で宿泊する温泉旅館の夜を思っても楽しいかもしれません。(略)一つ一つの言葉をひもといてゆけば、たった十七音でも、こんなに豊かな物語が引き出せるんですね。(神野紗希「俳句部、はじめました」)
「たった十七音」だからこそ表現できる世界がある。
それは、俳句という文学の大きな魅力だ。
俳句は、沈黙の詩型といわれます。十七音に語れなかった余白の部分に、ゆたかな思いや気分が抱きこまれているのです。(神野紗希「俳句部、はじめました」)
伝えたい感情を、すべて言葉にしてしまうのではない。
読者の想像を膨らませるところに、俳句の可能性がある。
夜のシャワー俺が捕ったら勝つてゐた 黒岩徳将
説明のない情景の中で、俳句を鑑賞することの楽しさが、この作品にはある。
青春を賭ける部活動も、かけがえのない友人を作る場です。この句は野球部でしょう。(略)「俺」というやや荒っぽい一人称が、本音らしさを強めます。(神野紗希「俳句部、はじめました」)
読者の共感に働きかける作品もいい。
雨がふる恋をうちあけようと思ふ 片山桃史
情景というよりは、恋をしている著者への共感が、この作品の大きなテーマとなっている。
この句には季語がありません。(略)恋もまた、季節に関係なく訪れるものです。雨がやんだら、君のところへ。無事に告白できたでしょうか、それとも。(神野紗希「俳句部、はじめました」)
雨が勇気を与えてくれるものだとしたら、雨が降りやんだとき、やはり、作者は告白することができなかったかもしれない。
作者の勇気は、雨が降っているときにかぎり有効なのだ。
不安定な青春期の心理が、「雨がふる」に投影されている。
それにしても「恋もまた、季節に関係なく訪れるものです」という解釈はいい。
こうした解釈ができるかどうかというところに、俳句のセンスは現れるのかもしれない。
それは、良い俳句(秀句)を見つけてくる才能にもつながっているものだろう。
本書『俳句部、はじめました』には、著者のセンスによって選ばれた素晴らしい俳句作品が、たくさん紹介されている。
俳句甲子園はゴールじゃない
現代風の作品が多いかと思うと、歴史的な評価を受けた名作も収録されている。
おおかみに蛍が一つ付いていた 金子兜太
金子兜太は、大正生まれの巨匠である。
古代の森の闇を背負い、おおかみが一頭、堂々と立っています。その体には蛍が一つくっついて、呼吸するように明滅していました。(略)このおおかみは、幻の気配をまといながら、俳句の中では蛍とともに、永遠に生き続けるでしょう。(神野紗希「俳句部、はじめました」)
自由な精神を尊ぶ金子兜太は、若い世代の俳句に積極的に関わるなど、後進の育成に熱心な俳人だった(俳句甲子園の審査委員長を務めたこともある)。
戦争が廊下の奥に立つてゐた 渡辺白泉
戦争俳句の名句もある。
廊下の奥の暗がりに誰かが立っていたら、ぞっとしますよね。作者はその恐怖を、戦争のしのびよる恐怖に重ねました。戦争は、気がつけば家の中にまで入りこみ、私たちを逃すまいと暗がりから見つめています。(神野紗希「俳句部、はじめました」)
「廊下の奥」には会議室があった。
ある日、その会議室の前に「立入禁止」の札が掲示された。
軍事作戦の会議場所となったのだ。
そのとき、作者の感じたものが「戦争が廊下の奥に立つてゐた」という十七文字の言葉になって残されている。
どれにも日本が正しくて夕刊がばたばたたたまれてゆく 栗林一石路
強い厭戦の思いは「自由律俳句」と相性が良かった。
かつて日本も、戦争へと突き進んでしまった時代がありました。その当時、昭和十年に詠まれた自由律俳句です。どこの新聞社の夕刊にも、日本は正しい、素晴らしいと賛美する記事しか載っていません。でも、本当に?(神野紗希「俳句部、はじめました」)
俳句は、歴史の証人でもあった。
短い言葉の中に、人々は歴史を刻みこもうとしていたのだ。
そして、新しい歴史は、今も俳句によって刻み続けられている。
我々の生きる日常生活という場を舞台として。
夕焼けやいつか母校となる校舎 大池莉奈(第十六回俳句甲子園)
巨匠の名作と並べて、俳句甲子園の作品を味わう。
これも、俳句だからこそできる鑑賞方法だっただろうか。
草の実や女子とふつうに話せない 越智友亮
「草の実」は、秋に雑草がつける実の総称。
草の実みたいに地味な僕だけど、あの子に話しかけてもいいのかな?(略)女子の反応が気になり、男友だちと話すみたいに「ふつうに」できません。でも、それがきっと、思春期の「ふつう」なのです。(神野紗希「俳句部、はじめました」)
俳句は、共感性の強い文学である。
共感を得られない俳句に、名作はない。
制服の下に水着をもう着てゐる 山下つばさ
待ち切れない青春の夏が、リアルな情景によって表現されている。
ごわごわした着心地、そわそわした気分。私も体験したことある!(神野紗希「俳句部、はじめました」)
中高生にとって、学校は日常生活の表舞台だ。
大人になってからでは遅い日常を詠む特権が、中高生にはある。
理科室の劇薬に夏来たりけり 佐藤郁良
「理科室の劇薬」と「夏」という組み合わせ。
鍵がかかっているとはいえ、手を伸ばせば届く距離に劇薬のあるはらはらした気持ちが、夏の近づいてくるどきどきと重なって、何かが起こりそうな予感が高まります。(神野紗希「俳句部、はじめました」)
良い俳句には、良いと感じることの理由が、必ずあるはずだ。
「良いと感じる理由」を探ることは、俳句鑑賞の目的のひとつである。
黒葡萄父にははいとしか言えず 千田洋平(神奈川大学全国高校生俳句大賞)
誰もが抱いただろう、思春期のもどかしさ。
少年の日への共感が「父にははいとしか言えず」という言葉にはある。
沈思をうながす黒葡萄には父との複雑な関係が、象徴されています。季語が心の陰影をくっきりさせ、一言では語れない家族への思いを差し出しました。(神野紗希「俳句部、はじめました」)
季語は、ただ季語として機能しているのではない。
言葉同士の化学反応が、俳句の意味を無限にも膨らませていくのだ。
泣き止めばいつもの葡萄ではないか 古勝敦子(第二十二回俳句甲子園)
葡萄に投影されているのは、作者自身である。
悲しくて泣きじゃくったあと、はっと我に返れば、何の変哲もない葡萄が一房、卓上に置かれていました。なんだ、いつもの葡萄じゃないか。いつもの生活、いつもの私。ときにはワッと泣いて寂しさを逃がしながら、日々は続くのでしょう。(神野紗希「俳句部、はじめました」)
俳句の楽しさは、鑑賞の楽しさであると言っていい。
本書『俳句部、はじめました』では、著者の作品解説により、俳句鑑賞の技術を学ぶことができる。
凍星やスクールカーストの女王 羽藤れいな
スクールカーストの女王は、凍りつくほど冷たい星だ。
その孤独な気持ちを誰が理解してくれるだろうか。
スクールカーストが恐ろしいのは、その序列が入れ替わることです。かつて女王だったあの子が、ある日突然、みんなから無視されてしまうなんてことも。傷つけ合ってしまう子どもの世界の残酷さを、凍星がさえざえと象徴しています。(神野紗希「俳句部、はじめました」)
その気持ちを表現するのに、たくさんの言葉はいらない。
十七文字の言葉があれば、きっと多くのことが伝えられるはずだから。
この恋は線香花火より永く 矢野玲奈
恋愛俳句は、まるでJ-POPの歌詞世界のようにも聞こえる。
あと少し、せめてこの線香花火の玉が落ちるよりは長く、この恋が続いてほしいと祈っています。終わりが来るかもしれないと予感しながら、今この時をつなぎとめようとする、切ない恋心を正直に打ち明けました。(神野紗希「俳句部、はじめました」)
俳句は作為的であってはいけないと、金子兜太は言った。
感じたことを素直に表現したとき、俳句は俳句としての力を持つのだ。
黒板に Do your best ぼたん雪 神野紗希
俳句に大切なものはリズム感である。
読んでいて気持ちのいいリズムがあるかどうか。
俳句に英語を使っていいのかって? もちろんOKです。俳句に使ってはいけない言葉はありません。(略)俳句はもともと、とても自由な詩なのです。(神野紗希「俳句部、はじめました」)
俳句を始めるにあたっての心構えを、本書『俳句部、はじめました』では学ぶことができる。
技術的なテクニックよりも先に、俳句とは何かという本質を理解すること。
本書の著者が重視しているのは、まさしく、そんな基本精神だったに違いない。
ラムネから噴き出している 時間、とか 佐藤 廉
俳句は、とても自由な文学である。
言葉を自由に組み合わせることで、無限大の自分を表現することができる。
作者は、ラムネから噴き出す炭酸のしぶきを、ほとばしる青春の時間そのものだとみなしました。わっと噴き出したら二度とは戻らないきらめきは、時間もまた過ぎ去り続けてゆくのだと、この世の真理を悟らせます。(神野紗希「俳句部、はじめました」)
もしかすると、俳句は、青春を表現するために最高のツールかもしれない。
年老いてからでは遅すぎるものが、青春にはあるのだ。
難しいことは、何もない。
たくさんの言葉に触れて、自分の感じたことを十七文字で置き換えてみる。
静寂は爆音である花吹雪 又吉直樹
感性とは、誰のものでもない、自分オリジナルのものだ。
「天牛の歩き尽くして飛びにけり」と詠んだ彼女は、これからも俳句を作り続けていくだろう。
その先には、きっと「歩き尽くして飛びにけり」という瞬間があるはずだ。
もしかすると「天牛」は、未来の彼女自身の姿だったのかもしれない。
書名:俳句部、はじめました さくら咲く一度っきりの今を詠む
著者:神野紗希
発行:2021/03/26
出版社:岩波書店(岩波ジュニアスタートブックス)