庄野潤三「引潮」読了。
本作「引潮」は、1977年(昭和52年)2月『新潮』に発表された長編小説である。
この年、著者は56歳だった。
単行本は、1977年(昭和52年)5月、新潮社から刊行されている。
神話のような異界の物語
作品集『絵合せ』(1971)の中に、「蓮の花」(1971)という短篇小説がある。
家族揃って広島の親戚の家まで遊びに行き、親戚と一緒に離島の釣り宿まで出かける、という話だ。
このとき、釣り船の船頭さんとして登場する「じいさん」がいる。
戦争でフィリピンへ行って、大変な苦労をしたという。
この「じいさん」が主人公になって生まれた小説が、本作「引潮」である。
棚井津の<倉本平吉>というお爺さんが、この作品の主人公である。
「引潮」は、庄野さんが得意とした聞き書き小説の体裁となっていて、作中の多くを庄野さんと倉本平吉さんとの会話が占めている。
庄野潤三の聞き書き小説には、ほかに『紺野機業場』や『屋根』『流れ藻』などがある、いずれも名もない庶民の人生を掘り下げている。
庄野さんは聞き役だから、ほとんど全部、倉本平吉さんの言葉で埋められている、と言っていい。
戦争中に台湾の少女と仲良くなったことや、フィリピンの戦地で事故に遭って大きな怪我をしたこと、ずっと若かった頃に船で遭難したこと、鯔の背びれで怪我をしたこと、まむしに噛まれたこと、結婚式で歌った歌のことなど、倉本平吉さんの言葉で語られる話は、まるで異界の物語を聞くように新鮮だ。
全部読み終ったとき、僕は、まるで一冊の神話を読み終えたような錯覚に陥った。
倉本平吉さんの話は、そのくらい我々の日常からかけ離れていて、寓話性に満ちている。
「いろんなことがあったですいなあ。過去を考えてみると。将来いうのはもう分からんけど。過去は長かったです。長いようで早かったようにも思う。夢の間に日にちがたったような気がします。それがなにかいうと、楽で通った時は早い。えらかった時は長い。じゃけえ、戦地におったあの一年か二年は長かった。ところが、帰ってからというものは、いつの間にやらつい年を拾うた。十年二十年夢の間いうくらい、早かったな」(庄野潤三「引潮」)
「いつの間にやらつい年を拾うた」という言葉に、倉本平吉さんのリアリティがある。
倉本平吉さんは、何事もなかったかのように昔を語るが、その内容は壮絶で悲惨だ。
何かの折にふと武上のおかみさんがいった。「倉本さんもお気の毒な方です。とてもよく出来るお子さんでしたのに。神経衰弱のようになられて」私は闊達で、茶目気もたっぷりあるこの人の、胸のうちにある悲しみを想像するしかなかった。(庄野潤三「引潮」)
大変なことを、倉本平吉さんは淡々と語り、庄野さんの聞き書きが、それをまた淡々と伝える。
倉本平吉さんの独特の方言が、戦争の生々しさを取り払い、遠い異国の物語のように聞かせるのかもしれない。
凡夫の浅ましさのお陰で生きてゆけるのかも知れませんよ
聞き役に徹している庄野さんの言葉の中で一か所だけ、引っかかるところがあった。
自分はいつまで生きるのだろうか、もっともっと長生きしたいと、倉本平吉さんは言う
「あれのことじゃ、凡夫の浅ましさというのはな」「それでいいのじゃありませんか。凡夫の浅ましさのお陰で生きてゆけるのかも知れませんよ、たいがいの人は」(庄野潤三「引潮」)
作品中で、ほとんど自己主張をしていない庄野さんが、この場面でだけ、自分の意見を述べている。
そして、「凡夫の浅ましさのお陰で生きてゆけるのかも知れませんよ」は、いかにも庄野さんらしい言葉のように思える。
もしかすると、このとき、庄野さんの心の中には、福原麟太郎が愛したあの「われ愚人を愛す」という言葉が浮かんでいたのではないだろうか。
戦争とは何かというよりも、人生とは何か、生きるとはどういうことかということを、この物語は押しつけがましくなく考えさせてくれる。
倉本平吉さんの体験談には、それだけの重みがあるということなのだろう。
書名:引潮
著者:庄野潤三
発行:1977/5/10
出版社:新潮社



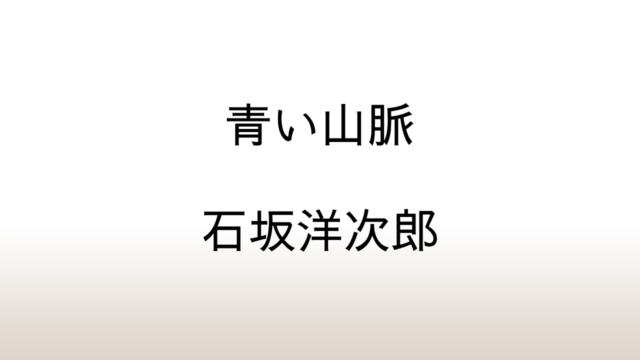


-150x150.jpg)








