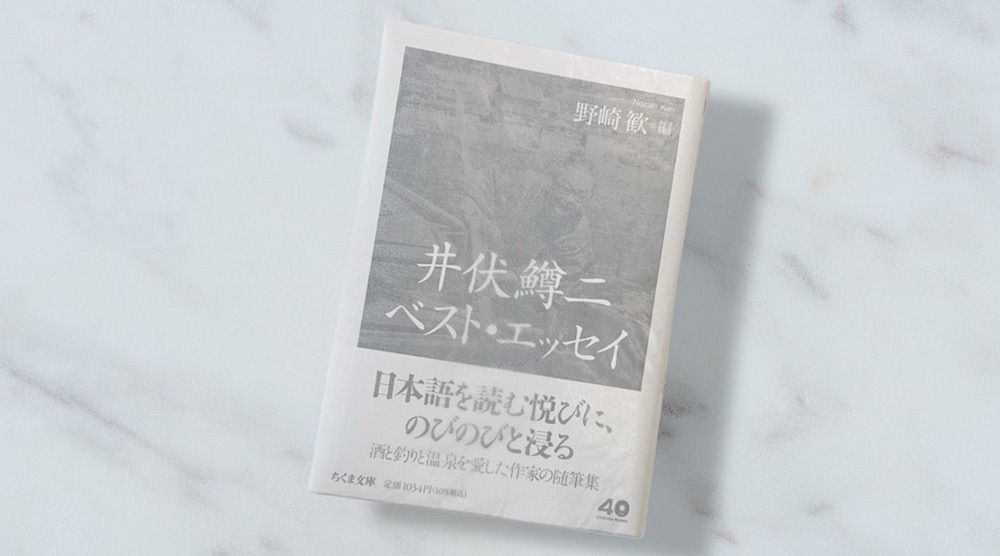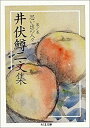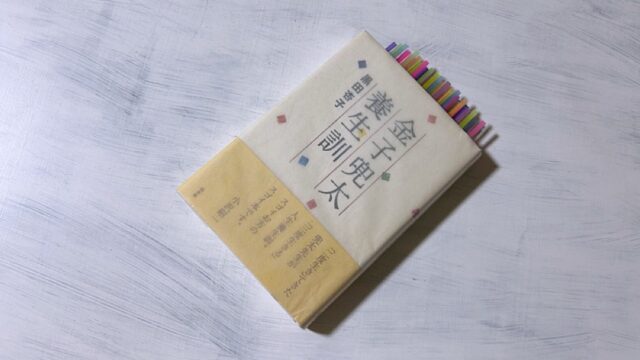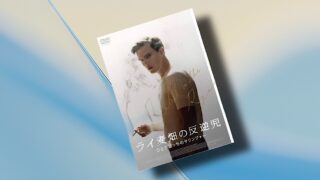野崎歓・編『井伏鱒二ベスト・エッセイ』読了。
本作『井伏鱒二ベスト・エッセイ』は、2025年(令和7年)10月にちくま文庫から刊行された随筆集である(ちくま文庫オリジナル)。
小説でも随筆でもない井伏文学
ちくま文庫には、既に『井伏鱒二文集(全4巻)』(2004)がある。
今回は一冊で楽しむことができる、井伏鱒二「ベスト・エッセイ集」の登場である。
巻末の「初出一覧」から見ると、1930年(昭和5年)の「終電車」から、1983年(昭和58年)の「下曽我の御隠居」まで、全38編の随筆が発表年順に並んでいる。
井伏鱒二の長い作家活動歴を「随筆」という観点から時系列に辿ることができる、というところが、本選集の特徴かもしれない。
収録作品は「森鷗外氏に詫びる件」や「坪内逍遥先生」「青羽雀のおじさん」「下曾我の御隠居」などのように『井伏鱒二文集(全4巻)』と重複するものもあるが、むしろ、これまで目立たなかった作品も多く含まれている。
真の意味で「これが井伏鱒二のベスト・エッセイか?」と言えば、他にも収録すべき作品は(もっとたくさん)あったかもしれない(もちろん、あっただろう)。
だから、本選集の「ベスト・エッセイ」は「初めての井伏鱒二」くらいの意味で考えるといいのだ。
井伏鱒二の作品を「小説」と「随筆」とで分類することは難しい。
酒場の飲みネタにさえ「物語性」を求めた井伏鱒二だったから、どの文章にも「物語性」というものが含まれている。
例えば、「終電車」(1930)には、終電車を乗り過ごして、見知らぬ男と二人で安宿に泊まる話が出てくる。
一時間ばかり経ったとき、洋服の人物は立ち上って周囲を見まわしたが、私の肩を掴んで叫んだ。「おい。ここはプラットフォームだぞ!」彼の言うことは嘘ではなかった。(井伏鱒二「終電車」)
荻窪駅を乗り過ごしたため、武蔵境駅で東京行きの電車に乗り換えたつもりでいたところ、作者(井伏鱒二)は見知らぬ男と二人で(武蔵境駅)のプラットフォームで眠りこんでいたのである。
二人とも「東京行きの電車に揺られているつもりでいた」とあるところがいい(「君は一たい電車に乗っていたのではないのか? 僕は君の隣りに腰かけて電車に乗っていると思っていたんだ」)。
武蔵境駅を出て「御安宿」と看板のある店の雨戸を叩いた二人は、売れ残っていた一つの部屋で一夜を過ごす。
そして一番の電車の通る音がきこえると同時に、彼は鼾を止し、「起きるぞ!」と掛声をかけて、勢いよくとび起きた。(略)「君、お先に失敬するよ。宿賃は僕の分は払っとくからね」(井伏鱒二「終電車」)
創作とも実話とも判別のしにくい「物語性」が、ユーモアを湛えて生き生きと描かれている(実に生き生きと!)。
井伏鱒二の「物語」は、いつでも「フィクション」と「ノンフィクション」の境界線のようなところで語られているものだ。
それは、仲間内の思い出話でも変わりはない。
「七月二十三日記」(1960)は、同郷の木下夕爾・近江卓爾と一緒に釣りへ行ったときの回想録である。
釣りに飽きた二人は木下夕爾に案内されて光明寺まで出かけた。
十何年前に釣りへ来たときにも、彼らはこの寺でお茶を御馳走になっている。
そのとき、見送りの少女が撞木杖を振り上げて柚子の枝を叩いた、ということがあった(柚子の実を落としてくれた)。
それから峠の道にさしかかったとき、不意に卓爾君がこう云った。「びっくりしたなあ、あのときは。発止とばかりに叩いたもんだ。ぱっと、空中に酸味が走ったようだった。僕は口の中に、唾がたまった」(井伏鱒二「七月二十三日記」)
釣行記のように思わせながら、釣り以外の話で読者を惹きこんでいくところが、井伏鱒二の話術である(つまり、物語性)。
「竜頭荘という鉱泉宿」の女中の描写もいい。
卓爾君は酒を飲まないが、夕爾君と私は飲むので宿の女中がお酌をした。この女中は半袖のシャツを着て半パンツに派手な前垂をしめていた。(井伏鱒二「七月二十三日記」)
「竜頭荘の女中」は、既に井伏文学の登場人物となっている。
そこから何かドラマが生まれてくることを期待させるかのような「物語性」がある。
本筋とは関係のない余白へ、どれだけの「物語性」を含めることができるか。
井伏文学の読者は、「余白」にこそ井伏文学の本質があることをちゃんと分かっているのだ。
「なかなか話が展開しないなあ」と思っているうちに、いつの間にか話は終わっている。
「琴の記」(1960)は、太宰治の最初の妻(初代さん)が遺した「山田流の琴」にまつわる思い出話である。
人気作家(太宰治)を知るエピソードとしても有名な作品となっている。
生田流の箏曲家(古川太郎)が「初代さんの琴」で、三好達治の「太郎をねむらせ太郎の屋根に雪ふりつむ/次郎をねむらせ次郎の屋根に雪ふりつむ」を歌った。
「さっきの雪のつもるところは、実際に雪がつもっているようだったね。朝、雪の降っているとき目をさますと、雪のにおいがするね。あの感じだ」私がそう云うと、「三好さんは、あの作曲が出来ているのを知ってらっしゃるでしょうか」と家内が云った。(井伏鱒二「琴の記」)
小山初代の遺品も、懐かしい太宰治の思い出へと流されていくことはない。
行き過ぎた感情を制御しながら、三好達治の詩を使って話をまとめる。
さりげない夫婦の会話は、やはり「井伏文学」の登場人物の会話である。
「朝、雪の降っているとき目をさますと、雪のにおいがするね。あの感じだ」と言った作者自身が、既に「井伏文学」を彩る登場人物の一人となっているのだ。
例えば、それは、長篇『黒い雨』(1966)の主人公(閑間重松)の言葉でもある。
僕は気がついた。その流れのなかを鰻の子が行列をつくって、いそいそと遡っている。無数の小さな鰻の子の群である。(略)「やあ、のぼるのぼる。水の匂いがするようだ」(井伏鱒二「黒い雨」)
井伏鱒二にとって、日常生活とは常に「物語」だったのかもしれない。
そして、井伏鱒二にとって文学とは「何かを創り上げること」ではなく、「何かを見つけること」だった。
そういう意味でも、井伏鱒二の文学を「小説」とか「随筆」とかいう分類でもって語ることに意味はない。
かつて、ちくま文庫が『井伏鱒二文集』を編んだ理由も、実はそんなところにあったのではないだろうか。
随筆で描く井伏鱒二像
「小説か? 随筆か?」問題は、井伏鱒二周辺でも大きなテーマだった。
1993年(平成5年)9月『文学界』の「追悼・井伏鱒二」特集で、高井有一と対談した三浦哲郎も、この問題に触れている。
三浦 井伏先生は「小説はフィクションだ、ウソを書く。だけども随筆はぼくは本当のことを書くんだ」とおっしゃってました。しかしぼくは、井伏先生の随筆の中にもずいぶんフィクションがあると知ってるんですよ。(三浦哲郎・高井有一「先生の遺訓」/『文学界』1993年9月号)
つまるところ、その「本当か嘘か分からないところ」にこそ、井伏文学の魅力があったのかもしれない。
三浦 どれが随筆でどれが小説でという境界線がないんだなあ。(略)それでぼくも随筆か小説かわからないようなものを書くことを覚えました。(三浦哲郎・高井有一「先生の遺訓」/『文学界』1993年9月号)
「随筆」の中で、井伏鱒二は盛んに「自分語り」をしている。
私の友人たちは、たいてい私のことを無鉄砲な人間だといっているが、なかには意気地なしだというものもある。私自身は私のことを、極く普通の人間だと思っている。また私の念願としても、私は極く普通の人間でありたいと思っている。(井伏鱒二「面罵の熟語」)
井伏鱒二の印象は、決して剛腕というものではなかった。
先輩作家(牧野信一)からは、かなりイジメられたらしい。
私は牧野さんに何回もやりこめられた。一度は、久保田さんや河上の見ている前でやりこめられ、わあわあと声をあげて泣いたことがある。(井伏鱒二「面罵の熟語」)
井伏鱒二は「弱み」を隠すことを知らない作家だった。
着飾らないところに、庶民作家・井伏鱒二の本領があったと言ってもいい。
着飾らない作家の周りには、いつでも(着飾らない)仲間たちが集まってきた。
私は友達がなくてはやりきれない。疎開中、三箇月も四箇月も誰にも友達に会えないでいて、つくづく友達ほしさに悩んだ経験がある。もうこのさき友達には誰にも会えないのではないかという不安を感じていた。(井伏鱒二「阿佐ヶ谷会」)
井伏鱒二の随筆には、実に多くの人たちが登場する。
文壇の作家仲間はもちろん、近所の将棋仲間や釣り仲間が次々に顔を出して、それが全然不自然ではない。
むしろ、彼らの存在が井伏文学を支えているとさえ思われる。
人間が好きだったからこそ、井伏鱒二は「人間」を書き続けたのだ。
一方で、井伏鱒二は、極度の「はにかみ屋」でもあった。
私は人とつきあってぎこちない。(略)私のうちのすぐ裏手に、玉のような人格者といわれている片山敏彦氏のうちがある。もう二十何年も前から私はすぐ近くに住みながら、道で片山さんに会うと目を伏せて通りすぎる。一度も口をきいたことがない。(井伏鱒二「阿佐ヶ谷会」)
多くの人脈を築いた井伏鱒二だったが、初対面から簡単に胸襟を開くタイプではなかったらしい。
相手を見極めるというプロセスが、そこでは重要だったのだ。
井伏鱒二の「講演嫌い」は、つとに有名である。
私は文壇的行事のうちで文芸講演が一ばんきらいである。講演をきくのは悪くないが講演するのは苦手である。(井伏鱒二「支離滅裂」)
「井伏鱒二のスピーチ」として、様々な逸話が伝えられているほど、人の前に出ることを、とにかく嫌がる(恐れる)人だった。
『黒い雨』でブレイクして「ノーベル賞候補」として騒がれたときも、井伏鱒二は記者会見の対応を、弟子の三浦哲郎に一任(丸投げ)していたという(「ぼくが先生のコメントを封筒に入れて、銀座の酒場で発表を待つようになりました」)。
自己顕示欲といったものが、まるで感じられない(有名な作家なのに)。
と言って、『ライ麦畑でつかまえて』のサリンジャーのように隠遁生活に徹したわけでもない。
ただ一人の庶民として井伏鱒二は、普通に生活したかっただけなのだろう。
表通りのまん中を歩くよりは、静かな裏通りをこっそり歩いていくことを好んだ。
鶴巻町は謂わば私の散歩みちの故郷である。(略)私はなるべく学生の通らない路地から路地をえらんで歩く。(井伏鱒二「牛込鶴巻町」)
広島県(賀茂村)出身の井伏鱒二にとって、東京は異郷の地だった。
私は大正六年、この東京に移住して来た人間であるが、いまだに東京の土地には馴染めない。(井伏鱒二「母」)
「東京の人間になりきろう」と無理をすることもなかった。
どこで暮らしていても、井伏鱒二は井伏鱒二だったからだ。
そういう意味で、井伏鱒二は、やはり最強だったと言える。
もともと私の容貌といい姿体といい、どことなく田舎風に出来ている。両腕にのこっている種痘のあとさえも、大きく野暮な形になっている。(井伏鱒二「晴耕せず雨読せず」)
野暮ったいところまで含めて、全部が井伏鱒二だった。
どれだけ実績を重ねても、井伏鱒二が「庶民の作家」であり続けることができたのは、彼が実際に「庶民らしさ」を失うことがなかったからだ。
「東京の偉い先生」になることを、井伏鱒二は望まなかった。
それは、作家・井伏鱒二というアイデンティティを守ることでもあったかもしれない。
やはり私の文体にも、田舎の言葉づかいや気風が大きに影響しているだろう。(井伏鱒二「「が」「そして」「しかし」」)
都会風に洗練された井伏鱒二なんて、既に井伏鱒二ではなかった。
都会風でも田舎風でもとっくに洗練されているのが「井伏鱒二」という文学だったからだ。
井伏文学は肩の凝らない文学である。
自然体という言葉が、これほど似合う作家はいない。
もともと私は感傷的な人間だが、文章を書くとき詠嘆的になりかけると、照れくさくて別の気分で感じる場面にすりかえたくなる。田舎の気風が顔を出す。(井伏鱒二「「が」「そして」「しかし」」)
感傷に流されない文章は、井伏鱒二の生まれに沁みついていたものかもしれない。
情緒的になりすぎないから、読者は安心して作者の話術に惹きこまれることができるのだ。
一冊の文庫本の中のどのページを読んでも、そこに井伏鱒二がいる。
それは、読者の(庶民の)身の丈に合った、庶民のための「物語」である。
青柳君は僕の書いたものは、「山椒魚」という処女作一篇のほかには五篇か六篇か、それも書きだしの五、六行しか読んでいないようであった。だが、それはそれでいい。ずいぶん長いつきあいであった。(井伏鱒二「青柳瑞穂と骨董」)
特別のことはどこにもないのに、井伏鱒二が死んだ後は、井伏鱒二の後を継ぐ作家は出なかった。
井伏鱒二は、井伏鱒二だけのオリジナルだったのである。
書名:井伏鱒二ベスト・エッセイ
著者:井伏鱒二
編者:野崎歓
発行:2025/10/10
出版社:ちくま文庫