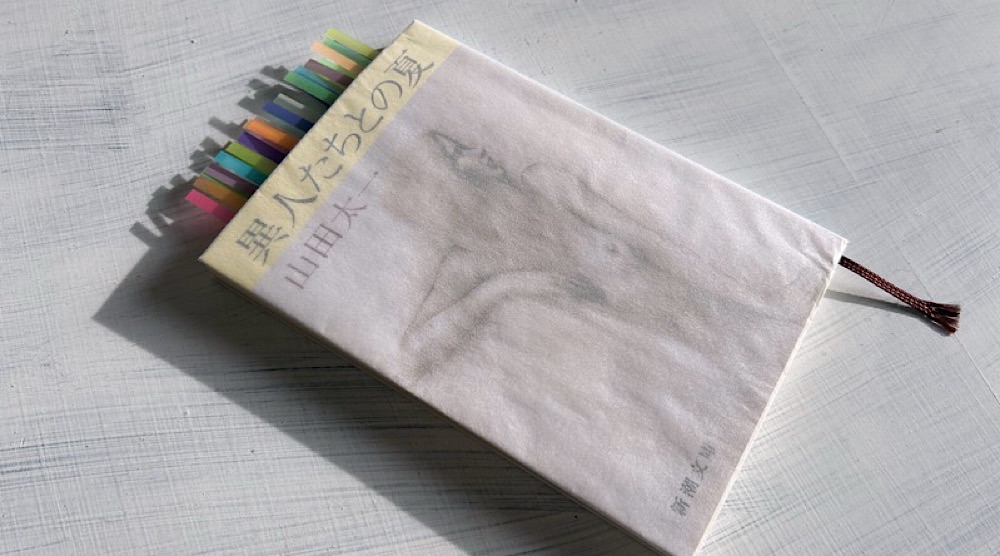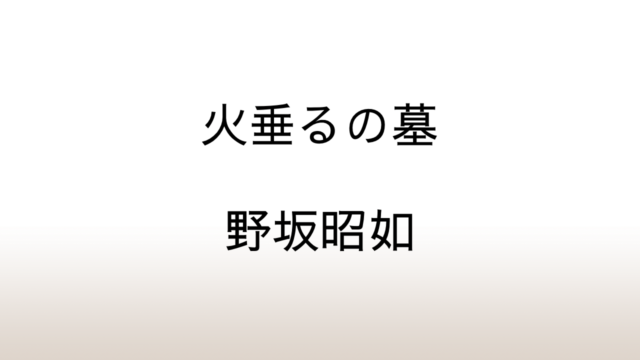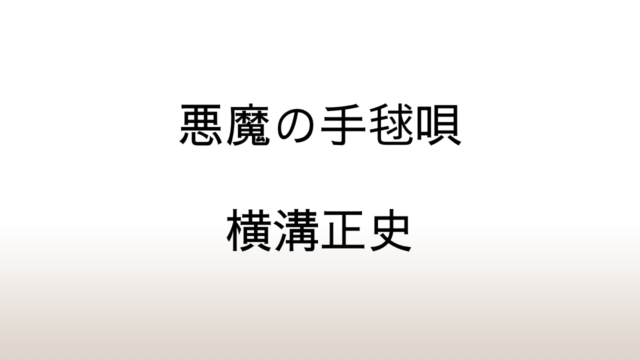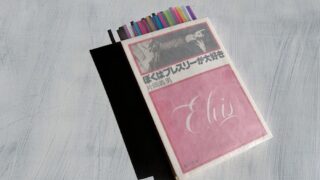山田太一「異人たちとの夏」読了。
本作「異人たちとの夏」は、1987年(昭和62年)12月に新潮社から刊行された長篇小説である。
この年、作者は53歳だった。
初出は、1987年(昭和62年)1月『小説新潮』。
1988年(昭和63年)、第一回山本周五郎賞受賞。
1988年(昭和63年)公開、大林宣彦監督、風間杜夫・片岡鶴太郎・秋吉久美子出演の映画『異人たちとの夏』原作小説。
消えゆく昭和へのノスタルジー
本作『異人たちとの夏』が伝えようとしているものは、消えゆく昭和へのノスタルジーである。
地上げ屋が活躍した80年代後半、それは、街が激しく変わっていく時代だった。
昨日まで当たり前にあったものが、突然消えてしまう喪失感を、この映画は描いている。
翌年の正月、父の自転車の荷台に母が乗って、乗用車にはねられて二人とも即死したのである。国際劇場前の通りであった。はねた乗用車は分からなかった。(山田太一「異人たちとの夏」)
主人公(原田英雄、48)が12歳の冬に、両親は死んだ。
父が39歳で、母が35歳だった。
さっきの位置からでも後姿は見えた。声とその後姿が、父に似ていた。死んだ父にである。(山田太一「異人たちとの夏」)
浅草演芸ホールで父と再会した主人公は、死んだ両親の暮らすアパートを頻繁に訪れるようになる。
浅草は私の生地である。浅草へ行ってみよう。私は急に方向を得た思いで、小走りに階段をおりた。(山田太一「異人たちとの夏」)
浅草は、昔ながらの東京が、まだ残る下町である。
その浅草にさえ、新しい時代は訪れつつあった。
男が戻って来る。「見たか?」「は?」「でかいホテルだろう?」(山田太一「異人たちとの夏」)
「国際劇場」跡地に建てられた「浅草ビューホテル」は、新しい時代の象徴として登場している。
両親が「国際劇場前の通り」で死んだのも偶然ではないだろう。
死んだのは、主人公にとっての浅草そのものだったのだから。
いい齢をして、なにをいっているのだろう。国際劇場もとうになくなって、大きなホテルになっているというのに。(山田太一「異人たちとの夏」)
浅草は、消えゆく昭和と新しい時代が(束の間)共存する街だ。
だからこそ、主人公は、遠い昔に死んだ両親と再会することができたのである。
新しい時代の中で、主人公は疲弊していた。
離婚による一種の神経症かもしれない。幹線道路の側のビルを静かすぎると感じるのは、普通ではなかった。(山田太一「異人たちとの夏」)
家庭生活の崩壊。
妻と離婚し、息子とも別れて暮らす主人公は、現代社会の犠牲者だ。
仕事仲間(間宮)は、別れたばかりの元妻(綾子)と交際したいと言う。
「すみません」間宮は深く頭を下げ、それから「これ以上、ここにいるのはつらくて」と泣くような声を出した。これじゃあよくあるテレビドラマじゃないの? そういう調子のいいドラマをつくるまいとして俺たちはあれこれやって来たんじゃないの?(山田太一「異人たちとの夏」)
人間関係の希薄な時代だった。
薄っぺらな言葉がまかり通る世の中に、主人公は疲れ果てていたのかもしれない。
女からも、なにもいって来なかった。まあ、あんな言葉は挨拶のようなものだ。テレビの世界では、口先だけのそんな約束や願望は、呼吸するように口にされ、誰も本気にしなかった。(山田太一「異人たちとの夏」)
両親の言葉は違う。
両親の言葉には「本当」があった。
「また来いよな」「ほんといらっしゃいよ」(山田太一「異人たちとの夏」)
現代社会に疲れた中年男性が、懐かしい時代へタイム・トリップしていく。
そんな構図が、この物語にはある。
「へえ。テレビの仕事なの? えらいんだねえ、頭いいのねえ」頭なんかよくないし、えらくもないし、ひとりっきりで、わびしい人生送ってますよ、お母さん。(山田太一「異人たちとの夏」)
それは、戦後社会を支えてきた中年世代へのエールだったかもしれない。
「モーレツ社員」と呼ばれ、「企業戦士」と呼ばれた男たちへの応援歌。
「十二で両親に死なれてさ」「ほんとですか?」「苦労したの。よくやったよ。よくやった、えらいよ」(山田太一「異人たちとの夏」)
走り続けてきたランナーが、息切れをするかのように、彼らはみな疲れていた。
それでも走り続けなければ、時代から取り残されてしまう。
走り続けることが、つまり、生きるということだった。
「あんたをね」と母がいった。「自慢に思ってるよ」「そうとも。自分をいじめることはねえ。手前で手前を大事にしなくて、誰が大事にするもんか」(山田太一「異人たちとの夏」)
自分を否定する主人公を、両親は全肯定して受け容れてみせる。
つまり、それが故郷というものだったのではないだろうか。
死んだ父と母は、優しかった昭和時代の化身である。
濃密な人間関係があった時代が、両親には投影されているのだ。
思い出すと、なにもかもが甘美で、私はタクシーの中で二人の声をくりかえした。「ほら、こぼした。いってるそばからこぼしてるじゃないの」(山田太一「異人たちとの夏」)
彼らは、甘えることの許されない責任世代である。
もちろん、逃避する選択肢なんてなかった。
消えゆく時代を懐かしむことは、新しい時代を否定することにもつながっていく。
自分が一種の鬱状態にいることが分かっていた。そこから抜け出さなければいけない。別の人生を生きはじめなければならない。(山田太一「異人たちとの夏」)
懐かしい夢を見た主人公は、古い時代(死んだ両親)に別れを告げて、新しい時代を歩き始める。
見逃すまいとした。父が消えて行く。「ありがとう。どうも、ありがとう。ありがとうございました」(山田太一「異人たちとの夏」)
「ありがとう。どうも、ありがとう。ありがとうございました」というセリフは、消えゆく時代に向けられた感謝と労いの言葉として読んでいい。
それは、彼らを育ててくれた時代だった。
バブル社会という急激な社会変容の中で、誰もが昔を思い出していたのだ。
まるで、遠い昔に死んだ両親のように、優しくて温かかった昭和という時代を。
映画『異人たちとの夏』が公開された翌年の一月、長かった昭和時代が幕を閉じる。
今観る『異人たちとの夏』は、まるで消えゆく昭和へ送られた追悼歌みたいだ。
新しい時代を迎える恐怖
一方で、孤独な女性(藤野桂、ケイ、33歳)は、寂しい現代社会の象徴である。
「どうしたのか、今夜、ひとりでいるのが、とてもたまらなくなって何度も迷ったんですけど来たんです。だって、こんな大きなビルに、真夜中、一人か二人しかいないなんて、怖いわ」(山田太一「異人たちとの夏」)
胸の傷痕には、現代社会に潜む闇が投影されている。
「火傷がひどいの」さらりと女はいった。「このあたりがひどくて」と胸に手をあて「切り張りしたけど、まだひきつったり色ちがいだったり」(山田太一「異人たちとの夏」)
「切り張りしたけど、まだひきつったり色ちがいだったり」とあるのは、古い建物と新しい建物とが共存する現代社会そのものだ。
急激な社会変容による歪みが、女の姿として描かれている。
新しい時代、他人には見せることができない闇を、誰もが抱えて生きていた。
「多分あなたには、私のとてもいいところしか見せていないの。胸を隠しているのがいい証拠」(山田太一「異人たちとの夏」)
新しい時代の美しさは、見えない闇と一体化した不気味な美しさである。
闇があることを知っていながら、闇を見ることはできない。
そこに、新しい時代の恐怖がある。
「美しい」「見ないからだわ」くずれるように女は身をかがめた。(山田太一「異人たちとの夏」)
それは、古き良き浅草の町を破壊し始めた、現代的なビルの美しさだったかもしれない。
私には、閉鎖され板で囲われている映画館やとりこわされたあとの空地よりも明るくて清潔なビルの方が、この街のいたましい傷痕のように感じられた。無論たちまちビルの方に合せて街は変り、そんな印象はなくなって行くのだろうが。(山田太一「異人たちとの夏」)
映画『異人たちとの夏』では、両親の暮らす古いアパートの遠く向こう側に、現代的な高層ビルが配置されていた。
物語としての『異人たちとの夏』を象徴する構図が、そこには象徴されている。
映画の中で主人公が鰻を食べた「浅草うなぎ 小柳」も、2013年(平成25年)に新しいビルへと生まれ変わった。
浅草でさえも、街は変わり続けていくのだということを、もちろん、主人公は知っていたに違いない。
「行こうじゃねえか」「どこへ?」思わず私は顔を上げて父を見た。「どこって、すき焼きだよ。真夏に冷房で、しっかりすき焼き食おうじゃねえか」(山田太一「異人たちとの夏」)
新しい時代と古い時代が(束の間)共存する浅草の町で、主人公は、死んだ両親とすき焼きを食べる。
映画では「今半別館」として登場する「すき焼き屋」には、過ぎ去った時代への郷愁が込められている。
インバウンドもオーバーツーリズムもなかった時代、浅草は、本当に人間らしい町だったのだ。
雷門方向の口から地上へ出ると、夕闇が濃かった。地下鉄の人の減り方から予想したほどのことはなく、街は小綺麗に明るく、歩く人も多かった。(山田太一「異人たちとの夏」)
古い時代の象徴としての浅草は、やはり、映像の方が美しい。
消えゆく時代の浅草が、映画には残されている。
「空地でした」深い淵へ声もなく落ちて行くような孤独を感じた。「アパートだったのを五月にとり壊して、周りをもう少し壊してビルが建つんだそうです」(山田太一「異人たちとの夏」)
街は、激動の時代だった。
時代に押し流されるように、それでも彼らは新しい時代を生きていかなければならない。
自殺したケイは、新しい時代を生きていくことのできなかった、現代社会の犠牲者である。
小さな黒いシミが胸のあたりに浮んだ。黒ではない、赤だった。みるみるその赤が白い布にひろがる。鮮血だった。(山田太一「異人たちとの夏」)
自殺したケイが、亡霊となって主人公と愛し合うのは、現代の怪談である。
ここにも、また、新しい時代への抵抗があった。
なぜなら、新しい時代を生きる人々は、怪談さえも消えてしまう時代のノスタルジーとしてとらえていたのだから。
「忘れましょう。それじゃなきゃ、これから生きていけやしません。どうかしていたんだ。御両親のことも、あまり入れ込まないで下さいよ。どうかしていたんです」(山田太一「異人たちとの夏」)
オカルトなストーリー展開は、この物語のテーマを示唆している。
新しい時代そのものが、既にオカルティックな存在だったのだ。
消えゆく時代への懐かしさと、新しい時代への恐怖。
本作『異人たちとの夏』に描かれているのは、移り変わる時代の狭間に迷いこんだ中年男性の幻想である。
そして、その時代、多くの人々が、同じような幻想を見ていたのではないだろうか。
「やっぱりねえ」と母が淋しい声を出した。「このままやって行けるわけはないと思っていたのよ」(山田太一「異人たちとの夏」)
バブル時代は、一瞬の夢を見せて、瞬く間に消えた。
夢だったのは、昭和時代ではなくバブル時代だったのだ。
もちろん、この時代、そんなことは誰も知らない。
新しい時代をしっかりと受け容れるためにも、彼らは、古き良き昭和時代に、きちんと別れを告げなければならなかった。
「お前に逢えてよかった」と父がいった。「おまえはいい息子だ」(山田太一「異人たちとの夏」)
「ありがとう、昭和」という思いを込めて、主人公は消えてゆく両親を見送る。
これからは、新しい時代を、一人で生きていかなければならないのだ。
本作『異人たちとの夏』は、もしかすると、消えゆく時代に捧げる線香のような物語だったのかもしれない。
書名:異人たちとの夏
著者:山田太一
発行:1991/11/25
出版社:新潮文庫